
この車人形応援団は石川博司氏の提案で、渡辺が勝手に作っています。(文責・渡辺国茂)
更新日 2004年03月29日


 ●引き幕 (小河内村) ●金平人形3体(下段) 
 ●御祝儀三番叟 ●人形頭(修理前) 昭和51年4月撮影 渡辺国茂 [川野車人形ふたむかし写真館] 東京の奥座敷ともいうべき奥多摩町川野地区に車人形が伝承されている。車人形は天保時代(1830〜44)武州加冶村阿須(現・埼玉県飯能市)の西川古柳(本名:山岸柳吉)により考案された箱車(内部に車輪が3つ組み込まれている:ロクロ車)をつかう一人遣いの人形です。 この箱車に座り、ずれないように腰に縛り付け、自分の足で人形の足をつかみ動かす。左手で人形の頭を操作し、右手で人形の右手を操作する、内部に仕掛けがあり、人形の右手を動かしながら人形の左手も動かすことが出来るようになっている。 江戸時代末期に考案された車人形が、明治18年(1885)小宮村(現:あきる野市小宮)の説教節の太夫、岸野清兵衛により川野地区にもたらされた。 川野地区には車人形が入る前に、二人遣いの人形芝居が伝承されていたらしい。現在でも宝暦2年から天明・文政年間にかけて作られた人形の頭部であるカシラが31個残っておりそのうち3個は「金平(きんぴら)頭」で文化財としても貴重なカシラだそうです。車人形が導入される以前の人形は二人遣いで、人形のカシラは小ぶりで動かず、手足もなく、主遣いが頭と人形の右手、もう一人が人形の胴体部をもち、人形の左手を担当していたようです。 川野には浄瑠璃本が百段ほどありましたが、火災で焼失し現在は約三十段位になってしまったそうです。 川野に入った車人形は村人の娯楽として3月5日箭弓神社の祭礼に民家で上演されていました。 ところが昭和6年ダム計画が発表されると、人々が昭島や羽村へ移住しはじめ、昭和13年からダム工事が着工すると多くの人たちがダム計画地から離れ、川野は過疎化しました。 昭和27年川野車人形は東京都無形民俗文化財に指定されましたが、昭和32年11月ダムが完成以後は人手が少なくなり、上演されなくなってしまいました。 昭和45年文化財を見直す機運が盛り上がり、東京都と奥多摩町の補助金で人形と衣装の修理が行われ、保存会を結成して、復活のための練習が始まりました。そして地元を離れた人たちが組織した「川野会」の援助もあり、現在では3月5日に地元の箭弓(やきゅう)神社の祭礼に川野会の人たちも川野生活館に集まり年1回の定期公演をたのしんでいます。 ○伝承演目 三番叟・東山朝倉草紙(渡し場:住家:子別れ) 出世景清一代記(「日向」とも)(阿古屋自害の場:獄舎破りの場:人丸姫道行の場) 東海道中膝栗毛(赤坂並木の段) 小栗判官一代記(七色の場) ○定期公演 3月5日午後1時頃〜3時頃 奥多摩町川野生活館 (文責:渡辺国茂 参考文献「多摩のあゆみ」「川野車人形を追う・石川博司著」) 石川博司著『川野の車人形を追う』 発行ともしび会より (平成13年3月15日発行) 『川野の車人形Ⅱ』 (P4〜6) 三月五日は東京都西多摩郡奥多摩町川野にある箭弓神社の祭礼である。この日の午後には川野の車人形が公開される。 車人形は、文楽人形の三人遣いとは異なり、箱車を利用することで一人で人形を遣う。人形遣いは、二輪の前輪と一輪の後輪のロクロ車を仕掛けた箱車に腰をおろして両手で人形の首と手で、両足で足の動きを操作する。また文楽では義太夫であるが、車人形は説教節である。 車の入った箱は上部が座りやすいように半月状になっていて、高さが最高18㌢で最低13㌢、長さが28㌢、幅16㌢である。車は前輪が幅2㌢2枚、後輪が幅9㌢でいずれも直径が8㌢、つまり三輪になって前後左右に移動できる仕掛けになっている。 この車人形を考案したのは、埼玉県加冶村阿須(現・飯能市)の西川古柳(本名・山岸柳吉 1824〜97) である。現在、車人形は、この川野の他に八王子市と三芳町(埼玉県)にみられ、一般には八王子市下恩方町の西川古柳座が知られている。 川野集落は現在約30軒、小河内ダムの出現で青梅や羽村・昭島に移転した人たちで作っている川野会の協力があるにしても、春3月5日の箭弓神社祭礼に行われる車人形、秋9月15日の小河内神社祭礼に演じられる獅子舞お保存するのはかなりきびしい。車人形は、説経浄瑠璃の太夫と三味線、それに人形遣いいずれも地元に住む人たちである。獅子舞は川野会の人たちも加わっている。 車人形は、公演に先立て舞台中央に三番叟の人形を飾り、三番叟の前に行われる「三番 のお神酒」で始まる。この種のものは、同町海沢の神庭の神楽でもみられる。関係者がお神酒を戴いてから、地元で行われる三・三・一の七つ締めで終わり、幕が下ろされる。 最初は、口上があって「御祝儀三番叟」から始まる。舞台の右手の袖には、三味線と説経の語り手が座る。人形は烏帽子をかぶり、鶴を描く上衣に紫の袴をつける。烏帽子の金地に黒の縞を6本入れて金と黒の線が各6本計12本で12ヶ月を表し、その上の片面に赤の丸(太陽)と他の面に赤の三日月がある。 次いで三分ほどであるが、人形遣いの説明がある。箱車につけた紐を腰に結びつけて、人形の衣装をはずして実際に首や手足を動かせて操作をみせながら説明する。地元の方々には何をいまさらと思われるかもしれないが、こうした説明が車人形の理解者を増やす役目お果たしている。 続いて段物の演技になる。平成8年の場合は、最初が源平盛衰記の「盛利注進の段」(10分)、次いで東山朝倉草紙の「住家の段」(22分)、最後が東山桜草紙の「子別の段」(34分)の演技である。「住家の段」は20年振りの演目という。三味線は一人で通したが、説経の語り手は段毎に変わって三人で務めた。 川野には浄瑠璃本が百余段あったが、二度の大火で焼失して現在では三十数段になってしまった。源平盛衰記・佐倉宗五郎・道中膝栗毛・小栗判官一代記・出世景清などが主な演目である。 川野車人形は、毎年箭弓神社の祭礼奉納されるが、他にも第五回と第十回の東京都民俗芸能大会をはじめ各地に招かれて公演しており、平成3年2月には交流協会の招きで台湾公演を行った。 (初出)『まつり通信』第445号(まつり同好会 平成10年刊)所収 (石川氏より転載許可いただきました) |
[川野車人形ふたむかし写真館]
○石川博司氏調査による「川野車人形文献目録」
| 著 者 | 題 名 / 書 名 | 発行所 | 刊行年 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 天野佐一郎 | 「車人形と説教節」・『多麻史談』2巻2号 | 多麻史談会 | 昭和9年刊 | |
| 広川 清 | 「小河内の車人形」・『日本民俗』2巻8号 | 昭和12年刊 | ||
| 東京市役所 | 『小河内貯水池郷土小誌』P246〜P249 | 同所 | 昭和13年刊 | |
| 東京都都民室 | 『郷土藝能と祭礼行事資料』 | 都民室総務部観光課 | 昭和29年刊 | |
| 本田安次 | 「小河内の郷土芸能」 『東京都の郷土芸能』P246〜249 |
一古堂書店 | 昭和29年刊 | |
| 本田安次 | 「小河内の郷土藝能」/『武蔵野』34巻1号 P15 | 武蔵野会 | 昭和30年刊 | |
| 都教育委員会 | 『東京都の文化財』P39 | 都教育委員会 | 昭和33年刊 | |
| 奥多摩郷土教 材研究委員会 | 『奥多摩郷土小誌』P351 | 奥多摩町教育委員会 | 昭和39年刊 | |
| 祝宮静/関啓吾 宮本馨太郎 | 『日本民俗文化財辞典』P284 | 第一法規 | 昭和44年刊 | |
| 都教育委員会 | 『東京都の文化財』P69 | 都教育委員会 | 昭和45年刊 | |
| 都教育委員会 | 『東京都の文化財』P69 | 都教育委員会 | 昭和46年刊 | |
| 小河内 車人形保存会 | 『人形浄瑠璃と車人形』 | 同会 | 昭和46年刊 | |
| 東京都教育庁 | 『東京都の文化財』P250 | 社会教育部文化課 | 昭和53年刊 | |
| 中村 規 | 『民俗・東京の祭』P226/228/351 | 鷹書房 | 昭和55年刊 | |
| 大館勇吉 | 『奥多摩風土記』P212〜4 | 有峰書店 | 昭和55年刊 | |
| 仲井・西角井 三隅 | 『民俗芸能辞典』P166〜7 | 東京堂出版 | 昭和56年刊 | |
| 奥多摩町 | 『奥多摩町の民俗−民俗芸能』P98〜101 | 教育委員会 | 昭和57年刊 | 奥多摩町誌史料集6 |
| 奥多摩湖愛護会 | 『湖底の村の記録』P280〜1 | 同会 | 昭和57年刊 | |
| 瓜生卓造 | 『奥多摩町異聞』P263〜5/P267〜9 | 東京書籍 | 昭和57年刊 | |
| 奥多摩町 | 『奥多摩町の文化財』P6 | 教育委員会 | 昭和57年刊 | |
| 東京都神社庁 | 『西多摩神社誌』P417 | 西多摩支部 | 昭和58年刊 | |
| 原 義郎 | 『東京わが町 秋冬編』(カラーブックス) | 保育社 | 昭和58年刊 | |
| 杉田芳春 | 「川野の車人形」『多摩のあゆみ』 | 多摩中央信用金庫 | 昭和58年刊 | |
| 梅田和子 | 「奥多摩町川野の人形芝居頭について」 『多摩のあゆみ』第33号 P28〜35・裏表紙 |
多摩中央信用金庫 | 昭和58年刊 | |
| 本田安次 | 『東京都民俗藝能誌 上巻』P655〜7 | 錦正社 | 昭和59年刊 | |
| 奥多摩町誌 編纂委員会 | 『奥多摩町誌 民俗編』 | 奥多摩町 | 昭和60年刊 | |
| 大館勇吉 | 『奥多摩の民俗』P512〜6 | 同人 | 昭和60年刊 | |
| 写真集湖底の 故郷編集委員会 | 『写真集 湖底の故郷』P8・184 | 奥多摩湖愛護会 | 昭和63年刊 | |
| タウンガイド ブック編集部 | 『青梅・奥多摩への道』P206 | 昭和印刷出版 | 昭和63年刊 | |
| 佐藤 高 | 「多摩の祭り歳時記」 『多摩のあゆみ』第56号P33 |
多摩中央信用金庫 | 平成1年刊 | |
| 佐藤 高 | 「多摩の祭り行事暦」 『多摩のあゆみ』第56号P41 |
多摩中央信用金庫 | 平成1年刊 | |
| 杉田芳春 | 『奥多摩町・川野車人形の歴史と現状』 『多摩のあゆみ』第57号P42〜5 |
多摩中央信用金庫 | 平成1年刊 | |
| 東京都教育庁 | 『東京都文化財総合目録』P45 | 社会教育部文化課 | 平成2年刊 | |
| 山崎介司 | 「川野の『車人形』」 『郷土研究』創刊号P24〜7 |
奥多摩郷土研究会 | 平成2年刊 | |
| 奥多摩町 | 『奥多摩町の文化財』P10 | 教育委員会 | 平成3年刊 | |
| 西多摩地域広域 行政協議会 | 『西多摩 見る・味わう・歩く』P42 | 同会 | 平成3年刊 | |
| 酒井 久 | 「川野の車人形台湾公演に同行して」 『郷土研究』第2号P58〜62 |
奥多摩郷土研究会 | 平成3年刊 | |
| 高橋秀雄 原 義郎 | 『祭礼行事 東京都』P138 | 桜風社 | 平成4年刊 | |
| 東京都教育庁 | 『東京都文化財総合目録』P45 | 生涯教育部文化課 | 平成2年刊 | |
| 東京都祭礼研究会 | 『祭礼事典・東京都』P33〜4/173/187 | 桜風社 | 平成4年刊 | |
| 中村 規 | 『江戸東京の民俗芸能4 獅子舞田楽・田遊び・地狂言ほか』 P140〜1/143〜6巻号 |
主婦の友 | 平成4年刊 | |
| 佐藤 高 | 『ふるさと東京・民俗芸能(2)』P87〜94 | 朝文社 | 平成6年刊 | |
| はちようじ車人形研究会 | 『八王子車人形』P31〜4/39/42/46 | のんぶる社 | 平成8年刊 | |
| 多摩民俗芸能研究会 | 『立川の伝統芸能』P71〜2 | 立川市教育委員会 | 平成9年刊 | |
| 石川博司 | 『平成9年の祭事記』P17〜9 | ともしび会 | 平成9年刊 | |
| 石川博司 | 「川野の車人形」『まつり通信』第445号P3/8 | まつり同好会 | 平成10年刊 | |
| 東京都民俗芸能大会 実行委員会 | 『第29回東京都民俗芸能大会』プログラムP17/23 | 同会 | 平成10年刊 | |
| 石川博司 | 『平成10年の獅子舞巡り』P9〜10 | 多摩獅子の会 | 平成10年刊 | |
| 石川博司 | 『平成10年の祭事記』P12〜5 | ともしび会 | 平成10年刊 | |
| 東京都東京 江戸博物館 | 『川野の車人形 調査と映像記録』口絵・P1〜139 | 同館 | 平成11年刊 | |
| 東京都民俗芸能大会 実行委員会 | 『第32回東京都民俗芸能大会』プログラムP10〜1/17 | 同会 | 平成13年刊 |
(*石川氏より転載許可いただきました)
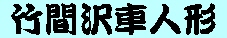
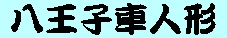
 八王子車人形・公演予定
八王子車人形・公演予定

| 日時 | 開場名 | 開演時間 | 演目 | 料金 | 備考 | 99年3月13日(金) | 成増アクトホール | 13時30分 | 蘆屋道満大内鑑 狐葛の葉子別の段 | 無料抽選 | 若松若太夫 終了 | 2000年1月頃 | 八王子 | 時 分 | 薩摩彦太夫出演予定 |
|---|
このページは車人形の写真を張る付ける予定です。 以下工事中
ホームへ
 民俗芸能へ
民俗芸能へ |
|---|