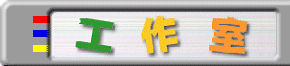 |

|
| | 概要 | 回路の設計 | ユニットの製作 | 取付調整 | まとめ | |
● ポジションライトの回路
ウインカーをポジションライト兼用にする回路です。
設計に当たっての前提条件を整理すると、次のとおりです。
- ヘッドライト内のポジション球の点灯と連動して、バイク前方の左右のウインカー球を点灯させます。
明るさは5W球相当としました。 - ウインカーが点滅動作に入ると同時に、左右のウインカー球のポジション点灯状態はキャンセルされ、完全に消灯します。
- ウインカーが点滅動作を終了すると、約3秒後に1.の状態に戻ります。
- スイッチの切替えによりこの回路の機能を無効にする事ができます。
また4.の条件は、バイクのメンテナンス時などに無駄な電力を消費しないようにするためで、常時点灯式のバイクの場合には特に便利です。
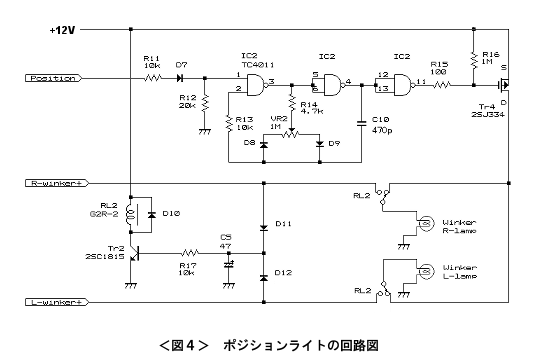
上の回路図で動作の概略を説明します。
ヘッドライトのポジションランプが点灯するとIC2の1番端子に電圧(Hレベル)が加わり発振を開始します。その結果11番端子からH/Lの信号がTr4のゲートに供給され、左右のウインカーへの電流がON/OFFされます。これがポジションライトの点灯状態です。この状態でバイクのウインカースイッチをONにすると、D11またはD12(ハザードスイッチをONにした場合は両方)を経由してTr2のベースに電圧がかかり、Tr2がONになります。これによりリレー(RL2)が動作して、ウインカーランプにはバイク側のウインカー回路から電流が供給されます。つまり通常のウインカーとしての動作状態になる訳です。ウインカーが消灯しても、C5に充電された電気でTr2は約3秒間ON状態を保持しますので、その間ポジション点灯は休止しています。
● ヘッドライトディマーの回路
ヘッドライトディマー回路の設計で前提とする条件は次のとおりです。
- ディマーが働くのはロービームに対してだけとします。
- ギヤがニュートラルになった場合、約3秒後に減光(または消灯)させます。
- 減光か消灯かはスイッチの切替えで選択できます。
- ギヤがニュートラル以外のポジションに入った場合、すぐにフル点灯します。
- スイッチの切替えによりこの回路の機能を無効にする事ができます。
また5.の条件は、車検対応として必要な条件です。
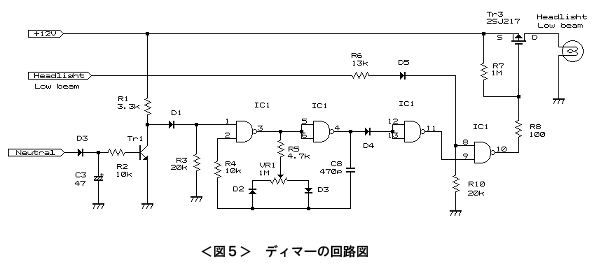
この回路のポイントはニュートラル信号の取り方です。
ギヤがニュートラルになるとフロントパネルのニュートラルランプが点灯しますが、このランプはアース側で制御されています。つまり、ランプのプラス側から分岐して電圧を取り出した場合、ランプ消灯時に+12V、点灯時には0Vに近くなります。そこでトランジスタ(Tr1)を使ってロジックを反転させ、ニュートラルランプの点灯時にIC1の1番端子にHレベルの電圧を与えています。コンデンサ(C3)は動作のディレイ用で、ニュートラルポジションになっても約3秒間動作を止めています。この機能が無いと、ギヤがニュートラルポジションを通過するたびにディマーが働いてしまいます。
● ヘッドライトの光量をアップする回路
R1100RTのホーンはリレー制御なのに、何故かヘッドライトの制御にリレーは使われていません。ヘッドライトはハンドルスイッチで直接制御していますので、配線距離は長くなり、スイッチの抵抗と合わせて途中の損失が大きくなります。これがRTのライトを暗くしている原因と思われます。試しにヘッドライトを直接バッテリーに繋いで照度計で測定すると、約40%も明るくなりました。そこでこのユニットにヘッドライトリレーを内蔵する事にしました。ただし、ロービームに関しては前項のディマー回路で同じ機能が実現されていますので、リレーはハイビーム用だけで良い訳です。
回路については、コネクタのハイビーム用端子から電流を貰ってリレーを制御するだけですから、説明を省略します。
● 全体の回路
POLEconの全体の回路図はこちらをご覧ください。[ POLEcon回路図 ](35KB)
E-mail :sakai@home.email.ne.jp
Copyright 1999-2001 by sakai. All right reserved.