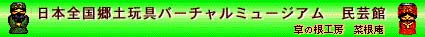 ----青森県篇(1)---- ----AOMORI(1)----
|

■馬乗りダッタン人(張り子)■(廃絶)
■牛乗り天神・羊に乗る乙女■(廃絶) 牛乗り天神・羊に乗る乙女は、「手捻り土人形(型を使わずに粘土を指先で形作る土人形)」です。 昭和55年頃まで、青森市内の美術骨董商の福原英次郎さんが作られていました。福原さんは、土人形のほかに、「馬乗りダッタン人」や飾り馬などの「張り子」、木彫りの「猿乗り八幡馬」なども作りました。 ■金魚ねぶた■ 古くから見られる灯玩具で、「ねぶた祭り」に子供たちが灯を入れて持ち歩きました。 夏のねぶた祭の季節になると、街で売り出されます。 --次回ページには、「扇ねぶた」を掲載しています。-- ◇「ねぶた祭」 「ねぶた祭」は、七夕の灯篭流しの変化したものともいわれています。 青森ではねぶた、弘前ではねぷたと呼ばれていますが、これは東日本に古くから残る習俗で、元来は「ねむた流し」の行事です。 ねぶたとは睡魔のことで、これを海や川に流すことにより、秋の収穫をひかえ労働の妨げとなる眠気を払うため、大きな作りものを作って練り歩き、その興奮の中で睡魔を集落から追い払う行事が本意なのです。 青森の歌舞伎人形の灯篭、弘前の扇形の灯篭、秋田の切り子灯篭なども同様のものといえます。 なお、(社)青森観光協会:のホームページには、「青森ねぶたの総合情報」に興味深い情報が詳しく掲載されていますので、ぜひご覧ください。 ■下河原焼(土人形)■ 「馬」「風俗人形」「内裏雛」「人形笛」 弘前(ひろさき)の郷土玩具の中でも、「鳩笛」や「人形笛」の下河原焼がよく知られているます。弘前市の桔梗野は通称「下河原」と呼ばれていたので、この名がついたものです。 「人形笛」はかなり古くから作られていたようで、大正6年(1917)刊の「うないの友」第7刊に「餅搗兎」の人形笛が1点掲載されています。 高谷充治さんが製作していましたが、平成11年、79才で亡くなられ、後を長男の信夫さんが継いでいます。高谷さんは「下河原焼鳩笛絵付教室」も開いていて、ここでは、絵付けの体験ができます。 ここの土人形は非常に種類が多く、中でも一番多いのが人形笛で、全長5、6センチ位の小型で、70種類あまりが作られています。土人形としては、鯛えびすなどの縁起ものや、風俗もの、童話、河童などの架空動物など、古い時代からのものも作られています。 製作者記録:高谷信夫:弘前市桔梗野1-20-8 TEL: 0172-32-6888 下河原焼鳩笛絵付教室:弘前市桔梗野1-20-4 TEL: 0172-32-6889 |
|
▼‥[Next] 青森県編(2) | ▲‥[Back] 北海道編(2) |

|
(1996.04.14掲載/2000.04.22/2002.06.25/改訂)