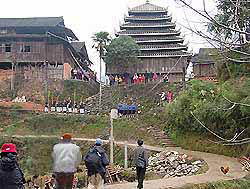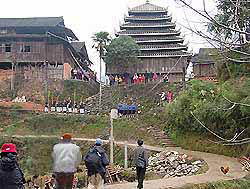トン族の村には、その建築物を見るために
建築学者が日本から訪れることも多いらしい。
その見学記にも、こんな風に村人から迎えられて、感激した
と書かれているのを読んだことがある。
村の鼓楼の前の広場に導かれると、
そこでは、踊りの準備が始まっているようだった。
私達が座るベンチが、すでに鼓楼を背景にした舞台の
正面に置かれていた。
私達と、この時に居合せたらしい
西洋人の一家(ご夫婦と、娘さん2人)が、腰掛けると
舞台の幕が上がった。
*(Aさんよりいただいた写真)
中国の劇などで、よく見るように、
中心となる一人の女の子が、ササッと、前に出て来ると、
ちょっと甲高い声で、活舌よく歓迎の挨拶をする。
(もちろん中国語)
歌のトン族、踊りのミャオ族、と言われているそうだ。
高い声が、合唱だったり、輪唱になったり、
独特の抑揚の美しい声が響き渡る。
*写真をクリックしてみてください
*写真をクリックしてみてください
 |
「芝刈り踊り」と言われる竹を使った踊りに
添乗員さんが、トライする。
トン族の衣装には、青が多く用いられるらしい。
一般に「黒」と「青」は、春、秋、冬に用いられ、
その他に好んで用いられるのは、白や濃い色の紫、
とのことだ。
夕食は、やはり、トン族の一般家庭で
家庭料理を頂くことになっていた。
山を降りてバスに戻るために、
粘土質で、泥んこの坂道を気をつけて、降りる。
橋のところで、又、賑々しいお母さん達や、お歳寄りの
人に引きとめられる。
「買おうかな?」せっかくだもの何か買いたい。
私は、まず、近くにいたくまさんを呼んだ。
すると、くまさんは、ずっと先に行っていたおかあさんを
大きな声で引きとめて、呼び戻す。
「Tはん、来てな!」
そうか、同じ関西の人でも、やっぱり馬力のある
おかあさんは、頼りになるらしい。かくて、おかあさんは、大忙しになった。
全部日本語で、後は、指の数字と、威勢のいい
啖呵で、交渉してしまう。
「いい?お嬢はん !( えっ、私のこと?)あんた、どれとどれが欲しいねん。
はっきり欲しいもん決めや。」「ん、これとこれか?」「じゃあ、コンくらいから
行ってえぇかぁ?」おかあさんは、早口に私に言い、
数字をちょっと、体を傾けた影で指で示す。」
私は、ただ、「は、はい。もう任せますっ。」
前に載せたガイドのリュウさんの衣装の胸当てと同じような刺繍があった。
一枚30元とのこと。日本円にすると、420円である。
私など、ついその位なら、と思うのだけれど、おかあさんは、それを10元にはするつもり
らしい。「オジョちゃん、あんた他に欲しいもんないのんか?」
と、聞かれて、私は、ズンズン迫ってくるあちらの
お母さん達をスリ抜けて、近くで目についた、
赤ちゃんの襟の刺繍を手にとり、「じゃあ、これもお願いしますっ!」
と、おかあさんに投げるように渡す。
最初の刺繍3枚に後で加えた襟飾りを一緒にして、
交渉の結果は30元!!
思いも寄らない結果に、へぇー!!!
とにかく、こちらのおかあさんの勢いに
あちらのお母さんが押しきられた感じだった。
平凡な刺繍3枚と、それらしい雰囲気の襟飾りが
1枚、なんと4枚で、420円だなんて・・・。
関西のおかあさんのスゴ腕に私は、驚くばかり。
それから、おかさんは、くまさんの所に行っていたのかも
しれない。橋のお母さん達の関心が、
よそに写っているスキに(そうでなければ、
私には、手に取って見ることも出来なかったからだけれど )
私は、おもしろい図柄の使い古した刺繍に目をつけた。個性的だ。
と、横に橋のお母さんが、ぴったりと、いて、
にゅっと、それを差し出した。370元だという。
これは、本人が作ったのだろうか。など聞きたいけれど、
中国語では聞けない。それに、橋のお母さんの方は、
そんな所じゃない。まずは、商売。
私は、おずおずと首を振り、もっと、下げてと、
ジェスチャーで言う。あちらも、だめだ、と
ジェスチャーで答える。何だか、これじゃ下がりようも
ないじゃない、そんな空気だった。と、そこへこちらの
おかあさんが来た。「あんた、そんなん、あかん! それ、一度
下に置かんと・・・。」 「ほしいのが、見え見えや。」
そ、そうか。私は、慌てて、その布をポタリと台に置いた。
でも、多分、商売は、スタートで
決まっていたのだろう。慌てて、落としてみたところで。
それから、おかあさんが、交渉してくれたけれど、
あちらのお母さんは、なかなか渋かった。
それでも、こちらのおかあさんのおかげで、
370元が、200元にはなった。2800円位である。
それでも、この土地の価格としては、高い買物になってしまったようだ。
帰ってから、冷静に計算してみると、
町の労働者のお給料が、650元(約9000円 )ということだから、
370元は、ひと月の給料の半分にあたるということ。おかあさんが、十分の一からでも
良い位という意味がようやくわかったけれど、日本に帰ってからじゃね。
呼ばれて、急いでバスに戻った。橋の上の値切り修行は、
これが、全部で10分位の間のことだったのだ。
目くるめく時間だった。
注: 「お嬢はん」の話を、家へ帰って主人と娘達にして、
「調子に乗って」と、バカにされたのは、言うまでもない。
でもそれは、「おかあさん」が、きっと人を苗字で呼ぶ
よそよそしさを嫌ったからだったろうと、思っている。
ついでに上手に持ち上げて」「くれたのだ。
夕食へ
少し離れた別の村での夕食
食事の間にも歌いながら、お酒をのませてくれる。
味は、日本酒に似ていたと思うけれど、
結構強かった。
ここで、特に驚きつつ、おいしかったのは、
日本にもきっとこの組み合わせの食べ物はある、
という気がするものだった。「高菜そっくりの」、あるいは、
「高菜の」お漬物と、ゴマと、もうひとつ、それが何かを
忘れたのだけれど、を炒めたものだ。
お隣にいた男性、Kさんも、「これは、うまいねぇ。ご飯に載せて
食べたらおいしいだろうねぇ。」と言いながら、
何回も食べていた。
この三江あたりのトン族は、お正月にもちつきをする
ということも本で読んだので、何だか、更に
身近な気がしたものだった。
食後には、彼女達が、又歌を歌ってくれる。
それが、本当に上手で、きれいなのだ。
独唱になったり、輪唱になったり、歌によって、自然に形を変えつつ、
歌っている。ものの本によると、これは、「ポリフォニー」
という形式の歌い方なのだそうだ。そして、トン族は、その
ポリフォニーがうまいとのこと。
空港で、自己紹介の時に、一人の男性が、
「前に他の所への旅で残念な思いをしたので、今回は、
歌詞をコピーして人数分持ってきました。」と挨拶していた。
名古屋から参加のAさんだ。その時は、わかるようで
わからなかったのだけれど、その意味がやっと、実感出来ることになる。
練習もしていないのだけれど、私達も歌詞を受け取り、
歌でお返し、することになった。
これなら、知っているかも、と、最初に選んだのは、
千昌夫の「北国の春」。でも、聞いたことは、ないらしい。
中国でも人気、とは言ってもさすがにこんな山奥までは、
伝わっていないのだ。バラバラに歌い始めて終わる
という、散々な返歌になった。
それに引き換え、彼女達が、次の歌を歌い
出すのは、早い。
歌詞カードのネタは、すぐ切れてしまった。
それで、「春」とか「ちゅーりっぷ」とか、皆んなが
知っている小学唱歌を次々に歌った。