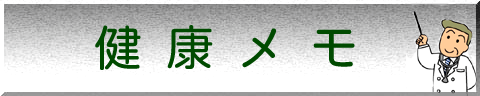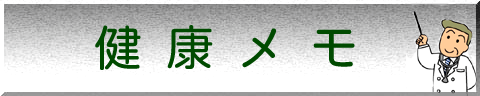■眼瞼下垂
まぶたが下がってうっとうしいと感じておられる方が最近増えています。テレビでもそういう話題が取り上げられ、肩こりや頭痛の原因の一つになっていると知られるようになり、その治療を希望される患者様が、形成外科によく来られるようになりました。
開きにくくなった目を一生懸命に開けようとすると、額の筋肉や首の筋肉が緊張したりします。そうした交感神経優位の状態が、肩こり、頭痛 、眼精疲労、不眠、うつ状態などを引き起こします。また、視野が狭い状態は日常生活とか車の運転などにも不便を来しますし、また額の皺(しわ)が目立つこともあります。
まぶたが垂れて十分に目が開かない状態を「眼瞼下垂」といいます。その中で加齢に伴う眼瞼下垂は「老人性眼瞼下垂」と呼ばれます。老人性眼瞼下垂には、細かく分けると二つのものがあります。一つは、「眼瞼皮膚弛緩症」であり、もう一つは「腱膜性眼瞼下垂(狭義の老人性眼瞼下垂)」です。
1)眼瞼皮膚弛緩症
加齢に伴いまぶたの皮膚が緩んで余ってきて、睫毛(まつげ)に皮膚がかぶさってくるような状態で、重度になると睫毛全体が皮膚で隠されてしまいます。この様な状態に対しては、上まぶたの皺取り手術を行います。すなわち、余った皮膚(そのすぐ下の眼輪筋という筋肉も)を切除する手術です。その際に通常は自然な二重まぶたをとなるように仕上げます。傷痕は、二重の線で隠れます。
2)腱膜性眼瞼下垂
まぶたには瞼板という板状の軟骨があり、それに腱膜というスジ状の膜がついています。まぶたを持ち上げる筋肉(上眼瞼挙筋)が働くと、その腱膜が引っ張られて、まぶたが持ち上がります。腱膜性眼瞼下垂とは、加齢に伴いその腱膜が引き伸ばされてたりはずれたりして、まぶたを持ち上げようとする筋肉の作用が瞼板に十分に伝わらないために、目が大きく開けられない状態です。
その治療には、腱膜を瞼板に固定し直す腱膜前転固定術と上眼瞼挙筋をつめる眼瞼挙筋短縮術という手術があります。多くの場合に皮膚も余っているため、皮膚も切除してやはり二重まぶたになるようにします。
眼瞼下垂の治療は、比較的短時間で高い効果の期待できるものが多いです。まぶたが軽くなり、うっとうしさが無くなったという改善のみならず、若返ったとして喜んでくださる方もあります。今後高齢化社会が進行するにつれて、この治療に対する人々の関心が更に高まってくると思います。状態によっては健康保険で治療が可能な場合もあります。「私は眼瞼下垂では?」感じておられる皆様、形成外科でご相談ください。
■けがの応急手当
秋本番となり運動会、スポーツ大会が各所で開催されます。健康の維持、増進ためにスポーツをすることは望ましいことですが、スポーツにはケガがつきものです。今回は、万一ケガを負ったときの為に応急手当の方法ついてお話しします。
Q:切り傷、擦り傷の手当について教えてください。
A:傷口が汚れているときは、水道の水できれいに洗って汚れを落とします。そして無色の消毒液(オキシドール、ヒビテン、マキロンなど)があれば、それで消毒します。色の付いた消毒薬を用いると、後に病院での診察の際にキズの状態が観察できなくなってしまいます。赤チン、イソジン、キズドライなどおすすめできません。
傷口から出血している場合には、ガーゼやハンカチ、タオルなどを当ててその上から手か包帯で圧迫します。また手足であれば、心臓より高い位置にすると止血しやすくなります。キズより心臓に近い場所を縛って病院に来院する人がよくいますが、縛ったためにかえって出血が多くなったり、血行を悪くする場合がありますのでしないでください。圧迫しておくことが一番です。だいたい10分間押さえていれば、大概の出血は止まります。それでも止まらないような場合には、圧迫したまま即座に病院に行くべきです。
Q:トゲを刺したなど刺し傷の場合にはどうしますか。
A:トゲを刺せば何とかすぐに引き抜きたいと思って抜こうとします。それでやったけれども全部抜けないから病院に来られる方が多いです。しかし、これを抜くのに麻酔して切開して探すということになるのですが、なかなか簡単にいかない場合もあります。できれば、容易に除去できるもの以外はご自分で抜かないでそのまま病院に行く方がよいです。トゲが血管の中に入って心臓に回ってしまうなどということはまずないので、極度に心配する必要はありません。足の裏にさびたクギなどを指した場合には、破傷風となるおそれがありますので、その予防のため病院で注射をすることが望ましいです。
Q:捻挫や脱臼、突き指、骨折などの手当についても教えてください。
A:これら骨、関節、筋肉、腱などの損傷に対する応急処置としてRICEというものがあります。
・ RーRest(安静):患部を動かさないことです。よく突き指で指を引っ張ると良いと思っている人がありますが、指を引っ張ってはいけません。指の脱臼の場合には引っ張って戻しますが、素人は止めたがよいです。
・ IーIce(冷却):氷や冷水、アイスパックなどで患部を冷やします。ただし、冷やしすぎによる凍傷には注意が必要です。
・ CーCompression(圧迫):スポンジやタオルで患部に当てて軽く包帯を巻きます。腫れを防ぐ効果があります。
・ EーElevation(挙上):患部を心臓より高く挙げます。血液の環流をよくして腫れを防ぎます。
これらの応急処置をした上で専門家である整形外科にかかることが望ましいです。
Q:頭を打った場合には、どうしたらよいでしょうか。
A:頭をやや高くして静かに寝かせます。意識障害があるかどうかをみることが非常に大切です。チェックするべきことは
・ 名前、生年月日が言えるか
・ 手足をつねって反応があるかどうか
・ まっすぐ歩けるか、麻痺がないか
・ 顔色はどうか
・ 強い頭痛がないか。
・ 耳や鼻から液がでていないか
等です。これらに該当する場合には、病院にかかるべきです。(専門は、脳神経外科です。)これらに異常がない場合、3〜5時間ぐらい様子を見ていて変わりがなければ心配ないでしょう。打ったところにコブがあれば、ぬれタオルなどで冷やすだけでよいです。
Q;鼻血の場合にはどうしたらよいでしょうか。
A:あわてずにイスに座ります。小鼻を親指と人差し指でつまんで押さえます。(10分〜15分ぐらい)それでも止まらない場合には、ガーゼを鼻につめ鼻の上を冷たいタオルなどで冷やします。鼻につめたガーゼは30分ぐらいはそのままにしておきましょう。鼻の打撲で外見上曲がっていたり凹んでいたり等変形ががある場合には、骨折が疑われますので、病院に行ってください。(専門は、耳鼻科、形成外科です。)
今まで誤った応急手当をしていませんでしたか?止血のためにひもで縛ったり、あわててトゲを引き抜いたり、突き指で指をひっぱたり・・・。正しい応急処置を知ってケガを悪化させないようにすることが大切です。それから早めに専門医の診察を受けるようにすることです。
■外反母趾について
- Q 外反母趾とはどういったものでしょうか。?
- A 足の親指(以下「母趾」)が中足趾節関節(付け根の関節、以下「MTP関節」)で外側に「く」の字に曲がる病気です。余りひどくなると母趾が内側に捻れて第2趾を外側に押し除けたり、第2趾の下に潜り込んで押し上げ第2趾のMTP関節を脱臼させます。
変形以外に、「く」の字の角の部分(=母趾のMTP関節内側部)が赤く腫れ、靴を履くと当たって痛みます。足の裏の第2、第3趾の付け根にもタコができて痛むことがあります。頭痛や腰痛を併発する人もいます。
- Q 外反母趾の原因はなんでしょうか。
- A 外反母趾は戦前の日本には希有な病気とされていました。鼻緒のある下駄や草履が外反母趾の発生を防止していたようです。戦後、大多数の人々が頻繁に靴を履くようになり、特にハイヒールがファッションとして流行してくると、外反母趾の数も急増してきました。
現在では特に珍しくはなくなり、一般の人にもポピュラーな病気になりました。女性には男性に比べ十倍以上多く、ハイヒールやパンプスなどの靴が強く関与しているようです。
しかし、一生涯、靴を履かない様な地域でも欧米の10分の1程度の発生頻度で外反母趾が見られることから、先天的な病因もあるようです。従って、一定の外反母趾になりやすい素因に、靴などの後天的要因が加わって外反母趾が発症すると考えられます。
- Q どういう治療がありますか。
- A 最近、外反母趾を防いだり、足の痛みをとるいろいろなグッズが出回っていますが、これらは予防的意味はあるでしょうが、いったん足が変形するとこの治療法ではほとんど治りません。
治療が必要な人というのは、指が何度曲がっているからではなく、靴を履いて痛いなど、生活に支障がある人です。足の形が変形していても、痛くないし、何とか履ける靴もあるし、生活に支障がないなら治療の必要はありません。その人の症状や生活様式にもよりますが、まずはハイヒールを履かない指導、そして足に合った靴選びの指導をします。治療としては、手術による治療が主となります。
手術は、外反母趾の進行がひどくて、痛みのため歩行に困難をきたすとか、どうしても治したいという患者さんの場合に、よく相談してから決めています。手術法でよく行われているのは、中足骨という骨を切って矯正した位置で固定を行う術式です。これは、1〜2週間の入院が必要となります。
そのあと数週間、踵を中心に歩くようになります。骨癒合するまでは、6週間前後を要します。介助者がいてベッド上の安静を保てる方の場合は、両足を同時期に行うことも可能ですが、通常はまず片方を行い、満足度が高い場合にもう一方を行います。他にも変形に応じて様々な手術術式を選択しています。
- Q 予防法はありますか。
- A 外反母趾を防ぐには「ハイヒールを履かない」「きつい靴・小さい靴を履かない」が基本です。人間の体は、基本的に踵を上げて歩くようにはなっていせん。ふつうに立っているときは、踵に5割以上の力が加わって、足の親指には3〜4割ぐらい、小指のほうに1〜2割ぐらいかかるような構造になっています。ハイヒールはそれを逆転させているので、足の先に余計な負担がかかってきますので、足にとって良くありません。
もともと外反母趾になりやすい因子をもっている人(例えば祖母も母親も外反母趾だという人)が、足に合わない靴を我慢して履きつづけて外反母趾になった場合、ハイヒールを履くのをやめても、変形が進行していくといわれています。外反母趾になる因子をあまり持っていない人なら、若いときに無理な靴を履いて外反母趾になっても、ハイヒールや小さな靴を履かなくなれば、足の変形はそこでストップします。いずれにしても足先に負担をかけない靴選びが大切です。
外反母趾は、一度なってしまったら進行するか、もしくは現状維持で、完治はしない病気です。よく病気は早期発見が大切といいますが、外反母趾も早期予防が最も重要であるといえるでしょう。
-
-
- ■ 耳介の変形
- 病院において聴覚器官としての「耳」と言えば、耳鼻咽喉科にかかりますが、顔の側面に突出した部分は「耳介」と呼ばれ、この部分の異常ということでは、主に形成外科が扱っています。また、マスクやメガネをかけるという役目も担っています。ほとんどは生まれつきの異常ですが、外傷によるものもあります。
- 立ち耳
耳介が著しく立ってダンボの耳のような状態です。欧米では非常に嫌われていますが、日本人は気にしない人が多いです。しかし、左右差が顕著にある場合などには治療が行われます。耳介の裏面から皮膚を切開して軟骨を出し、正常に近い軟骨の形にするように浅い割を入れて、適当な丸みを持たせて縫合します。
折れ耳
耳介の軟骨が、支柱としての役割を果たせずに折れ曲がった状態です。指で持ち上げれば正常の大きさがあります。立ち耳と正反対のように思えますが、治療は同じような方法で行います。
スタール耳
これは、スタールという人が報告したためこういう名前が付いています。後上方に細長く伸びる折れ癖のついた軟骨が存在するために、獣の耳の様な印象を受けます。この変形した軟骨を切除して、軟骨の形を整える手術をします。
埋没耳(袋耳)
これは日本人に多い変形で、手術法も日本人によって確立されました。耳介の上半分が、側頭部の皮膚の中にできたポケットに入ったような状態になっており、手で引っぱるとほぼ正常に近い耳の様に見えます。治療は、耳を引き出すようにしてこれが元に戻らないように、耳の付け根を絞めるように皮膚を移動する手術を行います。
副耳
耳介の近傍にイボのように突出した余分な膨らみが見られるものであり、その中に軟骨組織を含んでいることが多いです。治療はこれを切除します。
耳瘻孔
耳介そのものは正常ですが、耳介の付け根付近に小さな穴(瘻孔と呼ばれる)があるものです。この穴は行き止まりになっています。しばしば、炎症を繰り返すためこの瘻孔を切除する治療を行います。
耳垂裂
耳垂とは耳たぶのことです。生まれつき耳垂に切れ込みがある状態です。またピアスの重みで耳垂が切れた場合もこれに近いものです。手術は、切れ目をでこぼこがないように縫い寄せます。
柔道耳
レスラー耳とも呼ばれ格闘技をやっている人に起こる外傷性の変形です。内出血を繰り返すうちに血のかたまりが線維化を起こして、カリフラワーのような耳になってくるものです。治療は、線維組織で変形した軟骨を作り直します。
小耳症
程度は様々ですが、生まれつき耳介が小さいものです。ピーナッツの殻ぐらいのようなものが多いです。治療は、自身の肋軟骨を採取して耳の骨組みを作り、側頭部の皮下に埋込み、後からこれを持ち上げるように何回かにわたる手術を行います。
これ以外にも様々な耳介の変形があります。耳の形で気になることがあれば、形成外科でご相談ください。
-