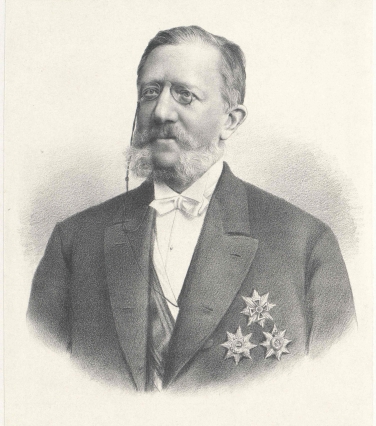ドヴォルザークの深謀遠慮
第5章 ドヴォルザークとドイツ語、そして言語統制

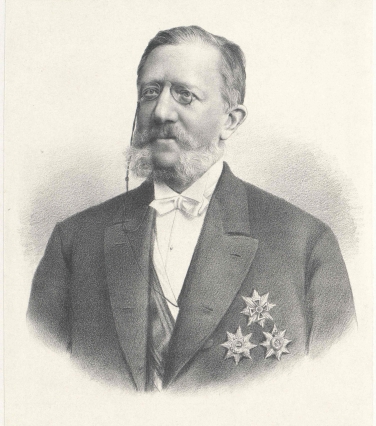
アントニーン・リーマン カール・フォン・シュトレマイヤー
ドヴォルザークとドイツ語
13歳のときドヴォルザークはズロニツェの肉屋の修業に行かされ、その修行或いは肉屋業にドイツ語が必須だったこともあり、そこで入学した職業専門学校の校長先生アントニーン・リーマンがドイツ語の教師であっただけでなく、教会のオルガニストでもあった、ということが多くのドヴォルザークに関する文献に書かれているのですが(クルト・ホノルカ著『大作曲家
ドヴォルザーク』 など)、これはデイビット・R・ベヴァリッジによって誤りであることが指摘されています。
「1853年、ドヴォルザークはズロニツェに移って叔父と叔母と一緒に暮らし、そこの小学校に通ったのですが、学校のレベルはやや高く、しかも授業はドイツ語で行われ、おそらくドイツ語の知識が不十分だったためか、彼はそこで早くに学校を中退したようです。しかし彼はズロニツェに3年間留まり、主にアントニーン・リーマンの指導の下で音楽、とりわけオルガンとピアノの演奏家としての腕を磨き、それに加えて作曲も初めての挑戦をしました。(中略)ドヴォルザークに関する文献では、彼がズロニツェで肉屋の見習いとして働き、職人の資格を取得したという主張がよく見られます。これは誤りであることが証明されていて、ドヴォルザークの両親と兄弟が1855年にズロニツェに移住してきた後、彼はそこで父親が始めた肉屋の仕事を手伝ったと考えられます。(中略)1856-57年の学年で、彼はプラハの北53マイル、ザクセンとのボヘミア国境に近い、当時はほぼ完全にドイツ系住民が住んでいた地域のベーミッシュ・カムニッツ(ドイツ語名:現在のチェスカー・カメニツェ)という小さな町のドイツ人家族と一緒に暮らしました。どうやら彼の両親は、オーストリア帝国で下層階級より上の人々と定期的にコミュニケーションをとる必要のある人にとっては必須だったドイツ語を学ばせるために彼をそこに送り込んだようです。ここで彼はドイツ人向けの学校に通い、そこでの成績はすべての科目で「sehr
gut」、つまり最高の成績を収めました。」( ANTONÍN DVOŘÁK: HIS LIFE, HIS MUSIC, HIS LEGACY
by David R. Beveridge )
ズロニツェ出身の教師、オルガン奏者、作曲家であったアントニーン・リーマンが同時に職業専門学校の校長先生だったかどうかは判明しません。アントニーン・リーマンについてのチェコ語のWikiには、ドヴォルザークがプラハのオルガン学校に通うまで約3年間ヴァイオリン、ピアノ、オルガンの演奏を教えたとはありますが、職業専門学校の校長先生だったことは書かれていません。ただ、リーマンからドイツ語も教わったことは推測できるかもしれません。なお、リーマンの元ではないにせよ、ズロニツェで肉屋の修行をしていたことは確かで、ズロニツェ滞在中の最後の年の1856年11月2日付で肉屋組合から2年間の修業期間に肉屋の仕事を学んだとする修業証書が残されています。(
渡鏡子著 『スメタナ/ドヴォルジャーク』 )
カレル・V・ブリアンによると、ズロニツェには聖母被昇天教会でオルガニストだったアントニーン・リーマンの他にヨゼフ・トマンという校長先生からも何かしらを学んだようです。トマンは聖歌隊を指導していた声楽家でしたが、何の校長だったのかブリアンは記していません。さらにリーマンはドヴォルザークにドイツ語を覚えさせようとできるだけのことをしたが、あまり上手くいかなかった、また、ズロニツェからベーミッシュ・カムニッツに行ったドヴォルザークは一年間ドイツ人の粉屋に住み込み、ドイツ語補修学校の3学年に入学したと書いています。しかし、この頃になるとドヴォルザークの両親は、リーマンなどからの説得もあって、息子を肉屋することを諦め、音楽家になることを認めていたようです。
その後ドヴォルザークは1857年にプラハに行ってオルガン学校に入学し、バッハ、ヘンデルのオルガン曲から通奏低音や和声学を学びます。また同時に教会関連の一般学校に通ってそこでもドイツ語で授業を受けました。さらにはドイツ系のチェチーリア協会管弦楽団にヴィオラ奏者として参加してベートーヴェン、シューベルトをはじめとする古典音楽や当時の先端音楽であるワーグナー、リストらの作品に触れています。しかし2年後、オルガン学校の卒業成積書における評価はあまり芳しいものではなく、それはドイツ語力が足りなかったからと推測されています(
クルト・ホノルカ著 『大作曲家 ドヴォルザーク』 )。
当時のプラハはウィーンに次ぐオーストリア・ハンガリー帝国第2の都市とされ、チェコ人が人口の大半を占めていました。1900年の人口統計によるとオーストリア全体でドイツ系38%、ボヘミア・モラヴィア・スロバキア系23%(約600万人)に対して、プラハではドイツ系は10%、ボヘミア・モラヴィア・スロバキア系が90%でした(
江口布由子著 『1897年のバデニー言語令事件:オーストリア社会民主党およびキリスト教社会党の指導層の動静を中心に』 )。
プラハにおけるチェコ人の人口は相対的に多かったとはいえ、少数派のドイツ人が社会的、政治的に優位にあり、商人、公務員、教養人など市民の大半はチェコ人を含めてドイツ語を使用していました。これは17世紀に起きたハプスブルク=カトリック勢力とボヘミアのプロテスタント貴族との間で勃発した戦闘「白山の戦い」でボヘミア側が敗北したことに遡るとされています。この敗北でチェコ人知識階級の中核およそ3万6千世帯が追放されるか、もしくは自発的に国外への移住を余儀なくされヨーロッパ各国に散らばる一方、プラハはドイツ人の都市と化し、行政機関、社交界などにおいてドイツ語が公用語として用いられていきます。中産階級以上が通う教育機関ではドイツ語が強制され、チェコ語は最下級の教区学校などで教えられるだけとなりました。国外に逃れた知識人の中には多くの音楽家が含まれていて、ヨーロッパ各地でチェコ出身の音楽家が活躍する素地ともなったのでした(付録『チェコの作曲家たち』参照)。なお、後にドヴォルザークはこの「白山の戦い」を題材とした賛歌『白山の後継者たち』を1872年に作曲しています(第1章参照)。
ドヴォルザークはこの『白山の後継者たち』に続き、1877年に『スターバト・マーテル』を作曲します。3年後にプラハで初演された後、1883年イギリスのロンドン音楽協会がロイヤル・アルバート・ホールでこの曲を演奏するとオラトリオ愛好家の多いイギリスの聴衆は熱狂し、ボヘミアのオルガニスト兼音楽教師ドヴォルザークの名は一躍有名になります。ロンドンの楽譜出版社ノヴェロは直ちにドヴォルザークをロンドンに招くことになり、その年の3月には、ドヴォルザークは満員のロイヤル・アルバート・ホールの指揮台に立って『スターバト・マーテル』を指揮しています。
この英国行きに先立ちドヴォルザークは英語の特訓をしていて、その時「ドイツ語はうまくいかなかったから英語で勝負しよう」と冗談を言ったとされています。また、コンサートの後のパーティーで、出版社ノヴェロの社長ヘンリー・リトルトンと挨拶を交わすとき、ドヴォルザークは「ドイツ語をマスターしていないので英語で話しましょう。」と言ったとされていますが、この真偽は定かではありません。1885
年にドヴォルザークは英国のバーミンガムに滞在中(4回目の訪英)に書いたヨーゼフ・ズバティーに宛てた手紙に、「私はまだ英語がわからないので、ドイツ語で少し話さなければならず、リトルトン氏はそれを合唱団とオーケストラに英語に訳してくれました。」と書いていることから、やはりドヴォルザークの英語は挨拶程度のものだったと考えられます。ヨーゼフ・ズバティーは同じ年の春に3回目の訪英をしたドヴォルザークに同行した人物です。
ドヴォルザークはこの後、米国にまで行ってまたしても英語に苦労することになります、本書ではこのことについてはこれ以上は触れないことにします。一方、1882年6月11日の手紙でハンスリックはドイツ語の優れた詩によるヴォーカル作品を作曲するように、さらにはウィーンへの移住を勧めています。
「世界はあなたにもっと規模の大きな声楽作品を期待しています。しかし、それがドイツの詩から感じられ、それに基づいて作曲されたものでなければ、完全に満足することはまずないでしょう。ごく少数の聴衆のためにチェコ語のテキストだけを使って作曲することに固執すべきではありません。さもなければ多くの聴衆は貧弱な翻訳に嫌悪感を抱き、直ちにあなたの作品に対して歪んだ評価を下すでしょう。」
「私の意見では、プラハから離れたところに 1 〜 2
年住んだ方が、あなたの芸術的発展と成功にとって非常に有利になるでしょう。ウィーンが一番いいでしょう。( 中略
)これほど大きな成功を収めた後、あなたの芸術にはより広い視野、ドイツの環境、そしてチェコ以外のより多くの聴衆が必要なのです。」(エヴァ・ブランダ著
『ドヴォルザーク音楽の研究』: ミラン・クナ編 『ドヴォルザーク書簡集第5巻』から引用)
こうした提案は他の人からもあったようで、ドヴォルザーク夫妻がベルリンを訪れた後の1887年10月29日にフリッツ・ジムロックがブラームスに宛てて書いた手紙からもわかります。それによると、
「ドヴォルザークの妻は素晴らしいメゾ・ソプラノの声の持ち主なのですが、彼女は夫が国家主義者の争いにとても苦しんでいてプラハからウィーンに移住することを切望しているのです。しかし、まちがいなくウィーンが物価の高い都市であるため、そこで子どもたちを養うのが難しい、と言っているのです。」
なお、1938年、オタカル・ショウレクはこの手紙の引用を、著書『 Dvolřák ve vzpomínkách a dopisech
』(『回想と手紙におけるドヴォルザーク』)の中に掲載しましたが、その後、この引用した部分が熱狂的で非常に熱心なチェコの愛国者というドヴォルザークの望ましいイメージに適合しないことに気づいたようで、この本の
1951 年版ではその部分は削除されています( ベヴァリッジ著『ドヴォルザークとチェコらしさの概念』 )。
ハンスリック、ジムロックに次いでブラームスも同じようなことを書いていて、おそらくハンスリックほどあからさまではないながら、1887 年 11
月 7
日付のジムロックへの手紙の中で、ドヴォルザークにもう何年か前にウィーンに移ってほしかったと漏らしています。これらの人々、特に自身ボヘミアの起源を持つハンスリックからであってもドヴォルザークは説得されなかったのですが、ドヴォルザークが受けた圧力は過小評価されるべきではありません(
エヴァ・ブランダ著 『ドヴォルザーク音楽の研究』 )。
このように、ドヴォルザークはドイツ語をテキストとする声楽作品を作曲することやウィーンへの移住を勧められていましたが、結局どちらも断りプラハの南西60キロほどにあるヴィソカーという田舎町に住み続けました。ウィーンの物価高が理由のひとつとされますが、決して得意ではなかったドイツ語で暮らすことへの不安、ドイツ語やその文化に精通していないのにドイツ語の詩やリブレットに音符を付けることへのうしろめたさなどがあったのではないでしょうか。では次に、そういったドヴォルザークが暮らしていた言語をめぐる環境について述べていきたいと思います。
言語統制
1800年代前半までのプラハは、17世紀に起きた「白山の戦い」によって多くのチェコの知識人階級が国外に逃れたとはいえ、チェコ系の人口比率はドイツ系に対して9対1くらいと圧倒的な多数派であったと推測されています(1900年の統計調査からの類推)。しかし、社会的、政治的優位にあったのはドイツ系であり、公的場面での使用言語はドイツ語に限定されていました。ところが、ドヴォルザークがプラハのオーケストラでヴィオラを弾いていた頃の1860年代半ば以降に起きた自由主義の流れに乗った政治的・経済的な規制緩和により、ドイツ系以外の民族、特にチェコ系民族による産業への新規参入の機会が増えていきます。第1章で触れたドヴォルザークに『モラヴィア二重唱曲集』の作曲を依頼したヤン・ネフは裕福なモラヴィア人商人であったことが思い出されます。
こうして経済的に重要な地位を占めるようになったチェコ系の人々は政治的にも発言力を増すようになっていきます。それに伴って、チェコ人居住地域におけるドイツ語の優位性に対する不満が噴出するようになり、道路標識をはじめ、レストランのメニュー、行政機関などでの使用言語について議会で度々論じられるようになります。チェコ系の議員団は時のオーストリアの首相であったエドゥアルト・ターフェ(第2次内閣1879-93年)に請願書を提出し、チェコ人宥和政策を取っていたターフェはその要請を受けて1880年4月に言語令を発します。その作成の中心人物だったのがこのターフェと司法大臣だったカール・リッター・フォン・シュトレマイヤーで、その名を取って「ターフェ=シュトレマイヤー言語令」と言われています。この法令では、ドイツ語とチェコ語のふたつの州言語のうち、内務及び司法省に関係するボヘミアおよびモラヴィアへの出先機関の公務員は、当事者が口頭あるいは書面で使用した言語で対応することを義務付けるというものでした(
江口布由子著 『1897年のバデニー言語令事件 : オーストリア社会民主党およびキリスト教社会党の指導者層の動勢を中心に』 )。
この条例は、チェコ人にとっては歓迎すべきではありましたが、プラハなど主要都市を含むボヘミアとモラヴィアのチェコ人居住地域におけるチェコ人とドイツ人の間の亀裂を拡大したという事実も見逃すことはできません。
なおこのシュトレマイヤーなる人物は1870年から1879年にかけては文部大臣を務めていまして、実は音楽史上で2度もその名を残しています。まず、1877年にドヴォルザークに助成金を手渡してします(第1章の『モラヴィア二重唱曲集』参照)。2度目はアントン・ブルックナーから交響曲5番の献呈を受けているということです。ブルックナーはこの曲の筆写譜の最後に日付(1878年11月4日)と署名を入れ、文部大臣シュトレマイヤーに同日付で献呈しているのです。
当時ブルックナーは、ウィーン音楽院の音楽理論教師の職を引き受けてから(1868年)、自身の生活水準は悪くはなかったにもかかわらず、創作の時間が無いという不安からウィーン大学の職に就くことを求めていました。しかし、同大学の主任教授だったエドゥアルト・ハンスリックら反ワーグナー陣営からの妨害があったためにその希望はなかなか叶えられませんでした。そこで、ブルックナーは嘆願を行なうために文部省に足しげく通っていたのでした。1874年から4回も請願を行なったとされ、文部大臣シュトレマイヤーの後押しもあってようやく翌年の1875年からウィーン大学で音楽理論の講義を講師として始めることができました。しかし、それは無給の名ばかり職だったとされ、ブルックナーのねらいは実現されませんでした。その最中の1878年に交響曲5番をシュトレマイヤー大臣に献呈したということは、3年前に講師になれたことへの感謝の印ということなのか、或いは給与が貰えるようにブルックナーが袖の下として使ったのでしょうか。その想いが通じたのかブルックナーは1880年から晴れて固定給を受けるようになっています。但し、その時シュトレマイヤーは既に大臣職を辞任していました。ウィーン大学で講師になれたときにシュトレマイヤーの後押しがあったのは何故か、交響曲5番の献呈が何故なされたのか、今ひとつ明快な回答は得られてはいないようです。ブルックナーへの給与が与えられるように大学当局に働きかけたのは実は敵対していたハンスリックだったという説もあるようです。
話しを戻しましょう。この「ターフェ=シュトレマイヤー言語令」が発令されたのが1880年4月でした。ドヴォルザークが交響曲6番の作曲を開始したのが同年8月であったことを思い起こすと、そこには、ドヴォルザークがこの条例を意識したかどうかに関わらず、この条例が巻き起こしたチェコ人とドイツ人との軋轢は間違いなくプラハの新聞・雑誌社の論陣にまで及ぶことになり、その最中に初演されたドヴォルザークの交響曲第6番はまともにその煽りを受けることになりました。つまりそのレビューの中にも明らかな一種の領土意識といったものが生み出されていったのでした。エヴァ・ブランダはこう述べています。
「(この交響曲は)チェコ人とドイツ人の間の緊張した関係の真っ只中に誕生しました。ストレマイヤー言語条例の後、何がドイツ語で何がチェコ語なのかを正確に定義することがこれまで以上に重要になりました。(
中略
)ドヴォルザークが最終的にこの分断のドイツ側につくかもしれないという脅威は、多くのチェコの批評家にとって常に非常に現実的な問題だったのです。」
「この作品のプラハ初演は、ドヴォルザークが出版された楽譜にドイツ語のタイトルとテキストのみを掲載することを明らかに許可したということを理由に、チェコのマスコミではドヴォルザークに対する否定的な見方がしばらく続きました。ドヴォルザークがドイツ人の聴衆を優先し始めているのではないかと疑ったチェコの批評家たちは、すぐに作曲家の目を国内の聴衆に向けるよう仕向けたのです。これらの批評家は、交響曲の背景にある「ウィーン」を隠して「チェコ」の要素を強調することで、この作品を利用して民族主義的な狙いを促進しようとしました。」(
エヴァ・ブランダ著 『ドヴォルザーク音楽の研究』 )
*このドイツ語の使用はおそらくベルリンに店を構えるジムロックの当たり前のやり方にドヴォルザークが従ったためと考えられます。『モラヴィア二重唱曲集』でドヴォルザークがジムロックにチェコ語の記述について苦言を呈したのは1885年ですから(第1章参照)、この1880年の段階ではまだドヴォルザークは大人しくしていたのでしょう。ドヴォルザークには何の意図もなかったはずです。
また、1883 年のブルノでの演奏後に雑誌『ダリボル』に書かれた記事では
「このオーケストラの傑作が純粋なチェコ語で私たちに語りかけてくれるという事実に、私たちチェコ人は至福の状態にありました。( 中略
)この交響曲の言語は一種の洗練されたチェコ語であり、ドイツ人ですらそれに抵抗できませんでした。」(1883年3月21日)として、
「1880年代初頭の政治的緊張とドヴォルザークの国際的名声の高まりにより、チェコの批評家はドヴォルザークが自分たちの作曲家であると主張することに熱心になり、オーストリア・ドイツの伝統に準拠していると解釈できる作品に対してチェコのラベルを貼ろうとしました。」(
エヴァ・ブランダ著 『ドヴォルザーク音楽の研究』 )
*参考文献の一覧は≪目次≫をご覧ください。
≪ 前のページ ≫ ≪ 目次に戻る ≫
≪ 次のページ ≫