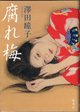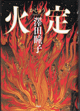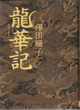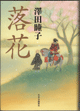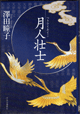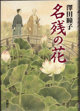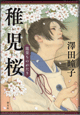| 11. | |
|
「師走の扶持-京都鷹ヶ峰御薬園日録-」 ★★ |
|
|
2018年05月
|
御薬園預と禁裏御殿医を兼ねる藤林家へ3歳の時に預けられ、京の洛北にある御薬園で育った女薬師=元岡真葛(まくず)を主人公とする“京都鷹ヶ峰御薬園日録”シリーズ第2弾。 まだ若い女性ながら、その育った環境と養父の藤林信太夫の配慮から、薬師といっても医術にも造詣の深いというのが、元岡真葛の主人公像。 そんな真葛は現在、御薬園で信太夫を継いだ義兄の藤林匡と初音夫婦と共に暮らしています。 ワーキング・ウーマンなど殆どいなかった時代、周囲の思惑から一時気持ちを揺れ動かすことはあるものの、長い目で見れば自分の進むべき道をはっきり見据えて揺るぐことがない。そんな真葛の凛とした佇まいが、本シリーズの魅力といって過言ではありません。 また、そんな真葛だからこそ本書に登場する、病気等に苦しむ人たちに寄り添おうという心も優しく温かい。 本シリーズ、これからも続きそうです。ファンとしては嬉しい限り。 「糸瓜の水」:小野蘭山の共をして常房総三州での採草行を終えた真葛、小石川御薬園を訪ねて行ったところ、対立する岡田家と芥川家の争いに巻き込まれ・・・。 「瘡守」:京への帰途、熱田に至った真葛は瘡毒に苦しむ女房と出会いますが、女房が苦しんでいるのは別のこと・・・。 「終の小庭」:京への帰途の共となった喜太郎、小野蘭山の元を辞して娘夫婦と同居する予定になっているのですが・・・。 「撫子ひともと」:義姉の初音が勝手に真葛の縁談を進めていると判り、真葛は初音と諍いするのですが・・・。 「ふたおもて」:御薬園出入りの薬種屋である亀甲屋の主人=宗平に不審な行動、その裏に年配の女性の陰が・・・。 「師走の扶持」:藤林家と疎遠な関係にある真葛の母の実家である棚倉家の老家令が突然、大殿に内緒で若殿の病気を診察して欲しいと藤林家に現れ・・・。 糸瓜(へちま)の水/瘡守(かさもり)/終(つい)の小庭/撫子ひともと/ふたおもて/師走の扶持 |