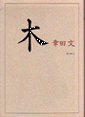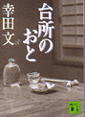|
|
|
|
|
2.闘 3.崩れ 4.木 5.台所のおと 6.きもの |
|
●「父 その死」● ★★★ |
|
|
2004年08月
2004/10/03
|
幸田文、生誕 100年記念として刊行された一冊。 やはり圧倒されるのは「父−その死−」。 もう一方の「こんなこと」は、日常の日々における父・露伴との日々を語った思い出の記。 「父−その死−」(1949年12月中央公論社刊) |
|
●「 闘 」● ★★ 女流文学賞 |
|
|
|
結核療養の病院を舞台に、医師、看護婦、患者、それぞれの葛藤、闘いをノンフィクション風に描いた作品。 お互いに直すため、直るため、また看護をする、という共通の目的をもっている訳ですが、多忙、苦痛、所詮ひとりの人間でしかない、ということが重なると、そこに繰り広げられるものはそれぞれ“闘い”であると言わざるを得ません。 時代的には古い作品ですが、文さんの文章のもつ臨場感に圧倒される思いがあります。まさにドキュメンタリーという印象です。 |
|
●「崩れ」● ★★ |
|
|
|
「木」「きもの」を読んだ時のような感動は、今回ありませんでした。ひとつには、本書の題材故のことだろうと思います。 |
|
●「 木 」● ★★★ |
|
|
1993/05/08
|
文さんの綴る文章の見事さに感動する思いでした。 刊行当時「木に対してよくもまああれ程の思いをもてたものだ」という書評がありましたが、私も全くの同感です。文さんにとって、木もまた生き物であり、その内に人間性までも備えた同胞だったかのようです。 |
|
●「台所のおと」● ★★☆ |
|
|
1995年08月
2000/06/03
|
読み始めてすぐ後悔しました。今まで本書はエッセイとばかり思い込んでいたのでした。短篇集だと判っていたら、もっと早く読んでいたのに。まあ、読み逃さずに済んで良かったです。 この一冊に収められた作品は、皆日常生活のささいな出来事を書き表したものです。それにもかかわらず、そこに書き出されている情感の豊かさ、深さには、溜め息つくばかりです。文さんの面目躍如というところでしょう。 台所のおと/濃紺/草履/雪もち /食欲/祝辞/呼ばれる/おきみやげ/ひとり暮し/あとでの話 |
|
●「きもの」● ★★★ |
|
|
|
うまいなあ、もう溜め息つく他ない、というのが読後感です。 着物を主題にしながらも、本書はるつ子という娘の、少女から娘へ、そして結婚に至る成長を辿るストーリィです。流れるように進む展開、言葉のひとつひとつ、文章のひとつひとつに細やかな人生の機微が含まれています。 |
|
●「ちくま日本文学005 幸田 文」● ★★★ |
|
|
2008/01/17
|
真に読み応えある一冊。 いずれの作品も文さんの人生が投影されていて、唸るような思いで読み続けました。 「勲章」は、結婚後の父・娘の置かれた状況の隔たりの大きさを描いて忘れ難い一篇。また「雛」は雛人形の飾りを描いて、気遣うことの深さに溜め息してしまった作品で、こちらも忘れ難い。 中篇「みそっかす」は、実母と姉の死、父と継母の確執の大きさを身に受けながら、頑なな性格故に自らもまた父母とぶつかり合うこと多かった中で成長していく少女(文さん)の姿を描いた名品。 勲章/姦声/髪/段/雛/笛/鳩/黒い裾/蜜柑の花まで/浅間山からの手紙/結婚雑談/長い時のあと/みそっかす/対談:樹木と語る楽しさ/(解説:安野光雅) |