| 5 温泉の化学 5-5 炭酸泉と炭酸水素塩泉 5-5-3 炭酸泉の特性 温泉分析表では遊離二酸化炭素(CO2)が1200mg/kgとか書いてあって期待したのに、浴槽のお湯はぜんぜんアワアワしてなくてがっかり。という経験をした方は多いでしょう。でもどうして? 分析表の数値は間違っていたのでしょうか?こうなってしまう理由は、遊離二酸化炭素が、ガス性物質(気体)で温泉に溶けているために、温度やお湯の扱いに非常に敏感なためです。 |
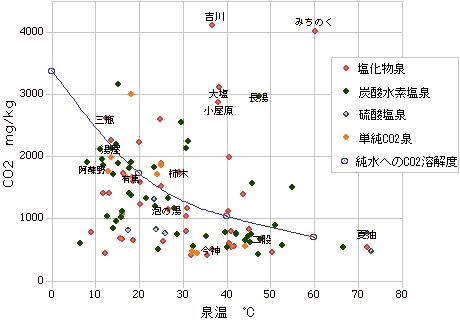
|
逆に、泉温32℃以下になると、炭酸泉の件数もCO2溶解度もぐんと増えてきます。しかし、この温度ではそのまま浴用にするには不向きです。浴槽で40℃くらいの温度になるように加熱して使用するのが一般に行われていますが、こうするとCO2の含有量は半分程度まで減ってしまいます。ボイラーの釜に接する部分では一時的にせよもっと高温になりますから、せっかくのCO2はほとんどお湯から抜け出してしまいます。これではまったくの台無しです。 また図をみると、CO2の溶解度曲線からはるかに離れたところに高濃度の炭酸泉がいくつか存在していることが歴然で、これはたいへん奇妙です。その理由はこうです。CO2に限らず、一般に気体の水への溶解度は圧力に比例して大きくなります。(註:塩化水素(HCl)のような溶解度の極端に大きなガスではあてはまりません)。温泉は地下深部(貯留層)では地上よりもはるかに大きな圧力がかかっています。湧き出す前の温泉にはたくさんのCO2が溶け込んでいられるのです。ところが、温泉を汲み出すと急に圧力が大気と同じ1気圧まで下がるので、溶け込んでいられなくなった過飽和のCO2は気泡となって分離し、ブクブクと泡立ちます。これの甚だしいときは沸騰しているように見えるので「泡沸泉(ほうふつせん)」とよびます。 しかし、長湯、小屋原、大塩、みちのく(青森県)、吉川(兵庫県)といった日本一クラスの高濃度炭酸泉では、上記のような説明ではちょっと納得できかねますね。これらはいずれも溶存成分の多い塩化物泉や炭酸水素塩泉ですから、このような濃い水溶液では、単純な溶解度だけでは表せない、炭酸ガスを水中に留める化学的なメカニズムが働いているのかもしれません。 |

図5-5-3-2 源泉のまま使用の小屋原温泉(38.2℃)では身体に大量の泡がつく
写っているのは腕です (photo by えびら)
|
天然炭酸水の利用 日本の養老の滝伝説をはじめ、世界各地には酒の流れる川の伝説がたくさん残っています。奈良時代に各地で編纂された「風土記」の中にも、「醴泉(こさけのいずみ)」や「酒水」という記述があります。これは炭酸泉のことではないかと解釈したのは、日本の温泉化学の開祖でもある江戸時代後期の宇田川榕庵(うだがわ・ようあん)です。昔のお酒はいわゆる「どぶろく」や「泡盛」の類で、発酵後に加熱・濾過をしないために沸々と炭酸ガスの泡がたつものでした。自然に湧出する炭酸泉の様子はこれとたいへん良く似ています。また、炭酸泉を飲用すると、体表部の血流が良くなって顔が赤くなり、少し酒に酔ったと同じような状態になります。 人工炭酸泉研究会 明治期になると、天然炭酸水の飲料が爆発的に流行しました。これは当時、世界的に流行したコレラの予防薬として広く信じられたためでもあるようです。最も古い発売は、京都の「山城炭酸水(1880年)」のようですが、有名なのは1888年に兵庫県川西市の平野鉱泉を用いて発売がはじめられた「三ツ矢平野水」で、これが後に「三ツ矢サイダー」となり現在に至っています。1889年には同じく兵庫県の生瀬炭酸泉を用いた「ウィルキンソン炭酸水」が発売になり、こちらも関西圏では今でもおなじみの商品です。しかし、どちらも現在では天然水ではありません。ほかにも、有馬炭酸泉、大塩炭酸泉(福島)などがあり、ヨーロッパを中心として海外に輸出されていました。 人工の炭酸飲料は、今では簡単に手に入ります。相当な山奥に行っても無人の野山に忽然と自販機が置かれていて妙な気分になったりします。でも、身体に良いからと意識して飲んでいる人なんて誰もいないですね。どうやら天然の炭酸水と人工のものでは根本的に違うところがあるようです。最近、炭酸泉の酸化還元電位(ORP)を調べた研究で、天然と人工では明らかな相違があり、天然炭酸泉では還元性を示すことが特徴であることがわかってきています(大河内ほか(2000))。これがどういう意味をもつのかは未だはっきりとはしませんが、興味ある結果だと思います。また、これも最近、天然炭酸水の疲労回復効果が高いことがわかり、ペリエの販売量が飛躍的にのびたということもあったそうです。 |