| 5 温泉の化学 5-4-3 火山性酸性泉(2) できかたもさまざま 酸性泉がお好きな方は、全国あちこちの温泉を入り比べられて、それぞれ微妙に「どこか違うな?」と感じられているでしょう。それは、酸っぱさ(pH)の差や味加減であったり、含まれる成分の濃さであったりします。このような違いは、もちろん、温泉の利用法(源泉のまま入れるか、加水しているか、など)にもよるところが大きいですが、温泉のできかたが左右していることはまちがいありません。この節では、酸性泉が火山体の内部でどのようにして作られているのか、いくつかのタイプに分けてご説明します。 |


図5-4-3-0 玉川温泉大噴(おおぶけ)の1995年(左)と1943年(右)の様子
単一の自然湧出泉としては日本最大の湧出量(概算9000L/min)を誇る強酸性泉(Type-B1)
約50年前と比較しても、外縁はいくぶん崩壊している湧出量はほとんど変わっていない
現在は事故防止のため柵で囲われ、源泉には近づけないが、昔はすぐそばまで行けた
酸性泉を分類する試み − 硫黄同位体のはなし |
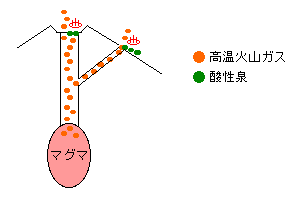
図5-4-3-1 Type-Aのモデル図
| Type-B:熱水型 これは火山ガスが直に地上に出ずに、火山体内部のどこかで地下水と接触して冷却、凝縮・混合して湧出してくるものです。2つのタイプに細分できますが、中間的なものも多いので、はっきりと区別できるわけではありません。 Type-B1:Cl-卓越熱水型 高温の火山ガスが、地表のごく直下まで達し、浅層を流れる地下水と混合してできあがります。火山ガスは膨大な熱量を輸送してきますので、地下水と混じり合ってもなお、高温かつ酸性の強い(pH1-2)温泉を大量につくりだすことができます。マグマ起源の物質が温泉水全体に占める割合は、5-20%と見積もられていますから、Type-Aを薄めたものと理解すればよいでしょう。有名な玉川温泉が代表例で、川原毛地獄、立山地獄谷などもこのタイプだと考えられています。このタイプの温泉はあまりに酸性度がつよすぎるせいか、利用されることなく放置されていることが多いようです。玉川温泉は世界的にみても珍しい利用例だといえます。 化学的な特徴は、Cl-/SO42-比が1以上、つまり硫酸成分よりも塩酸成分が多く含まれるということです。地上に達するまで液相を経験していませんから、水に溶けやすい HCl が失われないのです。また、酸性泉ができてから湧出するまでが間もなく、岩石と接触する時間が短いですから、高いpH に比べて、溶かし込む陽イオン成分が少ないのが特徴としてあげられます。よって、酸性−塩化物泉とか酸性−塩化物・硫酸塩泉という泉質名でよばれます。 ただし、前節でも触れたように、マグマの組成によっては当初から HCl をほとんど放出しない性質の火山もありますので、Cl-/SO42-比が1以下だからこのタイプではない、と一義的に決めることはできません。 |
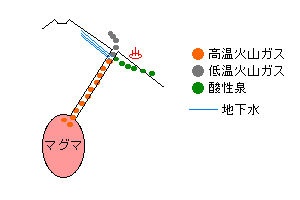
図5-4-3-2 Type-B1のモデル図
| Type-B2:SO42-卓越熱水型 これは日本の酸性泉で最も多いタイプです。川湯、酸ヶ湯、須川、蔵王、草津、万座、塚原など、名湯といわれるものが数多く存在します。Type-B1と比較すると、火山ガスと地下水が接触する場所が深いというのがポイントです。地下水じたいも深層水なので含有成分が比較的多いのに加え、酸性泉ができてから地上に達するまでの経路が長いですから、その間に周辺の岩石からたいへん多くの成分(陽イオン)を溶かし込んできます。とくに、Fe2+や Al3+ など、ほかの温泉では比較的少ない成分を大量に溶かし込むことができるので、陽イオンの大半はこれらの成分で占められていることが一般的です。 ただし、水に溶けやすいHClやHFは早い時点で除かれて、どこかに散逸してしまいますので、温泉水のCl-/SO42-比はかなり低くなっています。散逸した分は、火山性食塩泉に添加されているのではないかと考えている研究者もいますが、確かなことはまだわかっていません。それはともかく、このタイプの温泉は、酸性物質が主に硫酸からなっていることが特徴です。よって、泉質名では、酸性−Fe(II)・Al−硫酸塩泉であることが多く、旧泉質名で、明礬・緑礬泉というものが多くなっています。 さて、こうしてできた酸性泉は、当初は非常に高濃度の温泉でしょうが、地上に達するまでには、いろんなレベルで地下水の混合をうけて薄まったり、再び沸騰したりしなど複雑な出来事があることが考えられます。この間には、水に溶けにくい硫化水素(H2S)や二酸化炭素(CO2)が気相(蒸気)部分に濃集し、低温噴気として分離するようになります。これはまたType-Cの温泉の起源物質となっていきます。 地下に浸透した深層地下水は、ごくまれにですが、火山ガスと接触しないで単に加熱されただけで再び地上に湧出してくることがあります。こうなると、酸性泉のとなりにアルカリ性泉が湧出するという、たいへん奇妙な現象が起きることがあります。 |
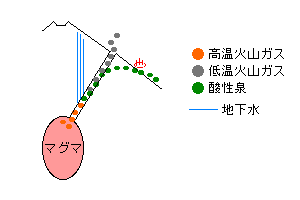
図5-4-3-3 Type-B2のモデル図
| Type-C:低温噴気型 いろいろな形の高温熱水から分離してきた低温の噴気でつくられるタイプです。低温噴気は水蒸気のほかには硫化水素(H2S)と二酸化炭素(CO2)を含むガスで構成されていますが、CO2は酸性泉の形成にはほとんど貢献していません。したがって、このタイプの主役はH2Sだけです。 Type-Bの温泉の周辺には必ずといっていいほど伴ってきますが、あまり利用されることはありません。むしろ、火山性食塩泉(3-3・4章)がつくられる過程で分離した低温ガスのほうが、分布が広くて重要なので、このメカニズムをもう少し詳しく説明します。 |
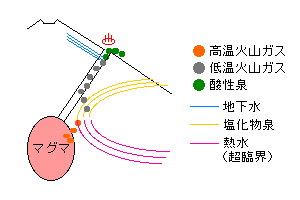
図5-4-3-4 Type-Cのモデル図
| 地下深部に浸透した深層水がマグマ(またはその固結した高温岩体)の近傍に達すると、水は高温・高圧の超臨界状態に入ります(熱水)。こうなると、岩石からいろいろな成分を取り込みやすくなるとともに、通常は水に溶けないガス成分も同時に大量に含有することができるようになります。実はこのガス成分は、マグマに由来するのか、それとも岩石に含まれていたものか、どちらなのか未だに決定的な証拠はありません。 超臨界の熱水は、地上にむかって上昇していくと、やがて温度・圧力が低下し、超臨界状態を脱します。つまり、液相と気相に分離し、沸騰を始めます。ここで熱水は、Na-Cl成分に富む火山性食塩泉と、水に溶けにくい H2S や CO2 を含む噴気に分かれるわけです。その深さは、概ね火山体の地下500mくらいではないかと推定されています。食塩泉のほうは地下の浅いところに透水性の良い地層があると、その内部をゆっくりと流動していきますが、噴気はそれとは関係なく、どこか岩盤に小さな割れ目があると、それに沿って勢いよく地上に噴出していきます。これが地表付近の比較的浅い地下水や表流水に吹き込んで、温泉ができるわけです。 地表付近の地下水は、比較的たくさんの酸素を含んでいますので、地下の無酸素状態では難しかったH2Sの酸化による硫酸の生成(前節(8)式)も、わりと簡単に起こるようになります。ただし、この反応はH2Sの2倍も酸素を必要としますので、通常は不完全に終了し、反応しきれないH2Sがかなりの分量残ることになります。こうやってできる酸性泉は、pH=2程度が限界で、Type-Bほどの強い酸性になることはほとんどないようです。このタイプの温泉は、岩石との反応時間が短いので、あまりたくさんの成分を溶かし込むことはできませんから、泉質名は単純硫黄泉(硫化水素型)となることが普通です。 ごくまれですが、Type-Cの酸性泉と火山性食塩泉とが再び出会い、混合して湧出することがあります。この場合、食塩泉の成分が、急激なpH変化で不安定になるため、沈殿や凝集をおこして様々の魅力的な色調の濁り湯を形成することがあります。なかなか面白い現象で興味がつきませんが、その詳細な原因はほとんどわかっていません。 |