| 温泉の科学特別編 |
| 温泉の科学特別編 |
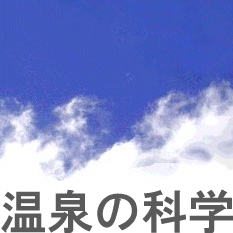 |
良い温泉を選ぶために −温泉ガイドの読み方− byやませみ その1 泉質と効能 その2 泉質による浴感の違い その3 新鮮な源泉であるか? その4 良いお湯の使い方をしているか? |
| さて今度はどこの温泉に行こうかな? どの宿に泊まろうかな? と温泉旅行の計画を練るのはとても楽しいことですが、反面とても苦しい作業にもなりがちです。それはどうしてかというと、たくさんある温泉地・宿泊・日帰り施設のなかから、どうやって良さそうなところを見つけたらいいのか、判断の拠り所がよくわからないからですね。 温泉関係の用語はなんだか馴染みがないし、ガイドブックにも詳しく書いてないし・・・頭の中がグルグル状態のそんなあなたのために、できるだけ易しく解説いたします。 良い温泉選びは、良い料理屋選びとたいへん似ています。今晩はちょいと奮発して旨いものでも食べに出かけようかなっていうときに、どういう基準でグルメガイドを読みますか? それは、1) 料理の種類、2) 好みの味付け、3) 素材の良さ、4) 料理人の腕、といったところですね。これを温泉にあてはめると、1) 泉質と効能、2) 好きな浴感、3) 源泉の鮮度、4) 適正な浴室環境ということになります。以下この順番にチェックしていきましょう。 |
| その1 泉質と効能 温泉はそれぞれに個性があり、どれ一つ同じものはないといっていいでしょう。これを大まかに区分したのが「泉質」です。今晩のおかずを決めるときには、栄養とか好き嫌いとか、その日の体調なんかを考えて選んでいますね。温泉も同じように、自分に合った効能とか浴感かどうかで、好きな泉質を知っておくことはとても重要です。 <泉質の分類> 温泉の泉質名はなんだか耳慣れなくてとっても難しそうです。でも、コツがわかれば、じつは案外簡単なんです。第一に、湧出地での温度で、以下のように分類しています(温泉法による規定) ・冷鉱泉 25℃未満の温度(泉温)で湧出しています。冷たいので「温泉」とは言い難い感じですが、温泉法で規定される成分を含んでいれば法的には温泉とみなされます(いわゆる規定泉)。ただし、含有成分がひじょうに豊富な場合もあり、温度が低いというだけで馬鹿にしてはいけません。浴用には加熱で使用されますが、源泉のままの冷たい浴槽もあれば試してみることをお薦めします。 ・温泉 25℃以上の泉温があれば法的には無条件で温泉とみなされます。26℃でも95℃でも、ひとからげに温泉とするのは無謀な気がしますが、注意するのは適当な温度で湧出しているかどうかです。60℃以上の高温泉は、多くの場合浴槽では水でうめられていますので、成分が薄くなっています。35℃〜50℃くらいの泉温では、そのまま浴用に使えるので、源泉のままを味わえる確率が高くなっています。 第二に、湧出したときの化学成分によって3種に分けられています(療養泉の分類) ・単純温泉 温泉水1kg(約1リットル)あたりに溶けている成分が1000mg(=1g)以下の薄い温泉です。薄いというとあんまり良くないことのようですが、身体への負担が少ないので、長期間の湯治に向いています。名湯には案外この単純温泉が多いのですが、反面「ほんとに温泉?」ていう不満が出やすい泉質でもあります。 ・塩類泉 温泉水1kg(約1リットル)あたりに溶けている成分が1000mg(=1g)以上の濃い温泉です。含まれる主な陰イオンよって、塩化物泉・炭酸水素塩泉・硫酸塩泉に分けられます。これに、主な陽イオンの種類をくっつけて、ナトリウムー塩化物泉、カルシウムー硫酸塩泉などと細分されています。おそばやさんで、陰イオンの方が麺の種類、陽イオンの方が具材とみなすと分かりやすいかと思います。天ぷらーそば、肉ーうどん、てな具合。塩類泉それぞれの違いについては後で。 ・特殊成分を含む療養泉 医療的にみて、こんな成分が効きそうだと目を付けられている温泉で、硫黄、鉄、アルミニウム、銅、二酸化炭素、放射能(ラドン・ラジウム)の6種類の成分と、pHのとくに低い酸性泉が指定されています。これらの名前は、塩類泉に含まれるときには泉質名のはじめに書かれます。含硫黄ーナトリウムー塩化物泉という具合。玉子とじー天ぷらーそば、みたいなもん。単純温泉に含まれるときは、単純硫黄泉となりますが、硫黄泉と略されることもあります。 あくまでもこれは湧出口の新鮮な状態のお湯を分析したときの数値をもとにしていますので、浴槽で使用されるときには幾分変化しています。とくに特殊成分は含有量が微量なことが多いので、お湯の使い方によっては全く失われている場合があります。で、3)に注意してください。 <温泉の効能> ガイドブックには温泉の効能がかならず書いてありますが、これを目安に温泉を選んでいる人は少ないんじゃないでしょうか?。もちろん療養目的に行かれる方にとっては重要な情報ですが、一般のガイド誌ではあまりにも説明が中途半端という気がします。医学的に個々の症状に対する効能はどうかと述べることは、私にはその知識はありませんから、ここでは一口に温泉の効能といってもいろいろある、ということだけ書いておきましょう。 ・共通効能(一般的適応症) 温泉ならばすべてに当てはまる効能で、神経痛・筋肉痛・冷え症・疲労回復・健康増進などです。入浴による温熱や浮力・水圧などの効果なので、お家の風呂でもおんなじですが、とくに温泉では効果が出やすいといわれています。温泉を選ぶ基準にはなりませんね。 ・泉質効能(泉質別適応症) 温泉の化学的成分が入浴によって皮膚表面から吸収されたり、飲用や呼吸で直接体内に取り入れられたりして作用するものです。温泉の泉質分類はまさにこのために行われています。個々の泉質が何に効くのかは、いろんなところに出ているので省略します。ただ、温泉の入浴効果は非常に緩慢なので、1〜3日の入湯ではほとんど効果は期待できない、とだけ言っておきましょう。 また、最近は飲泉も注目されています。飲用できる温泉は新鮮なものに限られ、飲泉設備のある宿は優良なところに当たる確率が高いので、ガイドに記載されていたら要チェックです。 ・慣習的効能 泉質効能は温泉の化学成分からほとんど自動的に決められているのですが、歴史的に長い伝統がある温泉では、固有の効能が言い伝えられています。なかには完全に迷信にすぎないものもありますが、医師の統計ではっきりと効果が証明されているものもあります。その温泉の何が効果を発揮しているかはほとんど解明されていないようですが、こんなところに注目して温泉を選ぶのも面白いかもしれません。 ・禁忌症 あまり注目されませんが、慢性の疾患や体調の良くない人、高齢者・幼児は注意してください。とくに、皮膚過敏な人の酸性泉・硫黄泉入浴、高血圧・腎臓病の人の塩化物泉の飲泉、下痢のときの硫酸塩泉・硫黄泉の飲泉は好ましくありません。 ※2001年3月掲載 |