| トップページへ | 研究指針の目次 |
目次
205.1 はじめに
205.2 観測データ
205.3 熱収支・水収支環境
(a) 気温鉛直分布
(b) 熱収支量の季節変化
(c) 熱収支・水収支量の年間値
(d) ボーエン比と気温の関係
205.4 樹木の間伐・倒木と林内環境の変化
(e) 林内気温
(f) 林内風速
(g) 土壌水分
205.5 気温上昇率
まとめ
参考文献
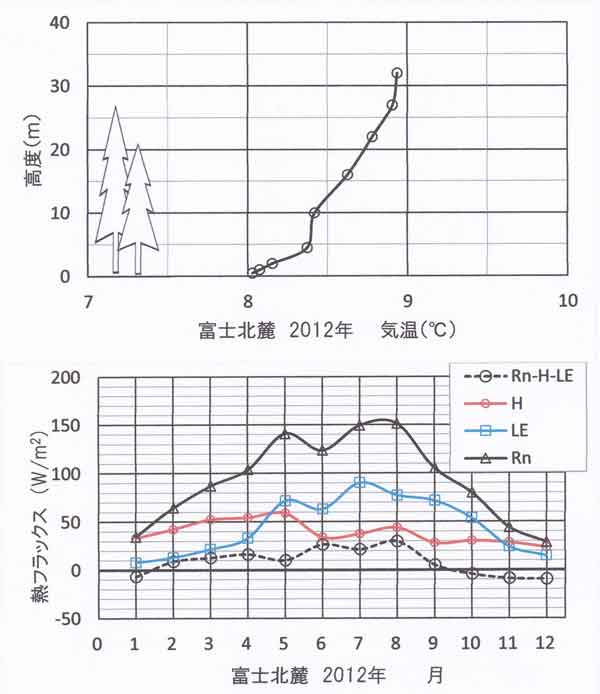

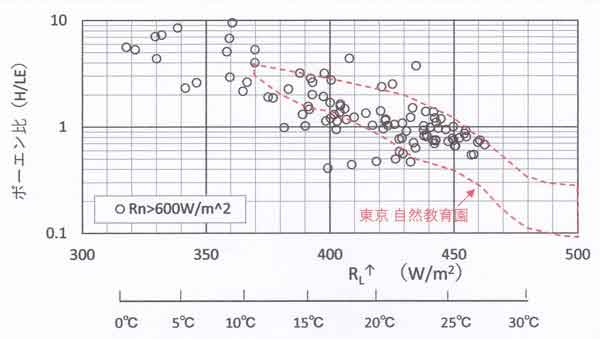
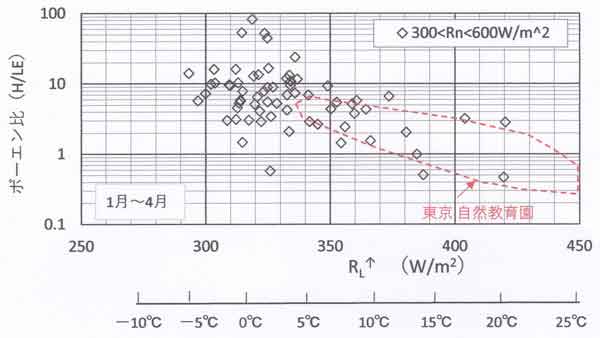
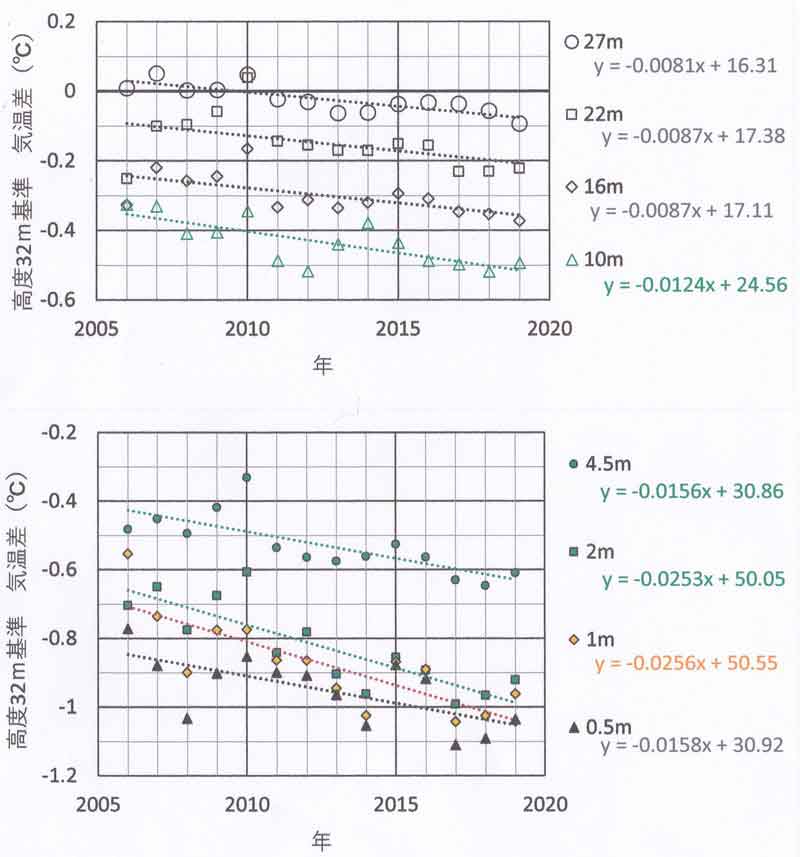
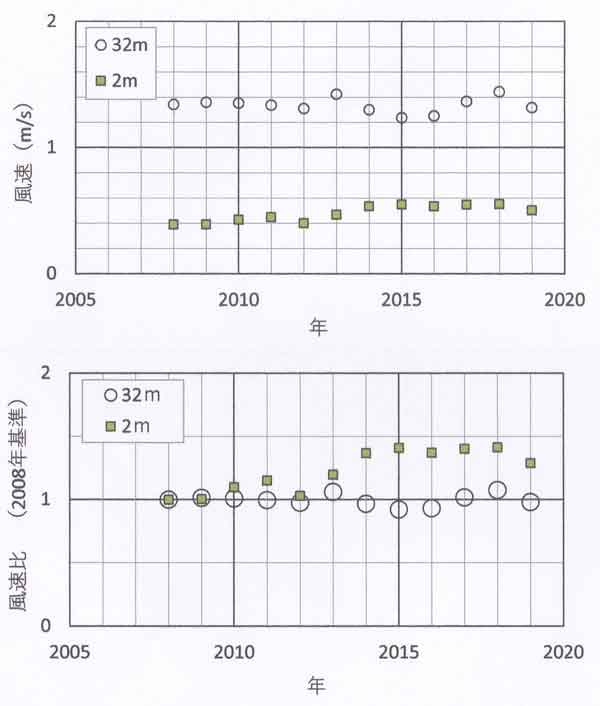
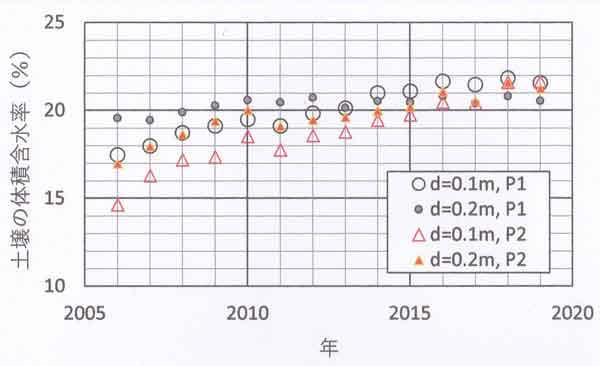
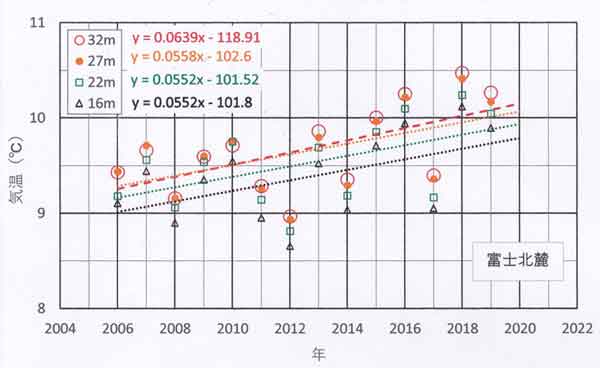
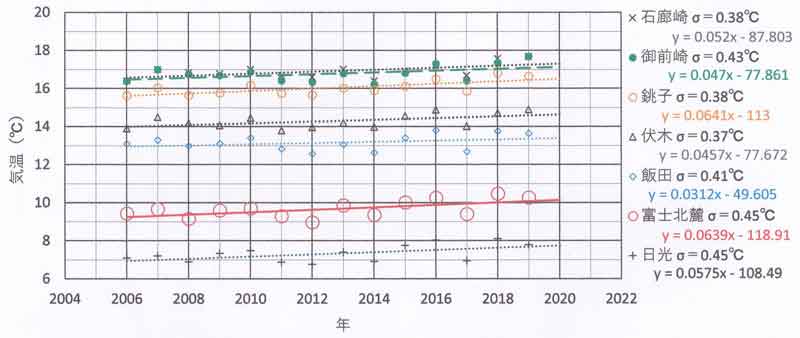
| トップページへ | 研究指針の目次 |