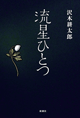|
|
|
21.ポーカー・フェース 22.キャパの十字架 23.旅の窓 24.流星ひとつ 25.銀河を渡る 26.旅のつばくろ 27.天路の旅人 |
|
【著者歴】、テロルの決算、深夜特急・第一便黄金宮殿、同・第ニ便ペルシャの風、同・第三便飛光よ飛光よ、象が空を、檀、オリンピア、贅沢だけど貧乏、血の味、イルカと墜落 |
シネマと書店とスタジアム、激しく倒れよ、一号線を北上せよ、無名、冠(コロナ)、杯(カップ)、1960、凍、「愛」という言葉を口にできなかった二人のために、旅する力 |
あなたがいる場所、月の少年、ホーキのララ、波の音が消えるまで、春に散る、暦のしずく |
|
●「ポーカー・フェース」● ★★ |
|
|
2014年05月
|
「バーボン・ストリート」「チェーン・スモーキング」に続く久々のエッセイ集、13篇を収録。 「バーボン・ストリート」は、私が初めて読んだ沢木さんの本です。それから早や27年。残念ながらその時の記憶はまるで残っていません。私が未熟であった故にその良さを十分味わえていなかった、という思いのみ残っています。 沢木さんのエッセイには、沢木さんしか醸し出せない味わいがあります。ひとつは、予想もつかない視点から視点へと話が展開していく点。もうひとつは、事実についてどこまでも突き詰めていくスタンスがある点。 ファンにとっては、手に取って読んでいるだけで楽しい一冊。 男派と女派/どこかでだれかが/悟りの構造/マリーとメアリー/なりすます/恐怖の報酬/春にはならない/ブーメランのように/ゆびきりげんまん/挽歌、ひとつ/言葉もあだに/アンラッキー・ブルース/沖ゆく船を見送って |
| 22. | |
|
「キャパの十字架 Capa's cross」 ★★ 司馬遼太郎賞 |
|
|
2015年12月
|
沢木さんの著書を読んでいるとロバート・キャパという名前は必ずや記憶の片隅に残っている筈、ではないかと思います。 70年以上も前に撮られたたった一枚の写真の真贋を確かめるために、アメリカ、フランス、スペインを訪ね歩き、当時写真が掲載された米仏の写真週刊誌の現物を確かめようとし、また実際に写真が撮られた場所を特定して訪ねる、さらには撮ったカメラまで特定しようと、多大な労力を沢木さんは費やします。 本書をどう読むかは人によって異なることでしょうけれど、私としては沢木さんの底知れない探究姿勢に圧倒された、が第一。 ※スペイン内戦・・・ヘミングウェイやオーウェルを思い出させられました。 1.崩れ落ちる兵士/2.真贋/3.彼の名前/4.小麦とオリーブ/5.その丘で起こったこと/6.突撃する兵士/7.ゲルダ/8.影は語る/9.ラスト・ピース/10.キャパへの道 |
| 23. | |
|
「旅の窓 The Window of your heart」 ★★ |
|
|
2016年04月
|
沢木さんが旅先で気まぐれに撮った写真に短いエッセイを加えた一冊。 ごくあっさりとした写真と小文だけですので、頁を繰る手はどんどん進みますが、頁をめくる内いつしか次第に楽しくなってきます。これこそ旅の楽しさをそのまま映し出した一冊であろうと。 「旅の窓」という表題は、飛行機、汽車、バス、ホテル等々の窓から見えた景色ということなのでしょうけれど、旅の本質を表していて象徴的と感じます。どんな景色も、そこに住む人ではなくあくまで旅人としての視点から見たもの。それでもアンテナがそちらへ向かって開いているからこそ感じるものであり、要は自分の心の窓が開いているか次第。 |
| 24. | |
|
「流星ひとつ」 ★★☆ |
|
|
2016年08月
|
元歌手・藤圭子自殺のニュースを受けて緊急刊行された一冊。 本書は、藤圭子が引退宣言をした後の1979年秋に都心のあるホテルのバーで、ウォッカ・トニックの杯をお互いに重ねながらインタヴューしたものをまとめたもの。 杯を交わしながら会話するという形のインタヴュー、極めて異例なものでしょうけれど、藤圭子という人に自分自身のことを語らせるのには恰好のものだったのでしょう。 本書を読んでいると、純粋で溌剌とした若い藤圭子さんの姿が今もそこにあるかのように生き生きと感じられます。インタヴュー自体の見事さと合わせ、お薦め。 |
| 25. | |
|
「銀河を渡る 全エッセイ Cross the galaxy」 ★★ |
|
|
2025年01月
|
沢木さんの作品は十分読んだ、という思いがあったので最初は見送るつもりでいたのですが、<全エッセイ>の3冊目と知り、思い直して読んだ次第。 最初に読んだエッセイ集は「象が空を」(全エッセイ2冊目)。この時は、その面白さ、内容の濃さに興奮し、続いて「路上の視野」(1冊目)も読むに至りました。 本書はそれから25年ぶりの全エッセイ3冊目。 再びあの時の面白さを味わえたかというと、残念ながらそれはありません。 今思い返すと、当時は現在進行中の物語を読む、という面白さがあったのでしょう。 翻って今は、本作は、というと、内容も過去の振り返りが多く、坂道の頂点を過ぎ、もはや下り坂にあるのだ、という思いを強くしました。 <歩く・見る・書く・暮らす・別れる>という構成は「象が空を」を踏襲したものとのこと。ただし、今回は<会う・読む>がなく、その代わりに<別れる>が入っての5パートとのこと。 そのことについても、時間の経過を感じさせられます。 それでも、本書を読んでいれば、また新たな面白さや懐かしさ、そして感慨を覚えることが多々あります。 「第一部 鏡としての旅人 *歩く」では、やはり沢木さんの本質は旅人であるところにあると思いますし、「第三部 キャラバンは進む *書く」では、中々単行本化されなかった「危機の宰相」の経緯、「檀」執筆過程での檀ヨソ子氏とのこと、世界的なクライマーである山野井夫妻との交流の末に「凍」が執筆されたという経緯等、新たな興味を引き立てられます。 そして、「第五部 深い海の底に *別れる」では、何と言っても(他でも既に読んでいましたが)俳優の故・高倉健さんとの関わりを書いた篇が捨てがたい。高倉健さんという人の魅力を語って何とも貴重な一篇。 この一篇が本書の最後を、特別に格調高いものに押し上げている気がします。 1.鏡としての旅人 *歩く/2.過ぎた季節 *見る/3.キャラバンは進む *書く/4.いのちの記憶 *暮らす/5.深い海の底に *別れる/銀河を渡る-あとがき |
| 26. | |
|
「旅のつばくろ」 ★☆ |
|
|
2023年11月
|
JR東日本の新幹線車内誌「トランヴェール」に連載した紀行エッセイの単行本化。 JR東日本というからには、書かれている内容は国内の旅。 日本国内を旅して書いたものとしては本書が初の作品、なのだそうです。 そういえば、確かに沢木さんといえば「深夜特急」に始まり海外のイメージが強く、国内紀行文を読んだ覚えは余りありませんでした。 その沢木さんの旅の始まりは、16歳、高校一年生の春休みに、国鉄の東北均一周遊券と三千円ほどのお金を持って出かけた旅だったそうです。 何だかんだとそれに絡む思い出が何篇にも綴られ、また以前行き着かなかった先として竜飛岬のことも何篇か費やして語られています。その所為か、その2つに関連するいくつかの篇が印象に残ります。 こうしたエッセイを読むと、旅に出たいという気持ちをそそられるのが常です。いろいろな思いや目的を詰め込んだ旅ではなく、ちょっとあそこへ行ってみたい、見てみたいという、一点集中的な気持ちで出かけてみるのも楽しそうだと思います。 旅って、いつ出掛けても良いものなんですね、そう思います。 |
| 27. | |
|
「天路の旅人」 ★★★ 読売文学賞随筆・紀行賞 |
|
|
2025年05月
|
第二次大戦末期、密偵として中国の奥深くへ。敗戦後もその歩みを止めず、結局8年という長きにわたり内蒙古~西域~チベット~インド~ブータン~ネパールを旅してまわった西川一三という稀有な旅人を描いたノンフィクション。 西川一三氏自身、25歳からの自らの旅を「秘境西域八年の潜行」(芙蓉書房、中公文庫)という著書にまとめて刊行されているのですが、沢木さんの本書とどう違うのか。 西川氏著書を読まない限りそれは判りませんが、沢木さんとしては、旅の記録より、西川一三とはどんな人物だったのか、どんな旅人だったのかを描きたかったそうです。 満鉄を退職した後<興亜義塾>に入学、そこで蒙古語等を叩きこまれますが退学させられたことから密偵の道を選び、蒙古人ラマ僧「ロブソン・サンボー」に扮して中国の奥深くへ向けて旅立つという流れ。 この長大な旅路の内容を紹介するなどとてもできることではありません。ただ、ユーラシア大陸を横断した沢木さんの「深夜特急」とつい比較してしまいます。 西川氏の旅の凄いのは、(インド国内を除けば)すべて徒歩での旅だったこと。それも砂漠や無人地帯での旅となれば、盗賊に襲われることや食料を確保することもできなくなるといった、命の危険さえも負った旅立ったことでしょう。 日本の敗戦を知り密偵の役目が終わった後も、何故西川氏が旅を続けたのかという点も興味深い。 旅を続ければ続ける程、西川氏の胸中には、まだ行ったことのないところへもっと行きたい、何物にも束縛されないことの自由な旅をずっと続けたい、という欲が募っていったということのようです。その気持ちには共感できるところ大。 興亜義塾の先輩にあたり、同時期にやはり密偵として中国の奥深く侵入、一時期西川氏と行動を共にし、帰国後「チベット潜行十年」を著した木村肥佐生という人物の対比も面白い。 西川氏から視た木村像ですから公正とは言えないのかもしれませんが、その土地、土地の人々と関わる姿勢に大きな違いがあったように感じられます。 すなわち、木村氏にはどこか現地の人を見下したところがあったのではないか。それに対し西川氏は、究極的に人が好きだったのではないか。そして相手が誰であろうと誠実に接することを信条としていたようです。そのため、現地で出会った人たちと親しく交わり、信頼を得ることも多かったような気がします。 最後、インドで日本人と判り逮捕されて日本に送還されることになるのですが、何とも呆気ない終わり方。西川氏の無念な気持ちも、この大部な旅行記を読み通してみればおのずと自ずと当然のこととして理解できます。 本書は 570頁と大部な一冊。でも本書の中には、それ以上に大きな旅の世界が広がっています。 読んでいる最中、西川氏と共に旅の最中にあり、読み終えた時には長い旅を終えた気分でした。 旅好きな方、「深夜特急」ファンの方には、是非お薦めしたい、稀有な旅行記です。 序章.雪の中から/1.現れたもの/2.密偵志願/3.ゴビの砂漠へ/4.最初の別れ/5.駝夫として/6.さらに深く/7.無人地帯/8.白い嶺の向こうに/9.ヒマラヤの怒り/10.聖と卑と/11.死の旅/12.ここではなく/13.仏に会う/14.波濤の彼方/15.ふたたびの祖国/終章.雪の中へ/あとがき |
沢木耕太郎著作のページ No.1 へ 沢木耕太郎著作のページ No.2 へ