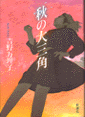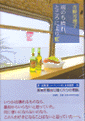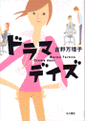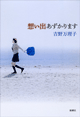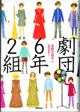|
●「秋の大三角」● ★ 新潮エンターテイメント新人賞 |
|
|
|
“新潮エンターテイメント新人賞”は、一人の作家が独断で選ぶ賞だそうで、本書「女子校生の切ない三角関係の物語」を応募作1320篇の中から選んだのは石田衣良さんだそうです。
たしかに帯に紹介されているとおり「横浜を舞台に女子校生たちの不思議な経験を描いた学園ファンタジー」ではあるのですけれど、本書ストーリィを正確に言い表しているかというと、ちょっと疑問。私としては、学園ファンタジーというより、ややホラーがかったところのある青春風サスペンス・ファンタジー、と言う方がふさわしいと思います。 となるとミステリ風なのですが、そこからストーリィはファンタジーというよりもむしろ非現実的と言う方がふさわしい展開へと進んでいきます。「切ない三角関係」のストーリィではないのでは?と思う次第。 |