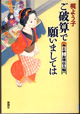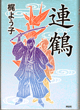| 11. | |
|
「桃のひこばえ−御薬園同心 水上草介−」 ★★ |
|
|
2017年08月
|
のんびり、ぼんやりした性格故に園丁たちからも軽んじて“水草さま”と呼ばれる御薬園同心=水上草介を主人公とする時代物青春ストーリィ、「柿のへた」に続くシリーズの第2弾。 前巻同様のほほんとした雰囲気でごく日常的な出来事、事件がいろいろとが語られていきます。そこに、ぼんやりし過ぎの観ある草介と常に若衆姿のお転婆娘=千歳とのかけあいが加えられているところが、本書の面白さ。 本巻では、御薬園の見習いかつ草介の後輩同心として新たに吉沢角蔵という若侍が登場します。 この角蔵が飛びぬけて生真面目、堅い一方の人物。主人公の草介とは対照的で、殊の外草介のぼんやりぶりが協調されるという仕掛けです。 さらに後半、千歳に縁談が降って湧いて、そうと聞かされた草介は呆然。さぁ草介、どうする!? しかしまぁ、この主人公、突破力は本当に皆無なんですよねぇ。 この水上草介という主人公と付き合っていると、こうした人物こそ希少価値、と思えてくることが楽しい。 アカザのあつもの/大根役者/女房のへそくり/柴胡の糸/桃のひこばえ/くららの苦味/清正の人参/相思の花/葉の文 |