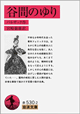|
|
|
|
|
2.ゴリオ爺さん 3.谷間の百合 4.幻滅 5.ラブイユーズ 7.オノリーヌ 8.従妹ベット 9.従兄ポンス |
|
●「「絶対」の探求」● ★★☆ |
|
|
1834年発表
2001/08/31 |
本作品にて、改めてバルザックという作家の特徴を認識したような気がします。 本作品のストーリィは、“絶対”なるものの発見に没頭するあまり、富裕な世襲財産の一切を失い、妻子を貧困の底に突き落としてもまるで顧みない、という人間の姿を描いた作品です。その当人は、フランドル地方の名家クラース家の当主バルタザル。 ※“人間喜劇”の中では「哲学的研究」に収録。 |
|
●「ゴリオ爺さん」● ★★★ |
|
|
1835年発表
1999年05月 新潮文庫 |
例によって出だしは読みにくい。けれども、バルザックにしてはまとまりのある、戯曲的な作品です。まるでモリエールを読んでいるような気がしました。 ※サマセット・モームが「世界の十大小説」に挙げた作品。 |
|
●「谷間の百合」●
★★ |
|
|
1974年06月 新潮文庫
|
|
|
●「幻 滅」●
★★☆ |
|
|
1837〜43年発表
2000年10月
1977/03/14 |
本作品には、当時のフランス社会、パリの実態が見事に描かれ、とても面白い。作者バルザック自身があまり道徳的な人間ではないから、その作風は美徳を一蹴し、現実社会の泥臭さを堂々と誇り、その中に逞しい生活力を満々と湛えている。ディケンズより泥臭く、その故にこそ、よりスケールの大きさを感じる。 |
|
●「ラブイユーズ」●
★★☆ |
|
|
1841〜42年発表
2000年01月
|
第2部以降は、ルージェから継いでその低能の息子ジャン・ジャックが保有する財産の相続争いが主ストーリィになります。ジャンの家には、妾兼家政婦のフロールという美貌の娘がいます。極貧育ちから“ラブイユーズ(川揉み女)”と蔑称されている娘。このフロールとその愛人マックスがジャンの財産を横取りしようとしているのですが、アガトとジョゼフという善人母子ではまるで太刀打ちできず。そこで、フィリップが乗り出すことになります。主役が第一部とまるで逆転。そして、フィリップ対マックスという悪漢同士の争いが展開されます。 |
|
●「アルベール・サヴァリュス」●
★★ |
|
|
1974年06月 |
|
|
●「オノリーヌ」● ★ |
|
|
|
※本論と関係ないのですが、モーリスがオノリーヌに向かって「青いダリアと青いバラを作ってみたい」という場面があり、読んだばかりの最相葉月「青いバラ」との偶然性を感じてニッとしてしまいました。 |
|
●「従妹ベット」● ★★★ |
|
|
1846年発表
2001年07月
1973/08/31 |
バルザックの小説は、最初が常に冗長で、ひどく読みにくいのが特徴。バルザック作品きっての面白さと言える本作品にしても、それは例外ではありません。しかし、
100頁辺りまで進むと、主要な登場人物たちも大方顔を揃え、本作品の面白さが現れてきます。 |
|
●「従兄ポンス」● ★★ |
|
|
1847年発表
1999年09月
1977/02/07 |
貧乏で善良な音楽家ポンスは、金持ちの親戚からいたぶられている境遇。しかし、彼が高価な芸術品を所蔵していることが知れると、その遺産を狙う貪欲な人間たちによって迫害され、ついに死に至るという、簡単かつ月並みなストーリィ。それにも関わらず本作品が評価を得ているのは、バルザックの筆力に負うものでしょう。
|