|
そこいらで撮影したテキトーな写真
【 懸垂下降の練習 】 【 ザックの軽量化 】 【 チタンボールのなべ化 】 2014 年 04 月 27 日(日)【 懸垂下降の練習 】 手軽に練習できる岩場とかジムとかあれば良いですが、近くにそんなの無い あってもしょっちゅう行けるものでもない 自宅の庭に立っている背の高いミモザの木の上部にアンカーをセット ロープを固定すれば懸垂下降の練習などできるようになりました~ クライマーなら似たようなことやってるのかな?っと思いますが・・・ 本格的なクライミングはしないのですが、経験的な練習は必要と思います 中学~高校生の頃にも以前の家の庭で同じようなことをした記憶が・・・ 具体的には将来的に、 ① キナバル、イタリアなどの via ferrata 登山に行く ② ガイドさんにお願いして岩場の山行に行く ③ 歩かれてない藪こぎを含むような山行での道迷い対策 ④ ガスに巻かれた下りでの道迷い対策 ⑤ 悪天候(強風など)下での自己確保 などを想定し、自己確保、懸垂下降くらいは練習して馴染んでおきたい あと、山岳コスプレ趣味・・・! 元々のコレクター気質と相乗し、様々な機器を購入! コスプレに関しては、主に「竹内洋岳」さんと「イモトアヤコ」さんですね 彼らのテレビを見て、「あのカラビナが欲しい」っとか言って購入するのです 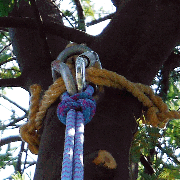 ミモザの木、トップのアンカー部分 高さは地上 4.5 m くらい・・・ 2 又に 2 系統のロープを巻き、2 つのカラビナに 8 の字結びでザイルを固定 この青いロープはダブル用の 10 mm ?っと思いますが、詳細不明! 練習用には使いますが、山には持ってけません 練習にも、「衝撃を加えない」使用法で、静荷重のみ 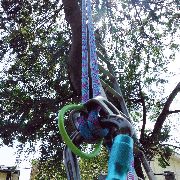 下から見るとこんな感じ ① 地面でハーネスにビレイ機をセット ② ビレイ機のロープを手繰りながら脚立で登る ③ ビレイ機で下りてくる この繰り返し  ビレイ機として標準的?な Black Diamond ATC-XP( 63.72 g ) 安定感があり、減速も停止もスムースで発熱も軽度 このグリーンのワイヤー、必要なんだろうか? カラビナは MAMMUT バイオニック HMS ツイストロック( 78.60 g ) イモトも使っていたし、マムートは竹内洋岳さん愛用のようです カラビナはこれくらいの大きさがあると使いやすい  こちらは超軽量ビレイ機、DMM バケット( 26.30 g ) こんなに軽量化したモデルなのに、この重そうな黒いワイヤーは必要なんだろうか? ATC などこのタイプのビレイ機のワイヤーはビレイ時の強度には貢献していない もう少し軽い素材にならないものかと思います 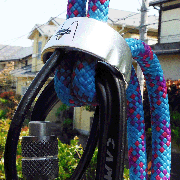 超軽量のビレイ機には超軽量のカラビナでないと・・・ このカラビナは CAMP Photon スクリュー( 42.81 g ) カラビナの R が小さくてビレイ機にハマり込んでいるのが心配・・・ でも、写真の状態は荷重状態で停止している 抵抗感が強く、奥のザイルを上方に上げればユルユルと下降する ATC と比べるとコントロール性は悪く、ザイルが厳しく曲がる感じで発熱量も多い シングルでもやりましたが、停止に問題はないもののザイルの曲がり具合はかなり厳しい 非常時にゆっくり下降するなら問題はないだろう 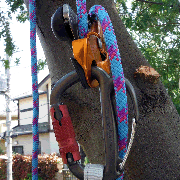 写真は落下時の確保機、ペツル グリグリ 2 ( 171.49 g ) カラビナはグリグリ用のペツル フレイノ( 85.45 g ) 主に岩場のフリークライミングでパートナーが使うもの シングルで登る際の自己落下用にも使える(ハズ) この練習では、シングルロープでのテスト時にサブとして使用 カラビナはグリグリから出るザイルを下向きに保持するガイド付き でも、この金具でやたらに指を挟む! 皮製のグローブをしてれば問題ないが、部屋でいじる時など挟みまくり・・・ グリグリには解放用のレバーがあり、グリグリ単独でも下降が可能 でも、速度の微調整が難しく、ガクンと止まったり、スカッと落ちたりする 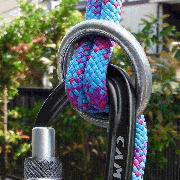 SMC ディッセンダーリング( 11.69 g ) このように使うものだが、強度的には頼りない?? よく見ると継ぎ目の様な線もあるし、問題ないのだろうか? 下降セットとしては、この組み合わせが手持ちの最軽量ではある (ビレイ機 11.69 g +ロッカカラビナ 42.81 g ) 操作性はまあまあだが、ザイルの曲がり具合は厳しく、停止性はイマイチ シングルではザイルをしっかり握らないと停止できない それでもイザとなればシングルでもしっかり握って降下 OK これが OK なら、ATC とか DMM バケットとかの ワイヤーは不要なんじゃ?? 少なくとも非常用にはカットして使用(携行)するのは「あり」?っかと思ってます DMM バケット、ワイヤーカットしたら何 g になるんだろう?? 勿体なくてできないけど、やってみた~い! 軽量化マニアですから、軽量なものばかり物色 けど、このジャンルに関してはロープがあまりにも重いので、軽量化の意義を感じにくい ギアが多ければ、各々の軽量化がかなり影響してくる でも、ギアが数点だとロープが 3 kg とかだから、数 g 軽量化してもね~・・・ だから、長いロープをダブルで使うようなクライマーはあまり軽量化に細かくないんじゃ?っと思います カラビナ 50 コとナッツ類たくさんとかなら、各々の軽量化でかなり違うと思いますけどね・・・ 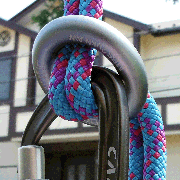 このリングはオメガパシフィックのラッペルリング( 32.11 g ) SMC のディッセンダーリングよりも明らかに強そうだけど、この使用法は適応外 内径が小さく、ダブルロープではスムースに動かない 写真は荷重状態ですが、手放しでも停止 ザイルを送ってやらないと下降しない シングルでも動きが悪く、メーカー指定使用法の適応外ということもあり、下降は× 重量的にも SMC のリングより重いし、下降用としての利点は「なし」でした~  オメガパシフィックのラッペルリングはこのように使うらしい 懸垂下降時に支点にセットする捨てリング とてもきれいでコレクター冥利に尽きるが、価格は 500 ~ 600 円前後と安価 U 字にダブルロープをかけ、降下後にスムースにロープを回収する ロープの保護と、確実な回収が目的 実際の岩場でよい支点がない場合に・・・ 今までは階段の吹き抜けとガレージでやってましたが、高さはどちらも 2 m くらい 4 m は全く違いました 恐怖感もあり、練習効果は絶大かと! やってみると、カラビナが逆だったり、何か落としてみたり、いろいろで・・・ 慣れてくると手順が分かって安定してきます 今後も様々な機器で何回も何回もやってみるつもり・・・ 2014 年 04 月 29 日(火)【 ザックの軽量化 】 軽量化おバカモードに入ってしまい、止まりません 現在のメインザック、カリマーのホットクラッグ 40 タイプ 2 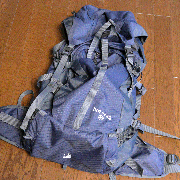  重さは 1,173 g ( 底部のザックカバーはなし ) すでにかなり軽量なのですが、ちょっと物足りない っというのは、以前のザックがかなり軽量だから・・・ オスプレイのホーネット 46 は現在実測 736 g !! あまり軽量化は期待できないのですが、やれるだけやってしまいました     あらためてザックを見ると、チャックの金具はかなり大きめ 雨蓋のチャック、ザック背面はダブルチャックで、計 7 つの金具があった ダブルチャックをセンターで停止すると、テンションで開きそうな気がする 片側に寄せて閉めることにするなら、シングルの方が良いと思います ダブルの方がゴージャスで人気が出るでしょうが、軽量化では逆! ダブルよりもシングルの方が良いんだ!っていうマニアックさが欲しいのですが・・・ 雨蓋裏面ポケットのチャック金具はかなり大きい メッシュ内側にはプラのホックがついているが、信頼性に乏しく使えない これをカットしても微々たるものだが、使わない(使えない)のでこれもカットしよう!  ザック背面の左右にピッケルを固定するゴムバンドがある 使えるものを、自分は使わないからカットする、ってのは機能を削ぐことになるのでしたくない けれども、幸いゴムひもの結び目を解くだけで外すことができたので、撤去保管することに・・・ ピッケルを使う際には再使用できる しかし、このバンドは使いにくいのでは? ピッケルのヘッドをザックの下部に固定し、先端部にゴム輪を引っ張って通す方式 やってみると 55 cm くらいまでのピッケル(アックス)なら問題ない でも、それ以上の長さだとゴムを伸ばしても先端を超えるのが難しくなる 70 cm ではちょっと無理 どんな使い方を想定してるのだろう?  思案の結果、使うにしても写真のような再利用できるタイラップなどが良さそうである コツコツと軽量化作業を進めます・・・ チャックの金具を取り外し、2 mm のロープに付け替えた  金具はニッパーで破壊 取り付け部分の金具を開いて外せるのだが、その後の締め具合に不安が残る どうせ再使用しないので、残る金具をいたわった 写真が取り外したもの全てで、重さは 31.29 g ザックは 1,144 g になりました~ 上部の口閉めロープやストッパーは未変更 使い勝手や機能性を考えるとこれ以上の軽量化は難しそう・・・  ジッパー部分はロープになってややチープ? でも、山行中はほとんど開閉しないし、軽量化オタクとしては普通ですね 2014 年 05 月 007 日(水)【 チタンボールのなべ化 】 以前にご紹介したチタンボール その際も鍋としての使用状態で 68.4 g とかなり軽量 しかし、取っ手があまりにもやっつけで実用に至らず・・・ 今回、さらなる軽量化と実用性を検討  ボールの上縁に 2 つの穴を明け、取っ手をつけました 針金はステンレスのφ1.5 mm 針金の曲がった部分を引っかけるだけの簡単な構造 この状態で 58.07 g ( ボール 53.33 g、取っ手 4.74 g ) 550 mL 入れても穴の縁まで到達せず、500 mL のボイルは楽々 水をフルに入れた状態で持ち上げても安定性は問題なし 針金が指に食い込む感はあり、長時間では手袋をして使った方がよさそう できればチタン製の丸棒で作りたいのですが、入手できてません 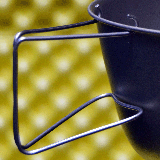 拡大するまでもなかったですか・・・ 定規で長さを測りながら先端の丸いペンチで手曲げ 製作時間は 3 分間程ですから、作るのは簡単 今回実用的な軽量鍋を作製したので、セットの重量を計測 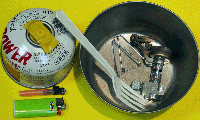 調理食事セット(ラーメンやカップ麺など 1 人分) 写真の状態で 271 g 楽々 300 g を切ることができました~ ( 梱包するビニール袋分加えねばなりませんが・・・ ) ① 今回の自作鍋(ボール+取っ手) ② ガス缶(キャップはテープに) ③ P-114 点火装置なし ④ 点火ユニット(ライターのフリント点火部分) ⑤ ライター(非常用予備) ⑥ プラフォーク ガス缶の重量に大きく左右されますが、ガス缶は 145 g で計測 ガス残量は約 38 g の計算で、ラーメン調理 2.5 回分くらい ( ラーメン調理 1 回のガス消費量は、富士山頂で約 14 g でした ) 新品満タンのガス缶は約 211 g なので、それだとセットは 339 g +袋分 ~ 軽量化計画はコツコツと進行 鍋自体の軽量化もいいのですが、鍋については他の利用法も・・・ サングラスや老眼鏡はハードなメガネケースなどに入れないと壊れてしまう でも、強度のあるケースってある程度の重さがあって軽量化が難しい 思案の結果、メガネや潰したくないものは鍋の中に入れることに! メガネケースが不要になり、収納場所の変更が 50 g 前後の軽量化となります 今回使用のボールは直径 13 cm で、サングラスの横幅にはちょっと小さい ちょっとだけ大きいボールが欲しいのですが、ありませんね・・・ つづく・・・
|