|
そこいらで撮影したテキトーな写真
【 御殿場ルートで富士山登山 】 【 4 ルート踏破の軌跡 】 【 富士宮ルートで富士山 → 水ヶ塚 】 【 新しいプロトレック 】 2013 年 08 月 21 日(水)【 御殿場ルートで富士山登山 】 先週、お盆休みに予定していた御殿場ルートからの富士山登頂 順延で今週になりました 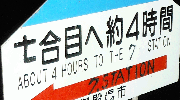 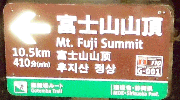 登山口にあった道標 「えっ!、そんなにかかるの?」 手持ちの資料よりも時間が長いけど・・・ 実際、砂走り状の登山道を登るので歩きにくく、かなり時間がかかりました 体調もあるかと思います 行程が長いので出発を早め、結果睡眠時間は 2 時間ほど・・・ 歩き始めから眠かったから  御来光は× でも、上下に雲があってその変化はきれいでした じっくり腰を据えて撮るわけではないので、モノにはなりませんが・・・  家族登山の後は自分のものにしたカリマーのホットクラッグ 40 タイプ 1 背面パッド、ウエストベルト、フレーム、いい感じ こんな写真しか撮ってませんでしたが・・・  これは御殿場口山頂から Fishey でお鉢を撮った写真 朝方は少し東側から撮った方が影が少なくて済みます  先日ゴムを交換したスパッツ 砂走りでは効果があったと思います  大変だった大砂走り 前日が雨だったのであまり走らない 気温も上がって汗だく 手持ちのペットボトルを飲み干してしまい、最後はつらかった 行程は、 0031 御殿場口五合目駐車場を出発 0536 七合目日の出館 0814 御殿場口山頂 0841 〜 0909 剣ヶ峰 0957 御殿場口山頂から下山開始 1114 七合目日の出館 1143 宝永山 1331 御殿場口五合目駐車場に下山 でした 結局、七合目までは 5 時間 05 分もかかってしまいました 山頂ではカメラを出して散策していますが、剣ヶ峰までは 8 時間くらい 睡眠不足がなければもう少し短縮できるのかな? 今はちょっと自信がありません DigiSpice2 による GPS の軌跡 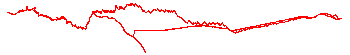 距離が長いので解像度が落ちます 左に回してるので、上が北ではありません 左が剣ヶ峰、下のヒレが宝永山 今回の山行で、本年だけで富士山登山 4 ルートを踏破することができました やり遂げた感がありますが、御殿場ルートはもうイヤですね 混雑する吉田ルートも避けたいかな・・・ 来年以降はどうなっっちゃうんでしょうか? 自分的には、 「便所臭いの何とかして!」 「登山道を山小屋経由に曲げるな!」 まずはこの 2 点ですね 営業小屋なんて無くていいんですよ トイレは国が立派なの建ててください 【 4 ルート踏破の軌跡 】 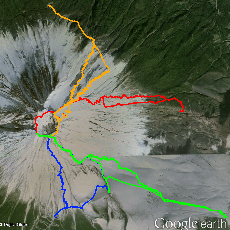 Google earth に DigiSpice2 の GPS データを表示した図 ( DigSpice2 のソフトで表示させることができる) 自分で歩いた 4 ルートの軌跡が確認できます これを見ると達成感が増します カラーは環境省のマップの色に合わせたので、登山マップのようです 06/26、08/13 富士宮ルート(青) 07/03 吉田ルート(オレンジ) 07/24 須走ルート(赤) 08/21 御殿場ルート(緑) 富士宮ルートは登りしか歩いてません 2 回とも下りに御殿場ルートから宝永山を経由したからです 御殿場ルートの下りにも宝永山を経由してます 宝永山に立ち寄りたいってのがあります 御殿場ルートはやはり長い スバルライン五合目から六合目もダラダラと長いですね DigiSpice2 を登山に持参したのは 06/26 から 今後は金時山など、他の山でも使用したいと思います DigSpice2 の動作環境を・・・ 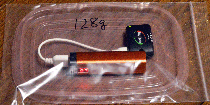 ザックの天蓋にセットする DigiSpice2 のユニット DigSpice2 のバッテリーは登山など長時間では容量不足 補助電源ユニットを接続して使用すると上手く作動しました 今回の御殿場口富士山登山では、全行程約 13 時間が問題なく記録できました さらに、今回の山行から安定して衛星を捕捉できるように工夫 ダイソーの軽量プラボックスのフタに両面テープで貼り付け これだと他の荷物との干渉を気にせずに済みます 防水ではないので、全体をビニール袋に入れました この状態で 128 g これを天蓋の上面に入れておきます 補助電源が重いですけどね・・・ 元々は携帯端末の充電用 ケータイの予備電池と兼用、と考えれば・・・ 【 高度の推移 】 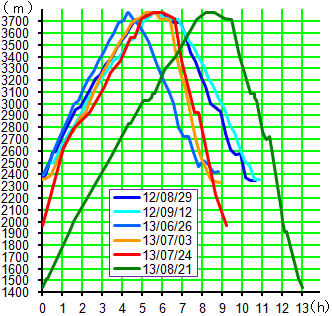 御殿場ルートの経過を前回のグラフに追加 このグラフにも 4 ルート入りました 線の色は環境省作製の富士山登山マップに倣いました 青系は富士宮ルート オレンジが吉田ルート 赤が須走ルート 緑が今回の御殿場ルートです 御殿場ルートはやはり長い 御殿場口五合目の標高が低いので、剣ヶ峰まで標高差 2,336 m! 下りはけっこう頑張ってるでしょう・・・? これって何か変えると短縮できるの? 少々体調が良くても時間を短縮できる気がしない ちょっと弱気になっちゃってます 次に登るなら富士宮口からかな〜・・・ 2013 年 08 月 28 日(水)【 富士宮ルートで富士山 → 水ヶ塚 】 そんなに続けて登らなくても・・・ でも、登山期間中に是非踏破したいルートがあり、行ってきました 前日(08/27)夜、水ヶ塚駐車場にクルマを置き、バスで富士宮口五合目へ バスは 2030 で、富士宮口五合目は 2100 でした そこで仮眠! 0111 に起床し、0201 に入山 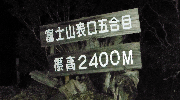 夜の富士宮口五合目は久しぶり 天気は良かったのですが、六合目を過ぎると強風! かなりで、ウエア選択が難しかったです  八合目上で御来光 調子がイマイチで、ペースがあがりません 剣ヶ峰着は 0651 で、4 時間 50 分と悪い 当然のように 4 時間を切るつもりだったので、落胆・・・ 途中で諦めたので丸々 50 分遅いわけではないけど 高山病ではなく、睡眠時間かな〜・・・ バスですでに眠かったうえ、仮眠も十分でなかったから 先週の御殿場ルートも影響してるかな?  山頂の「このしろ池」には氷が! カキンカキンではありませんが、今朝は冷えたようです  仮眠に使うマットとシュラフを背負いました マットはかなり目立ったようです ビニール袋に入れなくてもよかったのですが、砂でジョリジョリになるのがイヤだった 合わせて 1.3 kg ですから、重量的には デジ一眼を持っていかなければ負担になりません でも、このマットが風に煽られて体が振られる サイドに取り付けたいのですが、ザックに取り付け場所がなかった さて、今回の下山ルートは水ヶ塚駐車場まで歩くパターン 膝の様子を見て決行 御殿場ルートから宝永山を経由し、宝永第二火口縁から南下 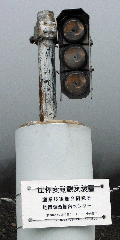 楽しみにしていた「山体観測装置」はこんな・・・  砂状〜ガレの下りは徐々に樹林帯へ 歩きやすそうに見えるでしょうが、下り傾斜が強くてヒドイ ずっとずっと下りが続くから、きつかった  登山道的には案内板がしっかりしていて道迷いの心配はなさそう  徐々に傾斜が緩くなっていい感じ でも、この頃には足が痛くなっちゃってるんだ  倒木がやたらと多く、気象が厳しいのか・・・  やっと道路に出て終点  そこは富士山スカイラインの水ヶ塚上 下りがきつく、また歩くのはイヤですね 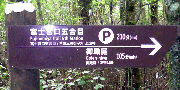 富士宮口五合目まで 210 分と書かれた道標 登るならあり? 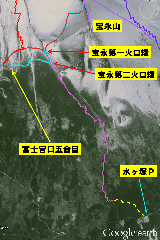 Google earth に今回の水ヶ塚ルートを追加 宝永第二火口縁 → 水ヶ塚の線が増えました なぜか最後の少しが記録されておらず、黄色点線で捕捉 樹林帯で電波が途切れて OFF になった? データが欲しい局面では休憩毎にチェックするのがいいかも 行程は、 0201 富士宮口五合目 0634 山頂 0651-0712 剣ヶ峰 0751 御殿場口山頂 1014 宝永山 1053-1102 山体観測装置 1310 水ヶ塚上に下山 でした 登りのタイムが悪かったので、お鉢巡りは止めました ウエアや行動食の出し入れが何回かあり、かなり時間をとられました ザックの中の整理が上手くいかず、グチャグチャ・・・ 初歩的なことでしょうが、毎回ササっとやるのは難しいです 仮眠に使ったツェルトがうまく袋に入らず、雨具の袋に入れたのが発端・・・ 雨具の袋がなくてあとは連鎖的に・・・ 今回はダメでした 富士山の登山シーズンが終わります 山頂の池も凍りました 9 月はどうかな〜 やる気があっても疲れがたまっているようで・・・ 毎週は難しいのかもしれません 自分の体力的に無理があるようです でも、限界にチャレンジしてるって感じはいい 倒れないようにやっていきましょうか・・・ 【 高度の推移 】 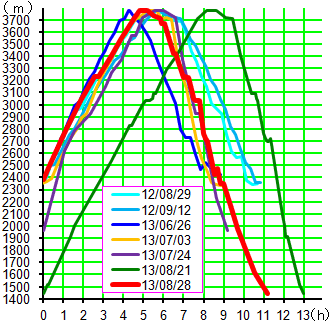 入山時間を 0 とした高度の推移 重なってきて分かりづらいですね 赤線が今回の経過 登りは八合目池田館で休んでしまい、遅れてます 下り始めてからのペースは良いようです 体調もあり、いろいろです 水ヶ塚は御殿場口五合目と標高がほぼ同じでした 【 新しいプロトレック 】 古い高度計付の腕時計、プロトレックが壊れてしまい、新調しました しばらくなしでガマンしていたのですが、高度が分かると励みになるから・・・  左が新しいプロトレック 右がここ数年間、普段使いの CASIO サブが欲しいと思っていたので、その点でも良かったかな? どちらもソーラー電波で、合理性で選ぶと CASIO になっちゃいます ブランド志向の私でも、すでに CASIO がブランド 新しいプロトレックはセンサーが小型化したそうです コンパス、気圧、高度のボタンが大きくて操作性が良い 時間あたりのメモリー機能がないのが残念です コンパスは小刻みで分かりやすい 重さはこのタイプで 100 g(カタログ値) 実測 92.73 g でした 照明付きの大きなデジタル表示は夜間も見やすそう・・・ 富士山でキズキズになっちゃうかな〜 つづく・・・
|