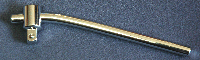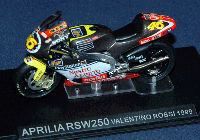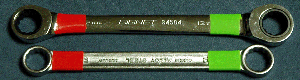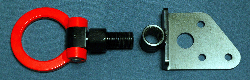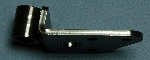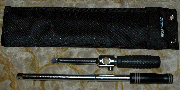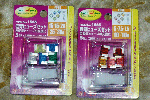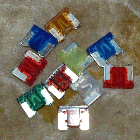�y �M�A�����`�Ƌ�C���� �z
�y �Ȃ��Ă��܂����X���C�h �s �� ���b�V�l�̃A�v�����A �z
�y �^�C������^�C���ցE�E�E �z
�y �G�A�Q�[�W 4 �� �z
�y 12�~13 �� 2 �� �z
�y �V�r�b�N�^�C�v R �̃t�����g�|�������t�b�N �z
�y �G�X�e�B�}���� �� �X�^�b�h���X�Ƀ^�C������ �z
2009 �N 11 �� 21 ���i�y�j�y �M�A�����`�Ƌ�C���� �z
�s�}��̍H�����܂Ńh���C�u

12�~13 �̃��K�l�M�A�����`�������Ⴂ�܂���
SIGNET ���ł������l�i
���ʂ� 12�~14�A11�~13�A13�~15 �Ƃ��ŁA12�~13 �͒������Ǝv���܂�
�l�ւ̏����p�[�c�� 13 mm �͂Ȃ��Ǝv���܂����A�ЊO�i�ł͑��p���܂�

������� 12 V �쓮�̃~�j�G�A�|���v�i1,280 �~�j
�V�K�[���C�^�[�\�P�b�g����d�������^�C�v�ŁA�d���͕t���i������ 633 g
�ƌy��
�{�b�V���̃o�b�e���[�G�A�|���v�����y�ʂň���
�ԍځi���j�p�ɗǂ����Ǝv���܂�
�G�[�X����ɓ��ڂ��Ă݂����E�E�E

���āA����̓z�[���Z���^�[�̎��]�ԃR�[�i�[�ŃQ�b�g�����~�j�t�b�g�|���v�i980
�~�j
�v�����Œ��y��
�t���i�Ȃ����� 218 g �ł�
�z�[�X���Z���̂ŁA�ԗ��ł̓o���u�ʒu�����ɂȂ�悤�ɒ�߂Ȃ��ƃ_���ł��傤
�u �o�C�N�A�����ԂȂǂւ̋�C�����͂ł��܂��� �v���Ƃ̒��ӏ���������܂�
�����A�^�C�v R �̃^�C�����g���Ē����e�X�g�����Ă݂܂���
�z��́u��փ^�C���ɃG�A�����đO�ւɎ��t����v�ł�
�G�A�� 175 �� 195 ��Pa ���炢�ɂ������E�E�E
170 kPa �ɂ��� 225/40R18 �̏����^�C��
�o���u�ւ̐ڑ��̓l�W���Ȃ̂ŁA���ߕt�����ɂ̓G�A�R�ꂵ�܂�
�T�T�b�ƒ��ߕt��
�S�̂��v�����ł�����A�����ɓ���Ő܂��Ă��܂�Ȃ��悤�ɒ��Ӑ[���������
100 ��
���O�������G�A�R�ꂵ�܂�����A�T�T�b�Ǝ��O��
�v��������C���͂Ȃ�� 196 kPa �I
100 �ނ� 170 kPa �� 196 kPa ���Ƃ������h�Ȍ��ʂƂȂ�܂���
���̂��炢�̋�C�����ƁA10 ���݂� 2.6 kPa�A�� 40 �ނ� 10 kPa �A�b�v����v�Z�ł�
�v�����Ȃ̂ŃK���K������M���Ȃ�����܂ꂽ�肵�Ă����ɉ��Ă��܂��ł��傤
�ł��A100 ����ă\�[�b�Ƃ�����蓥��ł� 2 �` 3 ���E�E�E�E
40 �^�C���͋�C�ʂ����Ȃ�����y���Ƃ��v���܂����A�Ƃ肠�����K�v�\���I
�����ԁE�o�C�N�̔��p�Ƃ��čœK����
2009 �N 11 �� 23 ���i���j�y �Ȃ��Ă��܂����X���C�h �s �� ���b�V�l�̃A�v�����A
�z
������������ԍڍH��̌y�ʉ�
�^�C���z�C�[���̏d�ʂ��v���������������Ƃ�����A���ۂɎg���邩�e�X�g���Ă݂�
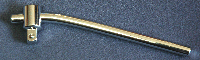
9.5sq �X���C�h �s �{ �����p�C�v�Ńz�C�[���i�b�g���ɂ߂悤�Ƃ�����A�ɂޑO�ɋȂ��Ă��܂��܂���
120 N�Em �` �Œ��߂��͂��̃i�b�g���O���܂���
����̓_�C�\�[���̕��ŁA�H��|���g�p���Ă��Ȃ����߁H��������܂���
�i�e�X�g�͂܂��_�C�\�[���̂��̂ōs�����E�E�E�j
�H��[�J�[�̕��ł��������Ȃ̂ŁA9.5sq �̃X���C�h �s �Ńz�C�[���i�b�g�́~�ł�
���ƁA�W���b�L���̂̓M�A�����` or ���`�F�b�g�łȂ��ƌ����������ă_�����ȁ`�H
��������p�ƌ����Ă��A������x�̉��K�����ۂ���Ȃ��ƁE�E�E
�y�ʉ� vs ���K���A�����ȃo�����X����������̂��ʔ����ł�
���Ȃ݂ɁAprodrive GC05F 8.5J INSET 56 �{ �`�c07 235/40R18 �̏d�ʂ́A�̏d�v��
19.6 kg �ł���
�����z�C�[�� 7.5J-18 INSET 60 �{ RE070 225/40R18 �͑̏d�v�� 20.1 kg �������̂ŁA�� 0.5 kg �y���ł�
7.5J �� 8.5�i�A225 �� 235 �Ȃ̂œ��T�C�Y�̔�r�ł͂���܂��A�f�b05�e
�͂��Ȃ�y���Ǝv���܂�
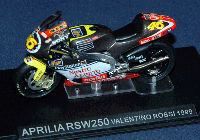
�d���W�̒m�l����o�C�N�̖͌^�������������Ⴂ�܂���
1999 �N�A���b�V�l�� 250 cc 2 �N�ڂɃ`�����v�ɂȂ������ɏ���Ă����A�v�����A�̃}�V���������ł�
���f���J�[���W�߂��͂���܂��A���߂Ă�Ɗ��S�[�����̂�����܂�
����ꏊ�ɍ���܂������AT ����i8 �j�̃t�B�M���A�W���u�[�X�ɒu���Ă��炤���ɂȂ�܂���
2009 �N 11 �� 25 ���i���j�y �^�C������^�C���ցE�E�E �z
�܂��V���[���i�C���Ƃ���Ă܂����E�E�E

���[���^�C���̃o���u�ɐڑ��ł���悤�ɂ����G�A�`���[�u
���a 6 mm �̍d���ގ��̃`���[�u�ł�
�^�C���ƃ^�C����ڑ�����ƁA��������������Ⴂ���փG�A�������n�Y�E�E�E
���������V���v���ɂ����������̂ł����A�莝���̍ޗ��ł���ȂɂȂ��Ă��܂��܂���
�d���͌���� 62 g
�K���[�W�ɒu���Ă���^�C�v R �̏����^�C�� 2 �{�Ŏ���
BS RE070 225/40R18 ���m�ł�
�ڑ��͗��[�Ƃ��l�W�~�߂Ȃ̂ŁA�ڑ����A���O�����ɂ̓G�A�R�ꂵ�܂�
����ŗ��[�����ɃT�T�T�b�ƒ��ߕt���A���O���E�E�E
�G�A�`���b�N�̕����ȒP�ł����A�������ĂȂ��ƃG�A�R�ꂵ�܂�����l�W�̕����m�����ȁH
| �^�C�� |
�O |
�� 10 �b�Ԑڑ� |
�� |
| �^�C�� A |
360 kPa |
�� |
327 kPa |
| �^�C�� B |
170 kPa |
�� |
197 kPa |
���ʁA�X�y�A�^�C���������ɏ[�U���Ă����A�ȒP�ɃG�A���[�ł��邱�Ƃ�������܂���
���܂����� 4 �{���{20 kPa �ɂł��邩������܂���ˁE�E�E
�ȑO�A�ȕւȃ|���v��������������ɂ���Ă���l���������Ƃ�����܂��i25
�N�O���H�j
���� 12V �̃|���v�Ƃ��ł��̂����ʂł��傤���A���̕��@�͑����ĐÂ��I�i�{���y�ʁI�j
��펞�p�ɂ͂��肩�Ǝv���܂�
�Ⴆ�A�钆�ɖ��Ƃ̋߂���X���ł͓d���|���v���g���ɂ����ł��傤����E�E�E
2009 �N 11 �� 29 ���i���j�y �G�A�Q�[�W 4 �� �z

���ݏ������Ă�G�A�Q�[�W 4 ��
������A
�@�@ ���t�����[�h�f�W�^���G�A�Q�[�WPRO RP128
�@�A BS ���[�V���O�G�A�Q�[�W RCG-20
�@�B KART PROF �^�C���Q�[�W D.63 �i�J�[�g�p�j
�@�C �X�g���[�g���f�W�^���G�A�Q�[�W�i���[�J�[�s�ځE�����s�j |
�w����
2,657 �~
8,381 �~
9,000 �~
1,380 �~
|
�g������͍��� 2 ���ǂ��Ǝv���Ă��܂����A�v���l�̍����ǂ̂��炢����̂����ׂĂ݂�
�� 260�A220�A200�A180�A130�A80 [ kPa ] �A5 �i�K�̃^�C����C���Ŕ�r
�^�C���̓V�r�b�N�^�C�v R ���� RE070 225/40R18 �{ �����z�C�[��
���Ԃ� �@ �� �A �� �B �� �C �� �@ �E�E�E���ƌv�����J��Ԃ��A5 �v������
�ق�̏������G�A��������̂ŁA�e���̐��l�͉E���������X���i���ɍŏ�i�E�E�E�j
�P�ʂ� [ kPa ]
| �@�@ RP128 |
�A BS RCG-20 |
�B KART PROF D.63 |
�C �X�g���[�g�f�W |
| 258 257 253 253 252 |
256 256 251 251 250 |
249 249 246 245 244 |
251 249 248 248 246 |
| 220 220 219 219 218 |
220 220 220 219 218 |
214 213 213 212 212 |
217 215 214 215 212 |
| 200 200 200 200 198 |
199 200 199 198 198 |
194 194 193 192 192 |
196 196 195 193 192 |
| 180 181 180 180 180 |
181 182 181 181 180 |
176 176 174 174 174 |
177 178 176 176 175 |
| 130 130 130 128 128 |
131 131 131 130 130 |
125 125 124 124 123 |
124 124 126 124 124
|
| 80 80 80 80 80 |
84 84 83 83 83 |
77 76 76 76 76 |
78 78 79 78 77 |
����
�E �@ RP128 �� �A BS RCG-20 �͂قړ������l�ň��肵�Ă����B
�E �B KART PROF �� �@�A�A �Ɣ�r���� 3 �` 5 �� �Ⴂ���l�ŁA200 kPa ����
5 kPa �͒Ⴍ�\�����ꂽ�B
�E ���炽�߂Č��Ă݂�ƁA��ς����邪�A�i���O���ł� 1 kPa �P�ʂœǂ߂�B�A BS RCG-20 �� �` 400 kPa�A�B KART PROF �� �` 2.6 bar �i260 kPa �j�ł��邪�A�A BS RCG-20 �̕����ǂݎ��₷���C������i���[�^�[�p�l���̖ڐ�������ׂ��j�B
�E �J�[�g�^�C���̒Ⴂ��C���t�߂ł��f�W�^���G�A�Q�[�W�͗L�p�Ǝv��ꂽ�B
�E �A BS RCG-20 �̓J�[�g�^�C���̒Ⴂ��C���t�߂ł͑��̃G�A�Q�[�W�������߂ɕ\������A�`
4 kPa �X�P�[���ł��邱�Ƃ��l������ƃJ�[�g�ł̎g�p�ɂ͌����Ȃ��Ǝv��ꂽ�B
�E �f�W�^�������A�i���O�����\���͈��肵�Ă��āA��������M���x�͍����Ǝv��ꂽ�B�i�H��X�̈����ȗA���f�W�^���G�A�Q�[�W�ł��v�������Ȃ�\���ɐ��m�I�j
|
�̍�������A�g�p����G�A�Q�[�W���ǂ��������X���Ő�����\������̂��m���Ă������Ƃ͕K�v�Ǝv���܂�
����ɔ����E�E�E�E
�֗��Ȃ̂Ń��C���Ŏg�p���Ă��� �@ RP128 �͕\�����Ȃ����l������I
�l�֎g�p��t�߂ł� 190 199 203 212 216 225 [ ��Pa ] ���\������܂���
IC ���Z�v���O�����̊W�Ő����������Ă��܂����̂Ǝv���܂�
������/cm2 �P�ʂł͂ǂ����Ǝv���Ē��ׂĂ݂܂���
����ƁA1.76 1.79 1.85 1.93 2.07 2.16 2.20 2.24 2.29 ���ƁA����ɑ����̐������\������܂���ł���
���� PSI �\�����ł��܂����A����������� PSI �Ȃ�A���ł��ׂĕ\�����邩������܂���
�ǂ����Ă� 199 kPa �ɂ�������ΒP�ʕ\����ύX���� 203 kgf/cm2 �ɂ���Α�p�E�E�E
�������A203 kPa �� 2.07 kgf/cm2�A212 kPa �� 216 ������/cm2 �ȂǁA�v���ł��Ȃ��̈悪����悤�ł�
�\������Ȃ����R�͕�����܂��A���̓_�̓A�i���O�ɕ�������܂��ˁE�E�E
�ł�����A�f�W�^������ �} 2 kPa �i����/cm2 �j�̌덷��������Ŏg�p����̂������Ǝv���܂�
�A�i���O���͋@�\��A�{�̂̉��x�A�C���ł̌덷�����肻�������A�V���b�N�ւ̋C�z�肪�ʓ|�E�E�E
���i�̓f�W�^���Ōv�����A���X�A�i���O�Ɛ��l���킹����̂��������ȁH
2009 �N 12 �� 03 ���i�j�y 12�~13 �� 2 �� �z
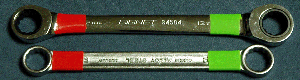
������Љ�� 12�~13 �̃M�A�����`
�X�g���[�g�߂��˂��~�����Ȃ��ăy�A�[�ɂ����Ⴂ�܂���
�����̃��[���ɏ]���ĐF�����e�[�v�������Ă܂�
�߂��˂� STAHLWILLE �i�X�^�r���[�j�Ƃ����h�C�c�̃��[�J�[��
�~���[�łȂ��̂͂����̂ł����A�\�ʂɓʉ����������肵�ăC�}�C�`���ȁE�E�E
�߂��˂��M�A�����`���X�g���[�g�^�C�v���D��
�g���ɂ����ǖʂ������̂ł����A�{���g�E�i�b�g�ɒ��ڃg���N�������銴���������ł���
2009 �N 12 �� 05 ���i�y�j�y �V�r�b�N�^�C�v R �̃t�����g�|�������t�b�N
�z
�t�����g�̌����t�b�N�����
�T�[�L�b�g�𑖂肽���Ă����ꂪ�Ȃ��Ƒ���Ȃ�
�����̌����t�b�N�͎ԗ��E�O�̉��ʂɂ���
������Ɉ����ς���ƃt�����g�X�|�C���[�ɂ��Ȃ�̃_���[�W���\�z����܂�
�U�X�T�������ǁA�t�����g�o���p�[�Ɍ��������K�v�ȃ^�C�v�ɂ��邵���Ȃ�����
���̓���肪���܂ł���Ȃɒ����Ԃ������Ă��܂����킯�ł�
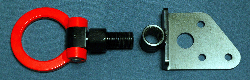 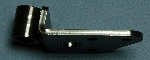
�t�b�N�̃����O�ƃ}�E���g�������ł���^�C�v
�t�����g�o���p�[���ɂ���r�[���̉E�����t���l�W�Ƀ}�E���g�����t����
�t�b�N�����t���錊�ɍ��킹�ăo���p�[�ɂ�����������K�v������
�}�E���g�͂Ȃ����X���Ă��āA���Ԃ��m�F���Ȃ��Ɨ��R�͕�����Ȃ�
�}�E���g�ɗn�ڂ��ꂽ�l�W�͌Œ肪�セ�������A����Ȃ��̂ł����̂��ȁH
�g�p�ɂ͖��Ȃ����������A�l�W���͗n�ڔM�ŕό`���Ă��čŌ�̕��Ŏ~�܂��Ă��܂��I
�l�W�͒��a 20 mm �Ƃ��Ȃ�̑����ŁA�s�b�` 1.5 mm �ƍז�
�Œ�i�b�g�� 27 mm �� ����ȃX�p�i�͎����ĂȂ����ǁE�E�E
�܂肽���ݎ������A�����ł͓ˋN���ƂȂ��ĎԌ��̓_���炵��
���܂�Ă�����̂ŁA���i�͊O���Ă����̂��ǂ������E�E�E
�{�̂� 503 g�A�}�E���g�� 298 g

���̂����Ƃ���
�Ԃ������͗������� 90���������A30�����ɃN���b�N�������Čy���Œ肳���
�o���p�[�ɐ��m�ɂ��ꂢ�Ɍ���������̂�������E�E�E
2009 �N 12 �� 12 ���i�y�j�y �G�X�e�B�}���� �� �X�^�b�h���X�Ƀ^�C������
�z
12 ���ɂȂ�A�g�~�̗\�z�ł����X�^�b�h���X�^�C���Ɍ���
3 �N�ڂ� BS REVO2 �ł�
�^�C�������̎ʐ^�͂���܂���
M ����i13�j�Ƀg���N�����` 120 N�Em �����ǁA���v���ȁH�E�E�E
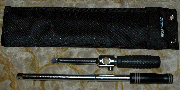 
�^�C�v R �̎ԍڃZ�b�g��g��ł鎞�ɏՓ����������X�g���[�g���̃X�s�[�_�[�����`
�\�������`�Ƀ\�P�b�g�������ł��A���ł�����̂ł�
�ʐ^�E�ł̓Z���^�[�ɌŒ肳��Ă܂����A�[�ɓ������X�s���i�[�n���h���̂悤�Ɏg���܂�
����͂���ł���Ă݂܂���
���ɂ͉��܂����A�L�����L�������ăC�}�C�`��]���ǂ��Ȃ�
�I�C���ł������Ηǂ��̂�������܂��E�E�E
�ł��A�d���C���p�N�g���g��Ȃ��Ă�����ŏ\���ł��ˁE�E�E
���ߍ��݂� 120 N�Em ���炢�Ȃ�L���b�ƒ��߂��܂�
�d���̓P�[�X�Ȃ��� 1,251 g �ƃY�b�V���E�E�E
�^�C�v R �̎ԍڍH��y�ʉ��v��������͑��X�ɗ��E���Ă��܂��܂���
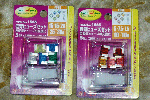 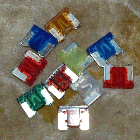
���āA�ߏ��̃I�[�g�o�b�N�ɍs���ă^�C�v R �p�̃q���[�Y�Z�b�g���Q�b�g
�o����͂܂��g��Ȃ����̂Ǝv���܂����A�O�̂��߁E�E�E
�i �N���}���x�ɂ��̃N���}�ɍ����q���[�Y��������Ă��܂����A�g�������Ƃ͂Ȃ�
�j
����͒�w�q���[�Y�Ƃ����T�C�Y�ŁA�Ƃɂ����������I
�i��w �� �Ȃ�ƓǂށH�E�E�E�e�C�n�C�H�H�j
�Ђ͖� 11 mm ��������܂���
��������ɂ������K�l���Ȃ��ƁI
���Ƃ����猩����̂���ςł��傤�H
�ꉞ�ԍڂ��Ă��������ȁE�E�E
���E�E�E

| �����Ƀ��j���[�t���[�����Ȃ��Ƃ��� HOME ���炨���肭������ |
|