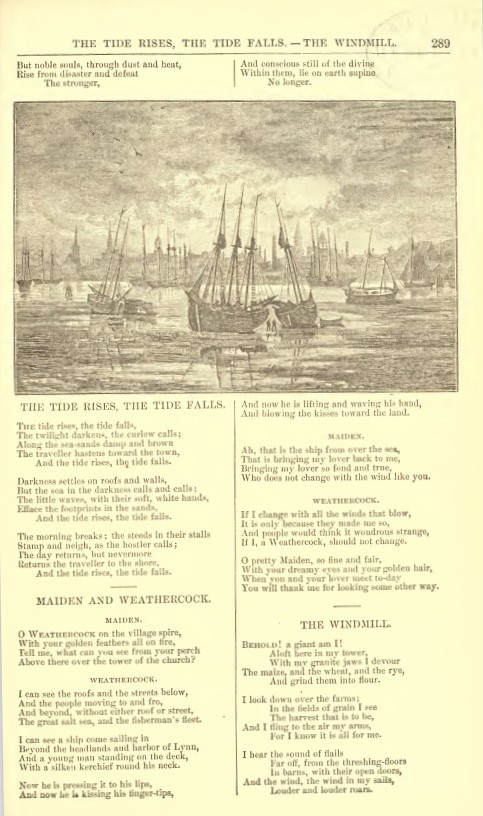草 枕 2014
草 枕 2014
Wandering in 2014
去年今年
- 12月29日、朝は晴れていたが、時折雪がちらついて寒い。東山の墓掃除をする。夏に行けなかった西山の墓所の折れた木の枝なども片付ける。
30日、餅を搗く。今年も3升で、神仏に供える二重ねと餡餅を少し、あとは平餅にする。午後同級生のK氏を訪ねる。中学の修学旅行のガリ版刷りの「しおり」をコピーしていただいた。夜、隣家のM氏と歓談。
31日、裏の物置の掃除をする。戦前戦後の家族の写真や私の小学校から高校までの日記などが出てきた。古い写真は1年かけて整理したばかりなのに、また仕事が増えた。日記を読み直す気力はないので、ぱらぱらとめくって埃を払い、元の場所に仕舞った。高校から大学までの手紙もあり、親からの仕送りの現金封筒が、コクヨの便箋に書いた便りを同封して全て残っていた。自分で残したものには違いないが、これも読む勇気はなく、箱に戻した。
- 1月1日、午前0時過ぎに龍神社と千燈寺へ初詣。帰りに空を見上げるとオリオンが南中していた。午後千燈寺護摩堂跡から観音堂を経て不動山へ登る。馬の背を吹き抜ける風が強い。
2日、アーサー・ランサムのシリーズ第4巻「長い冬休み」を読む。小学校高学年向けの本だが、面白い。ご近所から手作りの豆腐をいただく。
3日、買い物の帰りに散歩途中の同級生のYさんに逢い、路上で立ち話をする。
4日、隣のK氏来。しばし歓談。夕方、赤根の温泉へ。
急趨華圃
- 1月20日、大寒。旧「東京国見会」の事務局の方から2月の「大分学講座in東京」のご案内をいただいた。今回のテーマは、国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会会長の林浩昭さんの講演とその後の交流会だ。林さんは若くして国東に帰農し、農場を営んでおられる。氏の好きな言葉は三浦梅園の、「欲識華
與先繙華譜 急趨華圃」(花を知ろうと思えば、図鑑を開くより先に、急いで花畑へ走れ。)とのこと。2月にはできれば参加してお話を伺いたい。
南山城と桂離宮
- 1月27日、京田辺と木津の寺を巡る。観音寺、岩船寺、海住山寺で十一面観音や五重塔などを拝見した。このあたりをJR奈良線や近鉄京都線で通り過ぎたことは何度もあるが、歩くのは初めてだった。木津川とその流域の風土に魅せられた。
28日、念願の桂離宮を参観。あいにく整備工事中で、池の水がかなり抜かれていたが、興醒めというほどではなかった。ただ、水がなくなった庭と枯山水とは、やはり違うものだと、つまらないことを思った。
離宮から東山まで歩いて、高台寺のあたりで昼食。祇園で福栄堂の団子を買って帰る。
 |
| 京都下河原町石塀小路 |
干し野菜
- 2月8日、未明から降り始めた雪がかなり積もっていて、明るくなっても降り止む気配はない。長靴を持っていないので、ずっと使っていなかった冬山用の登山靴を引っ張り出して、リュックを背負い、散歩と買い物に出かける。雪を踏むとビブラム底の感触が頼もしい。雪はわずかに埃の匂いがした。散歩道の景色は、降る雪で視界がきかない分、普段よりきれいに見える。
本屋で、アーサーランサムのシリーズ第8巻「ひみつの海」と、塩野七生さんの新著「皇帝フリードリッヒ二世の生涯」を買う。
9日、晴れたので、昨日買ったダイコンを千切りに、ナスを輪切りにして、干し網に並べて干す。年末に干した赤トウガラシは冷蔵庫に入れてあり、時折1、2個ずつ輪切りにして、うどんなどにふりかけている。ナスはスパゲティにもよく合う。玉ねぎやニンジンも切干にするが、そのまま食べても美味いので、専ら酒のつまみにしている。
 |
| 中央林間の散歩道 |
浅い春
- 2月25日、久しぶりに横浜を歩く。先週の雪が建物や木の陰にわずかに残っている。赤レンガ倉庫の広場では、スケートリンクの撤去作業をしている。風は冷たいが、陽射しは強く、港には早春の気配が広がっている。
運河寄りのレンガのベンチに坐って、持参の弁当と缶ビールで昼食。山下公園から元町まで歩いて、ウチキで食パンを買い、中華街から地下鉄に乗る。少し暖かくなって、花粉の季節が始まった。
 |
| 大桟橋近くの船溜り |
有朋自遠方来
- 3月は、このホームページのページ数を減らしたり、過去のスケジュールを整理したり、まだ映るブラウン管テレビを液晶テレビに取り替えたりしているうちに過ぎてしまった。花粉症が治まらないこともあり、散歩以外の外出は控えて、専ら内向きの仕事に励んだ。
4月3日、朝からの冷雨で満開の桜が少し散り始めた。夕方、最寄駅で友人のM氏と2年ぶりに会い、他の友人も交えて行きつけの店で懇談。彼は筑波で数ヘクタールの農園を経営しており、休む暇もない身だが、ピンポイントの空き時間に訪ねてくれた。日付が変わる頃まで引きとめてしまった。時には雨もいい。
恩師の葉書
- 4月14日、小学校の恩師からのお便りで、昨年末から入院されていたことを知った。文面では、気丈な先生も心弱くなったご様子だが、「嵐が去れば必ず日の差す時がやって来る 私はそれを信じて嵐の中を力の限り生きてきました」と力強く書かれていた。
先生は感情の量が並外れて大きい。お目にかかると言葉が次々に湧き出て、あたりに風が吹き起こるようだ。ご高齢の今でも現役の教育者だと思う。まずはご退院おめでとうございます。
「女のいない男たち」
- 4月22日、花粉症もようやく終息し、鶯や雲雀が鳴き始めた。まだ塩野七生さんの「皇帝フリードリッヒ二世の生涯」を読んでいる。時代感覚に乏しいので、世界史年表で、この頃日本では源氏が末期を迎え、中国ではチンギス汗が台頭した、などと前後左右を確認しながら読んでいると、たびたび脇道に逸れてしまい、捗らない。18日には村上春樹さんの久しぶりの短編集「女のいない男たち」が出たので、さらに道草を食ってしまった。
女に去られた、あるいは去られようとしている男たちを6つの短編小説で描いている。第1篇の「ドライブ・マイ・カー」に出てくる北海道の町名は、文藝春秋掲載時の実在の町名「中頓別町」から「上十二滝町」に差し替えられていて、そのことが「まえがき」にも触れられていた。円満に解決してよかった。いつか読み返した時に、レコードに付いた小さな傷のように、このことを思い出すかもしれない。傷は曲とは関係ないけれど。
村上さんの世界をしばし漂ってみた。
太郎天
- 5月5日、地区の「妙見祭」に参加する。朝方の雨で、今年は山上の社ではなく、千燈寺で参拝した。妙見とは北極星のことで、仏教では北斗北辰妙見大菩薩という「役職名」を持っている。妙見和讃を唱え、清めの酒とご飯とイリコをいただく。
6日、千燈寺の豪宏さんを先達に、西の不動の太郎天石窟を訪ねた。西の不動一帯は、屏風のような岩尾根が東西方向に数本走っていて、太郎天を祀る石屋は、写真の大不動石屋からは南へ3つ目の尾根の岸壁にある。石窟からは、足下に小不動と大不動、伊美川を挟んで東の不動山、北には鷲の巣岳と姫島が一望できた。
太郎天さんは、今は千燈寺本堂に住んでいるが、北面する石屋からは鷲の巣岳の上の北極星が真正面に見えるから、妙見さんとは、ここで数百年もの間対面していたことになる。先人は石屋の位置を、北極星と鷲の巣岳を結ぶ線上に決めたのかもしれない。
豪宏さんが枯れ枝を拾って、かつて像が安置されていたあたりに置いた。太郎天が持つ蛇の代りだろうか。日没前に下山する。
 |
| 西の不動からの不動山 |
生きているものの数え方
- 6月7日、朝6時台のラジオで、作家の冲方丁(うぶかた とう)さんの話に聴き入った。氏が友人らと飲みながら話したことで、「生きているものの数え方は、その死後のかたちではないか」という話だ。
例えば、牛や馬などの動物は『頭』、鳥は『羽』、魚は『尾』、蟹は『杯』など。そして、人は『名』。人が死後に残すのは名前だと、話を締め括った。冲方さんの本は読んだことがないが、お話を聞いて、読んでみたいと思った。
午後、ミヒャエル・エンデの「モモ」と塩野七生さんの「皇帝フリードリッヒ二世の生涯」をようやく読了。
夏至
- 6月20日、人間ドックを受診した。頭と性格以外には、特に悪いところはないとのことで、ひとまず安心した。健診を意識していたわけではないけれど、成り行きで3週間ほど禁酒していたが、明日解禁できる。
明日は夏至だから、久しぶりに縁起物の冬瓜を食べてみよう。冬瓜と厚揚げの煮物で日本酒をやる、というのも悪くない。皮はキンピラにしても旨い。ただ、冬瓜は大きいから、適当なサイズのものが見つかるかが問題だ。
初蝉
- 7月19日、国立能楽堂で興福寺勧進能をみる。勧進の主な目的は約300年前に焼失した中金堂の再建で、4年後の竣工をめざしている。今年が12回目で、第一部の狂言「蚊相撲」と能「百万」を拝見した。
「百万」は、能の上演順(神、男、女、狂、鬼)の4番目の「狂」にあたる、「四番目物」の名曲だ。わが子と生き別れ、物狂いになった女が、京都嵯峨の清凉寺の大念仏会に現われ、念仏を唱え、身の上を語り、舞を舞い、探し求めていた我が子と巡り会う。「思へども たまたま遭ふは優曇華の 花待ち得たり 夢か現か幻か」と喜び、共に奈良の都へ帰っていく。
開演前の西野春雄さんのお話では、「百万」の原作は観阿弥で、これを子の世阿弥が改作したとのこと。今年は世阿弥生誕650年で、彼はシェイクスピアのちょうど200前に生まれたとの紹介もあった。
千駄ヶ谷の銀杏並木で、今年初めてセミの鳴き声を聴いた。去年の初蝉も勧進能の日だった。まもなく梅雨明けだ。
マツバボタン
- 8月9日、台風11号が接近して風雨が次第に強くなる。午後近所のKさんと夷谷温泉へ。ここは初めてだ。薄茶色の湯は錆びた鉄の匂いがした。入湯料300円也。
10日、一日中不要物の整理をする。見覚えのある机、椅子、古い飯台、10数組の布団や毛布、座布団、植木鉢とプランター、食器、ブラウン管テレビなどの家電品、等々。数年前に母屋の二階の古畳を全て剥ぎ取って、鼠が隠れるところもない状態にしたが、それ以来の作業になった。ゴミのように見えても、親にとって意味がありそうなものは棄てられないので、選別には時間がかかった。
11日、町でバイクのエンジンオイルを交換する。途中、友人二人、中学時代の音楽の先生に逢う。先生はお元気そうだ。「頑張りなさいね」「はい」昔と変わらない。
12日、午前中墓掃除、杉林の中なので草は生えないが、枯れ枝や落ち葉が多い。午後、市の臨時ゴミ収集車が到着。集めていた不要物を積み込む。2トン車が一杯になり、積み残しがあったが、今回は諦める。あと1、2回で何とかなりそうだ。
13日、大分から友人が来る。共に中学の恩師の初秋祭にお参りし、K氏宅を訪問する。初盆のT氏宅も訪ね、大分での秋の再会を約して別れる。
14日、Kさんと熊野磨崖仏を拝観する。彼は小学校以来、私は初めてだ。不動明王さんは近づく雷鳴の中でやや不機嫌そうだ。長い石段を下ると、雨が降ってきた。
15日、小学校以来の友人が遠方から来訪。2年ぶりだ。夕方、赤根温泉で4人の同窓会。話し足りず席を移して二次会。かろうじて午前様は免れた。
16日、久しぶりに晴れ間が覗く。夕方から隣家の友人二人とわが家で懇談。楽しく夜が更けた。
17日、庭一面に暑苦しく繁っていたヒメマツバボタンを抜いたら、マツバボタンが数株残った。別名は日照草、天気草、または爪切草。このあたりでは「いみり草」と呼んでいた。「いみる」とは、増えることで、この草は放っておいても元気に育つ。
18日、甘夏畑の草を刈る。初めての4サイクル刈払機の調子も良い。午後激しい夕立が来て、のち晴れる。夕方、赤根温泉の露天風呂で中学の同級生と逢い、湯につかりながら、来年の同窓会の予定を聞く。今度は出席するよと約束した。
 |
| 庭のマツバボタン |
雨の日
- 9月3日、都内の書店に本を探しに行く。本は見つからず、日比谷宝塚劇場近くのゴジラ像の横のベンチに坐って、持参の弁当を食べる。雨は今にも降りそうで降らない。
夜、ネットで、今日見つからなかったヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの詩集を注文する。高校の受験雑誌の「今月の詩」のページに載っていた、「潮は満ち、潮は引く」という詩の断片がずっと消えずに残っていて、もう一度読みたいと思いながら、この歳になってしまった。
彼の詩は、格言めいた意訳をされることが多い。「雨は一人だけに降り注ぐわけではない」、「降り止まない雨はない」(「雨の日」)など。意訳は嫌いではないが、好きでもない。
詩を訳すのは難しい。意味を伝えようとするからだ。意味を覆っている言葉の包みを解くと、間違いなく詩の音楽性が壊れてしまう。ビートルズの曲を日本語で歌うようなものだ。本が届いたら、意味は後回しにして、まず声に出して読んでみよう。
筑波山
- 9月6日、会社の友人と筑波山に登る。といっても、ケーブルカーの山頂駅から600メートルほど歩いただけで、登山とは言えない。山頂からは、昨夜山麓のホテルからかすかに見えた、都心の高層ビルが今朝は見えない。メンバーは新入社員の頃からの先輩、同輩で、朝まで語り、飲み明かした畏友もいる。最近はそれぞれジェントルになり、翌日の先輩からのメールには、「皆さんの酒の量が減ってきたのも印象的です。」とあった。
筑波山はその歴史が古いことで、深田久弥さんの「日本百名山」に選ばれた。万葉集にも多く詠まれているが、深田さんが「日本百名山」に載せている歌がいい。
「草まくら 旅の憂を 慰もる 事もありやと 筑波嶺に 登りて見れば 尾花ちる 師付の田井に 雁がねも 寒く来鳴きぬ 新治の 鳥羽の淡海も 秋風に 白波立ちぬ 筑波嶺の よけくを見れば 長きけに 思ひ積み来し 憂は息みぬ」(巻九)次は麓から歩いて登りたい。
 |
| 筑波山頂からの関東平野 |
光学的読み取り
- 9月17日、ロングフェロー詩集が届いた。没後2年目の1884年に出版された原本を2012年に再版したものだ。
本には、原本にはあったはずの挿絵がないので、がっかりした。また、巻頭から最終ページに至るまで、改ページはおろか、改行が一つもないことに驚いた。詩と詩、題名と本文との区切りもない。さらに、目次のページ数が本文と合っていない。
序言を読むと、古い原本を光学的に読み取ったため、1%ほどはスペルが正確でなく、目次のページ数も同様だ、とあった。
冗談だろうと思いながら、高校時代に読んだ、「潮は満ち、潮は引く」という詩を探す。苦労して見つけたら、タイトルは「THE TIDE EISES, THE TIDE FALLS」となっていた。RがE。1%にヒットしたのだ。
気を取り直して、序言の続きを読んだら、「読者の便宜のために、原本のフリーコピーを提供する」とあった。いい加減だが、親切なのだ。裏表紙のバーコード番号を入力して、出版社の会員ページから原本をダウンロードした。それは間違いなく130年前のもので、当然だが、目次も正確で、イギリスの画家フォスターの挿絵もあった。しばらくきれいな挿絵を眺める。
結局、役に立ったのは裏表紙のバーコードだけだ。本はどうしようか。
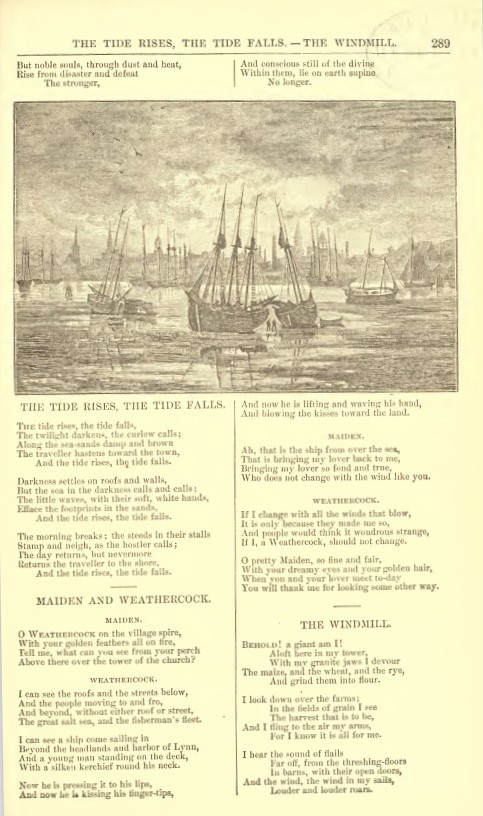 |
| 1884年版 |
ロードバイク
- 10月3日、町田市街を抜けて、鶴見川の支流の恩田川の流れに沿って歩く。河畔の散歩道をロードバイクが何台もすり抜けていく。後ろから来るサイクリストのほとんどは徐行してくれる。「通ります」と声を掛ける人も多く、不躾にベルを鳴らすような人はいなかった。
鍛えた体で漕ぐ細いフレームとタイヤが、ベアリングの軽やかな音を残して遠ざかる。見ているうちに、スマートな自転車を手に入れて、気分のいい道を走ってみたくなった。
秋の日差しは夏のように強い。高ヶ坂の焼き菓子店、成瀬のパン屋と和菓子屋に寄って、成瀬台を越えて帰る。3万歩には少し足りない。
 |
| 町田市高ヶ坂の菓子店 |
北上川と衣川
- 10月20日、盛岡駅から北東に数分歩くと北上川に出会う。川に架かる旭橋の中央には張り出しがあり、下を見ると北上川が川幅いっぱいに流れている。雨上がりなので、流れが速い。川上に目を上げると、岩手山が聳えている。南部片富士といわれるだけあって、稜線が美しい。
橋を渡って材木町を歩く。市が出ていて賑やかだ。
21日、衣川を南に渡り、平泉へ。中尊寺と毛越寺を参拝した。ともに天台宗の寺院で、国宝の阿弥陀堂があるなど、故郷の国東半島の六郷満山寺院と通じるものがある。国東は宇佐神宮、ここは奥州藤原氏の庇護のもとで栄えた。
寺域は広く、創建者の構想の大きさに驚いた。往時の堂塔は、金色堂などの他には見ることはできないが、それでも北方の王者の名残を感じることができた。奥州は、当時は事実上の独立国だったのではないかとさえ思った。
 |
| 毛越寺庭園 |
竹宵前夜
- 10月31日、大分市の友人宅を訪ねる。この前お邪魔したのは2003年の夏で、冷夏だったのを覚えている。
雨の中を臼杵の町を案内して貰った。国宝の石仏を初めて拝観して、「早春賦」の作詞で知られる吉丸一昌さんの記念館を訪ねた。夕暮れの町は明日の「竹宵」の準備にとりかかっていた。二王座の石畳を歩く。
夜は大分の同級生数人と旧交を温める。話は尽きず、夜も更けた。
 |
| 臼杵市 二王座辺り |
秋の上野
- 11月7日、上野の博物館で日本国宝展を見る。以前奈良や京都で拝観した仏様も、ここでは芸術品として鑑賞できる。約100点の過半は初見だ。薬師寺の休ヶ岡八幡宮で拝観できなかった神功皇后・僧形八幡神坐像、安倍文殊院の善財童子立像に見入った。
公開中の本館庭園を歩いて、上野から乃木坂へ。日展を覗いて、新宿から帰る。
 |
| 国立博物館本館庭園 |
初冬
- 12月3日、高尾山口の改札で友人のC氏と待ち合わせ、近くの蕎麦の老舗、高橋屋で会う。3年前の北鎌倉以来だ。八王子の地酒「桑乃都」を飲みながら話は尽きない。彼の点字ボランティア活動のこと、最近読んだ本、私が先日訪れた盛岡と平泉の感想など。岩手は彼の出身地でもある。2人で5合ほど飲んだところで、締めの蕎麦にした。
8日、思い立って鎌倉に行く。瑞泉寺か東慶寺かと迷ったが、江ノ電鎌倉駅から近い東慶寺に足を向けた。
人と車の多い巨福呂坂方面を避け、回り道をして佐助稲荷から源氏山に登って、化粧坂を下り、扇ヶ谷から亀ヶ谷坂を越えて行った。寺の紅葉も散り始め、墓苑は静かだった。小林秀雄さんの墓を訪ねて、浄智寺から源氏山の尾根道を辿り、木の実を頬張っているリスの番いなどを見ながら、銭洗弁天に下った。
 |
| 東慶寺 |
冬至
- 12月22日、書店で来年の理科年表と日記を買い、帰って大掃除をする。換気扇の羽根を磨き上げて終了。ついでに読みかけの本を読み終える。「物理学はいかに創られたか」(アインシュタイン、インフェルト)、「おどろきの中国」(橋爪大三郎×大澤真幸×宮台真司)、「新・戦争論」(池上彰・佐藤優)、「地方消滅」(増田寛也編著)、頭の中に急いで掃き込んだだけだが、これも大掃除。
23日、未明に起きて、こぐま座流星群を見ようと30分ほど北の空を眺めた。見つからないままに空が群青からオレンジに変わって、明るくなってしまった。寒い。振り返れば、南西の空にしし座のレグルスが消え残っていた。レグルスは獅子の心臓だ。



![]() 草 枕 2014
草 枕 2014