| 1.青 柳 坂 |
|
|
| 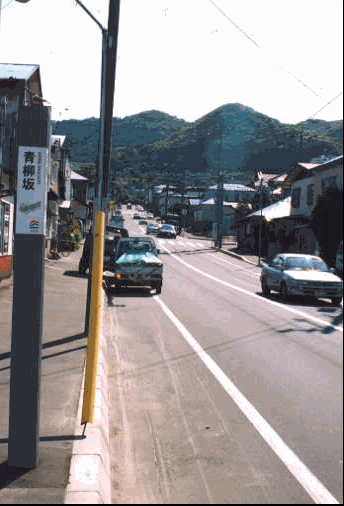 | 以前は、聖天坂や春日坂とも呼ばれたが、現在は町名の青柳町から命名されている。坂の途中にある天佑寺には仏教を守る大聖歓喜天という神様“仏様かな”が祀られていて、事業を営む人の信仰を集めている。 |
| 2.桜 坂 |
|
|
|  |  |
坂の命名の由来を示す文献を見つける事は出来なかったが、この坂の由来は、函館公園沿いに咲き乱れる桜の木からであることは、疑い無いことであろう。春に谷地頭から函館公園を見ると、公園全体が「桜色」に染まる。
すっかり、函館公園の駐車場となってしまっているが、整備次第では趣ある坂に変わることであろう。今年は、「桜坂」のヒットもあり、整備しても損は無いと思うのですが..。 |
| 3.あさり坂 |
|
|
|  |
以前は、坂の麓に有名な肉屋さん兼すき焼き屋さんの「阿さ利」があるのであさり坂かと思っていたが、本当はブラキストンと並んで日本の植物、動物の分布等で有名なアメリカ人のエドワード・モース等が当時周辺にあった貝塚を発掘し、たくさんのあさりなどの貝を発見したので、この名前となったとか。
そうすると「阿さ利」の名前は、逆にこの坂から付いたのかも? |
| 4.護国神社坂 |
|
|
|  |
名前のとおり、護国神社へ通じる、広い坂で、以前は護国神社の昔の名称である招魂社の坂と呼ばれていた。
麓に函館の商業の先人、高田屋嘉兵衛の像等があって、もっとメジャーな坂であっていいのだが、観光地から若干外れているせいで、静かな坂となっている。もっとも、観光地化されていない分だけ、昔の函館の情緒を残していると言うべきか。
以前は、汐見坂と呼ばれていたそうで、坂に面して門を作ると倒産することから「倒産坂」という裏の名前もあったとか。 |
| 5.谷 地 坂 |
|
|
| 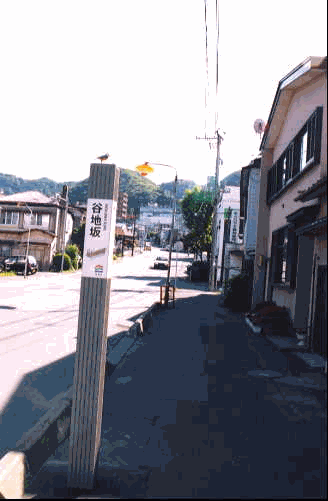 |
昔は、谷地頭に続く道があったことから、この道の名前が付いたそうで、函館大火の跡の区画整理等で、昔の坂が次々と改修される中で、安政年間からあまり位置が変わっていない古い坂である。
傾斜も外の坂に比べると緩く、普通に歩いていると「坂」であることを見逃してしまうほどで、「控えめな坂」である。 |
| 6.南 部 坂 |
|
|
|  |
坂の上、現在の函館壱番館の場所に、北方の警備のために派遣された南部藩の陣屋があったため、この名前が付いた。
当時は、蝦夷地は、幕府が直接管理する直轄地であったため、幕府にゆかりが深い南部藩にその任務が分け与えられたようだか、未開の蝦夷地に家族を残して派遣された藩士達は、さながら江戸時代の「防人」のようであったに違いない。
坂の下には、昭和四十年代半ばまで、丸井今井があったので「丸井さんの坂」しても親しまれたようだ。 |
| 7.二十間坂 |
|
|
|  |
道幅が約36メートル(二十間)あることから、この名前が付けられた。昔は、もっと狭い坂がいくつかあったようであるが、明治初期の大火の跡に「防火線」として、作られたものである。函館には、このような「防火線」として使われている道や坂が多い。
戦前には、函館山にあった「重砲隊」の弾薬の運搬にも頻繁に利用されていたようである。
坂の両側には、函館の洋食の老舗「五島軒」や豪邸が建ち並び、函館の坂の中でも、華やかな坂の一つである。 |
| 8.大 三 坂 |
|
|
|  |
1857(安政4年)に書かれた文献では、当時この坂に木下という人が住んでいたため木下の坂と呼ばれていたが、その後、近くの基坂にある函館奉行所に公用で訪れた、周辺に住む平民が宿泊した「郷宿(ごうやど)」を経営していた大三印義兵衛という人物が住んでいたため、いつのまにか大三坂と呼ばれるようになった。
カトリック教会、ハリストス正教会、亀井勝一郎邸も近く、元町地区では一番お勧めの観光スポットである。 |