| 鉄友MK氏自作のレトロなパワーパック制御器 061105 |
|
先日ひょんなことから、鉄友のMKさんが製作したパワーパックをお借りすることができました。それはM氏が今からおよそ20年程前(1980年代)に自作されたもので、鉄道雑誌の製作記事(ブレーキと緩行運転について)を元にしているそうです。その記事(TMS(注1))は更に以前に掲載されたもので、その後部品を秋葉原より調達し製作したものだそうです。
|
(注1)
その記事は1984年1月号、2月号(NO439・440)ということが、その後判明したそうです。
|
|
|
こういった、鉄道模型とラジオ工作の融合も楽しいものですね。
|
|
| お借りしたパワーパックの写真 |
|
 |
| 2006/10 |
|
| パネル全面|リア面(ヒューズ・端子ほか) |
| スピードボリューム|ブレーキ&スイッチ |
| 電圧計(左) |電流計(右) |
|
|
きょう体(金属の箱の部分)は部品としてお店から調達できるそうです。また、電流・電圧計も装着しデザインも垢抜けています。一目見て素晴らしい作品(プロの職人技的・・)でしたので、レトロな雰囲気を味わっていただくため、ここにご紹介させていただきました。スイッチやダイヤルの穴も金属ドリルで自作しているそうです。
整流器はセレンでなく、ブリッジダイオードでした。その後、MKさんから回路図をお借りして見てから、分かりました。現代では、簡単な整流部品が販売されているようですね。(汗)。。
|
|
| 盤面には通常のスピードダイヤル(パルス制御(注2)の加速ボタン)の他に、ブレーキダイヤル(減速ボタン)があります。緩行運転を楽しめる様に設計しているわけですネ。現在はカトーやトミックスからも運転台形式のパワーパックが完成品の形で市販されていますが、当時としては、珍しい斬新なアイデアだったと推察します。 |
|
|
|
|
|
|
| (注2) <パルス制御について> |
「制御回路の電圧の変化によりパルス(周波数と波形)の通電率を変える性質?」を使い、モータの回転数を制御するもの。パルス制御は自動加速・減速やスロー運転を可能にするため鉄道模型のコントローラに応用されるています(昔、雑誌で読んだことあり)。少し専門的ですが・・原理や仕組みを垣間見ることも、楽しいものです。
|
| ここから、ちょっと「大名鉄道ガリバー線」さんに寄り道してみましょう。 |
|
詳しくは、下記の「庭園鉄道・(大名鉄道ガリバー線)さん」の
ホームページをご参照ください。 |
| (鉄道模型の電子制御はここをクリック) |
| (自動加速・惰行・減速の原理はここをクリック) |
| ↓ |
| コンデンサーを巧みに操り、制御回路の電圧を緩やかに変化させている様です。 |
| 以上、庭園鉄道ガリバー線さんのHPでした。 |
↓
以下、パワーパックの話に戻ります。 |
|
| <HOでの試運転の様子> |
お借りした、トランジスタコントロールを実際のHOトラックを使って試運転してみました。まずは、電源を入れると緑のパイロットランプが点灯します。次に電源スイッチの左隣にあるキーをNOR(ノーマル)に倒してみますと、START・SETボリュームのダイヤルが電圧調整となりマニュアル運転のモードとなっているようです。次に、スイッチをTRCON(トラコン)にセットすると、SPEEDボリュームが、加速調整の役割、BRAKEボリュームが減速調整の役割を担っています。そのため、SPEEDボリュームをまわしている間、車両が徐々に加速し、ボリュームをOFFにすると惰性に変ります。次に、BRAKEボリュームを回しONにしている間中、減速開始します。
なお、START・SETボリュームは、加速時の初期値をかねているので、ゼロにあわせておけば、まさに超低速走行が可能でした。 |
|
電圧計(5V弱)・電流計(0.2A)の針が振れたところ
試運転の風景|トミックス製トラコン(左)と並んで
HOロコとパワーパック
|
|
|
|
|
| 「TMS764号(2007/3)」にリーベ鉄道が紹介されました |
|
私が小学生のころから時々愛読していたTMS誌にリーベ鉄道の紹介記事が掲載されました。というのは、第29回(2006/6月)レイアウトコンペに応募していたところ、努力賞をいただいていたのですが、その時投稿していた記事と写真が忘れたころの翌年冬発売(070220)の764号に掲載されていることに気づき、びっくりしました。長い歴史のある本誌に仲間入りすることができて、大変うれしく思いました。楯と表紙は下記の写真です。
|
【090103記】 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
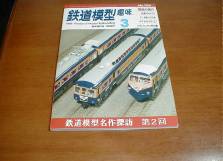 |
| TMSレイアウトコンペの楯 |
|
|
TMS764号の表紙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
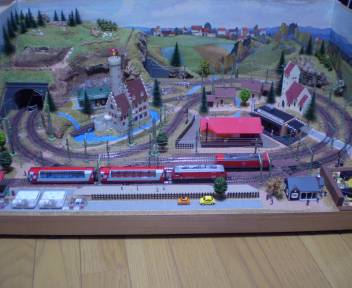 |
| リーベ鉄道全景 |
|
|
|
| **補足(日経新聞にTMS編集長の手記掲載)** 【140315】 |
|
| その後ひょんなことから鉄友MKさん(藤沢市在住)から電話があり(3/6)、日経新聞に「TMS編集長」の手記が出ていた旨お知らせをいただきました。また、後日切り抜き(本紙)まで送付いただき、嬉しく思いました。ご高配ありがとうございました。記事によりますと編集長は「石橋春生(いしばしはるお)氏・85歳」とのことでした。TMS創刊がS22(1947)年ですから、その当時から編集に携わっておられたとのことです。TMS誌はどことなく一本筋が通った感じが漂っていますよね! これは編集長のお陰だったんだなぁ〜と改めて思いました。また、つたないリーベ鉄道についても上記のレイアウトコンペやTMS764号への記事掲載の時に、編集長がおられたんだな!と思うと、感謝の念にたえません。ありがたい気もします。しかし、さすがに編集部の高齢化もすすんでいるそうです。心配ですね! (^^;) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
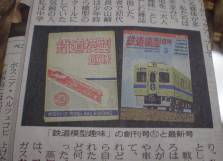 |
| TMS編集長紹介記事(日経新聞) |
|
|
創刊号(左)と最新号
(2014年3月・862号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TMS編集長の手記を要約すると次の通りです。 |
|
| ① |
創刊号から数えて、のべ860号を発行、
日本で最も古い鉄道模型専門誌 |
| ② |
初代編集長は山崎喜陽氏、
石橋氏は中学時代に当該クラブに入会 |
| ③ |
英国、米国、独国の鉄道模型雑誌をめざした
「大人の趣味」を提案 |
| ④ |
新製品紹介は自宅の地下室のテスト線区で
必ずテスト走行してから記事に |
| ⑤ |
85歳の今も、月に20ページを執筆 |
| ⑥ |
日本の鉄道模型ファンは10万人との推定
(30年前ごろから女性ファンも増えて) |
| ⑦ |
編集部の高齢化が心配、増刊は年2回、
コンペも含め、出来るだけ長く続けたい |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【140315記】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

