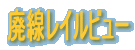
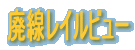
![]()
| 2−6 宇都宮起点10〜12マイル (1)引用 古田から4マイル43チェーンに長久保停車場を設けた。現在の蒲須坂駅南西1.5キロ、氏家(原文は矢板・・誤記と思われる)北西3キロの地点である。 |
 |
(2)10〜11マイルの現状 この区間には長久保停車場が存在した。その痕跡は、ほとんど残っていないが周辺には旧家が多く、今でも日鉄線のことが語り継がれている。 |
| 長久保停車場跡南側の旧線位置と思われる位置から停車場跡方向を見る。駅は、中央の森の左側に存在したものと思われる。奥が矢板方。 (2003.1.19撮影) |
 |
 |
停車場東側から停車場へと伸びていた取り付け道路のあと。現在は、私道となっている。 (2003.1.19撮影) |
| 西側から停車場跡を見る。左が矢板方。なお、この地区の方は、現在でも旧線をはさんで反対側の場所や家をさす「せんのむこう」すなわち「線路の向こう側」という言葉を使っておられる。また、聞き取りでも他の地区に比べ高い確率で旧線をご存知の方に出会えた。 (2002.3.2撮影) |
 |
 |
(3)11〜12マイルの現状 現在線と合流する旧線の最終区間である。線路跡はまったくといっていいほど残っていない。合流点は、有名撮影地(お立ち台)のすぐ南側である。 |
| 旧線ルートは、押上小の校庭を横切っていたと考えられるが、校庭南側に写真のような顕彰碑が作られている。レールの位置、方向は正確でありどのような方が企画されたのか興味がある。この碑の存在がある限りこの地区では、旧線の存在が長く語り継がれるに違いない。 (2003.1.19撮影) |
 |
 |
顕彰碑から矢板方を見る。この先、市の堀を越える箇所に残されている橋台の一部を小川氏は発見されているが、現在は枯れ草に覆われており、確認することができなかった。 (2003.1.19撮影) |
| 現在線との合流地点を蒲須坂駅北端付近から見る。旧線は、画面左から画面中央の現在線へ向かって伸びていたと思われる。なお、単線時代の本線は現在線の上り線と考えられる。 (2003.1.18撮影) |
 |
| 3.あとがき 宇都宮から12マイル強約20kmの旧線の旅は終わった。距離に比して遺構の数は多いとはいえないが、何れも見る者の胸を締め付けるようなインパクトのあるものばかりだった。それは、長寿を全うして逝ったのではなく、その使命を全うすることなく無念のうちに生を終えたイメージが強くあったからかもしれない。また、印象に残ったのは旧線の1/2強の区間において新幹線と極めて近い場所に旧線跡があることだ。「最短距離で北を目指す」コンセプトを正確に具現化しようとした当時の技術者の強い意志が感じられた。また、レトロなものをさがすという感覚を、新幹線の走行音がかき消してくれた。「そうだ、この遺構は古臭いものではなく当時の最新技術が生きたまま化石と化したものなのだ。廃線になったM30から時間が止まっているとも言えるのではないか!」その意味でもこれらの遺構は大変貴重なものだ。すべてを現状のまま残しておきたいが、これはきっとかなわぬ願いであろう。が、せめて旧線をいろいろな意味で象徴する存在である東鬼怒川のウエルを、氏家町の誇る匠の博物館「ミュージアム氏家」の敷地内にでも保存することはできないだろうか?明治の匠の技を永遠に語り継ぐために・・・・。 なお、本編に関し私の誤解・思い込みなどにより誤謬がありましたらぜひともご指摘ください。また、旧線の調査は非常に長い期間にわたり散発的に行っております。写真や現状については極力最近のものを用いましたが、さまざまな時期のものが混在していることをお許し願いたいと思います。 |
| 第−章 開通から路線変更まで に旅する 第三章 新線(現在線)を観察する に旅する。 |

トップページに戻る
【お願い】本サイトはフレーム構成です。
フレーム表示されていない場合は
上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る
更新
作成 2002.1.23
Copyright (C) 2002 Daruma-Kozo. All Rights Reserved