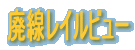
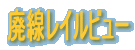
![]()
第三章 新線(現在線)を観察する(その1)
| 第一章で述べたように、新線は、M29.5に着工、翌M30.2.25に路線切り替えを行い同時に、岡本・氏家両停車場が開業した。この時期、当然ながら国有化は行われておらず、旧線建設から10年余を経てはいるが技術的な標準化、鉄(鋼)製品の国産化などは未熟な状況であった。したがって、新線切り替え時の構築物においても旧線と同等の価値があると考えられる。その中のいくつかをご紹介する。それに先立ち、新線関連の略史を記しておく。 <開業・開通> ■M32.10.21 宝積寺駅開業 ■M32〜33頃? 切り替え当時仮橋梁であった鬼怒川橋梁が完成。 ■M39.11.1 日鉄線は国有化され、各線区総称して「日本線」と呼ばれた。 ■T6〜7頃 現在の鬼怒川橋梁(上り線)が完成。 ■T12.2.11 蒲須坂駅開業(T9.12.2より信号場) ■T12.4.15 烏宝線(烏山線)開業 <複線化> ■S32.12.12 宇都宮−岡本 ■S35.10.20 片岡−矢板 ■S36.12.15 岡本−宝積寺 ■S37. 3.19 宝積寺−氏家 ■S39. 6.23 氏家−蒲須坂 ■S39. 9. 3 蒲須坂−片岡 <電化> ■S33.12.15 宇都宮−宝積寺 ■S34. 5.22 宝積寺−黒磯 |
![]()
| 2−1 新線に関する「日本鉄道覚え書」の記述 第二章で引用した「日本鉄道覚え書」には、新線に関して 新設本線は12マイル60チェーンで、長久保駅停車場の北約75チェーンの付近で在来の本線に接続する。現在の、蒲須坂駅北約700メートルの地点にあたる。(中略)線路工事予算27万4千円で、最大の工事は工費予算8万円、全長800フィートの新鬼怒川鉄橋であった。 2−2 新線をたどる(その1) 第一内川橋梁 |
 |
旧線西芦沼の橋台跡は鬼怒川の河岸段丘を下る箇所にあるが、その段丘を南にたどると、新線もやはり鉄橋を架けて段丘を下る。その鉄橋が第一内川橋梁である。場所は、岡本−宝積寺で東京起点116.767kmである。上り線側は、橋台、橋脚とも煉瓦で構築されている。 (2002.10.19撮影) |
| 両橋台とも改造されているが原型をよく保ち現在も列車の荷重に耐えている。質実剛健、飾り気はないが頼もしい。写真は、青森方の橋台。 (2002.10.19撮影) |
 |
 |
中間の橋脚。下流側は橋台と同じデザインである。上部は、コンクリートで補強されている。 |
| 同じ橋台を上流側から見ると、こちらは流線型に仕上げられており、なおかつ原型は段つきであったことがわかる。すなわち、この橋脚の断面は上流に船首を向けた舟型をしているのである。先端部には全高にわたり石材を用い、万全を期している。 |
 |
| 第−章 開通から路線変更まで に旅する 第二章 旧線跡をたずねる に旅する |

トップページに戻る
【お願い】本サイトはフレーム構成です。
フレーム表示されていない場合は
上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る
更新 2003.2.20 新線初代鬼怒川橋梁との関連記述を削除
新線初代鬼怒川橋梁遺構誤認に関するお詫びを掲載。
2003.3.1 新線初代鬼怒川橋梁に関する事実関係調査結果を
2−3項に追記したためお詫びを削除し次ページへの
リンク復活。
作成 2003.1.5
Copyright (C) 2002 Daruma-Kozo. All Rights Reserved