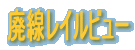
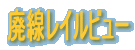
![]()
| 一冊の書籍がある。 大町 雅美編「栃木県鉄道史話」(落合書店) 達磨小僧が栃木に住み着いて以来15年以上バイブルとしてきた書籍だ。このページ、いや「とちレビ」自体この書籍との出会いによって生まれたといっても過言ではない。そして、そこに記された内容は、衝撃的だった。「東北本線は大規模な路線変更が行われていた。それも宇都宮の近郊で!」 それ以来、図書館に通い資料をあさっては現地調査を繰り返した・・・が、新たに発見できた遺構はわずかであった。10年近くの月日が過ぎ、もうこれ以上の遺構はないのではと思い始めたころ、光がさした 小川 幸宏氏の「19世紀に消えた鉄道を追う」 (2004.10現在 移転工事中とのことです) が彗星のごとくネット上に現れたのである。このサイトの調査結果は、秀逸かつ綿密でいかなる書籍より正確だ。そのおかげをもって、達磨小僧はようやく旧線の全貌がつかめたのである。小川氏の調査には及ぶべくもないが、2人の先達に感謝と敬意を表しつつ本題に入りたいと思う。 なお、本ページは 第一章 開通から路線変更まで 第二章 旧線跡をたずねる 第三章 新線(現在線)を観察する で構成されている。 なお、とちレビと時を同じくして「鉄路」さんも旧線を調査されている。あわせてご覧いただきたい。 2004.10 御用川の遺構、東鬼怒川橋梁遺構、富野岡の遺構など状況変化に伴い補筆を行った。 |
![]()
第一章 開通から路線変更まで
 |
(1)建設経過 |
| (2)路線変更 日鉄線開通時、鬼怒川は大規模な治水事業も行われておらず一旦出水すると周辺に大きな被害がもたらされていた。日鉄線も容赦なくその洗礼をうけ、早くもM23.8には西鬼怒川橋梁で橋脚が傾斜する被害が発生し、その後も東西両鬼怒川橋梁で列車の運休を余儀なくされるような被害が続いた。日鉄も護岸の強化など努力を続けたが、恒久的な安全が保証されないとの判断から路線変更が決定した。新線の建設は、 ■M28.3 線路変更申請 ■M28.10 線路変更許可 ■M29.5 着工 ■M30.2.25 新線開通(鬼怒川橋梁は、仮設) と、実工期10ヶ月余というやはり驚くべき速度で完成した。同時に、岡本・氏家の両駅が開業し、旧線および長久保駅が10年余、古田駅はわずか5年余でその歴史に幕を下ろしたのである。 |
| (3)どのようなドラマが・・ この路線変更の経緯は、多くの参考文献に記述があり、お雇い外国人にも対策の調査を依頼したが「打つ手なし」の審判を下されたなどと書かれている。が、この一件で当時の工事関係者が処分されたとの記述はない。天災として処理されたものとおもわれるが、現在で言えば新幹線が災害で路線変更したようなものだ。技術者に寛容な時代背景であったとはいえ、何らかのドラマがあったと考えるのが順当であろう。この区間の工事担当は一等技手小川資源。小川は、後に第5区線も担当している。小川は、あくまで工事担当であり測量を行い路線を決定したのは別人であったと考えられる。 (4)当時の技術 驚くべきは、その工事進捗の速さである。労働力は、農繁期を除き比較的容易に得られたかもしれないが、多くの箇所で並行的に工事が実施されていたのはほぼ確実であり、現場監督的な人材がすでに多く存在していたことを物語っている。橋梁の名人、小川勝五郎の手によるとされる東西鬼怒川橋梁もその完工時期からみて両橋同時工事であったと推測され、有能な部下たちに支えられて工事を進めたことが想像される。明治維新後、わずか20年足らずのことである。このことは、街道工事などで土木工事の基本的な技術や組織の運営方法は明治以前から確立していたことを物語っている。技術者たちは、固有(既存)の手法と、外来の手法をうまく融合させて建設を進めていったのであろう。 |
![]()
| (1)機関車 下に、M26時点の日鉄所属機関車を示す。(機関車の系譜図3より抜粋) なお、日鉄線は、M24青森まで全通している。どの形式がどこに配属されていたかは定かではないが、500・600形式および5230形式が主力であったと推測される。後に主力となる5500形式(2Bテンダ 機関車重量34.07t)はM27の登場であり、旧線も走行したと推定される。(機関車重量=運転整備重量) |
| 形式 | 軸配置 | 製造 | 機関車重量 | 両数 | 備考 |
| 140 | 1Bタンク | 英シャープスチュアート 1875(M8) |
23.37t | 2 | |
| 1290 | Cタンク | 英マニングワードル 1881(M14) |
16.81t | 1 | 善光号 工事用 |
| 1100 | Cタンク | 英ナスミスウィルソン 1885(M18) |
22.96t | 3 | |
| 400 | 1B1タンク | 英ナスミスウィルソン 1886(M19) |
31.65t | 4 | |
| 500 | 1B1タンク | 英ダブス 1887(M20) |
40.06t | 12 | 内両毛鉄道3両 |
| 600 | 1B1タンク | 英ナスミスウィルソン 1887(M20) |
36.88t | 20 | 内両毛鉄道2両 |
| 5230 | 2Bテンダ | 英ダブス 1884(M17) |
29.93t | 12 | |
| 5300 | 2Bテンダ | 英ベイヤーピーコック 1882(M15) |
31.57t | 2 | |
| 7600 | 1Cテンダ | 英ナスミスウィルソン 1889(M22) |
42.80t | 6 | |
| 1850 | Cタンク | 英ダブス 1884(M17) |
41.53t | 6 | |
| 2100 | C1タンク | 英ダブス 1890(M23) |
46.36t | 6 |
| (2)旧線の運転状況 ①M19開業時 一日2往復、ほどなく(長久保開業時)3往復となった。 ②青森全通のM24.9時点 旧線区間を通過する列車(旅客列車)は、3往復であった。 <下り列車> 宇都宮発 9:52(塩釜行) 15:03(福島行) 18:12(青森行) <上り列車> 宇都宮着 8:54(青森発) 12:10(福島発) 16:10(塩釜発) 下り青森行きの宇都宮発時刻が現在の1レ(北斗星1号)と同時刻なのは偶然とはいえ面白い。当時は、青森まで約23時間を要しており評定速度は27km/hほどである。因みに、北斗星では同区間を約8時間、新幹線利用では4時間強である。が、 徒歩で20日程度を擁した時代にその速度は現在の新幹線よりはるかに大きなインパクトを与えたに違いない。 |
第二章 旧線跡をたずねる に旅する 第三章 新線(現在線)を観察する に旅する。 |

トップページに戻る
【お願い】本サイトはフレーム構成です。
フレーム表示されていない場合は
上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る
更新 2003.2.7 サイト「鉄路」にリンク
2004.10.2 御用川 富野岡の遺構関連の補筆
作成 2003.1.1
Copyright (C) 2002 Daruma-Kozo. All Rights Reserved