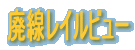
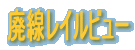
![]()
| 2−2 宇都宮起点1〜5マイル (1)引用 竹林・川俣・大塚・宝井の諸村落を経て、途中240チェーンのゆるいカーブのほかほとんど一直線に線路を進めた。沿線は概ね畠地で切取りや築堤は浅く、大塚村では古墳を貫通・・・・ |
 |
(2)1〜2マイルの現状 この区間に、旧線を偲ばせる遺構は残っていない。地図中央付近から現在道路と旧線の想定位置が重なるが、転用道路か否かは判然としない。小川氏のHPでは、かつて築堤が存在したと紹介されている。 |
| (3)2〜3マイルの現状 この区間にも、旧線を偲ばせる遺構は残っていない。宮環(R119)の建設により周辺の状況も急速に変化している。 |
 |
 |
宮環北側から矢板方を望む。耕地整理により痕跡はない。 (2003.1.12撮影) |
| (4)3〜4マイルの現状 川俣・大塚地区を通過するこの区間には2箇所の遺構が残る。 |
 |
 |
引用文に「古墳を貫通」とあるが、それが高麗神社(たかおじんじゃ)古墳である。説明文にも、封土の一部が掘削されていると書かれている。 (2001.5.20撮影) |
| 宇都宮方の旧線と推定される位置から見た古墳。古墳の前後に旧線の痕跡はない (2003.1.12撮影) |
 |
 |
古墳を掘削した切通し。写真の左右が法面である。一部は埋め戻されているようだが、古墳の中央部を貫通していた旧線の状況は今でもよくわかる。奥が宇都宮方。(2003.1.12撮影) |
| 矢板方から切り通しの様子をみる。画面中央を旧線が通過していた。 |  |
 |
もう一つの遺構である橋台跡。宇都宮方のみが現存している。川の名前は、1/2.5万地図に御用川と記載がある。なお、この川も、旧線と直交するように改修されてクランク状になっている。 |
| 住宅と資材置き場にはさまれ目立たない場所にあるこの橋台の観察は、個人宅の庭から川へ下ろさせていただく必要がある。苔がはびこっており、意匠の観察もできない。 |  |
 |
(4)4〜5マイルの現状 引用文にある「途中240チェーンのゆるいカーブ」がどこに存在したかが旧線をたどる上で難題であったが、各遺構をつなぎ合わせると宝井団地南方でやや北向きに方向を変えなければならない。したがって、この箇所が引用文のカーブを指すと推定される。この区間に、遺構は発見されていない。宝井団地にお住まいの方でかつてここに線路があったことをご存知の方はほとんどいらっしゃらないのではないだろうか? |
| 第−章 開通から路線変更まで に旅する 第三章 新線(現在線)を観察する に旅する。 |

トップページに戻る
【お願い】本サイトはフレーム構成です。
フレーム表示されていない場合は
上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る
更新
作成 2002.1.5
Copyright (C) 2002 Daruma-Kozo. All Rights Reserved