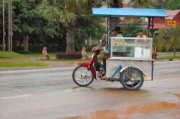成田〜バンコック〜シュリムアップ 浅草を出たのは、6時30分であった。  成田でANA NH0953便の飛行機に乗りタイのバンコック空港からカンボジアのシェムリアップに着いたのは、夜の7時前であった。バンコックでは外に出られず、空港内でカンボジア行便を待つだけである。 若い頃タイを訪れたときからどんなに変わっているかみたかった。空港は新しくなり、かなり変わっていた。 カンボジアに着いた時はすでに暗かった。ガイドのポーさんが待っていてくれた。かなり日本語が達者であった。 カンボジア第2日目は、前日、何度も念を押されて、早朝5時ころ起き、朝焼けのアンコールワットを見に出かけた。 ▲ページトップへ アンコール・ワット 早朝にもかかわらずたくさんの人が来ていた。アンコール・ワットは、テレビなどから記憶しているままのたたずまいで私達を迎えてくれた。少し残念だったのは、雲が厚く朝日がイメージどおりに昇ってくれなかったのと、建物の  一部が修復中でブルーシートがかかっていたことである。これは仕方がない。ここアンコール・ワットは、世界遺産の人気のランクで3位だというのがよく分かる。アンコール・ワットを中心としたアンコールの遺跡群は、カンボジアの首都プノンペンの北西250kmにあるが、周りは熱帯雨林で、土はかなり赤い。 一部が修復中でブルーシートがかかっていたことである。これは仕方がない。ここアンコール・ワットは、世界遺産の人気のランクで3位だというのがよく分かる。アンコール・ワットを中心としたアンコールの遺跡群は、カンボジアの首都プノンペンの北西250kmにあるが、周りは熱帯雨林で、土はかなり赤い。カンボジアの歴史は、紀元前、この地に建設された扶南国に始まるという。しかし扶南国はクメールに滅ぼされた。9世紀にここアンコールに王城を築いた。往時のクメールはインドシナ半島すべてを支配する大国で王都の人口は50万人を数えたという。その栄華が今に残り、1000近い遺跡があるという。 この膨大な遺跡群の中でも、圧倒的なスケールや華麗さを誇るのが、アンコール・ワットである。 アンコール・ワットは彫刻がすばらしい。同じお寺で、東大寺や法隆寺なども、世界に誇れる建物で何度行っても新しい発見があるが、アンコールワットもそれに劣らない。  石と木の違いはあるが、それぞれの国の材料で知恵を絞り、技術の粋を極めた建物である。 壁面に掘られた彫像は、日本は中性的だが、アンコールワットのそれは明らかに女性が多く見ていても楽しい。周辺の彫刻も「すごい」の一言に尽きる。人類はあちこちで手法はそれぞれ違っても大変なことをやって後世に伝えている。 石と木の違いはあるが、それぞれの国の材料で知恵を絞り、技術の粋を極めた建物である。 壁面に掘られた彫像は、日本は中性的だが、アンコールワットのそれは明らかに女性が多く見ていても楽しい。周辺の彫刻も「すごい」の一言に尽きる。人類はあちこちで手法はそれぞれ違っても大変なことをやって後世に伝えている。アンコールワットはヒンズー教の寺である。 その神話「乳海攪拌」の彫刻は50mにわたり、まるで絵巻物のように精緻な彫刻で、見る人に語りかけてくる。 不思議に思うのはこれだけの石をどこから運んだのかということである。 エジプトやマヤなどの歴史的建造物と、ほとんど同じ疑問が生じる。 当時のありあまる時間を、権力によりまとめて建造に当たらせたのは分かるが、それにしてもあまりにも大量の石が使われている。 ポーさんの話でこの建物の修復はフランスと日本の上智大学が頑張っているという。 アンコール・ワットは、周囲4.5kmもある環濠に囲まれている。環濠の水は、汚くはないが透明でもなかった。 ポーさんに、魚は釣れないのかと聞くと、「釣れるけれど神聖な場所なので釣りはあまりしませんね」ということであった。 アンコール・ワットの朝日を拝んで、ふたたびホテルに戻り、朝食をとった。メニューはごく一般的なものであったが、カンボジアの郷土料理もあり、心配した石けんの味のする、妙な香辛料もなく、なかなかおいしい料理であった。 パンもおいしかった。いろいろ食べたいから、つい食べ過ぎてしまった。 ホテルの前で、ふたたびアンコール・ワットに行く車を待ったが、とにかく目の前をバイクが疾走していく。 ヘルメットもなく転けたら怖い感じだが、多い人はカブ1台に5人くらい乗ってビュンビュン飛ばしていく。 しかし同じバイクでも日本のより格好がいい。カラーリングがカラフルなのと、フロントサスペンションがリンク式ではなくテレスコピック式なので、デザイン的にもシャキッとしている。 朝食後アンコール・ワットに戻った。アンコール・ワットへは、濠にかかった橋を渡っていく。 のっけからたくさんの彫刻群に出会う。ところどころ、欠けたところがあり、ガイドさんになぜかときくと、「ポルポト軍の兵士が、おもしろ半分に撃ったのです」と返事が返った。スフィンクスの鼻を欠いたのはナポレオン軍だが、やはり戦争はこうした文明の証の必要性すら、顧みる余裕もなくすのだろう。 アンコール・ワットの中央祠堂の入り口や塔門、回廊の外壁にデヴァターという女神像がたくさん浮き彫りされている。その数は2000体を超えるという。 ここアンコール・ワットの魅力はそれらの女神像にあると思う。どれ一つとして同じものはなく、頭飾り、髪型、動作、表情など、多彩でまるで生きているような雰囲気を醸し出していて見飽きない。 特に中央祠堂の入り口付近の女神像は気品高く優美に描写され、神秘的である。まだ見てはいないが写真で見る限りに於いて、インドの同じヒンドゥー教の彫刻は豊満でエロチックであるが、ここの女神像はどれもがかすかにほほえんでいる感じでほどよい色気があり、それでいて気高さを秘めた雰囲気であるため、よけい惹かれるのかも知れない。 クメール人の独創的な美的感覚がよくわかる。顔の表情や頭飾りなどに重きをおき、参拝する人に語りかけるように、そして話しかけたくなるような親しみ深さを表現している。 この女神たちを見るために、何度でも訪れたいという気にさせる。 中央祠堂の柱の一つに、1632年(寛永9年)、日本人の森本右近太夫一房が参拝した際に、墨書といえば格好がいいが、「御堂を志し数千里の海上を渡り」「ここに仏四体を奉るものなり」と落書きを書いている。 日本にもこの仏教寺院は知られていた事が伺えるのだが、ポーさんの説明では、インドにあるといわれる補陀洛浄土と間違ってしまったのではないかと言うことであった。 鎖国中でもあり、可能性はある。 アンコールの遺跡群は、カンボジアの首都プノンペンの北西250キロ。 1860年、フランスの博物学者アンリ・ムオが動植物の調査のために熱帯雨林の中をさまよっているとき、ここアンコール・ワットを発見したという。神の世界をそのまま地上に作り上げたアンコールワットは、規模の大きさや、調和のとれた建築美、壁を飾る浮き彫りの美しさに、誰もが感嘆する。中央にひときわ高くそびえる堂塔は、世界の中心にあるメール山(須弥山)、回廊はヒマラヤ山脈、周囲を囲む環濠は大洋を表しているという。この地上の楽園は、三重の回廊を進むごとに、天へと近づいていくのである。この堂塔に行くには、すごく急な階段を恐る恐る登らなければならない。 階段が狭い上に急であるため、皆こわごわであるが、思ったよりスムーズに降りることができた。 一気にたくさんの人が下りると危険なので、堂塔の中で順番を待つのだが、その間ゲームをやってるお兄ちゃんに出会った。 少し寂しかった。外国の子供たちは、壁のウォッチングしていた。
アンコール・トム アンコール・トムは、アンコール・ワットの西参道の入り口の道を北に進むと、巨木の並木がありその先にアンコール・トムの南大門が見えてくる。 南大門手前の陸橋の左右には、乳海攪拌図を立体化した欄干がある。所々頭部がかけたり、手がなかったりしているが、乳海攪拌図そのままに、引っ張り合うリズムやかけ声が聞こえてきそうな石像が並んでいる。 アンコール・トムは、9世紀から14世紀にかけ最盛期のアンコール王朝が造営した、周囲12キロ、高さ約8mにおよぶ城壁と5つの城門がある。その中心に、仏教寺院バイヨンが立ち、「クメールの微笑み」と呼ばれる、穏やかで慈悲深い微笑を浮かべた観世音菩薩の巨大な四面仏がある。ものの本によれば、アンコール・ワットの創建者スールヤヴァルマン2世はヒンズー教徒であり、ヴィシュヌ神と一体化したいと思っていたので、ヒンズー教の叙事詩や伝説を題材にアンコール・ワットの壁面に彫刻を彫った。 ここアンコール・トムの創建者ジャヤヴァルマン7世は、アンコール王朝始まって以来の仏教徒であり、これまでの宗教建築にないユニークな仏教寺院バイヨンを建てたのである。壁面の彫刻も、日常生活だったりクメール軍とチャンパ軍の戦闘場面だったりする。それは、当時の生活がよくわかる、記録写真的価値がある。 土産物売りは、どの国もおなじで車を降りると子供が本やアクセサリーを売りにくる。買ってもいいのだが、たくさんの子供が売りにくるので一人だけとはいかなくなり買えない。 それと買ってしまうと、日本人は買ってくれると思われて、付きまとわれる。 日本人以外には余り売りに行かない。これは土産物文化の日本人だからかもしれない。 他の外国人は、自分のために一点買いをしている感じである。 しかし考えてみれば、大量にお土産として配るのが楽しみであれば、こうしたものを安く値切って買うのもいいのかなと思う。日本人は日本人らしい買い物をすればいいので、恥じることはない。 買わないときはきっぱりと買わないといえばいいわけである。それで双方が納得すればいいという気になる。それにしてもこの3歳くらいの子供の、土産物を売り付けにくるのを断るにはかなりの意志を必要とした。この子一人から買えば、他にいた5,6人の子供からも何か買わなくてはいけない雰囲気だったからである。
象のテラス・ライ王のテラス アンコール・トムを見た後、象のテラスにむかった。  ここは、リアン・チョル・ドムレイと呼ばれ、王様が兵隊をチェックしたところという。勝利の門から凱旋した時に集合したり、あるいは出陣するときの点呼などが行われたという。 ここは、リアン・チョル・ドムレイと呼ばれ、王様が兵隊をチェックしたところという。勝利の門から凱旋した時に集合したり、あるいは出陣するときの点呼などが行われたという。名前の由来の象のレリーフのほか、馬や白鳥、ガルーダなどが刻まれていて、それらをきちんとチェックすれば日が暮れてしまう。それくらい形のいい彫刻がたくさんある。 写真の後ろが象のテラスといわれる元になった、象が3頭彫られている。象の鼻が蓮の花を持ち上げている。案内のポーさんがいろいろ説明してくれたが、十分に覚えきれなかった。 象のテラスを過ぎると「ライ王のテラス」に続く。ライ王のテラスはリアン・スダィッ・コムロンというらしいが、カンボジア語の発音は難しいので覚えられない。ポーさんはきちんとした日本語を話すのに少し情けない。ライ王は実際にライ病に冒されていたといわれる。 今でこそライ病は治る病気であるが、昔は業病ともいわれ、悪いことをした報いであるというような意味のある不治の病で、たしか私の祖母たちの年代では、この病気にかかった人を良くは言わなかった。ライ王のテラスは三島由紀夫の戯曲でもよく知られている。三島はアンコール遺跡を取材して、戯曲「らい王のテラス」を執筆し、北大路欣也の主演で公演されたというが、私は読んでいないので知らなかった。ポーさんの方がよく知っていた。ここのライ王像はレプリカで、本物はプノンペンの国立博物館に収蔵されているという。
スーパーマーケット・昼食 移動の際、スーパーに立ち寄った。その街にすむ人の嗜好や流行を知るには市場やスーパーマーケットに行くのが一番いいような気がする。そこではどこの国でも売れ筋の流行の商品を並べているし、食料品であればどれくらいで売られているかを観察できる。そして土産物を買う参考にもなる。 観光客向けの商売をしているところはあまり良くないが、地元の人向けのお店はおもしろい。 この日入ったスーパーでおもしろかったのは、サソリとコブラ、名前の分からない毒蛇、朝鮮人参などが入った酒で、いかにも絶倫になりそうな感じがする代物であった。陳列棚一杯に並べられていた。その向かいには、バイアグラもどきが売られていたが、何となくうさんくさい感じであった。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||