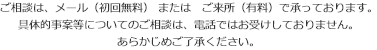薬事法(化粧品)の許可認可申請、MS法人・ドクターズコスメ専門の行政書士 せたがや行政法務事務所
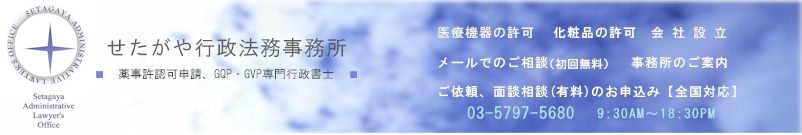
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
MS法人とは、いわゆるメディカルサービス法人の略で、医療法人が行うことのできない営利事業を担わせるために設立された「会社」のことをいいます。 医療機関は、医療機器や化粧品の販売を直接行うことが出来ません。また、医療機関内において(診療所や病院として届出をしている部分で)医療機器や化粧品の販売を行うこともできません。 そこで、これらを販売(医療機器の場合は賃貸・リースも)を行うために、医療機関とは別に、会社を設立し、この会社に業務を行わせるわけです。 MS法人、という呼称がありますが、法的な性質としては、通常の会社そのものです。法律上「MS法人」という法人形態があるわけではありません。
昔は、MS法人の設立は、医療機関の節税対策のため、顧問税理士さん主導で行われることが少なくなく、事業目的としても医業の現場に関係する周辺業務(リネン・駐車場管理関係など)や、自医療機関のみに対する医療機器のリース等を行うものが多くありました。 近年は、純粋な「メディカルサービス」に限定されなくなってきているといえます。 薬事法改正や介護保険法施行などを受けて、医業を生かしまた医業と連携を取れるような、新たな事業展開を目的としたケースが増えてきており(医療機器や化粧品の製造販売、訪問介護やデイサービス・デイケアなど)、 また、改正薬事法への対応のため、コンタクトレンズや化粧品等の販売行為を明確に医療機関から分離させるために設立するケースも増えました。 こうしたケースでは、法律上の許認可が関係することから、行政書士が指導・提案し設立手続きを代理することが多くなっています。
顧問先のMS法人が医療機器(医療材料や器具類も含まれます)の販売や賃貸・リースを行う場合、医療機器の販売業許可が必要な場合がありますので、扱う医療機器と、許可の要否を、今一度ご確認いただけるとよいと思います。 自医療機関のみに医療機器を販売・リースする場合であっても、医療機器が高度管理・特定保守などの分類に該当すれば、薬事法上の「販売業・賃貸業許可」が必要です。 医薬品についても同様に販売業許可が必要です。
診療所は、医療法第1条の5により、医業を行う場所として定義されており、この前提で、開設の際に診療所区画を明示して届出をして(法人開設の場合は許可を得て)います。開設後といえども、診療所は医業を行う場所ですので、ここで物品販売を行えば、届出内容に違背し、場合によっては虚偽申請をしたということになりかねません。また、医療法7条5項では、営利目的での診療所・病院開設に許可を出さないことができるとされており、非営利性が明確になっています。 さらに、コンタクトレンズの販売には、薬事法上の高度管理医療機器等販売業許可が必要ですから、こちらの面から見ても、販売区画と診療所区画は明確に区分する必要があり、診療所内で許可を取得することはできません。現実にコンタクトレンズを診療所内で販売しているとすれば、無許可販売ということで薬事法違反になります。 以上のことから、医療機関におけるコンタクトレンズ販売はできないと解されます。 化粧品については、医療機関における化粧品提供は化粧品の効能効果を超える効果をもつとの誤認を与えがちですので、十分な配慮が必要ですし、医療機関が営利行為を行う場所ではない以上、化粧品販売を診療所内で行うことは適法とはいえないでしょう。 なお、個別のケースについては管轄保健所の見解を確認してください。
MS法人は法的には一般の「会社」ですので、その設立にあたっては、医療法人等と異なり監督官庁の認可は不要です。 定款の認証、株主総会(社員総会)・取締役会等の決議、出資金払込みを経て登記を行うことで設立できます。
通常の会社と異なるのは、ここをお読みの皆様の場合には薬事法上の許可が必要になるということです。 そのため、設立にあたっては、事前に許可のことも視野に入れて準備をすることになります。たとえば、 ・許認可要件と規制 -
責任者の配置、組織体制の構築など よって、MS法人の設立にあたっては、薬事法・医療法、両方の法律の観点から検討をしなければなりません。
化粧品の製造販売元になるためには、化粧品製造販売業許可が必要です。 診療所の管理者である医師の方は、薬事許認可における責任者にはなれません。 管理者である医師以外の方を責任者としていただき、適切な事務所・製造所を確保していただく必要があります。
MS法人は、多くの場合、発起人の関係する(役員となっている)医療法人と取引関係をもつことが多いですから、法律上適切な役員構成を検討しておく必要があります。 ここは、単に会社設立を行おうとする場合と異なる点といえます。
医療法人とMS法人は、取引関係にあって利害の相反する立場となります。 理事は、法人から業務執行につき「委任」を受けた形になっています。利益相反する2法人の代表者が同じ人物であるときは、医療法人はその意思決定において原則である非営利性を貫かねばならず、一方で営利法人であるMS法人は、会社という性質上利益(営利)を追い求めます。 よって、同一人物が両法人の(理事会・取締役会等の審議を経ていても)代表権・業務執行権を持っているために、医療法人において営利法人の影響が否定できません。医療法人の大原則である「非営利性」に抵触するといえるでしょう。MS法人の代表取締役は、医療法人の理事長は避けるべきであるといえます。
理事は、民法上では対外的に法人を代表するとされます。しかし、医療法人においては、定款により『理事長のみが医療法人を代表する』こととなっています。 医療法は理事が法人を代表することを定めた民法53条、及び、理事の代表権に制限を加えても善意の第三者に対抗できない旨定めた民法54条を準用していませんから、結局医療法人では「理事長のみが法人を代表する」こととなります。 このため、モデル定款19条や『医療法人運営管理指導要綱』I
2役員 (4)1
では「理事長のみが代表する」としています。)
つまり、法律のみを見れば、平理事がMS法人の役員を兼ねることは禁じられていないのです。 しかし、医療法人とMS法人の取引の実態に鑑みて、医療法人からMS法人に過大な支払いがなされているような場合や、MS法人の役員報酬が過大な場合には、事実上医療法人の利益が分配されているとみられる(医療法54条違反)こともありますから注意が必要です。 こうしたことを考慮して、医療法人行政の現場では、下記の2つの要綱・通知を根拠に、「病院・老健を経営する」医療法人とMS法人(その他取引のある営利法人)の役員の重複を認めない「行政指導」をしています。 「医療法人運営管理指導要綱」 「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」
各都道府県の手引書などで、取締役と理事の兼職を認めないと書いてあるものがありますが、その根拠はこれらの通知にあります。 医療法人運営管理指導要綱の対象は、すべての医療法人ではなく、病院・老人保健施設を開設する医療法人ですが、都道府県の指導内容は、診療所に対しても同様の指導をしているケースもあります。 通知(行政指導)は、それ自体が法的拘束力を持つものではありません。 このため、コンサルタント等によっては、兼職を可としていることもありますが、行政指導をうける可能性があることは、あらかじめ留意した上で、役員構成を検討すると良いでしょう。 他方、理事長、理事が、 ただ、MS法人のあげた利益は最終的に株主・社員に配当という形で帰属しますから、理事長がMS法人に全額出資し唯一の株主・社員になる場合、医療法人はMS法人の唯一株主である理事長と取引したもの、つまり理事長の利益相反取引となるといえるでしょう。 以上のような、法的な根拠、行政指導などは、経営者が企業経営上の法的リスクを管理する(法的リスクマネジメント)にあたっての重要な判断材料になります。 そのうえで、事業環境・状況とを冷静に比較考量して、会社にとってもっとも適切な選択肢をえらびましょう。
社会福祉法人が関連法人を設立する場合は、「社会福祉法人審査基準」「定款準則」等の規定を参照し、より詳細な検討を加える必要があります。 社会福祉法人の役員要件は、これらの基準等により、より詳細に定められており、かつ、監督官庁により行われる指導検査・監査における指導項目です。 関連法人設立の場合は、役員要件について十分ご検討頂き、行政書士にご相談なさることをお勧めします。
当事務所で設立手続きを行ったMS法人の例をご紹介します。
申込み方法など、事務所についてご案内いたします。 03-5797-5680 (9:30am〜)
ご相談・ご質問フォーム*は必須項目です
|
| 薬事法(化粧品)の許可認可申請、MS法人・ドクターズコスメ設立専門の行政書士 せたがや行政法務事務所
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||