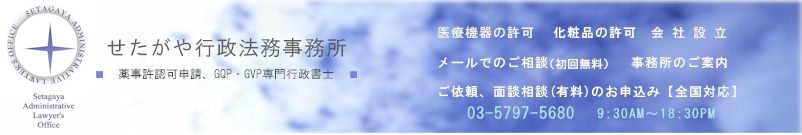本稿は、平成15年5月に、「国際行政書士協会」に寄稿した文章を改めたものです。
本稿は、平成15年5月に、「国際行政書士協会」に寄稿した文章を改めたものです。
 本稿を投稿した時期は、電子定款の制度が開始される前です。
本稿を投稿した時期は、電子定款の制度が開始される前です。
当時は、各行政書士が、近い将来の電子定款制度の発足を見越して、定款作成代理人として「紙」の定款作成を代理人として行い始めた時期でした。
 「行政書士とうきょう」15年9月号、10月号にも、定款作成代理に関する私の小論が出ておりますのでご覧ください。
「行政書士とうきょう」15年9月号、10月号にも、定款作成代理に関する私の小論が出ておりますのでご覧ください。
定款作成代理とその実例
行政書士 小 平 直
1.はじめに
代理権の明確化が謳われた新行政書士法が昨年7月に施行されましたが、以後、その代理権の実践として、全国の行政書士において、「定款」を「代理人として作成」する動きが広まりつつあります。
会社の原始定款の作成において、従来は、発起人・社員が作成した定款(実態としては、行政書士が行政書士法第1条の2により作成した定款)を、行政書士が官公署である公証役場に提出し、発起人・社員を代理して認証を嘱託しています。
本稿にいう定款作成代理は、認証嘱託手続きの代理ではなく、行政書士法に基づき、行政書士が作成自体を代理し、「作成代理人」として自ら認証を嘱託する形態です。
2.定款作成代理の意義
平成14年7月施行の行政書士法により行政書士の代理権が‘明確化’されましたが、定款作成代理は、同法第1条の3の実践です。
定款を代理作成することには、次のような意義があると考えます。
第1には、「代理」の実績の蓄積です。
代理の実績とするには、行政書士が代理人として「顕名」することが重要です。
第2には、定款が各官公署等へ提出されることにより「代理人行政書士」の認知がさらに広まるという点です。
会社設立後、定款は、許認可申請窓口、税務署、等へ提出されます。私たち行政書士は、原始定款の作成にあたり、たんに法務局で通る目的表現にするだけでなく、許認可の要件や運用に適するよう検討するわけでありますが、代理作成によって行政書士関与がよりいっそう明確になります。
第3には、当然ながら「会社設立手続」に「代理人」として関与していることの実績となり、かつ認知される契機となります。
定款認証の電子公証サービスの基盤が構築され、また経済産業省によるインターネットを利用した会社設立のワンストップサービスが構築される際に、行政書士が代理人として認証や一連の設立手続きに関与するためのシステムを組み込ませるには、現在の「紙」ベースでの段階において、代理人として関与している実績が不可欠だと思います。
3.行政書士による定款作成代理の根拠
(1)行政書士法第1条の2、第1条の3
「定款」は、権利義務・事実証明書類ですから、行政書士法第1条の2にいう書類に該当します。また、同条には権利義務・事実証明書類の例示として「官公署提出書類」があげられていますが、公証人役場は官公署であることから、会社設立時に必要な、「公証人の認証を受くべき原始定款」は官公署提出書類という性質も帯びています。
同法19条により、定款作成は行政書士の独占業務です。
同法第1条の3第1項及び第2項は、
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
です。定款が第1条の2にいう書類に該当する以上、第1条の3にいう「前条の規定により行政書士が作成することができる書類」であることは明白でしょう。よって、第1条の3により、「行政書士は業として定款の作成を代理できる」わけです。
ここで、行政書士法19条にある他法による制限に関し、司法書士法についても触れておきます。
一部公証人をはじめ、原始定款は法務局提出書類である、とする意見があるようです。しかし、法務局に提出するのは、公証人の認証した認証文付定款の謄本であり、発起人・社員から依頼・委任を受けて作成する書類そのものではありません。
原始定款として作成する書類は公証役場に提出するわけであり、官公署である公証役場に提出する書類の作成は行政書士法19条により司法書士はできません。よって、司法書士が公証役場に提出するために発起人・社員の依頼を受けて定款を作成する行為自体が、行政書士法に抵触します。
なお、次のような先例があります。
「会社設立に必要な書類の内、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状)の作成は、司法書士の業務の範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証)の作成は含まれない」(昭和29年1月13日法務省法務次官回答)。
(2)で後述の法曹会決議も同様です。
(仮に公証役場提出手続き・提出書類作成が法務局提出のための準備行為・附随行為であると捉えた場合、逆に、許認可申請や変更手続きのために行う変更登記申請もまた附随行為・準備行為と捉えることの可能性も否定できなくなると思われます。本論から外れますので詳細は別の機会に検討したいと思います)
税理士による作成が違法行為であることはいうまでもありません。
(2)昭和14年3月法曹会決議
公証役場に提出して認証を受ける「定款」の作成及び嘱託手続の「委任状」の作成については、行政書士は作成することが出来るが、司法書士は作成することが出来ない。
4.定款の代理作成に関する肯定的記述及び判例 20037.7,7.10追加
(1)日本公証人連合会『定款認証事務QandA』14〜15ページ 平成15年6月18日発行版
「13 代理人による定款の作成の場合の手続は、どのようにするのか
定款の作成自体を代理人によってすることもできる。この場合には、定款に記名押印(又は署名)するのは、代理人であり、公証人に認証の嘱託をするのも代理人であるから、認証嘱託の代理に問題にはならない。
しかし、代理人は認証嘱託に際し、自分が定款作成の権限を有することを証するために、発起人全員からの定款作成を委任する旨の委任状を提出すべきである。そしてこの委任状に認証がない場合には、発起人全員の印鑑証明書を提出すべきである。委任事項には、定款の内容を具体的に記載する必要がある。」
なお、日本公証人連合会『公証実務』8〜9ページ にも、下記のような記述があります。
「前に述べたように、定款の作成自体を代理人によって行うこともできる。この場合、定款上に署名または記名捺印する者は右の代理人自身であって、公証人に認証の嘱託をする者も右の代理人自身である・・・」
(2)元公証人山口和男『公証役場 公正証書 活用のすすめ』
(税務経理協会)273ページ
この書は、「六 代理人による定款の作成と認証嘱託」として一節を設け、代理作成が可能な旨、および定款作成の委任状様式を掲載しています。
当該ページには、「代理人が定款の作成自体を代理して行うことができます」とあります。
(3)その他の書物における肯定の記述
『公正証書モデル文例集』(新日本法規出版)1207ページにも同様の記述があります。
『会社法務の手続きと書式』(加除式・新日本法規出版)法務25・127ページには、次のようにあります。
「なお、定款は代理人によって作成することも可能です。この場合には、代理人は、本人たる発起人のためにすることを示して自己の署名または記名捺印をすることを要し、それで充分です(大審判昭7・6・29民集11・1262)」
『別冊法学セミナー 基本法コンメンタール 会社法1』122ページは、商法166条に関する解説部分ですが、その中段「[3]定款の作成・署名」にも、上記大審判昭7・6・29が紹介されています。
(4)商法第166条・有限会社法第6条との関係
商法166条第2項には
「定款が書面を以て作られたるときは各発起人之に署名することを要す」
とあります。有限会社法第6条も同様に、社員が署名することを要すとしています。
代理作成した定款には、当然ながら発起人・社員の押印がありません。
では、代理作成定款は、商法166条・有限会社法6条違反になるでしょうか。作成した定款を、出資金取扱いの申込みの際に金融機関に提出した際、発起人の押印がないために、当該金融機関から押印を求められた、というケースもあるとのことです。
定款作成に関して代理人の存在を排除する規定がないことから、発起人・社員が作成・記名押印自体を委任することは可能だと考えられます。
代理人による作成・記名押印については、下記のような先例があります。
(当方にて、カタカナを平仮名にし、無濁点部分については濁点を付しました)
| ●東京地裁大正4年(ワ)第141号、同年10月21日民2判決 |
| 仮りに甲が乙をして甲に代り定款に署名せしめたりとするも定款の作成が代理人により之を為すを許さずと解せざるべからざる理由あることなし |
| ●東京控訴大正5年(ネ)第100号、同年11月18日民3判決 |
| 会社の発起人が定款に代理人をして署名捺印せしめたることおよび株式を引受けしむることは商法の禁ぜざる所にして法律上有効なること論を俟たざれば定款および株式引受証に発起人の自署を必要とする趣旨の控訴代理人の抗弁は理由なし |
| ●東京控訴大正7年(ネ)第227号、同10年4月8日民3判決 |
| 発起人が定款に自己の署名又は記名捺印を為すの行為は正当の意義における法律行為なりと謂ふを得ずと雖も之亦会社の設立に関する行為にして法律行為に準ずべきものなるが故に其性質の許す限り又法律の禁ぜざる限りは法律行為に関する規定を準用すべく従つて発起人が定款に於ける書名を他人に委任し其受任者が右発起人の代理人として其旨を表示し定款に自己の署名又は記名捺印を為すときは法律行為の代理の規定に準じ本人たる発起人が定款に署名し又は記名捺印ありたると同一の効力を生ずるものと解すべきものとす |
5.定款作成代理の要点
詳細、作成した定款の実物は、文末の「実例」にリンクしてある定款作成代理のページをごらんください。
(1)委任状
委任の内容は
「有限会社○○○の設立に際し、別紙の通りその原始定款を作成し、公証人の認証を受ける手続きに関する一切の件」とします。
別紙として、定款と同内容のもの(第1章第1条から附則最終条まで)を付します。委任状には発起人・社員の実印を押印し、委任状鑑と別紙をすべて契印します。発起人・社員の印鑑証明書はこの委任状に添付します。
この委任状は、現在、提出を求める公証人が多いようですが、提出不要とする公証人もいます。私がこれまでに代理作成したケースではすべて委任状を提出していますが、そもそも定款作成を代理した当該代理人が自ら公証役場に出向き認証嘱託をする場合、発起人・社員が自ら認証嘱託をする場合と同様に扱うべきであり委任状の提出は不要である、とする見解があります。現段階での窓口運用は一定していません。
なお、前項4(2)に紹介した山口和男氏は、『公証役場・公正証書 活用のすすめ』273ページで、「自己が定款作成の権限を証する書面として、発起人全員の定款作成を委任する委任状が必要で、この委任状には、発起人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません」としています。 (2003.7.7)
(2)定 款
代理人として作成する際の要点は、「定款に押す印は職印のみ」ということです。
|
以上 有限会社○○○○を設立するため、社員代理人行政書士 小平 直 は定款を作成し、これに記名押印する。
平成 年 月 日
社 員 ○○ ○○
代理人 行政書士 小平 直 (職印)
|
となります。発起人・社員の押印はありません。
なお、末尾には行政書士法施行規則に基づく記名押印を付します。私の場合は次のようにしています。
|
本定款は、行政書士法第1条の3の規定に基づき、当職において代理人として作成した。
東京都世田谷区用賀2丁目41番18−305号
行政書士 小 平 直 (職印)
|
(3)認証文
「(定款作成)代理人 行政書士 小平 直 は、その記名押印を自認する旨を本職の面前で陳述した」
このような形になります。
この代理は、行政書士法第1条の3の代理規定に基づく代理ですので、認証文、定款には、行政書士という資格名を入れるべきと考えます。
|
 実 例 実際の定款の記載例、認証文が見られます。 実 例 実際の定款の記載例、認証文が見られます。
|
平成15年5月8日執筆
平成15年6月7日改筆
平成15年7月7日改筆
平成15年7月10日訂補
|