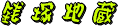 |
 山口町に伝わる昔の話です。武士であった夫と死別した山口と名乗る女の人がいました。この女の人には二人の子どもがいました。女手一つで子ども二人を育てるのはたいへん苦しいことでした。けれども、子どもの教育には心をこめて一生懸命に努めていました。 山口町に伝わる昔の話です。武士であった夫と死別した山口と名乗る女の人がいました。この女の人には二人の子どもがいました。女手一つで子ども二人を育てるのはたいへん苦しいことでした。けれども、子どもの教育には心をこめて一生懸命に努めていました。
女の人は、貧しさのあまり、自分の髪の毛を切って売ることがありました。これを知った親せきの人たちが、「そこまでしなくても、お金がなければ貸してあげるのに。」と言いましたが、女の人は、「働かないで得たお金は家のためになりません。自分の髪を切って売り、子どもを育てることは恥ではありません。」と言って、きっぱり断りました。
またある時、子どもたちが垣根を修理しようとして穴を掘っていると、土の中からたくさんの銭が出てきました。驚いた子どもたちが母に告げると、母はきびしい顔で、「武士たる者がお殿さまのお役に立たずにお金をいただくことは家の恥です。まして、理由のないお金を自分のものにすることはできません。そのお金はもとのままに、土の中にうめておきなさい。」と言いました。
二人の子どもは、この賢い母に育てられ、誰からも信用されるりっぱな若者に成長しました。そして、母の教えをいつまでも忘れないようにと、みつけた銭をうめた所に、地蔵尊をつくりました。この地蔵尊を銭塚地蔵と言い、今もお参りの人が絶えません。
東京の浅草観音境内には、山口町の銭塚地蔵と同じものがあります。これは、この時の子どもたちがつくったものだと言われています。地蔵尊には、「摂州有馬・山口銭塚」と彫られています。 |
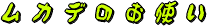 |
 昔、山口の名来という村に、働き者で信心深い籠六という男がいました。朝早くから夜遅くまで仕事に精を出し、田畑にはいつも米や野菜がみのり、豊かで恵まれた暮らしをしていました。 昔、山口の名来という村に、働き者で信心深い籠六という男がいました。朝早くから夜遅くまで仕事に精を出し、田畑にはいつも米や野菜がみのり、豊かで恵まれた暮らしをしていました。
ところが、いつのころからか、籠六の心に欲深い考えが芽生えるようになりました。おいしいものを食べ、きれいな着物を着て、楽しくおかしく遊んで暮らしてみたいと思う心は、誰にでもあるものです。「こんなところで毎日汗水流して働くよりも、大阪に出て米相場をやってみよう。何でも聞くところによると、相場で大儲けをして御殿を建てた成金さんがおるそうじゃ。」もはや一時もじっとしておれず、家中ありったけのお金を懐にして、大阪へととびだして行きました。欲につかれた籠六は、長い間働いて蓄えたお金を惜しげもなく米相場に使ったのでした。
米相場というのは、お米の値段が日によって変わって行くのを予想して買うのです。自分が買った時より値上がりすれば儲かるし、値下がりすれば損をするのです。日ごろから「バクチ」には手を出したことのない籠六です。とうとうすってんてんの無一物になり、すごすごと村へ帰ってきました。
それからというもの、籠六は浴びるほど大酒を飲んで、昼間からごろごろ寝てばかりいました。ただ一つ、変わらないことといえば、神さまをまつり、朝夕神棚にお灯明をあげていることだけでした。
ある晩のことです。酔いつぶれて眠りこんでしまった籠六の枕もとに、日ごろ拝んでいる神さまがお立ちになり、「これ籠六よ。おまえのように酒ばかりのんでいては、家の者が困るではないか。このままでは酒を飲むどころか、ご飯も食べられなくなるぞ。今まではまじめに働いてきたし、今でも信心深いところをみると、おまえにもまだ人間の良いところは残っているらしい。そこで、おまえが前のような人間になれるよう、一度だけ良い事を教えてあげよう。」とおっしゃいました。「よいか、わたしの使いとしてムカデをつかわそう。その頭の動きをよく見て相場を買うがよい。ムカデが頭を持ち上げた時は相場が上がる。頭を下げると相場も下る。」
翌朝、目をさました籠六は、壁にはりついているムカデを見て、神さまの夢がほんとうだったのを知りました。籠六は嫁さんに、夕べ見た夢の一部始終を話しました。そして金に換えるものはないかと、家中を探し回りました。「ほんに、もう金目のものは何もありゃしない。みんな使うてしもうたに。」嫁さんは、あきらめ顔です。それでも籠六は、「蔵の中に、まだ何かご先祖さまの残されたものがあろう。」と、必死です。やっと探し出したものは、古びた三つ重ねの重箱でした。ほこりをはらい、ていねいにみがくと、貝や金銀のかざりのついた、値打ちのありそうなものです。
重箱を売りはらって、わずかながらも元手にするお金のできた籠六は、いそいそと旅のしたくをすませると、ムカデに手をついて尋ねました。「おらあ、これから大阪へ行って米相場を買う。上がるか下がるか、どうか教えてくだされや。」壁にはりついていたムカデは、ぞろぞろと畳の上に降り立つと、頭をもたげてしきりにのびあがりました。
僅かな元手で買った相場は、上がる一方で天井知らずでした。ムカデの頭が下がったところで売りに走り、また上がると買いに走るのでした。こうして、またたくうちに大金を儲けた籠六は、千両箱を馬に積上げ、めでたく村へと帰ってきました。
それから後の籠六は、二度と相場を買うこともなく、以前のようにまじめに働き、ムカデも二度と姿を現しませんでした。 |
 |
その昔、奈良の吉野に仁西上人と呼ばれる徳の高いお坊さんがいました。紀州の熊野権現にお参りする旅の途中のことでした。疲れてぐっすりと眠り込んでしまった上人の夢の中に、権現さまが現れて言いました。「ここより西の方へ行くと、摂津の国の有馬という所に温泉がある。降り続いた大雨のために洪水や山くずれがおこり、すっかり荒れはてている。毎日不自由な生活を送っている村人たちを助けてもらいたい。そなた、これより行って村づくりをしてはくれまいか。」
権現さまのお姿に手を合わせた上人は、「かしこまりました。さっそく摂津の国の有馬へまいります。どのように行けばよいのかお教えください。」と、尋ねました。「そなた、朝になれば庭に出てみよ。庭木の葉に一匹の蜘蛛がいるはずだ。その糸をたぐって行けば、その地まで迷うことなく行くことができるであろう。」
翌朝、すがすがしい気分で目ざめた上人が庭に出てみると、夕べの夢のお告げどおり、庭木に一匹の蜘蛛がいました。早速、上人は、蜘蛛の行くのにしたがい、その細い糸をたぐりつつ、まだ見ぬ有馬の地をめざして急ぎました。陽の光にきらきらと輝きながら、細い蜘蛛の糸は谷を越えてまっすぐにのびていきます。険しい山道では引っぱるように、上人が疲れた時には労わるようにゆっくりとのびていきます。
幾日かの旅を続け、山口村の中野という所にさしかかった時です。大きな二本の松の木がそびえているあたりで、どうしたことか蜘蛛の糸を見失ってしまいました。途方にくれた上人は、二本松の下にひざまづくと、はるか紀州の熊野に向かって手を合わせ、権現さまの名を呼びました。「わたしは、ただいま中野の二本松までまいっておりますが、蜘蛛の糸を見失って困っています。どうか有馬の地までお導きください。
すると、どこからとなく、白いひげをはやした威厳のある老人が現れました。老人はにこやかに上人を手まねきし、小高い丘の上へと導いて行きました。「長い道のりをご苦労でした。この木の葉のまい落ちる所こそ権現さまのお告げのあった所です。」老人はそう言うと、かたわらの木の葉を一枚とり、空中高く放り上げました。木の葉はきらきらと輝きながら、風にのってゆっくりと舞い降りていきます。虫や鳥の声も一瞬止まったかのような静けさの中を、一枚の木の葉がふわりふわりとただよい流れて行くのでした。
木の葉の行方を追い求め有馬の地についた上人は、木の葉の舞い落ちた所の土砂や岩を取り除き、少しばかり掘ってみました。するとどうでしょう地中からあたたかい温泉がこんこんとわき出てくるではありませんか。
上人は村人と力を合わせ、村づくりに励みました。お寺を建て、家もふえ、有馬は温泉場として再び昔の賑わいを取り戻したということです。
山口の中野という所に「二本松」という姓の家が多いのは、このお話と関係がありそうですね。 |
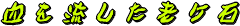 |
 河原にどっかりとすわっている大石を見上げながら、しきりに喜びの声を上げている一人の男がいました。この男は全国のあちこちを旅しながら、よい石を探し歩いている石職人でした。 河原にどっかりとすわっている大石を見上げながら、しきりに喜びの声を上げている一人の男がいました。この男は全国のあちこちを旅しながら、よい石を探し歩いている石職人でした。
「こんなすばらしい石は見たことがない。おらにも運が向いてきたぞ。」はるばるやってきたかいがあったと、ほくそ笑みながら、さっそく石を切るしたくにかかりました。船坂橋から二キロメートルほどの上流にあるこの大石は、地上に出ているだけでも高さ七メートル、横幅十五メートル、厚さ五メートルもあり、地元の人々から「老ヶ石(おいがいし)」と呼ばれていました。
鑿と金鎚を取り出し、今、まさに打ち降ろそうとした時でした。「おーい、ちょっとお待ちくだされ。」息せききって、村の人たちがかけつけてきました。いやはや、おどろいたのなんの。昔から、この石に刃物をあてた者には恐ろしいたたりがあると、先祖代々言い伝えられてきたのです。
なんでもその昔、ある男が酒に酔った勢いで、この大石を切ろうとしたのでした。「たかが石じゃないか。この俺様の石切の腕前をよく見ておれ。」 みんなのとめるのをふりはらい、石にのみをあてがうと、「エイッ」と金づちをふり降ろしたのです。すると、どうでしょう。みんなの目の前から、石の中にすいこまれるように、男の姿が消えてしまったのです。
こういうことがあったというのですから、「おまえさまも、やめておきなされ。石ならこの川の奥にも、なんぼもある。この老ヶ石だけは切っちゃなんねえ。」と、村の長老たちは、こんこんと男をさとしました。
けれども、この大石にすっかり心を奪われた石職人の気持ちを変えることはできませんでした。「そんなの迷信でしょう。わたしは石職人ですから、このようなよい石をそもまま見逃すことなんかできません。」するどくとぎすまされたのみが石にあてられるのを、村人たちはもはやなすすべもなく、ただ遠くはなれて見守っているだけでした。
カーン、カーン、カーン。静かな谷間に、石を切るのみの音がこだましていきました。村人たちはおそれおののきながら、石職人の一挙一動をじっと見つめていました。
突然、石を切るその手が止まりました。石職人は棒立ちになったまま、打ちこまれたのみのあとを見つめています。
何ごとが起こったのかと駆寄ってきた村人の目に、のみを打ちこんだ穴からまっ赤な血がほとばしって出ているのが映りました。
「これは大変なことになった。村の言い伝えを破ったからじゃ。」村人たちは、後ろも振り返らず、村へにげ帰りました。その後、石職人は原因不明の高熱が出て、そのあげく気がくるってしまったそうです。
今は、大石の上に祠があり、石仏がまつられています。 |
 |
 ひとりの男が、三田に向かって船坂峠をのぼっていました。船坂峠は険しく長い坂道で、男はあえぎながら登っていました。やっとのことで峠の頂までたどりつき、ほっと息をつきました。「ここらで少し休んでいこう。」男はあたりを見回して、道ばたの木かげに腰をおろしました。暑い日ざしの中を登ってきたつかれが出てきたのでしょう。男はこっくりこっくりいねむりを始めました。そのうちに深いねむりに引きこまれ、男はとてもふしぎな夢を見ました。 ひとりの男が、三田に向かって船坂峠をのぼっていました。船坂峠は険しく長い坂道で、男はあえぎながら登っていました。やっとのことで峠の頂までたどりつき、ほっと息をつきました。「ここらで少し休んでいこう。」男はあたりを見回して、道ばたの木かげに腰をおろしました。暑い日ざしの中を登ってきたつかれが出てきたのでしょう。男はこっくりこっくりいねむりを始めました。そのうちに深いねむりに引きこまれ、男はとてもふしぎな夢を見ました。
夢の中でも男は重い足をひきずり、船坂峠を登っているのでした。急いでいるのですがなかなか足が動きません。ふと見ると、道のまん中に人がたおれています。近づいてみると、それはひどい傷を受けた侍でした。侍はたいそう弱っていました。けれどもふらふらしながらも体を起こすと、男にたのみました。「いくさに負けたが、どうしても国に帰らねばならぬ。たのむ。なんぞ食わしてくれ。おまえの持ってる飯と水をめぐんでくれ。」男はあわてて手をふりました。「助けてあげたいが、あいにく何も持っていない。お気の毒になあ。」返事が聞こえないのか、男の着物を掴む侍の力がぐいっと強くなります。男は、侍の手をはなそうともがきながら、「ない。何も持ってない。」と叫びますが、侍の引く力は、ぐいっぐいっとますます強くなるのです。「やめてくれ。その手をはなしてくれ。助けてくれー。」男はおそろしさのあまり大声をあげながら、手足をばたばたさせました。
「もし、もし。起きなされ。えらくうなされて、どうしたのじゃ。」声をかけられて、男はハッとわれに返りました。男に声をかけたのは、ふもとの鷲林寺(じゅうりんじ)村の寺の和尚さんでした。船坂峠を通りかかり、苦しそうにしている男をみかけたのでした。男は、あまりにふしぎな夢だったので、和尚さんに話さずにはいられませんでした。
男の話をうなづいて聞いていた和尚さんは、聞き終わると両手を合わせ、深く頭をたれました。そしてしばらくの間お経をとなえた後、男に話し始めました。「だいぶ前のことになるがのう。いくさに負けた侍が、わしの村を通って落ちのびていったことがある。手傷は負うているし、ひもじさもあったのじゃろう。船坂峠のちょうどこの辺で、一歩も先へ進めなくなったのじゃ。峠を登る旅人たちに声をかけてもだれ一人助ける者はない。侍は、故郷で帰りを待ちわびている妻や子に心を残しながら、そのまま息たえてしまったのじゃ。わしの村で静かに休んでもらおうと墓をつくってとむらったが、やはり故郷が気がかりと見えて、これまでにもたびたび、峠を通る旅人に食物を求めて出てくるのじゃ。
村の人たちは侍の魂を「ひだる坊」とよんでお祭りしておりますのじゃ。」
これを聞いて、男はハラハラと涙を落としました。「和尚さま。故郷が気がかりなのは自分も同じでございます。年老いた母も乳のみ児も、村で自分の帰りを待っております。にもかかわらず、夢の中のあさましい自分の姿。お侍の心がわからず、にぎり飯も水もないと嘘をつきました。自分だけ助かりたい心がおそろしゅうございます。」
男は、鷲林寺の寺で修行させてほしいと申し出ました。男は、今夢を見たそのあたりをきれいにすると、ごはんと水を供え、和尚さんといっしょに手を合わせるのでした。
鷲林寺村の人々は、船坂峠を通る時には、必ず弁当を持っていったということです。峠で苦しんでいる旅人を見かけると、弁当を分けてやり介抱してあげました。また、木の葉にご飯を盛り、小高い所にそっと置いて、「ひだる坊さま、これをめしあがってください。」と、ていねいにおがんだということです。 |
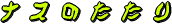 |
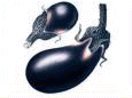 船坂は有馬温泉に通じる道すじで、峠になっています。今でも寒天づくりができるくらいですから、冬はとても寒い日が多いのです。その日も吹雪の舞う寒い日でした。お百姓の弥太八は、家の中で竹を割って籠を編んでいました。もう日が暮れかけています。 船坂は有馬温泉に通じる道すじで、峠になっています。今でも寒天づくりができるくらいですから、冬はとても寒い日が多いのです。その日も吹雪の舞う寒い日でした。お百姓の弥太八は、家の中で竹を割って籠を編んでいました。もう日が暮れかけています。
「おお、寒い寒い。これを仕上げて夕飯にしよう。」その時、トントンと、表戸をたたく音がしました。「もう暗くなっているし、今時分誰だろう。」と、戸を開けてみると、激しい雪の中に一人の老人が立っています。
「私は丹波の者ですが、有馬の湯へ行く途中、ひどい吹雪になり、おまけに日も暮れてしまい、困っています。一晩泊めてはもらえますまいか。」弥太八は親切な人でしたから、すぐに老人を中に入れ、囲炉裏端に招きました。
「さあさあ、火にあたりなされ。こんなところでよければ、休んでいきなされ。」やがて、茶わんの酒などを勧めます。老人は心から感謝し、うちとけて身の上話を始めました。
「私の村はなあ、丹波の山深い所でして、米や野菜があまりできませんのじゃ。村の者は、山で木を切ったり、炭を焼いたりして、細々と暮らしておる。私は暮らしのたしになるものが何かできないかと、考え続けてきました。このままでは、村のみんなが住めんようになる。いろいろ考えた末、私は決心し、妻や子を残して村を出てきましたのじゃ。あれからもう十九年、ずいぶん昔のことになります。ハイ。」
老人は、長い年月を確かめるようにうなづき、話を続けます。「何か村の役に立つことを見つけようと、北へ北へといきました。どれだけ訪ね歩いたことか。やっと、出羽の山形という所で、えらいお百姓さんに出会えましたのじゃ。」「そこは私の国より高い所なんですよ。その上、雨や雪が多くて、いい作物が育つとも思えん所じゃった。それなのに、りっぱなナスを作っていなすって、名物になっているのじゃ。私は、これじゃと思った。」「私はたのみこんで何か月か住みこみ、やっとナスづくりを教えてもらえた。そこのお方が、何年も何年も苦労し、改良に改良を重ねて作り上げなすったナスじゃ。村の外には出せない種なのじゃ。けれど、こんなに遠くまで来たお前さんのことだからと、大切なナスの種を分けてくれたんじゃよ。」いかにもうれしそうに顔をほころばせ、湯のみの酒をごくりと飲みます。
「私はその種を持って、丹波の家をめざし、急いで帰ってきましたのじゃ。長い道中のことで、賊に襲われて大事なお金をとられたこともあった。けれど、この種だけは守って持って帰ってきましたのじゃ。やっとここまで帰ってきたので、旅の疲れを休めようと有馬の湯へ向かっていたが、雪がひどいので行き倒れになるところじゃった。こうしてご親切に休ませてもらい、ほんとにありがたいことじゃ。」
老人は熱心に話し、うれしそうな顔で、その場に寝込んでしまいました。弥太八は聞いているうちに、自分がナスの種を探しあて、持って帰ってきて、船坂の村を豊かにするような気持ちになりました。船坂の村もこの老人の村と同じように高い土地にあります。ふつうの農作物がよく育たず、苦しい生活をしているのです。
「そのナスがほしい。そのナスを育てたら、村の暮らしはよくなるにちがいない。村中どんなに喜ぶことか。」弥太八はもうたまらなくなりました。弥太八の手がしぜんに動いて、老人の腹巻をさぐりました。「ああ、いけないことだ。」と、いったんは手をひっこめましたが、次の瞬間には夢中で、種の袋を引っぱり出しているのでした。ふるえる手で、別の種を入れかえ、元の腹巻に入れたのでした。
夜が明けると、老人は弥太八に何度もお礼を言い、出ていきました。弥太八はホッとしながらも、申しわけない気持ちでいっぱいです。じっと囲炉裏の火を見つめて考えこんでいました。その時、外で騒がしい村人の声がしました。とび出してみると、「村はずれで、旅の老人が死んでいるぞ。」と村人が大きな声で叫んでいます。「もしや」と思い、走って行くと、やはり昨夜の老人が倒れています。弥太八は老人にとりすがりました。
死んでいると思った老人が、大きく目を開き、うらめしそうに弥太八を見ました。「ナスの種がない。ナスの種をとられた。残念じゃ・・・。あのナスを作る者にたたってやるぞ。」そう言い終わるなり、息が絶えました。弥太八は、老人を手厚く葬りました。
やがて船坂の村は、ナスづくりが盛んになり、形も味もよい「船坂の長ナス」と言われ、有名になっていきました。ところが、どうしたことでしょう。そのころから村人の歯に黒い斑点ができるようになったのです。いくら磨いても落ちません。ひどい場合は歯が腐ったようになります。弥太八は、毎日を苦しい心で過ごしました。「これは、きっとナスのたたりにちがいない。」老人が死んでから十年目の命日に、弥太八は村人たちに集まってもらいました。そこで、老人のナスの種をすりかえたことを打ち明けました。村人たちに老人のお祭りを盛大にしてもらった後、弥太八は罪をつぐなうため、旅立ってお寺に入ったということです。
その後、「なすび歯」と言われた黒い歯はだんだんなくなっていきました。 |
 |
船坂の善照寺に、善想というお坊さんが住んでいました。ある晩のことです。善想の夢の中に、キラキラと黄金にかがやく仏さまが現れました。「私は、播磨の国の上久米村にいる如来です。今はこの村にいますが、ほんとうならあなたの住む善照寺にまつられることになっているのです。一日も早く迎えに来てください。」そう言うと、黄金の仏さまはすっと消えてしまいました。姿が消えた時、善想は目を覚ましました。
「ふしぎな夢じゃ。あの夢は本当のことじゃろか。それともただの夢か・・・。はっきりと声は聞こえたし、黄金に光るりっぱな仏さまじゃった。お迎えに来いと言われたのだから、やはり行ってみることにしよう。」早速、善想は播磨の国をめざして旅立ちました。有馬を過ぎ、西へ西へと歩いて行きました。夢に現れた黄金の仏さまの姿を思い浮かべながら、ひたすら急ぎました。
善想が、摂津と播磨の国境の淡河という村に来た時でした。向こうから一人のお坊さんが、何やら重そうなものを背負い、念仏を唱えながらやって来ます。近づいたお坊さんの背中を見て、善想は、「あっ」と大きな声で叫びました。なんとなんと、善想が夢で見た仏さまにそっくりな、黄金の仏さまではありませんか。善想はたまらなくなり、「もしもし、あなたが背負っておられる仏さまは、上久米村の如来さまではございませんか。」と呼びかけました。「よくごぞんじですね。この仏さまは、たしかに上久米村の如来さまでございます。しかし、あなたさまは、それをどうしてごぞんじなのですか。」 相手のお坊さんも、おどろきながら聞き返しました。
善想はそこで、ふしぎな夢の話をしました。すると、「ほう、そうでございますか。わたくしは、上久米村の如意と申す者ですが、実はわたくしも、あなたと同じ夢を見たのです。そこで、この如来さまをあなたの善照寺へお送りしていくところでした。あなたがお迎えに来てくれたのですから。それではここでお渡しいたしましょう。」そう言うと、背負っていた仏さまを、そっと石の上に置きました。「それはそれは、ありがたいことでございます。」二人は偶然の出合いを喜びあい、仏さまの前に揃って並ぶと、声をそろえてお経を唱えました。片方はお別れ、片方はお迎えの挨拶です。お経が終わると、「どうぞよろしくお守りくだされや。」「はいはい、大切におまつりいたします。」と声をかわし、二人はそれぞれ今来た道を、自分の村へと帰って行きました。
善想は、如来さまを背負い、「ありがたいことじゃ、ありがたいことじゃ。」と言いながら、わが村へと急ぎました。「大事にせねば」と肩に力を入れ過ぎたのか、善想は疲れてしまいました。そこで、船坂も近くになった時、石の地蔵さんの前で一休みすることにしました。背中の如来さまをおろしたところ、「船坂まで、ここからどれぐらいあるかの」と、如来さまが聞かれました。「一里ぐらいでございます。」善想が答えますと、「まだ一里もあるのか、遠やのう・・・」と、如来さまは呟くように言われました。それから後、そこの地蔵さんは「遠矢地蔵」と言われるようになったということです。
さて、善照寺に如来さまをお迎えした善想は、大切に大切におまつりしていましたが、ある夜ふけのこと、このお寺に泥棒が忍び込みました。如来さまが黄金でできているという噂を聞いたからです。本堂 に安置されている如来さまを見つけた泥棒は、「噂以上にすばらしい仏さまだ。黄金に輝いている。これさえあれば、おれは大金持になれるぞ!」と、にんまり喜びました。 に安置されている如来さまを見つけた泥棒は、「噂以上にすばらしい仏さまだ。黄金に輝いている。これさえあれば、おれは大金持になれるぞ!」と、にんまり喜びました。
さっそく如来さまを持ち出そうとしました。しかし、なんと、如来さまにかけた手がすいついたように離れず、思うように力が入りません。それでも泥棒は、何とか縁側までは如来さまを引きずり出しました。が、とうとう、金しばりにあったように手と足が動かなくなってしまいました。「黄金どころではない、こんなことをしていると、自分の命があぶない!」泥棒は、如来さまからやっと離れると、後をも振返らず逃げだしてしまいました。
この話はたちまち広まり、善照寺の仏さまは泥棒よけになると信じられるようになりました。如来さまの足は台座から少し離れ、紙一枚が入るほどの隙間があります。如来さまを拝みに来る人々は、この隙間に紙を入れ、足形をとるようになりました。如来さまの足形を家に置いておくと、泥棒が入らないおまじないになるというのです。
こうして、善照寺の仏さまは「浮足如来」とも呼ばれ、人々に親しまれるようになったという事です。 |
 |
むかし、行基という偉いお坊さんがいました。国中のあちこちを旅しながら、悪い病気に苦しむ人たちをみては治していました。行基が摂津の国の有馬に名湯があるとの話を聞いて、やってきた時のことです。
険しい山を越え、ちょうど船坂あたりにさしかかると、行基は一歩も歩くことができなくなってしまいました。どのくらいたったでしょうか。山仕事を終えた村人たちが通りかかり、松の木にもたれてぐったりとしている行基を見つけました。急いで村へ連れて帰りました。
村人たちは、「何か元気の出る食物を」と考えるのですが、村は貧しくその日暮らしがやっとで粗末な食物しかありませんでした。「そうだ、鯉を食べると元気が出るそうだ。」「よし、わしがひとっ走り山をこえて、奥の池の鯉を掴まえてこよう。」威勢のいい若者が大きな籠を抱えて、かけ出していきました。やがて、帰ってきた若者の籠には、池 の主かと思われるような見事な大鯉が入っていました。早速、村人たちがその鯉を料理して、行基に食べさせました。行基はみるみる元気になっていきました。 の主かと思われるような見事な大鯉が入っていました。早速、村人たちがその鯉を料理して、行基に食べさせました。行基はみるみる元気になっていきました。
すっかり元気な体になった行基ですが、なぜか心は晴れません。庭にすてられた鯉の骨を見て、行基は考えるのでした。「わたしの命は助かったが、その代わり、命あるものが一つ消えてしまった。」行基は念仏を唱えながら、ていねいに鯉の骨を拾い集めました。そして塚をつくり、鯉の供養をしました。
船坂の、今ではゴルフ場になっているあたりに「鯉塚」という地名が残っています。 |
 |
 宝塚から有馬温泉に行く道すじに、蓬莱峡という景色のよい所があります。長い年月のうちに風化した岩山が、幾重にも重なるようにつき出ています。 宝塚から有馬温泉に行く道すじに、蓬莱峡という景色のよい所があります。長い年月のうちに風化した岩山が、幾重にも重なるようにつき出ています。
昔のことですが、京都に一人の座頭が住んでいました。座頭とは、目が見えないので、琵琶をひきながら歌を歌うなどしてくらしをたてていた人のことです。この人は目が見えない上に、小さいころから病気持ちで大変苦しんでいました。
ある時、有馬の温泉につかるとよくなるという、耳よりな話を聞きました。「目が見えないのに、一人での長旅はあぶないからやめなさい。」「しばらくしたら、わたしが商売で有馬の近くまで出かけるから、それまで待ちなさい。」近所の人たちが気づかって止めるのを振り切って、座頭は一人で旅立って行きました。目の見えない座頭の一人旅に、途中道行く人たちは同情し親切に道案内をしてくれました。
その日は、街道の宿屋で一夜を明かしました。「今日もいい天気だ。明日には有馬の温泉につかって病気をなおすことができそうじゃ。あとひとがんばりだ。」朝早く元気に宿を出た座頭は、昼ごろには有馬街道にさしかかりました。武庫川の支流・太多田川にそったこのあたりは、七曲りといわれる険しい山道が続きます。まだ太陽も高く、杖を頼りに山道を辿って行きました。
ところがどうしたはずみか、街道から左手の谷に迷いこんでしまいました。目が見えないので、あっちこっちといろいろな方向へと歩いてみましたが、すぐに岩かべにつきあたって進めなくなります。しかたなくかたわらの岩に腰をおろして、旅人の通りかかるのをじっと待ちました。さらさらと流れるせせらぎと谷に吹きこむ風の音、あたりに住む猿の鳴き声が聞こえるばかりです。
「みんなの言うことを聞いて、誰かといっしょに来ればよかった」「せっかくここまで来て、あと少しで有馬の温泉につかれるというのに」秋の夕暮も早く、いつしかひんやりとした空気がただよってきました。山肌を赤くそめて陽がしずんでいきました。落ち葉や木の実の落ちる音が、寂しさを募らせます。「このままじっとしていても仕方がない。」また、杖を頼りに必死に歩いてみましたが、やっぱりだめでした。どっちへ向かっても、すぐ岩壁に行く手をさえぎられてしまうのです。心細く、その上寒さと空腹に、座頭は気もくるわんばかりです。
とうとう、なりふりかまわず大声で助けを求めました。「誰かおりませんか。わたしは目の見えない座頭です。ここから出してください。」「助けてください。お願いです。だれか来てください。」しかしその声は、まわりの岩かべに山びことなって、むなしくこだまするばかりでした。
日もとっぷりくれた谷間で、病気が急にひどくなり動く気力を失った座頭は、ばったりと倒れてしまいました。旅に出るのを止めてくれた近所の人たち、心配そうに見送ってくれた人たちの顔が、次々と浮かんでは消えて行きます。座頭は、有馬の湯にゆったりとつかっている自分の姿を夢に見ていました。
二、三日して、土地の猟師が冷たくなった座頭を見つけました。その後、地元の人たちは、だれ言うとなく、この谷を「座頭谷」と呼ぶようになりました。 |
 |
 昔、京の都に琴の名手として有名な一人の娘がおりました。身分は高くありませんでしたが、顔かたちもよく心の優しい娘は、都の若者たちのあこがれのまとでした。いつのころからか、娘は、位の高い貴族の若さまを好きになり、結婚の約束をしました。まわりの人たちからは祝福されたのですが、若さまの両親だけは二人の結婚を許しませんでした。若さまには小さいころから妻になる人として親の決めたお姫さまがいたのです。 昔、京の都に琴の名手として有名な一人の娘がおりました。身分は高くありませんでしたが、顔かたちもよく心の優しい娘は、都の若者たちのあこがれのまとでした。いつのころからか、娘は、位の高い貴族の若さまを好きになり、結婚の約束をしました。まわりの人たちからは祝福されたのですが、若さまの両親だけは二人の結婚を許しませんでした。若さまには小さいころから妻になる人として親の決めたお姫さまがいたのです。
しかたなく、娘と若さまは、手をとりあって都をぬけ出しました。若さまの乳母の里である九州の地をめざして旅に出たのでした。若さまは横笛を懐に入れ、娘は琴をいだいていました。途中、有馬の宿に立ち寄り、二人はしばらく幸せな日々を過ごしました。娘が琴をひけば、若さまはそれに合わせて横笛をかなでます。まるで夢のようでした。やがて、二人の間には玉のようなかわいい赤ちゃんも生まれました。
ところがある日、若さまが重い病気にかかってしまったのでした。妻は夜も寝ず一心に介抱し、神にも祈りましたが、若さまはとうとうこの世を去ってしまいました。妻は嘆き悲しみましたがどうすることもできません。両親のいる京の都へ帰ることにしました。
夫の遺骨を胸に抱きしめ、赤ちゃんを背に負い、寂しく宿を出ました。秋半ばを過ぎて、有馬街道は紅葉に美しく彩られれていましたが、心細さが募るばかりです。険しい山道の蓬莱峡をやっと過ぎたころ、とつぜん背中の赤ちゃんが火のついたように泣き出しました。すぐに降ろしてお乳をふくませましたが、飲もうとしません。泣き続けるばかりです。途方に暮れ、泣き叫ぶ赤ちゃんを背負い、助けを求めて村里に向かって走りました。背中で揺られていた赤ちゃんの泣き声が弱くなったかと思うと、そのうち全く聞こえなくなりました。おかしいと思い背中から降ろしてみると、すでに赤ちゃんは息絶えていたのでした。
しばらくの間、赤ちゃんを抱いたまま、ただ呆然と立ちつくしていました。やがて、よろよろと歩み出し、小高い丘に登ると、穴を掘り、夫の遺骨と赤ちゃんを並べて葬りました。悲しみに打ちひしがれ、またしばらくその場に呆然としていましたが、やがて、愛用の琴をひきはじめました。寂びしく、悲しい琴の音色でした。「ご両親さま、わたしは今から夫と子どものもとへまいります。先立つ不幸をお許しください。」遠い京の都に向かって、いつまでも手を合わせていましたが、秋の日は早くも暮れかけます。ふらふらと立ち上がると、深い木立の奥へと入っていきました。
それからというもの、夜になると、谷間からは赤ちゃんの泣き声が聞こえ、山の方からはもの悲しい琴の音が聞こえるようになったということです。人々は、この山を「琴鳴山」と呼ぶようになりました。 |
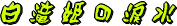 |
遠い昔のことでした。六甲山の北側のふもとの山田という里に、真勝(さねかつ)という若者がいました。「このままこんないなかにいては楽しくもない。都に出て、何か新しい仕事がしたいものだ。」都へ出た真勝は、幸いにも、天皇に仕えることができました。
ある日のことでした。真勝が庭の掃除をしていると、その日に限って御殿のすだれがまきあげられていました。「今日はどうしたのだろう。何かお祝いごとでもあるのだろうか。」近づいて、中を、そうっとのぞいてみました。なんと、なんと、美しいお姫さまが座っておられるではありませんか・・・。薄衣をまとった肌はぬけるように白く、物思いに沈んだ瞳は、底深い湖水の色をたたえていました。
姫の名は、白滝姫といいました。ある大臣の娘で、都の若者たちの噂の的になっていました。真勝は、白滝姫の美しさにすっかり心を奪われてしまいました。「あんなお姫さまをお嫁さんにできたら、これ以上の幸せはあるまい。あー、あー何とかしてお嫁さんにもらうことはできないだろうか。」真勝の胸の中は、姫のことでいっぱいになり、はりさけんばかりになりました。そこで「朝な夕な、あなたのことを一時も忘れることができません。あなたへのおもいを募らせています。」という恋文を送りました。
しかし、姫の心をとらえることはできませんでした。恋文を送り続けて、春が過ぎ夏が来ました。秋も来て冬を迎え、また春がめぐってきました。とうとう、恋文は千通を超えてしまいました。それでも姫は、まっ黒な顔をした庭はきの若者を、かえりみようともしませんでした。
「そうだ、歌合わせだ。歌合わせに勝てば、姫もみとめてくれるだろう。」その頃、御所では「歌合わせ」といって歌のよみくらべをして勝ち負けを決める遊びがありました。真勝は、さっそく、天皇にお姫さまとの歌合わせをお願いしました。千通もの恋文を送ったという真勝を哀れに思った天皇は、姫との歌合わせを許しました。
歌合わせの日がやってきました。真勝は、姫を恋している胸のうちを歌によみました。『水無月の 稲葉の露もこがるるに 雲井をおちぬ 白滝の糸』(六月の稲田では、稲の葉にやどる露の水さえ待ちのぞまれているのに、どうして空からは、白滝のような雨が落ちてこないのだろう。わたしもかわいた稲田と同じです。心から白滝姫を待っているのです。)
姫も、真勝に返し歌をよみました。『雲井から ついにはおつる白滝を さのみな恋そ 山田男よ』(待っていればいつかは空から白滝のように雨が落ちてくるでしょう。そんなに恋しく思わないことです。いなか者さん。)
二人の歌を聞いた天皇は、真勝の真剣な気持ちに打たれました。そして、心のなびいていない姫に言いました。「姫よ、そなたは真勝をいなか者と思ってきらっているようだが、真勝はすばらしい歌を読むことができるではないか。人は顔かたちではない。そなたに千通もの恋文を送り、そなたを恋したってくれる男に嫁ぐほど幸せなことはあるまい。そなたは真勝の嫁になるがよかろう。」
いくらお姫さまでも、天皇の命令にそむくことは出来ません。姫は、真勝に嫁ぎ、都をあとに山田へ向かうことになりました。西国街道から、生瀬を経て有馬街道に入り、荒れ果てた河原を、飛び石伝いに上がっていきました。都をはなれてからいく日も過ぎていました。ようやく二人は、船坂を越えるあたりまでやってきました。
真勝に手を引かれ支えられ、やっとここまで来た姫でしたが、とうとう、くたくたと、その場にくずおれてしまいました。生まれて初めての長旅の疲れからでしょう。もう一歩も歩く力も気力もありませんでした。真勝は、姫を背負って歩いて行きました。背負われた姫には妻をおもいやる夫のやさしい心が、背中を通してひしひしと伝わってきます。夫の背中に顔をあてて、姫は泣きました。姫のはげしく泣くようすにおどろいた真勝は、姫をそっと降ろして、道ばたのやわらかい草の上に横たえてやりました。
「たとえ命令とはいえ、父や母に別れてこのような山奥で苦しむ自分がかわいそうです。けれども、都を出て何日も過ぎた今、あなたのやさしい心がわかりました。あなたのやさしさを知って、よけいに心が苦しいのです。」姫はそう言うと、その場に泣き伏し、さめざめと涙を流すのでした。すると、ふしぎにも、土に落ちた姫の涙は泉となってあふれ、川となって流れだしていきました。この川は、その後も絶えることなく、清い流れは、旅人ののどをうるおし喜ばれました。人々は、この川を「白水川」と呼びました。 |
