生活用,業務用,工場用など。
原単位の時系列分析が主ですが,その他の手法も必要に応じて。
生活用水量の推計について。
業務用水量の推計について。
一人一日平均使用水量の傾向について。
| 作成者 | BON |
| 更新日 | 2004/07/04 |
需要予測の方法と,各項目の特徴についてとりまとめました。
| 用途別水量の分類 生活用,業務用,工場用など。 |
|
| 需要水量の分析方法 原単位の時系列分析が主ですが,その他の手法も必要に応じて。 |
|
| 生活用水量 生活用水量の推計について。 |
|
| 業務用水量 業務用水量の推計について。 |
|
| 一人一日平均使用水量 一人一日平均使用水量の傾向について。 |
【参考】
一応は完成。あと,原単位や推計方法,重回帰分析など,まとめなければならないことは多いんですが...まあいずれ。
需要の予測は原則として用途別に行います。これは,生活用水の概念を導入して人口の推移と需要水量の変化を連動させること,用途別の需要水量の傾向をつかむこと,などが理由と思われます。
水道水の需要用途については,設計指針において,以下のような区分が提案されています。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 摘要 |
| 生活用 | 一般家庭用 | 家事用 | 家事専用(一般住宅,共同住宅,共用栓)のもの |
| 家事兼営業用 | 家事専用のほか一般商店等営業用を兼ねるもの(店舗付き住宅等) | ||
| 業務・営業用 | 官公署用 | 官公署用 | 学校,病院,工場を除く国,地方公共団体の機関 |
| 公衆用 | 公衆便所,公衆水飲み栓,噴水等 | ||
| その他 | 官公署以外の非営利的施設で他の用途分類に属さないもの | ||
| 学校用 | 学校用 | 学校,幼稚園,各種専門学校等 | |
| 病院用 | 病院用 | 病院,産院,診療所等 | |
| 事務所用 | 事務所用 | 会社,その他法人,団体,個人の事務に使用されるもの | |
| 営業用 | 営業用 | ホテル,旅館,デパート,スーパー,一般営業用で住居を別にするもの,キャバレー,料亭等の特殊飲食店,料理飲食店,軽飲食店結婚式場サウナ,バス・タクシー会社の洗車用等,劇場,娯楽場等 | |
| 浴場用 | |||
| 工場用 | 工場用 | 工場用 | |
| その他 | その他 | その他 | 船舶給水,他水道への分水等 |
| 水道事業用水,水道メーター不感水量等 |
【備考】
分類の表は,水道施設基準(1990)参考表1.4より編集のうえ抜枠しました。
需要水量の推計・分析の代表的でオーソドックスな手法には,以下のようなものがあります。もっとも一般に使用するのは時系列分析で,生活用水では原単位の,その他用途では直接の時系列分析が一般的です。
ただし,必要に応じて他の手法の適用も検討します。特に,基本計画であるなら,さまざまな角度から検討する意味で,他の手法も試してみるといいでしょう。
| 1 需要水量の時系列分析 | 2 原単位の時系列分析 | 3 回帰分析 | 4 用途別積上原単位による方法 |
| 需要水量を時系列とみなして直接推計する。 | 人口などをフレーム値として需要水量の推計を行う手法。生活用一人一日需要水量や人口一人当りの業務用水量などを時系列分析する。 | 複数の説明変数を用いて需要水量を表現しこれらの説明変数の推計結果から需要を予測する。説明変数が一なら単回帰分析となる。説明変数には政策値などを適用する。 | 需要の用途別分析資料を用い,これを積上げて推計する。生活用水を例にあげると,風呂,散水,炊事,掃除洗濯,のような用途別に,使用水量及び使用回数を積上げる。用途別需要水量についてはさまざまに研究されている。 |
| 計算が簡単であり,短期予測によく用いられる。原単位などが無い場合,数理的な説明が困難な場合でもある程度予測値を設定できる。 | 計算が簡単であり,短期予測によく用いられる。また,給水原単位の動向を直接把握でき,人口予測と連動できるため,生活用需要水量の推計などではもっとも広く用いる。 | 適切な変動要因を用いることで,水需要量の説明に説得力を持たせることができる。また,統計的に妥当性が評価できる。 | 用途別,使用目的別に積み上げていくため,生活行動面で実感として理解しやすく,社会動向についても対応することが可能である。 |
| 水使用構造の変化など水使用動向に変化が生じた場合予測値にずれが生じやすい。需要用途と全く別に推計するため検討の一貫性が問題。 | 水使用構造の変化など水使用動向に変化が生じた場合,予測値にずれが生じやすい。 | 採用する説明変数について十分な検討が必要。十分な説明変数のデータと分析がないと,分析そのものが意味をなさない。 | 種々の基礎水量や回数の把握が難しく,またこれらの将来の不確実性も大きい。さらには誤差の累積にも注意する必要がある。事業計画ではあまり使用しない。 |
このほか,システムダイナミクスのような直接的モデルを探る方法,立地ポテンシャル×原単位で検討する方法,昼間人口,住人口,生徒数,従業者数,延べ床,昼間就業人口,内風呂率,経済成長率,水洗化率等の細かいデータを重回帰的に用いて飽和的需要を探る方法,など,いろいろ工夫の余地はあります。
ただし,どのような方法が正しいか,というより,どのような設計思想で水系を行うか,の方が数倍重要ですので,これからの時代には,必要に応じ,ニーズに応じた検討方法をその都度開発するくらいの気構えが必要でしょう。
【備考】
1)生活用水量とは
生活用水量の推計は,全体計画における割合が大きいことや,人口推移の直接の影響を受けることなどから,特に重要です。
生活用水量は,通常,一人一日平均生活用(有収)水量と給水人口を乗じて計算することで,人口の増減との相関性を持たせます。よって,推計自体は一人一日平均生活用(有収)水量に対して行います。
一人一日あたりの生活用水量は,数年前までは基本的には増加するものでした。特に影響が大きいのが核家族化の進行による世帯人員数の減少です。つまり,洗濯や風呂用水などは世帯あたりの家族数が減少することで,一人当たりの水量が押し上げられることが多い,ということです。さらに生活スタイルの変化,特に水洗便所や清潔指向などが水需要を押し上げているケースもあります。
ただし,ごく最近では,これが頭打ちの傾向も見られるようになったケースもあるようです。節水機器,特に洗濯機の影響が指摘されていますが,これに関する情報は筆者はもっておりません。
あと一つ,確実に需要水量の低下をもたらすのは渇水の経験です。通常,数年程度前のレベルまで需要水量が低減しますし,渇水頻度の高い都市の一人一日平均生活用(有収)水量は低く出る傾向があります。
生活用水量原単位とは,一般に一人一日平均生活用水量を有収水量ベースでとらえたものです。
水道メーターの検針結果を家庭用について集計し,これを給水人口で除して求められるため,料金収入との相関性が高く経営上非常に重要な指標であると同時に,水需要の大きな部分を占めることが多いため,事業計画の中核となるのが普通です。
生活用水量原単位は,簡易水道事業を新設する場合では,一般に200L/人/日,これに加算水量を加えて240L/人/日とされており,生活の程度が進んでいると見なされる地域については,さらに上積みが認められています。
原単位は,地域によって大きく異なります。たとえば福岡のように渇水の頻度が高い都市,井戸を併用できる地域では,原単位が低くでるケースが多く,200L/人/日を割り込むケースもあります。
さらに,近年では,環境意識や節約意識の高まりから,節水機器などの浸透が需要に影響を与えているとの指摘があります。その影響に関する調査も個別に行われているようです。参考まで,節水機器関係情報のサイトを紹介。
| 【国民生活センター】 商品テストなどの情報。節水機器関係とかもあります |
なお,原単位は一人一日で計算するため,一般に人口が減少を始めると上昇する傾向を示します。これは,人口減少が世帯の減少と完全に一致しているのではなく,核家族化や社会の成熟により,世帯あたりで使用する水量が,一人当たりで使用する水量に比べてあまり減少しないためと考えられます。需要予測の際には押さえておかなければならないマメ知識です。
【備考】
1)業務・営業用水量
官公署,病院,学校,事務所,商店など,業務用に使用される水量です。一般に,直接推計を行えば十分なのですが,重回帰分析により経済指標とのリンクを図るケースもあります。また,第52回研究発表会では,事業地の面積を原単位として推計できるという報告がありました。今後の計画で参考にさせていただきます。
2)工場用水量
その名のとおり,工場用水量です。経済情勢や,コスト縮減のための努力の効果が現れるため,時系列分析を適用しにくいケースが多くなります。工業用水道事業などでは,工場用水量の推計に,工業団地の分譲計画など工場の立地予定企業を産業中分類に従って業種想定し,それぞれの原単位を乗ずる方法で算出する場合もあります。
3)その他水量
船舶給水用などが特殊用途として計上されることがありますが,推計というよりは能力計上にならざるを得ないでしょう。その他水量のまま,ラウンドに使用してしまう荒技もあります。
4)統計データ
業務用水量の分析にあたっては,直接の統計値を説明変数に用いて,重回帰分析などを行う場合があります。ネット上には,説明変数として役立つような情報を掲載している公的サイトも多数あるようです。
【備考】
この関係はいろいろあるんですが...ノウハウとしては未整理なので,おいおい充実していきましょう。
一人一日平均使用水量は,給水量を給水人口で除して算出するものです。生活用水原単位は有収水量ベースの生活用水のみを対象としていますが,一人一日平均水量は給水量ベースの全水量を対象としています。ちなみに,給水量とは,水道事業者が送り出した全水量のことで,先に示した用途別水量(生活用,業務用,工場用,その他等)の合計です。
一人一日平均需用者一人当たりの使用水量は需用者の水使用状態を把握し,水道事業者の経営上の効率を把握するうえで大きなヒントになる数字です。大口の工場やレクレーション施設などがあり,かつ住人口が少ない場合に大きくなる傾向があるほか,渇水などを経験することで,大きく下がる場合もあります。このあたりは生活用水原単位の欄を参考にしてください。
さて,下図は一人一日平均使用水量の実態を知る必要から作成した図です。とりあえず手に入った平成11年度の水道統計から,一人一日平均使用水量のヒストグラムを作成,分布を見て見ました。このヒストグラムからは,大体が320-420L/人/日の範囲と見られますが,もっとも基本的である一人当たりの使用水量においても,地域によって大きく異なる傾向があることがよく分かると思います。
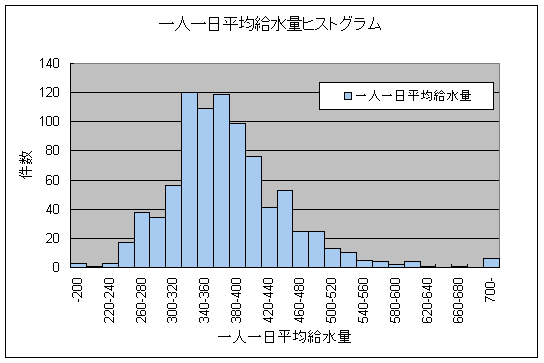
【備考】