[礼文3日目]
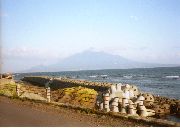 礼文三日目の朝。毎日旅人が入れ替わるので、名前を覚える暇もない。今日もフェリーターミナルでお見送りだ。
礼文三日目の朝。毎日旅人が入れ替わるので、名前を覚える暇もない。今日もフェリーターミナルでお見送りだ。
三日目ともなると、段々とここでの生活パターンにも慣れて来る。この宿が初めてで、私より後にやって来た人たちは、私がそうであったように、一様に勝手が掴めない表情でいる。そしてやはり私と同じような第一印象を持つ。
「なんで、いつも団体行動しなくてはならないの?」
そして、何時の間にか私が慰める立場になっていたりするのだ。
今日は島の北を歩くことにした。花に詳しい常連のOさん、そして昨日到着したこちらも常連の女性三人。そして私と同じく今回礼文が初めてらしいTさんの6人パーティだ。
宿のオーナーに出発地点の西上泊まで、車で送ってもらうことになった。
途中、小さな川に寄ってもらい鮭の遡上を観察したりしながら、西上泊に到着。ここからは歩いて北端のスコトン岬を目指す。いわゆる4時間コースを逆からたどる感じだが、「道」には「正しい行き先」はあっても、「正しい方向」なんてないのだから「逆」というのは正確ではない。


まずは澄海(スカイ)岬へ。ここは西上泊からすぐの場所にある。名前の通りエメラルドブルーの澄んだ海の色で、とても北国の日本海とは思えない。これに珊瑚礁でもあれば、南の島にいるような感じだろう。
快適なトレッキングコースを歩く。
途中、一旦ゴロタの浜付近の集落に入り、小さな漁港で「なぎさ特製弁当」を広げた。この弁当はかなり大きな握り飯が2個と、おかずに煮ホッケ。シンプルだが、却ってその方が美味しく感じることもある。もっとも適度な運動の後は、何を食べても美味しいのだが。
こうして歩いていると、「何だかいいなぁ」と知らず知らずに呟きが漏れるのだ。そして、弁当を食べ終わった後にも、また同じ呟きが漏れていた。
昨日よりは雲も多く晴天と言うわけには行かないが、風は穏やかだし、遠くには礼文岳越しに遠く利尻山も見える。
そんな快適なトレイルをゆったりとした気分で歩いている内に、やがてスコトン岬に到着した。


このスコトン岬は語感が面白い地名だが、漢字で書くと「須古頓」になる。この集落にある小学校は、集落の規模に対して大きな校舎を持つのだが児童数は「2名」しかいないらしい。同行のOさんに教えて頂いた話だ。
須古頓は、本数こそ少ないが、バス路線が通っている集落なのだ。普通に考えれば近くの大きな町、例えば船泊まで通学しても良さそうなものだと思うのだが・・・。以前はもっと児童数が多かったのか、それとも将来的に増加することが見込まれているのか。
スコトン岬では「最北端牛乳」なる名物(?)の牛乳を飲み、ついでに北限の公衆トイレ(トイレの名前がそうなのだ。本当にそうなのかどうかは知らない)にも寄って、帰路についた。ここからは路線バスで、フェリー乗り場まで向かうことになる。


一日目、二日目までは「自由の利かない旅」にうんざりしていて「早めに礼文を発ってしまおうか」と考えもしたのだが、三日目ともなるとこの雰囲気にも馴染んでくる。旅の刺激は少ないが、代わりに故郷に帰ったような居心地の良さも感じ始めている。ただし、この「故郷」というのがミソ。
私は「故郷」というものは、心から羽を伸ばせる反面、親族特有の「お節介」やら「煩わしさ」やらも一緒に付いて回るものだと思っている。
都会で一人暮らしの人は想像してみると良いだろう。盆暮れに田舎の両親のところへ帰るときの気持ちを。それは両親に久しぶりに会える喜びと、ある種の「うざったさ」が同居したような気分ではないだろうか(私は経験が無いので、あくまでも想像だが)。
この民宿なぎさには、常連の客が多い。
一度泊まった宿に再び泊まるということは、設備が快適だったり、料理が旨かったり、あるいはサービスが良かったりなど、人によって様々な理由があるだろうが、この礼文の小さな宿は、その「故郷に帰ったような気分」がもっとも大きな理由として、常連客を増やしているような気がしていた。
それにしても今回礼文に来てからは酒量が大幅に減っていた。食事の時、晩酌代わりにビール1本、日本酒1杯を飲むくらいで、一度も「食事の代わりが酒」になったことはない(それが普通なんだけど)。もしかすると3ヶ月も礼文に滞在すれば、私のγ-GTP(アルコール摂取が多すぎると、肝機能検査でこの数値が上がる)も、平常値まで下がるかも知れない(笑)。
でも「礼文最後の夜なんだ」と思うと、なんとなく酒でも飲んで過ごしたくなってくる(無理矢理に「飲む口実」を作っているだけのような気がしないでもないが・・・)。
そこで、オーナーが明日の朝食の下拵えをしている調理場へ行き、ビールを頼もうとすると「山田さん、一緒に飲もう」とオーナーに誘われた。すでにOさんが一緒に飲んでいる。
「山田さん、今度は5月においでよ。人が少なくてさ、もっと静かだし、花も見られるし・・・のんびりできるよ」
何だか「礼文最後」をあらためて感じるような夜だった。
[礼文4日目]


礼文を離れる朝が来た。今日も青空だ。初日の台風を除けば、天候にはず〜っと恵まれていた。
朝食の後、すぐに民宿の前を散歩した。のどかな漁村と言う感じがする。祖父が住む森町の、子供の頃見た漁村風景がそこにはあった。
最後の記念撮影を宿の前で行い、フェリー乗り場へ向かう。
今日旅立つのは私一人。しかもこの後私は利尻へ向かうため、フェリーの時間がいつもより後の方にズレている。それに他の人も早くどこかへ出かけたいだろう。だから「お見送りはいいですよぉ〜」とスタッフのTさんに遠慮してみたのだが、相手にしてもらえなかった。う〜ん、やっぱり「お見送り」はこの民宿の神聖な儀式なのだなぁ(笑)
実を言うと遠慮をしていると言うより、見送りされることが照れくさかったのだ。
フェリー乗り場では全員でジャンケンをした。今回礼文に来てから三度目のジャンケン大会だ。
いくつかのグループに分かれてジャンケンをして、一番負けた人がグループの全員にジュースを奢るという、たわいのないゲームだが、これが結構盛り上がる。
そんなことをして時間を過ごしている内に、どんどん出発の時間が近づく。急に落ち着かない気分になってきた。
・・・名残惜しいのだ。何に名残惜しいのかは自分でも分かってはいない。「礼文」という場所への名残惜しさなのか、それとも「人」への名残惜しさなのか・・・。

やがて乗船時間。
仕事を辞めて最果ての島までやって来たT君とA君。そして礼文にただ一軒のケーキ屋で、泊まり客全員にケーキを買ってきてくれたKさん。2日に渡って一緒に歩いてくれて、花のことなどを教えていただいたOさん。そしてお世話になった宿のスタッフの方々。そんな一人一人と握手を交わしながらお別れの言葉を交わす。
ふと「なんだ、いいじゃん。たまにはこういう旅も」と思う。一人旅だけど、一人じゃない。煩わしいけど、居心地がよい・・・。
船上からお別れの言葉を叫ぶ。なぎさのテーマソングが聞こえてくる。
明日また幾人かが旅立ち、そしてまた新しい旅人が訪れる。
この民宿なぎさも10月上旬で今年の営業を終える。最果ての島の、旅の季節は終わりに近づいている。
船が動き出した。「行ってらっしゃぁ〜い」例の言葉が聞こえる。
「絶対照れくさくて言えないぞ」と思っていた言葉が、ごく自然に私の口から出ていた。
「行って来まぁ〜す!」
船は港の外に向かう。さっきまで握りしめていた紙テープが一本切れ、二本切れ・・・民宿の皆が、波止場の先端まで走る姿が見える。先頭を走っているのはオーナーだ。
再び「行ってらっしゃい」の言葉が聞こえてくる。続けて「また来いよぉ〜」の言葉。
やがてそんな彼等の姿も防波堤の陰になり、見えなくなった。
姿が見えなくなっても、いつまでも彼等の送る言葉が聞こえているような気がしていた。私の中で「また来いよぉ〜」の言葉がリフレインしていたためかも知れない。

礼文島は日本最北端の有人離島。別名「花の浮島」と呼ばれる美しい島。そしてそこは北の最果ての島。
「最果ての島は家族の島」
ある意味の煩わしさも、故郷のような居心地の良さも。
お節介にも似た気分も、初めてなのに何故か感じる懐かしさも。
何もかも全てひっくるめて、私にとっての礼文島は、確かに「家族の島」だった。
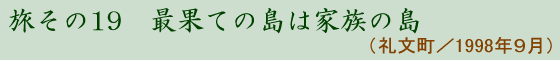
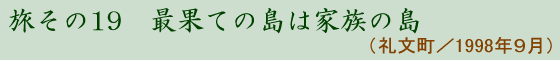
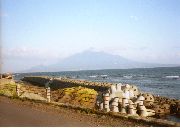 礼文三日目の朝。毎日旅人が入れ替わるので、名前を覚える暇もない。今日もフェリーターミナルでお見送りだ。
礼文三日目の朝。毎日旅人が入れ替わるので、名前を覚える暇もない。今日もフェリーターミナルでお見送りだ。
 まずは澄海(スカイ)岬へ。ここは西上泊からすぐの場所にある。名前の通りエメラルドブルーの澄んだ海の色で、とても北国の日本海とは思えない。これに珊瑚礁でもあれば、南の島にいるような感じだろう。
まずは澄海(スカイ)岬へ。ここは西上泊からすぐの場所にある。名前の通りエメラルドブルーの澄んだ海の色で、とても北国の日本海とは思えない。これに珊瑚礁でもあれば、南の島にいるような感じだろう。
 このスコトン岬は語感が面白い地名だが、漢字で書くと「須古頓」になる。この集落にある小学校は、集落の規模に対して大きな校舎を持つのだが児童数は「2名」しかいないらしい。同行のOさんに教えて頂いた話だ。
このスコトン岬は語感が面白い地名だが、漢字で書くと「須古頓」になる。この集落にある小学校は、集落の規模に対して大きな校舎を持つのだが児童数は「2名」しかいないらしい。同行のOさんに教えて頂いた話だ。
 一日目、二日目までは「自由の利かない旅」にうんざりしていて「早めに礼文を発ってしまおうか」と考えもしたのだが、三日目ともなるとこの雰囲気にも馴染んでくる。旅の刺激は少ないが、代わりに故郷に帰ったような居心地の良さも感じ始めている。ただし、この「故郷」というのがミソ。
一日目、二日目までは「自由の利かない旅」にうんざりしていて「早めに礼文を発ってしまおうか」と考えもしたのだが、三日目ともなるとこの雰囲気にも馴染んでくる。旅の刺激は少ないが、代わりに故郷に帰ったような居心地の良さも感じ始めている。ただし、この「故郷」というのがミソ。
 礼文を離れる朝が来た。今日も青空だ。初日の台風を除けば、天候にはず〜っと恵まれていた。
礼文を離れる朝が来た。今日も青空だ。初日の台風を除けば、天候にはず〜っと恵まれていた。 やがて乗船時間。
やがて乗船時間。 礼文島は日本最北端の有人離島。別名「花の浮島」と呼ばれる美しい島。そしてそこは北の最果ての島。
礼文島は日本最北端の有人離島。別名「花の浮島」と呼ばれる美しい島。そしてそこは北の最果ての島。