■ 2003/09/03 (水)
[Comp]英辞郎
さて、妻の電子辞書を買って、自分にも電子的な辞書が欲しくなった。ただ、我が家に既に電子辞書をもっていて、さらに数万を電子辞書だけのために使うというのはちょっと惜しい。また、サイズ的にも自分が携帯して使用するためには小型のものが欲しいが、今回いろいろ観察して、小さくて十分な語彙数と使い勝手を兼ね備えた機種がないことも良く分かった。そこで再び小物好きの血が騒ぎだしてしまったのだった。すなわち、リナザウに英辞郎を入れるという考えに取り付かれてしまったのであった。
まず英辞郎についてウェブで調べてみた。語彙数は116万語(Ver.66)。この語彙数も、よく単純な辞書にありがちな訳語を列挙しただけというような物ではなく、例文なども充実しているようだ。実際英辞郎を作っているグループのEDPのページには「英辞郎を使って英語で日記が書けるかな?」というページがあり、そこでは検索ソフトから英辞郎の例文を辿って英作文をしている例が示されている。
どうやら辞書としては結構よさそうだ。ただ今回対照として電子辞書をもってきており、こちらはさすがに使い勝手が練られている。これに比べてコンピュータ上の検索ソフトの使い勝手が悪かったり、フットワークに欠けるようであれば、電子辞書を買った方がマシということにもなりかねない。Windowsで標準的に使用されているPDICというソフトウエアはさすがになかなかよさそうなものであるが、私が使用しているのはMacであり、さらに今回の目的はLinux Zaurusでどうかという部分である。
とは言えLinux Zaurusを持っている人が身近にいるわけでもないので、そこの使い勝手を実際に確かめることはできない。ただとりあえずMac上で、辞書の使い勝手などの具合を確かめるだけなら可能だろう。また、帯びて使うことができないというだけで、Macについても携行して使用しているのだから、ここに辞書を持つ意義は決して小さくない。そこでまずはiBook上で英辞郎を試してみて、その成果次第でリナザウへの応用を考えてみることにした。
早速ウェブから注文。2200円。いつ手元にくるのかな。
■ 2003/09/04 (木)
[Comp]英辞郎
もうついた(^^)。
[Comp]英辞郎ビューア
さて、この英辞郎、どうやって使うか。WindowsではPDICという定番ソフトがあるようだが、さてMac上では、とウェブで探してみた。jdixというソフトやや昔懐かしJammingなど、比較的定番ぽいのはあるが、X対応じゃなかったり辞書ファイルにひと手間いったりするものが多い中、英辞郎ビューアというのがX上のソフトで、そのままのデータを扱えるようだ。さらにフリー。というわけでとりあえずまずこれを試してみた。ざっと検索をかけてみたところ、検索の時のオプションの指定などがないようなので、あまり凝った検索はできない。しかし、比較的さくさくと動いてくれるので、とりあえずはこれで使用してみることにした。
ただ、検索ウインドウに何も入力せずにリターンを押してしまうと、全データを表示しようとするのか延々と帰ってこなくなってしまう。これはしょうがないのかな。
■ 2003/09/05 (金)
[Comp]リナザウに悩む
さて、ハードとしてのリナザウはどうしようか、悩む。
要はそこまで踏み切れないのだな。キーボード付きであのサイズというのは魅力だが、そのキーボードにしてもJornadaのような一応ブラインドタッチのできるものではないから、快適なメモ入力が本当に可能なのかどうかがいま一つ不明である。また、ディスプレイが回転する仕組みも、かえって使いづらいように感じてしまう。
時として欲しい気が盛り上がりかける時もないわけではないが、なにか心の中でストップをかける部分が残っている。時系列で見れば2002年11月に第一世代の700、2003年6月頃に第二世代の750/760が出た。ここは第三世代を期待して、せめて年末まで待ってみるべきかなあ、というのが現時点での結論。760の辞書無し型の発展系が出るといいなあ。
■ 2003/09/12 (金)
[Comp]リナザウ目撃
会議でお茶の水の方に。隣の席に来た先生、途中でなにかごそごそとやっているのでふと目を向ければ、そこにリナザウ。メールチェック?なんだかこういうばりばり?に使用しているのを目撃すると、ちょっとグラッと来ちゃうよなあ(^^;。
[Movie]パイレーツ・オブ・カリビアン(新百合ヶ丘ワーナーマイカル)
お茶の水から新百合ヶ丘に直行(正確には秋葉に寄り道してちょっとLinux Zaurusを眺めたりした後秋葉原から、であるが(^^;)。レイトショーに(6月?から映画を見続けてゲットした平日無料券を使用(^^))。お目当ては前回見ることのできなかった「カリブの海賊」。
舞台となる画面は、時代の雰囲気に浸れる程度にはそこそこキチンと作り込んであるが、色合いにしろ雰囲気にしろ変に暗かったり汚かったりはしない。また、海賊物だけあってそこそこ残酷な状況はないわけではないが、ディズニーランドのカリブの海賊を元にしたとかいうだけあって、ほんとに残酷な場面を直視しない作り方をしてあって、不快な映像があまりなく、安心してみることができる(その辺り物足りなく思う向きもあるのだろうが)。
しかし、なによりも雰囲気を作っているのがジョニー・デップ演じる海賊。ヒロインも奇麗で勇ましいし、もう一人の主人公の男の子もかっこいい、敵役も憎々し気で良いのだが、なによりもジャック・スパロウのいかがわしさがこの映画の大部分でしょう、って感じ。とにかく前評判通り、とっても楽しめた娯楽映画でした。
■ 2003/09/13 (土)
[Music]音楽案内人加羽沢美濃presents 3大ピアニスト名曲コンサート
加羽沢美濃が司会と冒頭の名曲メドレーを弾き、その後に本編として横山幸雄、青柳晋、近藤嘉宏による
- チャイコフスキー:花のワルツ(2台)
- ショパン:幻想即興曲
- ショパン:子犬のワルツ
- ショパン:プレリュード第24番
- ドビュッシー:亜麻色の髪の乙女
- ドビュッシー:喜びの島
- ショパン:英雄ポロネーズ
- ショパン:エチュード「革命」
- ラフマニノフ:2台のピアノのための組曲第2番から第4楽章「タランテラ」(2台)
- ラヴェル:水の戯れ
- リスト:ハンガリー狂詩曲第6番
- 横山幸雄:アヴェ・マリア(バッハ=グノーの主題による即興)
- リスト:マゼッパ(超絶技巧練習曲集より)
- リスト:愛の夢
- リスト:ラ・カンパネラ
- 横山幸雄:祝祭序曲(2台)
- [アンコール]横山幸雄:ショパンの別れの曲による別れの曲(2台4人)
といったプログラムを聞くことが出来たコンサート。クラシックのことをほとんど知らない私でも聞いたことのある曲を、個性の異なる若手の人気ピアニスト4人が弾いてくれると言う、実に楽しいコンサートであった。個性が異なると書いたが、実際に私の耳でも同じ時に聞き比べることができることにより、横山幸雄さんは力強く、青柳晋さんは繊細な感じに感じられたのであった。
場所は狛江エコルマホールにて。こういう市のホールの企画だと安価にこういうコンサートが楽しめてうれしい。有意義な午後であった。
■ 2003/09/14 (日)
[Comp]秋葉再訪
今日はたまたま私が一人フリーになってしまった。金曜日にあーゆー気分になった直後の今、秋葉に行くのはまずいとは思ったが、ついふらふらと秋葉に行ってしまったのであった。
とりあえず暫定的なターゲットはSL-C760。理由は電池とメモリ。特にメモリは拡張が効かぬだけに、760に狙いを定めていた(電子辞書化として英辞郎の利用を考えていたため内蔵辞書は邪魔だが)。ここ数日kakaku.comなどでチェックしてみていると、今の最安値は5万7千円程度のようだ。また秋葉原の大通り沿いに、最安値グループの店のうちの一つがあるようだ。ということで、まずはその店に向かってみた。本日の価格は57,500円。kakaku.com通り。相対的に見て安いとは言え、絶対的に見て決して衝動買いできる価格でもない。また、必須な周辺機器の一つであるSDカードも、相性が良いとされるPanasonicの256Mタイプで11,000円。足すと税込み7万超。悩みながらさらに秋葉を徘徊する。
とにかく現物がどの程度使えるか、それが決め手である。今の場合には、キーボードがどの程度使えるものであるかが判断の決め手となる。こればかりは試してみなければ分からない、とLAOX The COMPUTER館を訪れる。ここには700/750/760が各1台ずつ、自由に使える状態で展示してあるのだった。あまり一台を占有し過ぎて他の人に迷惑をかけてはと、適当に機種を換えつつひたすらにメモ帳を使って文章を打ってみた(っていくら3台にわけたといってもトータルで2時間近くそんなことしてたら十分迷惑です(^^;)。まずはブラインドタッチを試みてみるも、展示品故タグがつけてあり、置いたときの安定度が悪い。この状況でははっきりと分からないが、ちょっと普通にブラインドタッチをするのは辛そうだ。続いてとにかく親指タイプで、普段打ちそうな文章をひたすらに打ってみることにした。初めはスピードが上がらなくて駄目かと思えたのが、少しずつ意外と使えるかな、という評価に変わってきた。画面の表示も奇麗で、デフォルトの文字フォントの感じも悪くなく、使っていて楽しい感じがしてくる。これはやばい(^^;。
それでも価格がなあ、と思いつつ先のショップに向かうと、そのご近所に前に一度訪れたことのある「Mobile専科」が。ちょっとここも覗いてみるかと入ってみる。店員さんに値段を確認すると、56,800円。あ、そ、と思って店を出た後に、初めのお店よりさらに安かったことに気付く(^^;。店に戻り750の間違いでないことを確認したり、さらにLAOXに戻って試し打を繰り返したり。悩んで悩んで秋葉到着後3時間を越えたところでついに観念して銀行に足を運び、「Mobile専科」に。やってもうた(^^;。
SDカードもあわせて購入しようと思い(CFはJornadaで使っていたマイクロドライブがあるから当面良かろう)、Panasonicの256Mを頼むと、店員さんが、その隣のアイオーデータのものと中身は同じであると教えてくれる。いーひとだよー(笑)。ついでにこれも良いとの評判を聞いた液晶保護シートOverLayBrilliantを購入。1枚入り1500円弱。初めは液晶保護シートなんていらないぜ、という気分だったが、いざ金を出してみると痛むのが恐くなっちゃったのだった。
さて、スタンドアロンのままではオンラインのソフトを入れるのにも困ってしまう。有線のLANカードが安いが、リナザウに有線でもなかろう、と無線LANカードを調べにLAOXに。ここでも親切な店員さんに教えを請い(まさか買ってしまうとも思わなかったのでここまでは調べてなかったのだ(^^;)、webサイトを見せてもらって一通り動作確認のとれたCFの無線LANカード類をチェック。値段は6800円ほど。ちょうど手持ちの万札を崩さねばならない額であったので躊躇して、ふとLAOXの向かいのソフマップ中古PDA館に入ってみると、BuffaloのCFタイプワイヤレスLANカードWLI-CF-S11Gがあるではないか。4,980円。LAOXの親切な店員さん、ごめんなさい(^^;。
かくしてやってもうた760を胸に抱いて帰宅。帰宅後早速充電を開始。そのまま満充電まで待とうかと思ったのもつかの間(^^;、液晶の具合が心配で、我慢できずに電源をオン。とりあえず液晶に目立ったドット落ちはない模様。良かった良かった(笑)。
[Comp]Linux Zaurus SL-C760使いこなしへの道:第一回連係編
頻繁に見ていただいている奇特な方は、前回(9月12/13日付)の更新時にサイトデザインが変わったことに気付かれただろう。これまではごてごてしていたため、結構広い画面で見通しながらでなければ快適な更新はできなかったのだ。今回りなざうを入手したことから、ゆくゆくはりなざう上での更新も視野に入れ、単純な構造に変更したのであった。そーゆー訳なのであったのだ(^^)。(あとなるべく「正しい」HTMLにしたいと言う思いもなくはなかったので、これを機会にいろいろと改めようと思っているのであった)
さて、これからりなざうの使いこなしが始まるわけだが、今回はPalmやJornadaの時のようにやったことを時系列にずらずらと書くのではなく、なるべく自分なりに少々まとめつつ書いて見ようと思っている。まずは第一回として連係編。
せっかく入手したリナザウであるから、デフォルトで入っているソフトだけを、他との連係もなく単独で使っていてもつまらない。オンラインのソフトウエアを入手するにせよ、連係をとるにせよ、何らかの手段で外部との通信/連絡手段を確立する必要がある。Zaurusは本来はWindows系パソコンとの連係を前提としているマシンであるため、私がWindows系のマシンを使用していればUSB(シリアル)接続によるPCリンクと言うシンクロの手段が提供されているためさほど悩む必要はない。しかし私の使用しているマシンはMacintosh。その基本的な手段は使えない。それ以外のもので考えられる方法としては以下のようなものがあるだろう。
- USB(シリアル)接続(PCリンク以外)
- LANによる接続(有線/無線)
- CFスロットのカードによるファイル交換
- SDスロットのカードによるファイル交換
- その他
これらについて順に見ていってみよう。
1. USB(シリアル)接続
さて、はじめにMacintoshだからUSB接続ができないと言っていてなんでいきなりこの方法が来るのか。実はしばらく前にいろいろ情報を集めていた中で、OS Xハッキングというサイトの第62回 OS XでLinux Zaurusを使う(1)にて、
「フリーのドライバを導入すると」、「USB接続の端末として認識されるようになる」
という記述を見つけていたのだ。それで何ができるようになるかと言うと、
「PIMのデータを同期するといった便利な機能はないが、SL-Zaurusをファイルサーバとして使えるほか、telnetでリモートログインできるようになる」
とある。それだけできればとりあえず十分である。というわけで、早速試みようと、このサイトを訪れた。さてドライバーをどこから入手すればできるようになるのかな、と先の記述を探す。あったあった。と改めて上記引用箇所をよく読むと…。
「フリーのドライバを導入すると、v10.2以降のOS XでUSB接続の端末として認識されるようになる」
私10.1.5ユーザーなんですけど(^^;。りなざうかっちゃったからOSのバージョンアップを先送りしたんですが(^^;。挫折であった。
- ★念のため備忘として、そのドライバと、関連して必要なもののリンクをメモ
- ※Mac OS X USB driver
- ※Sharity
2. LANによる接続(有線/無線)
LAN接続の手段としては上述の通り無線LANカードを入手済みである。というわけでCFスロットに無線LANカードを挿入。なんだか勝手に自動接続を開始しはじめる。当然なにも設定していないから失敗して停止。そこで改めてQtメニューの「設定」から「ネットワーク設定」を選択し、「セットアップ」をタップ。まず、挿入しているカードを設定に利用するか、と聞いてくるので「はい」を選択。続いて「プロバイダの選択」。使用するのが自宅アクセスポイントであるから「その他のサービス」を選択。後はネームサーバを自動検出のままにしておき、ぐじゃぐじゃとした設定を行い、Mailの設定も行って設定完了。改めてタスクバーの地球アイコンをクリックすると自動接続が開始され、今度は接続に成功した。
電波の具合だが、主に使用することになる居間で他の機械を使ったとき、例えばiBookではInternet Configでの信号レベルは2/3程度、メニューバーの扇型はフル、Jornadaでもおおむね表示がグリーンの状態で使えていた。その同じ位置から接続を行って、良くて表示が黄色もしくは赤で電波が弱いぞと怒られちゃうような状態である。なんだかとってもシビアな感じだ。やっぱりCFタイプと小型だから電波がシビアなんだろうか?
かくしてまずはりなざうの外部への通路は確保した。
3. CFスロットのカードによるファイル交換
リナザウにはメモリカード用のスロットがSDとCFの2種類ある。このうち通常SDの方は、メモリカードを本体に挿しっぱなしで運用し、いわばパソコンで言えば内蔵HDDの様に使用する。一方CFの方は、通信カードもCFタイプであったりなど、挿し換えを前提とした運用を行うため、こちらで使用するメモリカードがリムーバブルメディアに相当する。従って、Macとのファイル交換にはCFを使うと言うのが自然な流れかと考えた※1。CFタイプのカードとしては、Jornada時代に1Gのマイクロドライブを持っている。こちらを活用することにした。RioSU30を買った日に購入していたカードアダプタGeSPEC Slotinカードリーダ/ライタを取り出し、まずはマイクロドライブをiBookにマウント!…認識してくれない(^^;。マニュアルによるとマイクロドライブは接続パソコンによっては供給電力不足で使用できないことがある旨かかれているが…(^^;。とりあえずまたも挫折であった。
※1メモリカードをMacにマウントすると、Finder.datなどのよけいなファイルをいろいろ書き込んでくれるし、特にMac OS Xではメモリカードにファイルを転送する際に、転送したファイル毎にドットで始まるファイルが出来ちゃうから、できればメインに使用することとなるSDカードはあまりMacにマウントしたくなかったというのもある。
追記:普通のCFカードではきちんと読み書きが出来た(当然か)。Jornada用、デジカメ用に何枚かCFカードは持っているから、適当に中身をあけてファイル交換用に使用することにしよう。(2003/09/16)
4. SDスロットのカードによるファイル交換
こちらは無事に読み書きが出来た。とはいえ、案の定finder.datや"."ファイルがドッと出来た。内蔵のファイラである「ファイルホーム画面」では、finder.datはともかく、基本的にunixの不可視ファイルである"."ファイルを見ることができない。そこで(とりあえずこの時点でインストール済みであった)コンソールにおりて、ひたすらrmやrmdirしまくるのであった(^^;。いやいや、おかげでちょっとCUIの感じを取り戻したよ。ってうれしくなーい(^^;。とりあえずZau→Macの時は、必ずSDカードにロックをかけて行おうと心に誓うのであった。
5. その他
その他に考えられる手法として、2.で触れるべきところを触れるのを避けていた事項が一つ。LAN経由でのファイルのやり取りというのが残っている。が、MacOS X上の手ごろなftpサーバソフトを見い出していないこと、りなざう上の適当なftpクライアントを試していないこと(CUIでやってもいいんだけどさー)から手を付けていない。前者に関しては、休眠しているLibrettoをファイルサーバとして復活させるという手もなくはないが…ざうの別の用途のために復活させようかと中を開いてみたところ、HDDの空きはあまりない(もともとが2Gしかないのだ)上に、ちょこちょこと何が入っていたのかを確認しているうちになんとなく潰してしまうのも惜しくなってしまい、元の様に眠りにつかせてしまったのであった。大掃除のとき、中を見なければ捨てる決心が付いた本を、つい中を眺めてしまったために惜しくなって捨てない方にまわしてしまう心理と同じであるな(^^;。
Librettoに関しては、まじめにそろそろWindows95のままでは動かないアプリケーションの類いも増えてきたこともあり、いっそBTRONを入れようかなどと考えていたこともあったのだが。手持ちのWinマシンがこれしかないと言うのが毎回の引っ掛かりの原因。とはいえこれまでLibrettoを必要とする理由を作ってきたPalmもJornadaも第一線を退いた今、変なところで惜しんでないで、Linuxでも入れてサーバーにしちゃった方が有意義なのかなあ。
■ 2003/09/15 (月)敬老の日
[Comp]Linux Zaurus SL-C760使いこなしへの道:第二回電子辞書編
さて、今回りなざうを購入した最大の口実は電子辞書であった。である以上、なんとしてでも使える電子辞書をセットアップせねばならない。間違っても内蔵の辞書でお茶を濁すことは許されない(^^;。幸い数多くの先達たちによって道は作られている。後はなぞっていくだけ。とはいえwebにある先達の業績は主としてWindows上における作業を前提としている。若干の不安を覚えつつ作業を開始したのであった。
まずウェブにある情報を改めてチェック。私家版携帯端末考の、「なんとかなるさLinuxZau」の「辞書は電子手帳の常識編」が非常に良くまとまっていたので参考にさせていただいた。このページをざっと見ると、MacではDicCompressorというソフトを使用するとの記述が。早速これをサイトからダウンロード(v1.0.1)。さて、これをどう使うのかな、と改めて私家版携帯端末考を見ると…。EPWINGの辞書の圧縮のためのソフトとある。すなわち、英辞郎の辞書のままでは駄目なのだ。まずこれをEPWING形式に変換しなければならないのだった。
改めてウェブ上で「Mac」で「英辞郎」を「EPWING」にするためのものを探すが、見つからず。Mac上での変換作業を断念した。
途方に暮れて、ここはWindowsを使うしかないのかとLibrettoを引っ張りだしてみたは良いが、HDDの空きスペースが300M程度。とてもそのような作業を行なえるような空きがない。さらにはWindowsの圧縮ソフトはWindows95では動かないとの記述も。これは駄目だ。いろいろと誤算が出てくるものだ(^^;。
仕方がないので、こっそりと職場のPCを一時利用させてもらうことにした。作業の詳細についてはZaurus SLを参考にした。まずは英辞郎をEPWINGに変換するソフトのEBStudio v. 1.60をダウンロードする。登録すれば後方一致などの検索が可能となるらしいのだが、未登録でも前方一致検索は可能とある。とりあえずは未登録のままで作業を行ってみることにした。Windows2000上で、記述に従ってC:の直下に\eijiroを作って、その中に英辞郎CD-R中のtxtファイルを移す。EBStuidoを起動し、eijiro.ebsを指定。変換を開始させるがエラーが出て終了してしまう。eijiro.ebsの記述を眺めてみると、テンプレート上ではeijiro52などと、ver. 52のファイルとおぼしきものを指定している。書籍の添付の英辞郎はver.52だったのかもしれないが、私の持っているのはver. 66。ということで、テンプレート上のファイルネームを*66に修正して再開。今度は無事に変換できた。
続けてBuckingham EB Playerもダウンロード。アーカイブ中のBuckingham EB Compressorを用いて最大圧縮をかける。C:\eijiroから、変換前の*.txtファイルを削除しておいてから圧縮開始。こちらは無問題。作業終了した\eijiroを、USBメモリカードに移し、USBメモリカードをMacintoshに挿し、USBカードアダプタ経由でSDに移す。その際、SDカード直下に「Dict」というディレクトリを作成し、その下に「eijiro」をそのまま移行。これで辞書の準備は完了した。(正確にはうざいMacintosh由来のファイルを消しまくったりと言う無駄な作業も入ったのだが詳細は前日参照(^^;)
辞書検索ソフトとしては、定番と言えそうなZtenを使用することにした。Ztenの「ダウンロード」から「kakasi (ver. 2.3.4-2)」と「zten (ver. 1.6.2)」をダウンロード。こちらはMacでダウンロードしたipkgファイルをメモリカード経由でZauに移しただけで大丈夫だった。本体にインストール(kakasiは本体に入れることが必要)。Ztenを起動し、「ファイル」→「辞書の選択」で英辞郎、和英辞郎、音辞郎、略語郎を指定。「辞書一覧」で全てにチェックを入れて、設定完了。入力欄に文字を入れていくと、一文字入れる度に検索結果がパッパッと変わる。圧縮を行うと遅くなると言うので気になっていたのだが、非常に素早い。検索結果の表示に関しては若干一覧性が悪いが、これは表示エリアのサイズと見やすい文字サイズを考えれば仕方あるまい。おおむね満足の行く結果となった。
かくして電子辞書のセットアップはとりあえず完了した。今回、電子辞書はりなざうのメインのアプリとする予定である。よって当然Ztenについては「高速起動*1」にチェックを入れておく。また内蔵電子辞書の高速起動は解除。(ついでに使用頻度があまり高くない「メール」と「アドレス帳」も解除。「カレンダー」「ToDo」は使用頻度が高めだから、「イメージノート」はいざ画像ファイルをタップした際に時間がかかるのも面倒だから、「メモ帳」は念のため、「NetFront」はとりあえず高速起動のまま)
*1「常駐」状態にして起動を速くする設定。当然メモリを消費する。
あと、Ztenで選ぶことのできる検索方法にはちゃんと後方一致とかも入っている。より電子辞書の有効性を高めておくために、ここはEBStudioのシェアウエアフィーを払って登録を行い、辞書を完全にしておいた方が良いかな。
■ 2003/09/16 (火)
[Comp]Linux Zaurus SL-C760使いこなしへの道:第三回SNESエミュレータ編
さんざん電子辞書のために導入したと言っておいて、第三回にしていきなりゲーム編(^^;、SNES(スーパーファミコン)エミュレータの導入である。といってもLibrettoでもiBookでも「活用」している、個人的に裏のキラーアプリとでも言うべき存在であるため触れとかないわけにもいかないだろう(^^;。
とはいえ、何も私がここで事細かに紹介する必要は一切ない。りなざうテクノウの「snes9xやっとく?」において、まさに手取り足取りという感じでインストール方法を教えて下さっている。そういうわけで、以下簡単に備忘。
まずはlibsdlがないと動かないとのことで、libsdl 1.2.5(Agawa:Welcome Page)をインストール。つづいて本体snes9x 1.39aをSL-Zaurus 対応 emulator 置き場から持ってくる。これはzipファイルなので、unzipも、unzip 5.24をZaurus Software Indexから。unzipをインストールしsnes9xをデコード。出来た「snes9x」について、コンソールにおりて(コンソールについては後述)cpしたりchmodしたりするのだが、これも事細かに記述があり、その通りやるだけで問題無く、無事にインストールが完了した。
これでコンソールからCUIでSNESエミュレータを使えるようになったわけだが、さらにGUIでROMの選択を行ったりすることをできるようにするランチャーがあるという。ということでZEmu Front End Ex ver. 0.1.1-3exを、サイトの「ダウンロード」よりダウンロードしてインストール。ここでROMデータを/mnt/card/snesに入れ、「ZEmu Front End Ex」を起動。無事にゲームが行えることを確認した。ただ、ZEmu Front Endがインプットスタイルで操作しているにも関わらず縦長画面でしか起動しなかったので、「アプリケーションをVGA(480×640ドット)の画面に最適化して実行する」のチェックを外す。これでインプットスタイルのまま操作可能となった。
ちなみに言うまでもないがここで使用しているROMデータは、所有しているROMカセットと同じものである。念のため。
早速試してみる。SNESエミュレータを知ったのは結構昔だが、当時メインに使用していたマックではあまり使い物にならなかった(し、まだ本体も現役状態にあったのに、わざわざデスクトップのマックで質を落としたゲームをする必要はなかった)。これがLibrettoSS1000の時代になると、音を消しておけばそこそこ楽しめる域に達し、持ち歩いてゲームができると言うことで、かなり「活用」するようになった。その時点ではLibrettoの画面でゲームをすることが当たり前であったのだが、これが一旦メインがiBookに移り、そちらでも「活用」するようになってからLibrettoに戻ってみると、とてもじゃないが画面が小さすぎて楽しむ以前に疲れてしまうと感じるようになった。さて今回のりなざう、Librettoどころではない画面の細かさに加え、まだなれぬ操作性。目がちまちましてきて軽く頭が痛くなってきたよ(^^;。りなざう上でやるのなら、スーパーファミコンよりはファミコンのゲームの方が解像度の点からはいいかもね(^^;。
■ 2003/09/17 (水)
[Comp]Linux Zaurus SL-C760使いこなしへの道:第四回ソフトウエア編その1
辞書(とゲーム)だけでは携帯端末として面白くない。私に関して言えば、Palmの頃から携帯端末には、テキストを中心としたデータの入力と参照を、時と場を問わずに行えることを求めている。それを行うためのソフトウエアとして、内蔵ソフトもそこそこ充実しているが、多くの偉大なる先達たちのおかげにより、操作性や機能面の小技の効き具合などでさらに優れたソフトウエア群が存在している。今回はそういったソフトウエアのうちで、私がこれまでに試すことのできたものについて若干書き記しておこう。
1. テキスト関係
なんといってもまずはエディタである。もっとも入力量の多い日常の記録をつけるにせよ、webの更新を行うにせよ、またC760の場合はLinuxということで各種設定ファイルがテキストファイルとなる。こういったものをいじくる際もエディタが必須となる。内蔵の「メモ帳」は、意外に使い勝手が悪くもないが、セーブを行うと自動的に拡張子がtxtとなるらしく、htmlをいじるのが面倒であるらしい。何度も出てくる私家版携帯端末考に各種エディタの比較があり、どうやらZEditというのが定番中の定番っぽい。早速、Satoshi Web Siteを訪れ、ZEditor v1.2.9をダウンロード。
ちなみに内蔵のブラウザ「NetFront」でダウンロードを試みると、りなざう用の?パッケージである.ipkをダウンロードしようとするときには、デフォルトとして本体メモリの「application/ipkg」を示してくる。こういうソフトのパッケージをいちいち本体に入れていてはあっという間にいっぱいになっちゃいそうなので、SDカードに「application/ipkg」という本体メモリと同様の穴を掘っておいて、ここにをダウンロードしていくことにした。また、インストールの操作も簡単。「設定」から「ソフトウエアの追加/削除」を選ぶと、ファイルの一覧が出る。そこにはソフトウエアの名称とバージョンが記されており、さらにインストール前のものについては赤い紐のかかった箱のアイコンがついており、これがインストール済みになると青い玉のアイコンに変わるという親切設計である。さて実際に一覧の中から「zeditor」をクリック。インストールする場所を本体かCFかSDかと聞いてくる。本体にインストール。ソフトウエアの追加/削除を終了してHomeを見ると、「ZEditor」というアイコンが出来ているという次第である。
さてZEditorであるが、起動直後のデフォルトの文字がとても小さいので、[Fn] + [2]で文字サイズを大きくした。普通に使い勝手良く使うことが出来そうだ。いろいろメニューを見ていると、メニューから日付けをはめ込むことができるようだ。また、設定でそのフォーマットも変更可。気が利いている。この日付け、CTRLキーを使えるようにするとワンストロークで入力できるらしい。これは便利そうであるが…。
そう、りなざうにはCTRLキーがないのだ。しかしこれについても先達が解決済みである。またまた私家版携帯端末考経由でLinuZau ToolBoxへ行き、KeyHelper (ver. 1.0.9-1)をダウンロード。設定の方法は私家版携帯端末考に非常に詳しく書いてあるのだが、正直難しい。今度プリントアウトしてじっくりやることにする(^^;。とりあえずKeyHelperの効用として、[Shift] + [Home]で起動中のアプリを切り替えられるようになったことでとりあえずよしとする(^^;。
さらにまたまた同じ私家版携帯端末考に、ファイラとして紹介されていたZaurus File Manager (ver. 1.5.0-1)も試してみることにする。ツリー形式でディレクトリを移動し、タブで画面を切り替えてファイル操作をするというファイラであった。
さて、エディタも入れたことだから、とJornadaやiBookからテキストファイルを移動した。ZEditで見え具合などを確認しているうちに、どうやら困ったことになったことが判明した。いくつかのファイルをりなざう上で見た時に、画面上で改行が効いていないのだ。確認してみると、Jornada移行時に問題となったUnixのLFは問題なく改行してくれているが(当たり前か)、Macの改行コードCRのファイルで画面上に改行が効いてない。なにかこの辺りを対応してくれているソフトはないかと、まずはもう一つの定番ソフト、
yEditもZaurus Indexからダウンロードして試す。キーカスタマイズができるのが特徴らしいのだが、それ以外のところは、とりあえず個人的にはZEditの方が好きかも。
各種テキストファイルの内、当サイトのhtmlファイルの方は、SJIS/LFであるため、りなざう上での編集に問題はない。というわけで、0914の日記で既に言及したようにりなざう上での編集/更新も一応視野に入れて、サイトデザインを簡潔かつ正しいHTMLを目指した形に変更することにしたのだった。
その他テキスト関係では、JustReader+ (ver. 1.6f-3)をダウンロード。これは適宜辞書を引きながらテキストを読めるものらしいのだが、インストールはうまくいったものの、なんだか辞書の指定がうまくいかずに、使用をペンディング中。
2. コンソール
りなざうの「りな」らしさを簡単に味わえる部分として、コンソールの利用がある。しかしこのコンソールからだと、逆に何でも出来ちゃうだけに危険な存在でもあるのだろう、C700では出荷時から搭載されていたものが、C750/760では添付CDから追加でインストールすることになっている。ただ、添付のコンソールは機能的に不足気味らしく、別のコンソールを使っている人が多い。ならばはじめから定番のコンソールを入れるが良かろうと思い、毎度お馴染み私家版携帯端末考のお勧めのものを試すことにした。
いとしの lizaからqpe-embeddedkonsole-ja 日本語入力欄付きワイド版パッケージ (1.6.0-jinput3_arm)をダウンロード。インストール。初めは文字も小さく、他のアプリケーションの様に[Fn] + [2]で文字を大きくしたりもできないのでとっても戸惑った(ちなみに[Fn] + [2]はフルスクリーン化で画面が一行広がるだけなのだ)。そのうちふとしたきっかけで[Fn] + [Q]でポップアップメニューが開くことに気付き、そこからフォントや背景色などを変更できることに気が付いた。その後は、ウェブサイトで改めて各種操作方法を確認して、今度は困ることのないように、メモ帳に転載しておいたのであった。
コンソール絡みで、PC-98(EPSON含む)時代に愛用したファイラであるFDclone (ver. 2.04a-1)をFDclone for Linux Zaurusからダウンロードしてインストール。ちょっと試しては見たのだが、さすがに離れて10年以上の年が流れているため、当時は手が覚えていて直感的に使えていたはずの使用法がかけらも思い出せない(^^;。ま、必須というほどのこともなし、コンソール絡みの作業をするときに、時として使えれば便利なこともあるでしょう。
3. 内蔵ソフト
ついでにこれまで使用したことのある内蔵ソフトの使用感についても若干。
- PIM系
- 「アドレス帳」「カレンダー」「ToDo」が該当するか。「メモ帳」も一応この範囲に。このうち「アドレス帳」については使用していないが、「カレンダー」と「ToDo」は使用頻度が高め。そもそも一旦紙のメモ帳でもいいかと思っていたのをやはり電子手帳系に引き戻した理由の一つが、スケジュール管理をしたかったからであるため、これは当然。「カレンダー」については、月表示のところで小さい字で予定が書き込んであるため、使いやすい。また日表示の所では「ToDo」を表示可能で、これは時に便利(C750/760から。凄く要望と言うか苦情が多かったらしい)。「メモ帳」はテキストエディタ的に使用できるファイル管理の「Text」Tabの画面と、Palmのメモ帳と同様の「Memo」Tabの画面の2種類ある。このうち「Text」についてはテキストエディタを入手済みであるため、2画面開きたいときの参照用などに使うには便利かもと言う程度。「Memo」については、第一行がタイトルとなって一覧表示がされるもので、Palmでその使い手の良さを感じて以来結構こういうタイプ好き。ただ、一面しかないのでベタの管理しかできない。Palmの様にカテゴリ分けできれば便利なのにね。
- 通信系
- 「メール」はあまりりなざうでメールを見るつもりもないので、たまに使えればいいかと言う程度。その程度の扱いではまあこれでいいやと言う感じ。「NetFront」はとりあえずデフォルトのブラウザなので使用中。特段不満もない。
- マルチメディア系
- 音楽用の「Music Player」と動画用の「Movie Player」が入っているが、いずれも未使用。音楽に関してはある程度キチンとすわれるところではiBookが、歩きながらではRioSU30があるため、あまり使う局面がない。もっとも今後英語の勉強としてディクテーションを行おうって時にはりなざうが便利かもと思っており、そういう際には使うことになるかもしれない。動画に関しては計画も可能性もなし。ただ、サンプルの動画(店頭でアクオスのデモなんかに使っていた動画と同じものか)を見てみると、映像が思ったより奇麗で滑らかに動いているので感動。さすが液晶のシャープ。
- Office系
- スプレッドシートの「HancomSheet」とワープロの「HancomWord」、プレゼンテーション用の「プレゼンテーション」が添付。「プレゼンテーション」はpptが使えるわけではなく、母艦のWin機から「ザウルスショット」でとってきて編集するとかの使用法。当然私には使い物にならない。「HancomSheet」について、少なくとも当面使いたいケースとしては、Jornadaで使用していたPocketExcelのデータの閲覧と活用になる。しかし、PXLのファイルはそのままではHancomSheetで読み込めなかった。残念。一度どこかでxlsにしておく必要があるか。「HancomWord」については未使用。というかあまり使用する機会はないかも。
- その他
- 「イメージノート」はデフォルトの画像ビューワ。メモリカードの中の画像データをうっかりクリックするとこれが起動する。個人的には中身確認とかに使うことが多いので、デフォルトが全画面表示の方が良いように思うんだが、まずは等倍で開くので、画像の右上部分が拡大表示されちゃった変な画像として出ちゃうことが多い。「電子辞書」は、「Zten」+「英辞郎」を使っているので使用していない。「ブンコビューア」はXMDF形式の電子本を読むためのビューア。縦長スタイルにして、横についているジョグボタンを使って読むとかなりいい感じ。内心ちょっと魅力に思っているものの一つであったりする。あとは「ボイスレコーダ」は未使用。「電卓」はこれも電子手帳の基本だが、個人的にはあると便利なこともある程度でさほど積極的に欲しいと言うものでもない。電卓は専用のものが一番ボタンとか押しやすくて楽だ。まあ指数は欲しいこともないわけじゃないので、その程度の使い勝手のいい電卓ソフトもあるとうれしいが。あとは「世界時計」と「時計」というところ
■ 2003/09/18 (木)
[Comp]Linux Zaurus SL-C760使いこなしへの道:第五回操作感編
というわけでここ4回にわたり、周辺環境およびソフトウエアのセットアップと、ソフトウエア面での第一印象について語ってきた。それらの作業の中で本体をいろいろと操作してきて、そろそろ操作の習熟度が第一のプラトーに達する辺りであろうと思われるので、ここらでハードウエア面での印象について記しておく。
1. ディスプレイ
まずは出力に関わるマンマシンインターフェースの中心をしめるディスプレイについてであるが、これについてはさすがに「液晶のシャープ」である。とにかくきれいで、細かい字もとても読み取りやすい。明るいところではさすがに最大輝度でも見づらいが、Jornada710の頃と比べれば見える(さすがにバッテリ駆動時のデフォルトのままだとちょっと明るい程度のところでも暗すぎて画面が見えないが)。
2. キーボード
さて、入力に関わるマンマシンインターフェースの中心であり、りなざう最大の特徴の一つであるキーボードについてである。そもそも思い起こせば、Palmは参照には非常に優れていたが、ペン入力と言うことで入力に難があり、JornadaはLibrettoで小型キーボードになれた私にはほぼブラインドタッチが可能なキーボードを持っていることにより入力に優れていたが、サイズ的に時と場を問わない参照というには少々難があった。C760はサイズ的にはPalmとほぼ同じで携行には難がない。問題は入力の方なのである。
まずは総合的な感想としては、これまでiBookで付けていた日誌や日記などの書き物をほぼりなざうに移してこの数日(から一週間程度)入力を続けてきた現時点においては、メモツールとしては優秀な感じだが、フルキーボードのマシンがそうであるような思考のツールって程ではないかもしれないなあ、というところ。webのファイルももってきたが、リナザウ上での作業はしんどそう。少なくとも今は。
構造としてのキーボードの使用感だが、キータッチはペコペコ音がして、静かな深夜などには少々気になるのと、長期耐久性があるのか不安な所を除けば、打っていて時に楽しいと思える程度には快適である。ただ、通常これまで使ってきたキーボードは右側に記号のキーがあった。言い換えれば、アルファベットを使用する時にはキーボード全体の2/3程度までしか使用していない。この感覚が思ったよりも身に染み付いているらしい。KやLといった、右端の方のキーを使おうとする時、つい心持ち左を押してしまうのだ。結果、「かば」は「じゃば」となり、「ls」は「ks」となってしまうのであった。
あと、同じキーを続けて押すのがまだ苦手。コンソール使用時に上のディレクトリに移動しようとして果たせなかったことが何度もあるような感じである(^^)。この辺りは慣れかもしれないし、またKeyHelperのお勧めのキー設定なんかにキーリピートの変更といった項目があったりするから、その辺りをいじくれば改善されることもあるのかもしれない。
でもまあ使い始めからこの程度の文章がそう大きなストレスなく書ければ良しとすべきかな。Palmではついに「文章」を書くには至らなかったものなあ。ちなみに評価についてはほぼすべて親指打に関してである。会議中にToDoや予定についてメモを取る時に、時についこれまでの機種の様に机上においたまま操作しようとする時があったが、非常にやりにくかった。りなざうは基本的に親指マシンだと感じた次第である。
■ 2003/09/19 (金)
[Comp]Mac:miをちょっと使いこなしはじめる
最近Mac上でのエディタとしてはmiを愛用している。HTMLのタグに従って自動的に色を分けてくれたり(Jornada上のWZにも似たような機能はあったが)、よく覚えていなかったり(^^;長々と入れるのが面倒なタグを打つ時に便利なツールがあったりする。またawkなどで遊ぶときにもCモードで使うとCの予約語を色分けしてくれたりインデントがしやすかったり括弧の対応が楽だったりなど、まさに「かゆいところに手が届く」という感じで、とっても便利なのである。と、いろいろ使ってきておきながら、メニューバー上の「ジャンプ」の項目の意味がずっと分からずにいたのだった。
今回なるべくタグを正しく書く方向にといろいろとHTMLファイルの書き方を変更しているうちに、miのジャンプというメニューの意味を初めて(^^;知った。そもそも私は見出しタグについて、これまではタグの中身を独立した行に書き、タグだけの行ではさむという書き方をしていた。今回の修正の中で、まとめて一行に書くように変更すると、見出し行が緑に色分けされるではないか。これは見やすくなったと思っていたら、さらにこれまで空だった「ジャンプ」メニューにその見出し行の中身が入っている。すなわち、HTMLモードでは見出しタグ(一行で指定したもの)の行を自動的に登録してくれて、それを使ってタグジャンプができるのだ。さらには今現在カーソル位置のある項目が何であるかが、下の欄外に表示されているのであった。
これを活用しない手はないと、この「日々」の見出しをなるべく<Hn>タグを使用する仕様に変更した。おかげで「ジャンプ」メニューから見出しを辿って編集項目を選べるようになり、ますますマック上での更新が便利で楽しくなってきた。この分ではりなざう上でする気が起きるのはネタメモまでと、若干の訂正程度かなあ(^^;。
楽しくなったところでさらにタグの整理を行うことにする。一日の括りに<P>タグを使用することで<P>を入れ子にしてしまっていた(減点ポイント!)ので、それを解消し、一日の括りを<DIV>タグで囲むことにする。また、同時に括りごとにスタイルシートを設定した。見た目も改善(当社比)した上に、採点サイトの得点でもマイナス(^^;だったのが90点台に。満足である。
またさらにいろいろとモード設定の中身を調べるうちに、miにおけるジャンプの仕組みが分かってきた。そうなると毎日の日誌/日記へも応用したくなり、日記用に日付けのフォーマットをタグジャンプのキーワードに設定してみた。自分で設定をいじると、日記のシステム設計という感じになって、非常に面白くなってきた。ただ私は日誌を、年単位程度の大きなくくりを1ファイルにしておくことで、検索の時に便が良いようにしていた。しかしこれでは検索のときは便利でも、このタグジャンプメニューに関して言えば、最大300以上のタグがずらずらたてに並ぶことになってしまい、決して使い勝手がよくもなくなってしまう。階層化が可能になっていればこのままでもいいのだけどねえ。ファイルを分けて、検索のときにマルチファイルの仕組みを何か考えるか、それともこのままの運用でなにか別の工夫をするか。悩みどころだが、楽しい悩みではある。
■ 2003/09/20 (土)
[Comp]Libretto:リブでもLinuxをやってみる Knoppix編
14日の最後にちょこっと書いていたように、ここ数日Librettoの再活用熱が高まり、LibrettoのLinux化についていろいろと調べていた。今日になってふと気付く。何かLinuxが必要な理由があるわけでもなし、ファイル交換にしても他の手法がなんとかなりそうな状況で特段ファイルサーバを必要としてもいないし、別に何もそこまでやらなくても…。というわけで今日は新宿にお出かけをすることにした。
…気が付いてみたら本屋でLinux入門のムック本「Linux magazine for beginners 2003」を買っていた(^^;。これは2枚のCD-ROM付き。一枚はCD-ROMから起動する=インストール不要というKnoppixというものの3.2日本語版。もう一枚はVine Linux 2.6 ftp版であった。
ちなみになぜLinuxをLibrettoに入れようと言うだけでこれだけ調べたりためらったりする必要があるのか。それは、Librettoが小型ノートパソコン故にいろいろと特殊な状況にあるからなのであった。具体的には、FDDやCDドライブがPCMCIA接続というところにある。純正のFDDやCDドライブを使えば当然そこからの起動は可能である。しかしインストーラが立ち上がって以降はドライブが認識されず、そこでインストールがとまってしまうと言うのだ。
とはいえウェブの情報については、LibrettoSS1000は古いマシンでありHDDも2Gと小さいためにあまり最近の報告はない。一方で最近のインストーラはその辺りのノートパソコンの事情も結構分かっているようなことも耳にした。そこで、まずはLibrettoの環境に手を加える必要のないKnoppixから試してみることにした。
まずはLibrettoに純正互換のCD-ROMドライブを挿す。「C」を押しながらCD-ROMから起動。Knoppixのインストーラ画面が立ち上がった。まずは起動オプション無しで試すが、立ち上がらず。よく聞く話の通り、CD-ROMドライブを探しにいったところで止まってしまう。ここまでは一応織込み済みの話である。さて、webで調べたところでは、Knoppix日本語版ではLibrettoで
boot:dynabook
とやれば起動できるようなことがかかれていた。試してみるが、「そのような名前のものは登録されていない」といった趣旨ののメッセージが出て駄目。雑誌に収録されているのは3.2の日本語版と書かれているので出来そうなものなのになあ。
改めてwebで調べていると、http://unit.aist.go.jp/it/knoppix/hardware/index.htmlの動作実績リストの中で、Dynabookについて
boot:dynabook
あるいは
boot:knoppix ide2=0x1a0
でうまくいったとの記述があった。早速後者を試してみると、確かにCD-ROMを認識するところまではうまくいった。しかし、
Accessing KNOPPIX CDROM at /dev/scd0...
Total memory found: 94560 kB
Creating /ramdisk (dynamic size=72368k) on /dev/shm...Done.
Creating directoties and symlinks on ramdisk...Done.
Starting init process.
INIT: version 2.78-knoppix booting
Processor 0 is Mobile Pentium MMX 166MHz
APM Bios found, power management function enabked.
と、ここまでで止まってしまう。
boot:knoppix 2 ide2=0x1a0
と、テキストモードで立ち上げを指定しても変わるものでもなし。同サイトのやはりスペックの低いマシンについての報告で、起動に5分くらいかかるという話もあり、万一この止まって見える状態がそうか?などと思い放置しても変化は見られない(それはそうだろうなあ(^^;)。ここでふと思い付いて、
boot:knoppix ide2=0x1a0 nopcmcia
と、入れてみたら、今度はさらに先まで進んだ!!「pcmciaを探すのをやめるよ」、というようなことを言ってから続きがはじまるので、どうやらそういうことだったらしい。
進んだは良いのだが、メモリが足りないからスワップを作れと言われてしまう。作らないとKDEは立ち上がらないとか。最低の60Mを作る(操作を間違えて最低レベルで止めてしまったのだが(^^;)。さらに立ち上げは続き、Xの起動開始後、画面が出てからかなりしばらく待って、ようやく「XXを初期化中」という画面が出初め、さらにしばらく待ってKDEのデスクトップとなった。ついにKnoppixがたちあがったのだった!
しかし感動はそこまで。古いCPUに少ないメモリという制約も効いてか、何かというとCDを読みに行ってカリカリ音がなったままで止まったままになっちゃうし、おそらくスワップも激しいのだろう。まあ使いものにはならん。分かっていたこととは言えここまでとは!というところか。
■ 2003/09/21 (日)
[Comp]Libretto:リブでもLinuxをやってみる Vine Linux編その1−Let's try!
KnoppixでLibrettoのCD-ROMから一応起動できたことに気を良くして、勢いでVineのCDでも立ち上げて見る。が、CDからインストーラ自体は立ち上がるが、これはインストール時にPCMCIAのCDドライブは想定していないみたいだ。インストール元の選択で、CD-ROMからインストールするのかHDDからインストールするのかと聞いてきて、CD-ROMからのインストールを選択すると、ドライバのフロッピを入れろといってくる。当然そこでストップ。
そこで引き返せば良いものを、今日はなんだか少々切れちゃっていたようだ。どうせしばらく使っていなかったLibrettoであるから、HDDが飛んでいたとでも思おう、などと妙な言い訳を心に言い聞かせ、LibrettoのHDDの初期化を行ってしまったのだった!!Librettoをそこそこの期間利用していたが、実に初体験である(^^;。
リカバリCDをCD-ROMドライブに入れ、Cを押しながら起動。HDDが全部消えちゃうけどいいか?と聞いてくるのに震える手でyesを選択。後は出荷状態に戻るのをひたすら待つ。再起動後、ユーザー名やOEMのWindows95のIDを入力。久々に初期画面を拝見した。
復元後、CD-ROMを挿すと、ドライバがないといわれる。再起動時に指示どおりにCDドライブ抜かなかったら、CDドライブの認識がおかしくなった?と思い、念のため再度復元操作を繰り返す(^^;。結果は同じ。「C」起動で自動で認識してくれるドライブなのにドライバが必要だったようだ。そういえばそんな記憶がかすかにある。ドライバのフロッピーを探すが見つからない(^^;。ここは一発ネットからダウンロード。7200経由でFDに落としておく。無駄な手間かけまくり(^^;
プレインストールの不要なソフトウエア類を削除しまくり、空いたスペースにVine Linux 2.6のCDの中身をコピー。さらにでWindowsの「アクセサリ」→「システムツール」中の「デフラグ」でHDDの最適化を行う。その状態でCDから起動。インストール元に「ハードドライブ」を指定した。…が、「CDイメージがない」と怒られる。ちょっと待てその『イメージ』ってのは何だよ?CDロムをコピーするのじゃいけないのか。
ここはネットでCDイメージをとってくることにしよう。せっかくVine 2.6の起動CDディスクはあるのだからと、VineのサイトをMacから調べる。ftp版のミラーサイトにasahi-netが入っていたので試してみることにしよう。
ここで問題が。初期化したLibrettoからはIE3をアンインストールしてしまっていたのだった。とりあえずDOSのftpが使えないかと試してみる。connectまでは行くのだが、何か操作をしようとするとasahi-netのメッセージが流れてそこでキー入力が効かなくなる。数度試みてあきらめ。ブラウザ経由なら行くだろうかと思いデスクトップを眺めていると、「IE4のインストーラ」なるものがある。これを起動するとIE4のインストールが始まった(^^;。こーゆーのがまだ残っているところを見るとまだまだHDDシェイプアップの余地あるね。インストール完了後に改めてasahi-netを訪れ、2.6のi386のディスクイメージをダウンロード。600M超。おそらく24時間ほどかかる計算になる(^^;。途中で途切れませんように。時刻は早朝5時。月曜の朝には無事終わっていることであろう。さて寝るか(^^;。
[Movie]DVD鑑賞
○「クイーン・オブ・バンパイア」(QUEEN of the DAMNED):原題、直接バンパイアといっているわけではないのね。それとも英語の響きでは「呪われた者たち」≒「バンパイア」なんだろか
○「12人の優しい日本人」
21日付の記録の作製は24日2時。Linuxのインストールに難航しつつも眠くて続けられないので寝ようとするその前に更新。なので超手抜き(^^;。状況の詳細についてはまた23日付の記録などで。といいながら自らの閲覧の便のため、ついつい目次を作成してしまう。シンプルにしようといっていたのにまた複雑化することしちゃったよー。しかも眠いのにー(^^;。
■ 2003/09/22 (月)
[Comp]Libretto:リブでもLinuxをやってみる Vine Linux編その2−暗中模索
さて、無事ディスクイメージのダウンロードは完了したようだ。次はパーティションの確保。現在Librettoは2.1Gを1パーティションとしているから、Linux用に領域を確保せねばならない。ということで、CDからFIPSをHDDにコピーしておいて、DOSを立ち上げる。FIPSを試みるが、46Mほどしか確保できない。そりゃそうだとデフラグをかける。それでもプロパティで確認できるほどの領域が確保できない。
いろいろな待ち時間にウェブで関連情報を検索していた中で、Install LinuxというページにLibrettoへLinuxを入れる際に参考になりそうなことがかかれていた。
- ※消すことのできるものとして、
C:/windows/options/cabs/
のファイル群があること
- (これを消すとドライバのインストールの際面倒なので消す前に必要なドライバをインストールしておくこと)
- ※デフラグをかけた後でもあまり領域が確保できないときはread onlyやhiddenの属性のものについてこれらの属性を消してやる必要があること
- (DOS上で
dir /s /a:r
やdir /s /a:h
で検索ができる。Windows上で属性変更可能。DOS上で簡単にやるにはどうするんだっけ?)
さて、cabsを消してしまう前に必要なことは、と考えてみると、せっかくダウンロードした600MBを越えるファイルを、バックアップもとらずにこの先の作業をするってのもおバカな話だ。その手段を考えてみると、
- ネットワーク経由で他のマシンに
- 外付メディア
くらいしか思い付かない。いずれにせよ何らかのインストールが必要だ。ネットワーク経由だと、そのマシンにサーバ機能を立ち上げたりなどいろいろ面倒だから、できれば外付のメディアが良い。が、リブにつながる書き込み可能な外部記憶装置といえばFDDしか買っていないなあ、と頭を悩ませているうちに、MicroDriveはどうだ?と思い付いた。幸い空きは十分にある。ということでリブにMicroDriveのドライバをインストールし、VineのCDイメージをバックアップ。その後でCabsを含め、消せそうなものはとことん消す(^^;。さらにread onlyやhiddenの属性を外しまくる。かすかな昔の記憶から、io.sysとmsdos.sysはなんとなく恐いからそのまま(^^;。
また、Libretters netによると、LibrettoのSS/M3以降はハイバネーション領域をパーティションで確保する必要はなく、ファイルであるだけなのだとか。ということでHDDの末尾の変なパーティションは消してしまうことにし、さらにハイバネーションファイルも消去して空きスペースの確保にまわした。かくして約1.2Gほどの空きスペースを確保した。
あらためてfips。しかし確保できたのは750MBだけ。まだ何か引っ掛かっているのかなあ?でもとりあえずは先に進みたい。Xを入れなければ大丈夫だろうと根拠なく判断し、先に進んでみることにした。
ここまではまだそれでも適当に記録を取りながら作業を進めていったのだが、この後はいけない。とにかく自分でも何をやっているのかはっきりとは分からず闇雲に、インストーラ上の選択を迫られている部分にチェックを入れたり外したりしているだけ(^^;。かろうじて自分で判断が付いているのは、HDDの末尾に内蔵メモリとほぼ同程度のswap領域を切り、それとDOS領域の間を全てext2にしてLinuxの領域としたことくらいか(^^;。その上でVineをCDから起動し、インストーラの選択肢を変えつつ何度もインストール。とにかくXウインドウシステムを含めてある程度最低限のものをインストールするには1.4Gとか必要なのに650Mしかない状況だから削りまくるしかないが、何をどう削れば良いのやら。しかしその度にインストーラが途中で止まっちゃったり、行くは行ったけどLILOの途中LIで止まっちゃったり、Linuxが立ち上がりはしたけどpcmciaがどういう状況なのかまるきり分からなかったり。とりあえず内蔵HDDについてはmount -t msdos /dev/hda1 /mnt
(mntの中身が使えない状況で不要なのでとりあえずmntに貼っちゃっただけ。間違っているのは一応分かってるつもり)したら見ることが出来たんだけど。
といったことを、月曜の夜にはじめ、火曜日(秋分の日)にかけてやっていたわけだ(昼間は外にもお出かけしていたから、何もこんなことばかり延々とやっていたわけではないが)。もう少し状況が理解できるようになってから改めてまとめ直すことにします。今日のところはとりあえずここまで。
■ 2003/09/24 (水)
[Comp]Libretto:リブでもLinuxをやってみる Vine Linux編その3−Retry!
前回までのところでとりあえずCUIのLinuxは立ち上がりはした。実際あとはPCMCIAを使えるようにしたり、ネットワークにつながるようにしたり、という方向への遊び方もあるわけだが、正直インストールのところでの混乱のため、現状何がどうなっているのかさっぱり分からず、もう一つすっきりしない。ここはもうちょっとLinux領域を広くして、もう少しゆとりをもったインストールを試みてある程度把握したところで改めて削っていった方が良いんではないだろうか。
ということで、改めてWindowsの初期化CDを引っ張りだして、Windows95の再インストール。想定していた作業は、これで改めて2.1GのまっさらなHDDに戻した上で、改めていろいろ削っていこうと思っていたのだが…CD起動の再インストールではHDDを丸ごとフォーマットしているわけじゃないんだ。ということは1stパーティションを極端に削っていたらにっちもさっちもいかなくなっていたってこと?(^^;。幸い現状は1.2Gほどのパーティションに753Mを入れるだけなのでなんとかなった。ここにまずはCD-ROMドライブ、マイクロドライブのドライバーをインストール。Vine 2.6のCDからFIPSをHDDに移す。
さて、まずはHDDの中身がぐちゃぐちゃにならないうちにパーティションのサイズを変更しておこう。今回はハイバネのファイルはなるべく消さずにやってみたい。そうするとWinをかなり削ってもシェイプアップ後にVineのCDイメージを入れることを考えると、900M程度が限界か。そのようにFIPSでパーティションを削る。その上で、CDイメージが収まるまで、とにかく思い切り消しまくる。IMEの辞書類やCabsといったものもとにかく削る。スクリーンセーバーや壁紙なんかもコマゴマ削り、ようやくマイクロドライブからVine 2.6のCDイメージを戻すことが出来た。901Mのうち10Mほどが空領域。なかなかギリギリのところであった。
さて、改めてVineのCDを接続し、インストールを行ってみる。今度はGUI系の姿を拝んでみることを目的にパッケージを選択。デベロッパー系Publisher系はとりあえず全て削り、Documentも説明を見てどーしても入れておいた方がよさそうなもの以外は削る。今回はX系はそのまま。ついでにAmusement系もなるべく残す。削ったものが依存関係の為に復活してくるのを何度か行き来してHDDにおさまる範囲に押さえ込みながらインストール。今回もなぜか途中で止まっちゃったりして何度かリトライするも、結局インストール後の起動の時、LIで止まっちゃう。
くさりつつも、インストールの待ち時間に改めてwebで情報を集めていると、LibrettoでもCDロムからインストールする方法がありそうな情報に辿り着きはじめた。初めにそれを知ったのは「いっけんや」*1。ただ、そこに記述のあった
boot: linux ide2=0x1a0,0x3a0
でも、「Vine 2.1の場合」という
boot: linux ide2=0x1a0,0x3a6
でもいつもと違う部分のようではあるが、それでも途中で止まってしまう。なにか設定をいじればどうにかなるのかと思い、ide2=の部分の意味を知ろうとさらに検索を行っていくなかで、Linux on Dynabook SS 3480というページを見つけた。そこの記述を見ると、
- BIOS起動(Esc押しながら電源on→F1)でPC CARDのController ModeをPCIC Compatibleに設定。
- CD起動後、
boot: linux ide2=0x1a0,0x3a6
とある。この通りやると、これまで止まっていた部分を通り過ぎて、しっかりCDを認識したままインストーラが立ち上がった!しかもグラフィカルである(^^)。HDDからのインストールはテキストモードオンリーなので、今回初めてグラフィカルインターフェースのインストーラを拝むことができたのだった。これでようやくすべてCDからインストール作業が可能になった。
さて、「ラップトップ」でインストールをはじめ、「GNOME」と「NOTE」にチェックを入れて、さらに個々のパッケージを選択する。グラフィカルインターフェースのおかげでパッケージの説明のためにいちいちウィンドウを開く必要もなく、作業効率がアップ。基本的に先ほど同様開発系とPublisher系余計な?ドキュメントなどを削り、試行錯誤の後(依存関係確認後で)419 package, 1006Mを指定。今回は、とにかくXウインドウの雰囲気を拝むために、本来の目的と掲げていたsambaのサーバ機能も外した。CDからインストール可能になったことが分かった以上、改めてホントにサーバにする気になったらまたインストールをすれば良いとの判断である。ついでにWinのパーティションについてもVineのCDイメージを入れておく必要もなくなったのだから、基本的に使える機能を搭載した上で、さらにパーティションを削れる可能性もあるな(オフィス系を入れなければ、だろうが)。
CDからのインストールということで、HDDからよりも時間はかかったが、40分程度のインストール完了。モニタなどの設定に入る。モニタについては検出したというTOS5080が、「TOS」から始まってもっともらしいのでそれを選択。X設定のカスタマイズのところで、色深度16bit、解像度に800×600の選択があったので、これにしてみる。(失敗だったかも)。そして再起動。LILOの画面がパッと出た!!。なぜかLILOにこれまでは「Linux」と「Win」しか選択肢がなかったのに今回は「Linux up」とか「Linux 2 up」とかいう選択肢もある。とりあえずは素の「Linux」を選択。その後も順調に起動は続き、時間はかかるが、なんらトラブルもなくlogin画面に至った。
初めはデフォルトのGnomeを試みる。Knoppixに比べれば(^^;使える範囲とは言え、非常にとろくてGUIではやってらんない感じ。ちょっと何かを呼び出そうとすると、かなり待たされる。コンソールを開くと快適なのだが…。やはりLibrettoでXは重すぎるのかと思い、寝る前にふともう一個のWindowMakerを試す。見た目に少々個性が強く、初めは何をしたらどうなるのか良く分からなかったが、こっちはけっこう軽くて快適である。これならGUIのらくちんさとCUIの小回を同時に味わえそうだ。そう、Gnomeをいじっている間はいっそCUIにしてX系をごっそり削ったところに開発系でも入れようかと思っていたのだが、ちょっと軽く操作できると分かったとたん、GUIを失うのが惜しくなってしまったのだった(^^;。軟弱になったもんだねー。
*1ちなみに「いっけんや」さんにはPCMCIAの設定の話などもありいりいろと参考になる。
[Comp]Linux Zaurus SL-C760使いこなしへの道:番外編:ブンコビューア
ふと思い付いてブンコビューアで手持ちのテキストファイルを読んでみた。思ったより使えることが判明。先日来不満をもらしていた改行コードの問題がないことが分かったのだ。改行コードによらずちゃんと読むことができる。しかも、ブンコビューアの操作性は悪くなく、特にビュースタイルにして読んでいるとなかなか気持が良い。ただし実際に快適に読むことができるのは日本語のみ。基本的に縦書き表示してくれるので、逆にアルファベットだけのものを読む時は90度横になってしまっていて操作しづらいのだった。ただ、ブンコビューアでテキストを読むときはデフォルトのフォントは少々読みづらい。ぱうフォントでも入れるとさらに快適になるかもしれない。
これで過去にダウンロードしたテキストの小説類なども気軽に閲覧可能となった。ただこれらは結構読んじゃっているから、新作も補充したいところだが。かくして新しい小物を買う度に無用な出費がかさむのであった(^^;
■ 2003/09/25 (木)
[Web]デザイン変更
19日に書いたように、この「日々」のページについては極力正しいHTMLにしていくべく、デザインを変更した。が、日常的に見るページとしては他に「トップページ」と「日々のメニュー」のページがある。古いところは自分の未熟の記録として残しておくにしても(面倒だからという理由が最大のものだが(^^;)、この2ページは改正しておかねば意味がない。とはいえ、ただ単に同じ見た目を保つように引き写すだけではつまらないので、この際内容の見直しも行うことにした。
今回の最大のポイントは、「日々」最新号をトップに置いたこと。自分でもいろいろなサイトを巡回していて、いちいち穴を掘っていかねばならないところよりも、ダイレクトに読みたいものが読めるこの手のデザインの方が見やすくて好きだったのだが、更新が面倒そうで(^^;避けていたのだった。今回知ったmiのタグジャンプで、項目のピックアップが少々楽になったため、試みることにした。
またこれにより、トップページから直接、月毎にまとめているページの最新号当該日にジャンプできるようになった。そうなると、せっかく各月のページの冒頭に付けた目次を目にしてもらう機会が減り、置いた甲斐がなくなってしまうように思えた。このままでは悔しいので、各日付けの右側にページの先頭に飛ぶためのリンクをつけることとした。
ついでに、Jornadaの比重が激減したことから、本当はWinCE WebRingも外そうかと思ったのだが、一応登録を解除するまでは残しておくことにした。
このような見えるところ以外でも、極力「正しい」HTMLを目指して、自分でおかしいと思ったタグは修正しまくったのはいうまでもない。トップのロゴなんか変なタグがいっぱいだったので結構苦労したのだった(^^)。だいたい前と近いデザインのまま変更できたと思っているのだが。なにか御覧になっている環境で、おかしいなと思うことなどありましたら、お知らせいただければ幸いでございます。
■ 2003/09/30 (火)
[Comp]怒濤の更新早くも停止!?
先週までは毎日の様に更新を行っていたのに、前回の更新から1週間近く間が空きつつある。これは早くもりなざうに飽きたとかそういうことではない。逆に、思ったよりも早く自分の道具になってしまったということなのだ。もともと近年の私は道具いじりよりは、早々に使用形態を定めて使うというタイプになっている。今回は、
- 日記のための「ZEditor」
- 単語登録用の「ユーザー辞書」
- 英辞郎のための「Zten」
- 予定表のための「カレンダー」
- 読書用の「ブンコビューア」
といった辺りが常時起動しているもの。
- 予定表の一部としての「ToDo」
- ファイル操作用のコンソール
- お仕事の計算や作表のための「HancomSheet」
- テキストファイルの一時閲覧と雑記メモ用の「メモ帳」
- 同時に二つのテキストファイルを扱いたいとき用の「yEdit」
といった辺りが比較的使用頻度のあるものといった具合に、ほぼ固定して使用している。それ以外にブラウザとして「NetFront」も使用しているが、職場では常時いる部屋には電波が届いていないから無線LANの使用は意味ないし、また家庭でも普通にiBookを持ち歩いて使える以上あまりりなざうでweb接続していなかったりする。「メール」はさらに問題外。
かくしてテキストメインの閲覧・入力マシンとして、ほぼ単機能に限定した状態で見事に地位を確立してしまった以上、ことさらにいじる必要性を失ってしまったのであった。そういったなかで、唯一現在導入を考えているのは、PDFのビューア。当初はこのサイズのディスプレイでPDFでもあるまいと思っていたのだが、「見づらい」と「見ることができない」というのは、「マライア・キャリー」と「マラリア・キャリア」くらい違うことに気付き、試みてみようと思った次第。これについては追って報告する機会もあろう。ちなみに24日に検討を考えていたぱうフォントについては、基本的にあまり小さなフォントを使用しない状態に使用形態が落ち着いてしまったことから、急いで試す必要性を感じなくなってしまったのであった。デフォルトのフォントはもともと、ある程度サイズが大きければ非常に読みやすいのだ。
ブンコビューア追記
今回の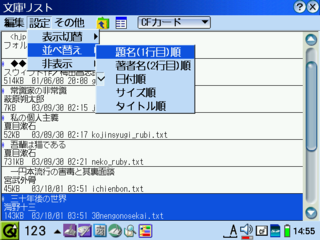 りなざうに転向したことにおける収穫は24日にも触れたことであるが、意外にも「ブンコビューア」だった。
りなざうに転向したことにおける収穫は24日にも触れたことであるが、意外にも「ブンコビューア」だった。
過去の(携帯)端末上でも小説類を読んでいなかったわけではないが、基本的にエディタを使用して読んでいたためもあり、書名とファイル名の不一致などから文書管理がやりにくかったり、平行して何冊かを読んでいると、どこまで読み進んでいたかの管理がやりにくかったり、読み進める時の操作性が悪かったりといったことから、精々で一度起動して読みきれる程度の掌編小説が中心であった。そのような文書となると、ちゃんとした小説よりは、ウェブ上のいわば素人の小説やエッセイ類といったテキストの方が、適当に短い単位で管理されていて案外便利なため、そればかりを読む傾向にあった。それに対してりなざう上における「ブンコビューア」では、
- 文書を正式なタイトル(1行目)と著者名(2行目)で管理/選択することができる(上図)
- 読み終えてor読み進めているものに*印が付いている
- 文書ごとに現在読んでいる位置を記憶していてくれる
- 全画面表示による読みやすさ(下図)
- ビュースタイル+ジョグレバーの読み進めやすさ
- 掌にすっぽりおさまる読みやすさ(主にビュースタイル)
といった特徴により、長文を平行していくつか読んでいても苦にならないし、またいつでもどこでも食事中などにも(お行儀が悪い(^^;)まさに文庫本代わりに読むことができる。
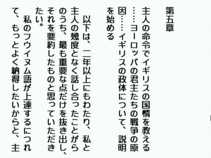 それにより青空文庫に再度目が向きつつある。実際に最近は、ずっと昔Libretto時代にダウンロードしたもののほとんど読み進めていなかった「ガリバー旅行記」を読んでいる。初めは文庫本の携帯を忘れた時に、やむなく読みはじめたものであったが、これが思った以上に快適だったのだ。かくして改めて青空文庫からいろいろとダウンロードしてみているのであった。
それにより青空文庫に再度目が向きつつある。実際に最近は、ずっと昔Libretto時代にダウンロードしたもののほとんど読み進めていなかった「ガリバー旅行記」を読んでいる。初めは文庫本の携帯を忘れた時に、やむなく読みはじめたものであったが、これが思った以上に快適だったのだ。かくして改めて青空文庫からいろいろとダウンロードしてみているのであった。
それにともなって、改めてパピレスにも足を運んでみたのだが、こちらはなんだか酷いことになっている。ほぼWindows環境しか想定していないようなダウンロード(詳細は不明。分かっているのはIE/MacOS X 10.1.5からはダウンロードできず、なんとかDLLといったものをやたらよびだそうとしていた)だったり、いろいろな端末で利用しやすいテキストではなくPDFですらないeBookとかいう形式のファイルがやたら増殖していたり(正直言ってあまり突っ込んで調べていないから不適当な批判もあるだろうが、ここは個々の技術的なことを云々したいのではなく、それをもたらした思想的な部分に不満があるのであしからず)。で、あきらめてザウルスの専門店から探そうとすると、一気に対応する書籍が減る。いろいろ制限をかけようとするのは最近の風潮で理解できぬ部分もないではないが、まだろくな普及段階でもない現状で制限することばかり考えていてどうするよ。かくして結局青空文庫しか選択肢がなくなったりしちゃったのであった(^^;。
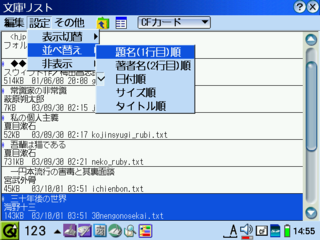 りなざうに転向したことにおける収穫は24日にも触れたことであるが、意外にも「ブンコビューア」だった。
りなざうに転向したことにおける収穫は24日にも触れたことであるが、意外にも「ブンコビューア」だった。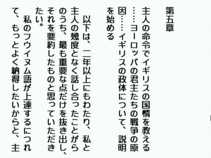 それにより青空文庫に再度目が向きつつある。実際に最近は、ずっと昔Libretto時代にダウンロードしたもののほとんど読み進めていなかった「ガリバー旅行記」を読んでいる。初めは文庫本の携帯を忘れた時に、やむなく読みはじめたものであったが、これが思った以上に快適だったのだ。かくして改めて青空文庫からいろいろとダウンロードしてみているのであった。
それにより青空文庫に再度目が向きつつある。実際に最近は、ずっと昔Libretto時代にダウンロードしたもののほとんど読み進めていなかった「ガリバー旅行記」を読んでいる。初めは文庫本の携帯を忘れた時に、やむなく読みはじめたものであったが、これが思った以上に快適だったのだ。かくして改めて青空文庫からいろいろとダウンロードしてみているのであった。