|
一筋の道
武蔵野って、さまざまに変化してきたようです。 ここに紹介したいのは、7世紀の頃の武蔵野の姿です。
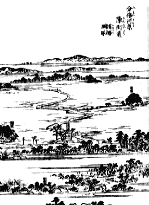 |
行く末は空も一つの武蔵野に
草の原より出づる月かげ
(摂政太政大臣 新古今)
13世紀、武蔵野はこう詠まれました。京の都に住む人の印象です。空と野が一緒になってしまうような、ものさびれた茫漠とした広野に、細い道が一筋、消えるように続く風景を想像します。
事実、江戸時代でも、図のように細い道が蛇行して原をたどる姿を描いています。(江戸名所図会 分倍河原 陣街道)
(江戸名所図会・陣街道)
それよりも、さらに600年程前のことです。野の中を走る「一筋の道」がありました。 |
自然条件からあまり人が住めなかったであろう
7世紀のことです。
なんと、幅12メートル、両側に側溝のような溝が付いた
原の中をどこまでも、一直線に延びる道路が
つくられていたことがわかってきました。
神奈川県から武蔵野の中央部を通って群馬県に達します。
ともかく、まっすぐです。
坂があろうと、窪地だろうと、多摩川も利根川も
そのまま渡ったようです。
要所、要所には、緊急連絡や公文書の伝達
役人の旅行のために
馬や宿舎が用意されたはずです。
現在の府中市にあった「武蔵国府」と畿内の中央政府とを結ぶ
れっきとした「官道」です。
「東山道 武蔵路(とうさんどう むさしみち)」と呼ばれます。
古代版ハイウエイとも言えそうです。 |
 |

1994年11月17日、衝撃的なニュースが伝えられました。
国分寺市の旧国鉄中央鉄道学園跡地で約330メートルにわたる古代の道路が発掘されたというのです。
坂上田村麻呂が蝦夷征討の時(801年)に使用されたとの伝承にもふれられました。
現地説明会が開かれて、その現場を見ることが出来ました。
写真は、そのときのものです。国分寺市から府中市の方角に向かって写しました。
白く光っているところが、当時の人が歩いた跡と言われます。
よくも再現できたものです。
ところで、この道は、何を意味するのでしょうか?
原の中を真っ直ぐに通る道・・・
12メートルの幅を必要とするほど、交通の量があったのでしょうか?
第一、そんなに人がいたのでしょうか?
役人が往来し、軍隊も通ったと考えられています。
武蔵国分寺の建設のために、屋根瓦が運ばたといわれます。
それにしても、庶民はこの道を使ったんでしょうか?
白く光った踏み跡は微妙にカーブしています。
それが、歴史を証言しているようです。
この道が終わる頃、庶民の生活の拠点に向かう踏み跡だろうと考えられています。
古代から中世への踏み出し、分かれ目のようです。
(武蔵路の変遷)
 |
これは、道路の両側に掘られていた溝です。側溝のように見えますが、ところどころ切れ目があって、全部がつながっていません。そこからいろいろ推理がされます。
何の目的で、こんな溝をつくったのでしょう?
どういう人が働いたのでしょうか?
その人はどこに、どんな住宅に住んでいたのでしょう?
道具は何で、そのときの武蔵野はただただ原っぱだったのでしょうか?
今から1200年ほど前の「武蔵野」の原風景を思うとき、後から後から疑問がつきません。
(7世紀の原風景) |
この道は、11世紀ぐらいまで使われた後、やがて土の中に埋まってしまいました。
最近になって、道路の一部が各地で発掘されて、全体の姿の想像がつくようになりました。
この道の持つ意義も少しずつ、はっきりしてきました。
全国支配のネットワーク、権力の象徴、蝦夷討伐・・・etc。
しかし、細部はまだまだ霧の中です。それが、解き明かされようとしています。 何はともあれ、喜ばしいことは
「武蔵国府」
「武蔵国分寺」
「道」
が、3点セットで、武蔵野の古代史を語る格好の素材が提供されたことです。
保存の問題
これだけの遺跡です。当然に保存すべきとの声があがり、現在運動が続けられています。保存の方法をめぐっても、知恵が持ち寄られています。しかし、この財政難です。今後とも、いろいろと難題が出てきそうです。それらについては、別にご紹介します。 |
 |
 |
東京一極集中
武蔵野は家康が入府して、江戸が「都市」となった時、大きく変わりました。人も物も情報も、ほとんどが江戸を中心に集まるようになりました。
五街道の整備が行われて、江戸を中心とする放射状の構造が主要な位置を占めました。武蔵野は全面的に模様替えです。東京一極集中の原型です。
それにしても、皮肉なものです。一極集中のおかげで、武蔵野はほとんどの地域が都市になろうとし、過密になって一極集中はソシリの元になりました。そして、その弊害の解消の一つに、新しい交通手段として、モノレールが通ります。
なんと、それは、古代の道路のルートと同じように、南北につくられています。
古代とモノレール、進む工事を毎日目にしては、『こんなに急いで、武蔵野はどこへ行くのか・・・』と古代人が皮肉を言っているように思えます。 |
ホームページへ
|