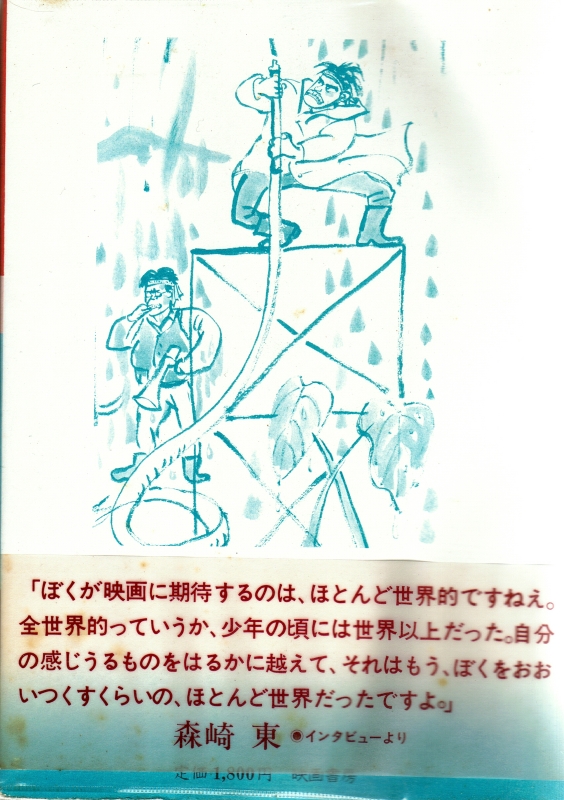
| 対談者 | ................ | 森崎 東、 山根 貞男 |
| 出典 | ................ | にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇 |
| 著者 | ................ | 野原藍 |
| 発行 | ................ | 映画書房 |
| 発行年 | ................ | 1984年10月9日 |
| ................ | ||
| 裏表紙イラスト | ................ | 森崎 東 |
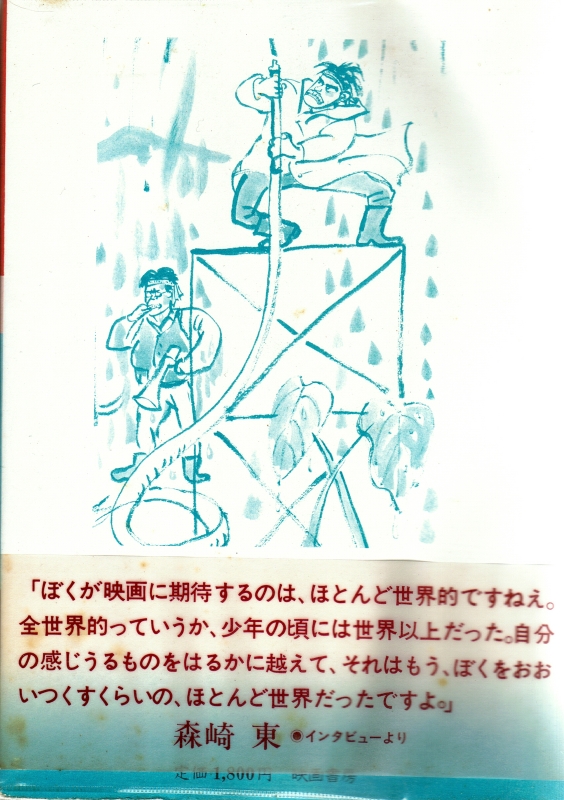
| ( その1 に戻る) I わが映画遍歴、そして家族 1981年9月19日 「リンゴー!」のファンだった。 七朗義兄さんと湊兄さん 香川京子にファン・レター ヌーベル・バーグと反合理化闘争 |
| (その2 に戻る) 脚本部から監督デビュー 家族ってのは恥ずかしい。 |
II 心の結ぼれをほどく芸能を求めて 1981年12月27日 庶民派ドラマでありたい 山根 森崎東の映画といったとき、まず思い浮かぶイメージは、庶民を描いた喜劇が多いということです。デビュー作『喜劇・女は度胸』からはじまって、ほとんどの作品が庶民喜劇ですね。むろんこれは、松竹という会社なりプロデューサーなりがそういう映画を撮らせたということがあるんでしょうが、森崎さんご自身は庶民喜劇であることをどう考えていらっしゃいましたか? 森崎 自信を持って言えることは、庶民と喜劇とに分けますと、意識的ではないにしろ庶民ドラマでありたいと強く思っていたということです。庶民でなきゃっていう感じがありましたねえ。喜劇がどうかについては、おっしゃるように、会社が第一作のときに喜劇できたということが、ひじょうに大きく作用した。第一作というのは、自分とドラマの出会いみたいな、いわば一生の最初の女みたいなとこありますからね、それの影響を受けてるってのは自分自身感じますけども、やっぱり喜劇が肌に合ってたということは、いえるんじゃないでしょうか。 山根 その庶民のドラマでありたいってのはどういう意味ですか。とにかく庶民のお客が面白がる映画というなら、森崎映画のような生活臭のあるものだけてはなく、荒唐無稽な活劇なんかもあるわけでしょう。ても、森崎さんの映画を見ていると、そういう映画は想像しにくいんずすね。 森崎 活劇だとかなんとかっていうのは、ドラマのジャンルであって、庶民かどうかってことになると、庶民活劇ってのがあるわけでしてねえ。そういう意味で庶民でありたいってことであって、活劇であってもいい。あまり撮ってませんけど、たとえば『高校さすらい派』なんてのは、喜劇というよりも活劇なんで、ああいうのを撮ってるととっても楽しいってことを自分で発見したんですけビね。 山根 だけど『高校さすらい派』の主人公などは、いわゆる庶民ってのとは違うんじゃないですか。 森崎 まあ、庶民ではないねえ。しかし、必ず出てくるでしょう、こうヌーボーとした漁師ふうの男が。 山根 ええ、弟分みたいな相棒がね。 森崎 あれがどうしたって出てくるわけですね(笑)。 そういう意味では、まったく庶民が出てこないで、というふうにはならないんですよね。いいか悪いかは別として。 山根 そうしないと自分の映画にならないと思うんですね。 森崎 そうですね。たとえば武田泰淳は大好きな作家ですけども、『貴族の階段』を映画にしたいなあとは思いませんねえ。 山根 なるほど。そこのところですね。何でしょうかねえ。 森崎 もう単純な反感だと思いますよ。権力だとか金だとか、何か文化だとかを持つてる人に対する;…。要するに、しがない九州の西の果ての商売人の息子という自己規定ってのは、ものすごくあるわけでしてね。だから映画も、たとえは病院長の娘が医学校を出たいい男の先生と結婚するとかっていう話は、ぜんぜん面白くないと思いながら見てたわけで、そういうものばっかりではないんだっていうふうな異議があったたんじゃないでしょうか。映画の観客として。 山根 そうすると、殺し屋がさっそうと暴れまわるような活劇ってのは考えられないですね。 森崎 うーん……。やっぱり片岡千恵蔵は、傘張り浪人みたいなんがいいんでね、『多羅尾伴内』に出てきてさっそうとやるのは止めてくれつて感じが正直いってありますよ、あんまり見てませんけどね。もちろんそれも庶民の楽しみのひとつではあるわけだけど、自分がつくるのは別ですからねえ。 山根 一例をあげますと、沢田幸弘監督のデビュー作『斬り込み』(一九七〇)は、組をつぶされた暴力団のチンピラたちがあがいて生きのびたあげく、大きな組織に圧殺されるというドラマなんですよね。そこには別にいわゆる生活者大衆なんかは出てこない。だけど見てて、ものすごく興奮するし、これが映画だっていうふうに思うんですねえ。たとえばそういうふうな映画は……。 森崎 正直いって大好きてすし、撮りたいですよ。撮ってませんけどね。それは、ロはばったいけれど、撮らせれば、沢田幸弘さんの次ぐらいにくっついていきますよ、ええ(笑)。 山根 森崎映画の中では『野良犬』がいちばん活劇ふうだと思うんですけど、あれにもちゃんとね、黒沢明の『野良犬』(一九四九)と違って、沖縄の少年たちが出てきて、現在的な問題とてもいえる何かが出てくるでしょう。ピストルを奪われた刑事の話を活劇として描くというだけにとどまらず、なぜ沖縄が出てくるのか(笑)。 森崎 ハッハッハ、それは、出てきてもいいではないかということと同じですよ(笑)。 山根 でも、森崎さんの場合、出てきてもいいてはないか、じゃなくて、出てこなければならない、でしょう(笑)。 森崎 そうなんですよ。うまく言えないんですけども、『野良犬』でいいますと黒沢さんの作品には映像美学の極みたいな名場面が必ずあって、しかもそれがすばらしい。ぼくも映画をやろうと思って、それにしびれた方なんですが、自分がつくるとなると、なぜか、これはひじょうにわかんなくて、それはわかんなくてもいいんじゃないかと思いますけども、名場面っていうふうな意識で、つくりたくないっていう気があるんですよねえ。 山根 ははあ、それは何ですかねえ(笑)。 森崎 何ですかねえ。 山根 そこなんですよねえ。 森崎 ですから映像美学って言われると、なんか気持ち悪いって感じが感性的にあるんですよ。俺も感性は庶民だから、庶民の中に美学ってのはまずないんだ、あったとしても冷奴の食い方はこうやって食うといいとかね(笑)、そういう種類のことであって、なんかチャラチャラしたもんにはないんだろうというふうな気持があるんじゃないですかねえ。ですから、美学だとか、名場面だとかいうと横向きたくなるし、ウェル・メイドの珠玉のような作品なんていわれると、自分の作品がじゃないですよ、なんか、いや!という気があるんですよねえ。 だから、チンピラが出てきて、ヤッサワッサ走りまわったり、落っこったり、滑ったり、女に振られたり、わめいたりってのは好きですね。それは大好き(笑)。 ただ、幸弘さんの作品がどういうのか知りませんけど、そいつらのエネルギーは必ず体制の中で圧殺されてしまうんだというふうに、そこでふと芸術的美学になってしまうというか、美学にするためにそうしてるかどうかわかりませんが、負けるものの美学だとか、滅亡するものの美学だとか、庄殺されるものの美学だとか、死に瀕する美学とか、不健康の美学とか、そういうふうなものにつながりやすいと思うんですけど、それはいやですね。いや!(笑)。ぼくはそうしない、ラストを(笑)。 山根 森崎さんは映画をつくるときに、現実というか生活の地平というか、そこを必ずつなぎとめておきたい、そこと切れたものはやりたくない、ということですね。 森崎 そうです。 山根 美学ってのは当然切れますからね。だから反生活だと思うんですよ。 森崎 そうそう、美学の講義を受けたことないケド、たしかそのとおりですね(笑)。 山根 そこが問題になるところですが、ごく一般的な観客がたまに映画を楽しもうとするときに、自分の生活とはスッパリ切れた映画、まるで嘘みたいに無縁な世界を描く映画を見たい、ということはあるんじゃないてしょうか。 森崎 それはわかりますよ。ぼくだって、同じ値段で見るとすりゃ外国映画を見ますよ。異文明についての憧れっていいますかねえ きれいな人が出てきて、ぼくらの生活感情とはまったく無縁のところで、ある世界を楽しむというか 私自身そうですから、それは否定しません。 山根 それなのに、どうして自分がつくるときには……。 森崎 他でたくさんやってらっしゃるから(笑)。 山根 同じことはやりたくない(笑)。 森崎 ぼくらが助監督で入ったころ、監督ってのは格別の美意識を、それはなんであれ、ある独自の美学を持たねばならん、モタモタ下手な編集して、何か汗臭く、こやし臭く、古畳臭いようなやつはいかん、と言われてたわけでしょう? そういうものへの反挨はありますよ。そいつらの椅子を持ってて、コンチキショウと思ってたわけですから。 それで、ぼくらは戦後ですからね、ひじょうに不遜にいえば、小津さん溝口さんも含めてですね、そこと切れたところで出て行きたい、自分がつく監督たちとは、基本的に感性において違うところでやりたい、という気持があったわけですね。 しかし何ていいますかねえ、当時、いちばんぼくらをとらえて離さないものは、もう助監督はモ口そうでしたけども 美的感性よりも、日々の生活への屈辱感だったですよね。なんかそいつが酒飲んだり、わめいたり、泣いたりするのは、必ず屈辱感からきてましたからねえ。そういうものをさしおいて、最後にはその屈辱感も越えてしまって、崇高な、ある破滅への盲目的な欲望みたいなもので、美意識に行ってしまう。全部ゾロゾローッと行ってしまうわけですよ、昭和二十年以前の川の流れに。あえてそれを、逆の方向に流れてみたいということが、まずありましたねえ。 山根 それはたいへんよくわかります。でも、またさっきの観客のことになりますが、生活の地平に縛りつけられて、毎日をあくせく暮らしている庶民にしてみれば、そういう意欲でつくられた森崎さんの映画であっても、どうしてまた生活に縛りつけられてジタバタしてるようなものを見なくちやならんのか、と……。 森崎 これが大問題ですねえ。 山根 もっと夢みたいな映画の方がいいじゃないか、と(笑)。 森崎 うーん、そうそう。それは、ぼくの死活の、つまり、日々メシを食う意味での大問題だと思ってますよ。 たとえばぼくにもなぜか、テレビからホン書けと言ってくるわけですね。なんとなく庶民喜劇をやれるやうというふうなありがたいレッテルがありまして。ところがやっぱり、変に濁ってくる。黒いってんですねえ。それ、モニターにも出るんですけどね。何かこうブラックユーモアふうなのが入ってくると、気持ち悪いという庶民感覚、要するにたかがテレビドラマ、たかが映画じゃないか、それなのに庶民がギリギリどこで本音を吐くか、みたいなことはね、税務署との喧嘩の最中には起こるかもしれないけれど、映画を見てるときには起こらんのよ、という言い方は、ぼくは正しいと思いますよ。そのとおりだと思いますよ。 でもですね、いっさいが現実の苦しみを忘れる子守唄であるというふうにオーバーに言ってしまわれると。そうでない部分があっていいだろうと言いたいわけですよ、ええ。 山根 そうではない部分ってのはどういう部分ですか。濁る部分ですか。 森崎 濁っちゃまずいんですよね。ぼくもそう思うんですよ、自己批判としては。 たとえば山田洋次という、ぼくにとっても公私ともどもひじょうに意味深い人がいるわけですけども、年齢的にも近いし、思想的な面でも、つまり戦前映画に対する我々って言う感覚でも似てたと思うんですが、チャップリンの好きな彼が言うには、「現実が砂漠だから映画ではオアシスを描きたい」と。それは、ぼくはやさしさとしてあると思うんですねえ。ある作家が自分を自己規定して、オアシスを与える、それが蜃気楼であろうといいではないか、と。 で、たとえば彼の『男はつらいよ』という作品でテキ屋が出てきますが、彼はテキ屋と会って話そうとはまったく思わない。リアリティのあるテキ屋の話など入れていくと、せっかくのオアシスにコールタールを投げ込むような結果になるということを、彼は知ってるわけですね。で、それはひじょうに正しい。 ただぼくも『男はつらいよ』を一本作りましたが、自分が作るのならば、どうあっても、テキ屋とまず会いたい、いろんな話を聞きたい。で、聞きました。ひじょうに面白い話で、これを必ず映画に生かしたい、テキ屋という、いわば差別された人たちが持ってる、誰にも言わない屈辱感みたいなものを、どうしてもモチーフにしたいとぼくは思ったわけですね。結局、それはうまくいきませんでしたけれども。 そういうオアシスにコールタールをぶちこむみたいなよけいなことをやりたがるというのは、ぼくの性質のいかんとこだってことはよくわかってる。けれど、もし、その寅さんの屈辱感が、はっきりと映画館の中で受け止められた場合には。そこにすさまじいばかりのコミュニケーションが成り立つはずだという夢を、ぼくは捨てきらんのですよ。 山根 どういうコミニュケーションが成り立つと思われるんですか。 森崎 寅さんのようなタイプで描かれる屈辱感みたいなものによってしかわからないものを、もし観客たちが持ってるとすれば、それをはっきり自分で見ることができると思うんです。逆にいうと、白塗りのいい男たちが出てきたりするような映画では、そういう屈辱感に思いあたるってことはまったく契機として与えられてない。むしろ、それを忘れろ忘れろというふうに常にうたってるわけでね。 けれど、寅さんの中に動いた、ある屈辱感、誰にも言えない憤りとか悲しみとかが、観客に伝わるならば、それは小説だとか何だとかってものより、はるかにビビッドな伝わり方をするだろう。もともと映画ってのはそういうものなんじゃないか。と、そういうふうに広がっちゃうんですね。 山根 だけど、こうは言えますね。映画を見てですよ、どうして自分の中の隠れた屈辱感を目の前に見せつけられなくちゃならないのか、と(笑)。 森崎 いや、ぼくは観客の顔を歪ませたいわけじゃまったくないですよ(笑)。 むしろ歪んでる顔を客観的に見て、にっこりしてもらいたい。その屈辱感に思いあたって、それが愉快であるように思いあたってもらいたい。その愉快たるや、相当なもんだ、千五百円は安いかもしれん(笑)と、こう思うわけですよ。 山根 『男はつらいよ』シリーズのうち、森崎さんが一本だけ監督した『男はつらいよ・フーテンの寅』を見れば、よくわかるんですが、山田洋次と森崎東は、どこかでピタッと一致してるんだけれども、最終的には背中合わせっていうか、向いてる方向が逆だという気がしますね。さっきのテキ屋に取材するかしないかの話に出ているように山田洋次は寅さんという人物像にリアリティを与えるに当たって、観念的というか理念的というか、そんな作業を行なう。ところが森崎さんだったら、まず取材して、というふうに、具体的な現実の方に向かおうとする。明らかにべクトルが逆に向いていますよね。そのことは当然、両者の描く大衆像の違いになっていると思います。たとえば渥美清のイメージで比べてみると、寅さんによってつくられてきた渥美清と『喜劇・女は度胸』で河原・崎健三の兄貴をやる渥美清との違いだと思うんですよね。あの兄貴の方の渥美清はグータラで、すごい助平で、要するに欲望まるだしの男であるけれど、山田洋次が築き上げてきた寅さんの渥美清ってのは、そういう肉体性みたいなものからどんどん離れていってますね。 森崎 早い話が、セックスをどう描くかっていったら、やっぱり寅さんはノンセックスであるという……。また、それで保証される世界ってのがある。そこでは芸というものがたっぷり見せられる、と。 さっき言いました美学というのと、もうひとつぼくがピンとこないのが、芸という言葉ですね。これもなんか坐りが悪いんですよ。尻がこそばゆくなってくるっていう感じで、どうせ俺とは無縁だと、こう横向きたくなる(笑)。 ところが大衆見世物の場合、芸なんか離れるとまったく成り立たんわけで、『たかが映画じゃないか』って題名の本があったそうですけど、本来は、たかが映画であってですね、そこで、拍手喝采を浴びるのは芸でなくちゃいかんとは思うんですよ。だからまあ正直に言いますと、あんまり正直であっちゃいけないのかもしれませんが(笑)、芸の方は自信がない、と(笑)。だから人とちょっと違えるとすれば、このへんは誰もやっとらんじゃないかという重箱の隅を(笑)、きたないものをほじくるという、作業に私の品性が向いとるんじゃないか、という自己規定はありますね。そう自己規定してしまうのは、あんまりいい気持じゃないですけど(笑)。 なぜ税務署員が出てくるか 山根 ぼくの感想では、森崎さんは、芸になってしまうことにも、ブレーキをいつもかけてるっていう気がするんですけどね。 "女シリーズ"の森繁久弥の演技がそうですね。森繁久弥はすごい芸の人だと思うんですが、他の映画のどれとも違って、森崎さんの"女シリーズ。のあの親父だけは、芸で見せながら、ついに芸としてピタリと完結して芸の世界に閉じこもっちゃうのでなくて、スレスレのところでそうはなってない。そこが魅力だと春うんですね。 森崎 俳優さんの芸を、ぼくだって演出家ですから、見て楽しみたいわけですねえ。テストのときに二ヤリとしたり笑いたいわけですよ。森繁さんの場合は、ほんとに吹き出して困っちゃったみたいなことありますけど。ですから、芸にブレーキをかけようとか、森繁さんの芸を抑えようとか思ったことはまったくないですよ。逆ですね。もっと笑わしてもらいたい、とぼくは思いましたよ。単純に楽しんでましたねえ。でも、そのこととはぜんぜん別に、今、そういうふうに言われると、ひじょうに嬉しいんですよね。なぜですかね(笑)。 山根 ブレーキをかけるという言い方はあまりよくなくて、要するに芸に成り上がってしまわないようにするということですね。あんまり見事な芸に成り上がっちゃえば、笑いの質が違うと思うんですよ。そりやあ笑いますけビね、そのときの笑いってのは高級な笑いになって、どんどん高級化していくだけで、それは美学といっしょだと思うんですよね。森崎映画の場合はそうじゃなくて、なんかそいつの生身が、肉体がチラッと見えちやうよう,になっていて、そこで笑っちゃう。芸プラスなにかなんですね。そのなにかってのは、生活的リアリティだと思うんですよ。 森崎 うーん……。余談ですけども、渥美清さんに第一回の『男はつらぃよ』のときに 「早ぃ話が、俺がイモ食や、お前のケツから屁が出るかい」って言わせたんですよね。ぼくはあのセリフが気にいってまして、このあいだテレビドラマ書いてまして、またぞろ使ったんですよ。「早ぃ話が、あたしがイモ食ったら、あなたのお尻から屁が出るの」って、淡谷のり子さんが浅丘ルリ子さんに言うんですよ。ぼくは気に入ってた。あの人が言うから面白い、ぼくのいう芸になる、と。 そしたらね、プロデューサーが、淡谷のり子さんがひじょうにお怒りである、と。あでやかな淡谷のり子っていうイメージがあってですね、イモを食って庇をひるなんてセリフを言うってのは言語道断だ、とは言いませんけども、ぼくに遠慮して言わなかった分をつけ加えていうならば、そういう感じなんですねえ。 ぼくはハタと膝を打ったですよ。ぼくのような、そういう下世話な、ダジャレめいたものを、皆さん全部に言ってもらおうというのは、私の思い上がり、と。淡谷のり子という人はですね、やっぱりイモだとか屁だとかは無縁に窓を開ければ港が見えなきゃいかんということで世界があるわけですね、このごろコマーシャルに出てきて生活風のこととを言うんで、すぐ私がのっかって、さあイモだってことになると。ピシャッとやられる。ことほどさように芸というものは厳しいものであってですね、そこいらの境界をメチャクチャにしようなんていう不埒な魂胆はいかんのではないかと、このごろ反省をしていますよ(笑)。 でも、境界線がはっきりあるということをひじょうにシビアに自覚しながら、なおかつ、そこいらの境界線を微妙にゴチャヤマゼにしたいという気持は、まだあるんですけどね。それはあんまり言うといやがられるから、いわないことにして、そうは思ってますよ(笑)。 山根 そのときに森崎さんなりの芸のイメージがあって、それはなにも淡谷のり子のイメージをよごしてやろうということじゃないんですよね。 森崎 そうですよ。淡谷さんにぼくはある種の憧れを持っていて、それをやらせたい。それで自分が演出するならば、淡谷さんのファンがそれによって増えるという自信がありますよ。信じて疑わないですねえ。 山根 プロヂューサーではなくて、淡谷のり子本人が言ったんですね。 森崎 ええ。あたしの淡谷のり子のイメージと、ホン屋さんのイメージはまったく無縁である、と。ぼくは、すてきだと思うんですけどね。あの人がそれをシレッとしてやればますます好きになる人が多くなると思うんですが、しかしそれを、絶対の審理であるといって押し付けるわけにはいかんと思うんですね。単純にぼく個人がそう思い込んでるんだなあってのを知ったですよ。 というのは、そういうものがほんとに楽しみなのかという、山根さんが今提出していらっしゃることと、関係があると思うんですねえ。 山根 ぼくがこだわりたいのは、映画であれ、テレビであれ、いったん映像の世界になってしまえば、生活そのものとは違うということです。切れちゃうと思うんです。だから、どんなリアルな生活劇であろうと、荒唐無稽な殺し屋のアクション映画であろうと、映画であることにおいては等価だと思うんですよね。で、森崎さんは、それでもね、なんかこう、現実生活とスクリーンの中とを、一種パイプでつなげようとされてるんではないかな、と。 森崎 そのとおりですねえ。 山根 だけど、映画ってのは、切れてることは確かなんで……。 森崎 だからね、ないものねだりしてるな、とは思いますよ。つまり人々の心は結ぼれてますな、変な言葉ですけど。こう、シコリができてますねえ。それをほどくためにまったく無縁の虹色の世界というものがありますねえ。もしくはラジカルな『8時だヨ!全員集合』みたいな喜劇だとかありますねえ。そんなのでも、ほどけますよ。ぼくは松竹をクビになって、憂欝な時間を過ごしてた頃には、よく『8時だヨ!全員集合』を見てましたよ。こう、ほぐれるんですね。とっても嬉しいと思いましたよ。このためにいかりや長介がいる、みたいな感じがしましたけども。 これは仮定でしかないんですけども、あるX型の喜劇があるとして、その喜劇のギャグだとか、ある高揚感だとかでないとほぐれない結ぼれがあるはずだと思うんですよ。それほど現代人の内面は結ぼれてると思うんですよ。ええ。だから少なくとも、それを見つけたいために映画をやるみたいな、ね。 テレビのホンを無責任にガンガン書いてりゃいいんですけども、なんか胃が痛くなるような気持を押して、やっぱり映画をやってみたいと思うのは、それを見つけたい。それは無限にないものねだりかもしれないけども、そういうものがあって、それをほぐすことができたら、すばらしいなと思わないことにはやっていけない、ということはありますねえ。 山根 問題はそのときに、その結ぼれに対して映画がどう働きかけるか……。 森埼 そうです、そうです。 山根 で、チンピラやくざが大組織から圧殺されていくような、そういうドラマでその結ぼれにショックを与えるやり方もあると思うんですよ。 森埼 そうです、そうです。 山根 それから山田洋次のようにね、一種理想郷のような庶民世界を描くやり方もある。 森埼 そうです、あの楽天性ですよ。楽天的にそれで結ぼれをほどこうという、ねえ。 山根 で、森崎さんのは、もうひとつまた違うんですね。 森崎 そう、それで思い出しましたけど、ぼくが学生のころ、京都で飲みに行ってた店のおばさんが、一人で飲み屋をやってんですけども、たまに映画を見に行くってんですよ、昼間暇なときに。そうすると、映画の中の世界とはまったく無縁に,「あっ、そうだ」と思うことがある、と。それはたとえば、明日税務署がきて、アンチキショーがこう言ったら、こういうふうに答えてやろうと思いつく。そういうのは映画を見てるときが多いんだというんですね。 それ聞いたとき、ぼくは映画をやろうと思ったですねえ、偉そうにいうと(笑)。市会議員になろうとは思わなかったですねえ。市会議員になって、京都の税務署長を呼びつけてね、どなり散らすみたいな発想もちらっと動きますけども(笑)。 そういう意味でいうと、ぼくの映画には税務署員が往々にして出てくる(笑)。 たとえば小沢昭一なんて人が出てきて、いやらしい演技をやりたがる(笑)。それを笑って見ることで解決できればいいけれど、現実はそればど単純じゃないんだ。税務署はしたたかなんで、それに対してどうしようかっておばさんの心は結ぼれてるわけで、映画に小沢昭一の税務署員が出てきてバカなことやって、ああ税務署員もバカだからいいんだ、というふうな次元では、けっして結ぼれはほどけない、もっというならぼ税務署員なんか出てこない方がいいんだ、生活と切れれば切れるほど、それは高度に作用するんだ、といわれてしまえばですね、ぼくの中でガラガラと何かが崩れますね、困ってるんですよ(笑)。 山根 とにかく森崎さんとしては税務署員を出したくなる、ほっとくと(笑)、やはりそれはベクトル生活の方に向けた映画を作っているからですね。 森崎 うーん……。 山根 そのときに森崎さんは、どのへんに作り手ってものの位置があると思っていらっしゃるんですか。 森崎 うーん、「来たな」って感じがするんですけどね、その質問は(笑)。ひじょうに困るんですよ(笑)。 さっきの言い方にまで引きずるならば、ぼく個人の感じとして、いちばん心の結ぼれがほどけるのはゼニをとらぬ芸能ですよ。ゼニを払って見るものはいっぱいありますけれど、ゼニをとらぬ芸能ってのは、もう今やない。だから、ないものねだりなんですけども。 エー、最近の経験でいえば、藤枝市ってところに、変なおじさんがいまして、そこでゼニを払わずに私は芸能を見たんですが。そういうものが昔はあった。柳田国男さんのいう常民の世界では、そういうものの効用をみんなが知ってた。それで結ぼれをほどきつづけてきた。 そういうものがなくなった今、たとえば西武劇場というところへ行って、すばらしいきれいなものを見る、高けりゃ高いほど気持がいいみたいな。そういうところでは、ぼくの心は絶対にほどけないし、よけい結ぼれちゃうんですねえ。というのは、ゼニを出すのがイヤってのが、まずありますねえ(笑)。そのくらいのことにゼニを出すのはイヤっていうふうにいいたいんですけど、これはやっぱり、ぼくの育ちに関係してますよ、どうしても(笑)。 もうひとつ、横向きたくなる言葉が、豊かさってやつですね。豊かな感性だとかってのはぼくは大好きですし、やっぱり貧乏とか、貧乏くさいってのはひじょうにいやなんですけども、豊かさで保障されるというものがいやなんですね。つまり誤解をおそれずにいいますと、ゼニをとって見せる見世物は、しかもそれが高度に資本主義化されてる場合には特にそうなんですが、いくらめでたい世界がそこに確立されようとも、ぼくの結ぼれたものは、絶対ほどけない。むしろ芸能を見ることで、よけい結ぼれていくという現象を、ぼくの場合は呈してますねえ。 山根 じゃあ映画なんかダメじゃないですか(笑)。 森崎 だから映画なんか見ませんよ(笑)。テレビドラマだって見ません、ええ。 山根 しかし、それを自分の仕事にしている……。 森崎 だから何を隠そう、ぼくはひじょうに困ってるわけですよ(笑)。ひじょうに不幸です、そういう意味じゃ。 山根 森崎さんにとっていちばん理想的な芸能ってのは、生活の中で古典的な祭り的空間をつくって、そこで生活してる人たちがたがいに芸能をやることなんですね。 森崎 そうそう、そうそう。いや、前半があまり気にくわないですね(笑)。「古典的な」ってのはいらないですね。 山根 でも、古典的になっちゃうんじゃないですか。今はそういうものは全部商業過程に入ってしまうから。 森崎 いや、宴会でいいわけ。たとえば八月一日に茅ケ崎で花火をやる、見るのはタダだから(笑)、浜辺へみんなで行って、安い酒を飲みながらそれを見る。そこでどっかの奥さんが、立って歌を歌ったり踊り出したりすると、それもカネ出さなくていいわけだし、ひじょうに効果的にほぐれるわけですね。別に古典的な民衆芸能の形をとらなくても、いっこうにかまわない。 ですから、今度つくろうと思ってる映画では、今問われてるところを、映画をつくることで答えたいと思うんですが、宴会映画にしたい、と(笑)。 山根 宴会映画、ねえ(笑)。 森崎 何かというと宴会をはじめる映画、登場人物たちが。 山根 いや、ちょっと待って下さい。そこは違うんですよ。茅ケ崎海岸で花火を見ながら宴会することと、宴会映画であれ、画をつくることとは、同じではないんじゃないですか。宴会そのものは生活の一部ですけれど、映画は生活の中にあるにしろ、表現のレベルにあるものだし、今の世の中に出てゆくときは商品になってしまいますからね 森崎 そうそう。でも、少なくともつくってる最中は、宴会をするごとくつくるということはありますよ 山根 ええ、そうでしょうね。 森崎 だから、自分のつくったものが商品として、表現媒体として、商品化されることについてはですね、いやともやってくれとも、別に積極的にはいえませんね。 山根 でも、商品にならないと、映画をつくれないわけでしょう。 森崎 それはそうだけど。 山根 商品になるという前提があって映画をつくるわけでしょう。 森崎 それじゃ、商品をつくってるわけですか。 山根 そうです。森崎さんの映画は、作り手がどう思おうと、商品という形をとるんですから。つまり、作り手たちが宴会をやるようにしてつくった映画にしろ、実際にはあとで必ずお客にお金をとって見せるという過程を前提にはじまってるわけですからね。それをなしにするんだったら、自分のお金で、八ミリかなんかで、非商業映画をつくrしかない。で、タダで見せる、お客にも。それだったら一貫されますけれどね。 森崎 別に一貫しなくてもいいんですよ、ぼくは。 山根 だけど商業映画ですからね。 森崎 だから、プロデューサーは、そうだろうと思うんですよね。プロデューサーが商品をつくる、監督は森崎である、と。そう思うことについては異論はとなえませんが、ぼくの中で商品をつくると思わなくてもつくれるってことですよ、映画は。 山根 ええ、もちろんそうです。ぼくはなにも商品をつくってくださいとか、商品をつくると思わなければならないとか、言いたいんじゃないんです。商品になることがはっきりしているという、ただそれだけのことを強調してるだけです。 森崎 その前提は、ぼくにとってはね、どうでもいいことなんですね。 山根 どうでもいいんですか。 森崎 いや、ちょっと違うかなあ。エー、つまり、そのことについて思いをいたすことが、映画の出来、不出来に関係すると言われると、それは関係ない、と。ですから もっと正確にいわなきゃいかんのだなあ(笑)。つまり、いちばんいいぼくの心のほぐれ方のものが芸能であると。それは職業的な人がやらなくてもいい。芸というものはむしろ、芸のなさみたいなものの方がいいんで、しかもそれは美学の美の字もないわけで、そういう意味では豊かでなくて、というふうになるわけですね。エー、そうすると、自分にとっての表現行為、芸能を作業することが、それとまったく無縁にするとするなら、ある種の強制を自分にしなくちやいけない、逆に。ほっとくと、それはつながってしまうわけですよ、ぼくの中で。でも、つながることによって、そいじゃお前は今の商品交換経済の中で、どういう位置を一人の表現者として占めてるんだっていうふうに問われると、なにがなんだかわからない(笑)。 山根 問題はやっぱり、自分が芸能を楽しむこと、森崎さんの場合、それは映画をつくるってことですね そのことと、それが表現として作品になることとの関係でしょうね。その作品がどう商品過程にのっけられるかってのは、さっきいわれるとおりプロデューサーの問題なんですね。そうじやなくて、映画づくりがひとつの表現として完結した作品の形をとつてしまうことを、どう思ってられるのかなと思うんです。 森崎 ひじょうに困ったもんだと思ってますね(笑)。それと無縁でありたいですね、ええ。 山根 つくることは楽しく面白くやりたいけれども、結果的に作品が残っちゃうわけでしょう。 森崎 自分の映画を封切館で、研究のために見るべきだとぼくも思うんですよ。でも、そう思いながら、行く気がしない。いやですね、ひじょうに。それで、ほめられるぶんにはいいけど、けなされるといやだし、当たらなかったとか言われると、もう、いても立ってもおれないし、自分が楽しんだ分だけ、どっかで罰せられてんのかと思うし、いやですね、だから、できることなら無縁でありたい。 山根 罰せられてるのかとおっしゃいましたけど、ということは、表現過程だけを純粋にうまく楽しめればいいというわけですね。 森崎 ええ、そうです。 山根 それは逆にいえば、そんなことはありえないのだとわかってるわけでしょ。つまり、表現過程、表現行為そのものが、結果によって束縛されたり逆襲されたりすることはわかりきってるわけで、そのことを忘れようとしたって無理なんじゃないですか。 森崎 でも、音楽があって音楽会があるから、ガダニー二問題が出てくるわけですよ。表現いっさいがほっとくとあのとおりになるわけですよ。誰も文句をつけられないんですよ、音楽が美しいからそうなるんで。だから、音楽はきれいなものであると信じてたのに私はくやしいっていう人がいますけども、チャンチャラおかしい。音楽が美しいから、アウシュビッツの中で人を燃やしながら毎日聞いてたわけで。 だからやっぱり、どこからか月夜の晩に笛の音が聞こえてくるというのが、音楽としてあってほしい状態だと思いますよ。笛の名士だそうで、顔もきれいで、金も払つても惜しくない、となればですね、それは梅野先生をやっつける立場ってのは、我々にはないと言わざるをえない。それじゃ劇場だとか何とかはぶっ壊しちゃえばいいのかつていうと、そうではないんですけビね。極論すればそういうことで……。 山根 森崎さんの映画を見ると、じつは観客のことをたいへん気にしてらっしゃると感じられますが……。 森崎 ええ、ものすごく気にしてます。気にしすぎてですね、「俺は気にしてない!」みたいな大きなこと言っとるわけで(笑)。 ひじょうに気になるから、そのことから無縁でありたいと思うわけで。何を隠そう(笑)。 山根 隠したつもりでも、映画に出てますよ、バッチリ(笑)。 森崎 アハハハハ……。たとえ映画監督として映画は商品であると思っても、これは社会学者の見る角度とまったく違うと思うんですね、商品を見る角度が。 ただ往々にして、我々の周囲では、特にテレビ界では、まさしくその作品の中に加えられた労働力の総和みたいな形で、何ていいますか、鍋釜つくるよりも、ミカンつくるよりも、何つくるよりも、無残に赤裸にされた商品そのものとして、経済学での講義みたいな形での原価計算というやつがなされます。もちろんその中には視聴率という名の交換価値という、芸術価値でも文化価値でもなんでもないんですが、そういうものがモロに出てきますねえ。と、それに敵対は絶対できませんね。一表現者は何のヨロイも着てないし、何の武器も手に持ってないんですから。 そうすると武器は宴会をするようにつくるしかない。つくることは楽しみであるはずだと思い込んで、実行して、その結果また悲しくなったりもするんですが、それ以外にない、と思いますね。 山根 くどいようですが、問題は、そのときに作品の受け手、つまり観客をどうイメージとして持つかですね。 森崎 これは話しましたかねえ。ぼくが思っている観客のイメージを具体的にいうと、姉の婿さんである、と。それは男で、中年で、教育が中程度以下でっていうふうなことがありますから、それはそれでひとつの意味を持つんでしょうけども、ぼくはそうじゃなくて、単純にあの人に見てもらいたいと思っているわけですねえ。 で、このあいだテレビで、『帝銀事件』てのをやったんですが、監修の野村芳太郎さんがぼくのホンを読んで、これでは平沢は犯人ではありえないというひじょうに硬直した発想のの押し付けである、そういう作者のテーマが生硬にすぎて逆効果であると、こうおっしゃって、その意見にぼくはある種賛成するところもあったりして、少し最終過程で直したんです。 というのは、観客のビビッドな反応に対して、つくる人間もつくる過程においてひじょうにビビッドに反応すべきであると、ぼくは思ってるわけですよ。ただひとつの文法があるわけじゃなくて、しかも個性というものがあるわけだし、基本的には、センシブルであるべきだというのが唯一のプリンシプルだと思うんです。 で、つくったわけですね。そしたらなんと、ぼくの好きな姉の婿さんから電話がかかってきまして、「東さん、よかったばい」、ここまではいいんですよ。「やっぱり平沢がやったっちゃねえ」って言うわけですよね(笑)。 愕然としましたよ。俺はいったい何をやったのか! まさしくガクゼン! ガーンと頭を殴られたような。それで何をこたえたのか、まったく覚えてなくて、もう早々に受話器を置いたはずですよ。 思わぬところに伏兵ってやつで、足元からガタガタッと揺れたわけですね。オーバーに言うと、俺はもうつくれない、と。俺の感性は、自分でもわりかし信用してたけど、これはダメだと思ったわけですね。だから、そういう意味で実感として言うと、ぼくのイメージする観客ってのは、なにがなんだかわからない。化けもの。ぼくを、ある日、足元から脅すような、まがまがしき存在ですね。安心できない、ええ。もうイヤ!(笑) 山根 困ったもんですねえ(笑)。 いくら森崎さんが宴会映画をつくろうと言ったって、できあがったものがどう見られるかは、まったくわからないわけですね。 森崎 そうです。「なんのこっちゃ」ってわけですよ。今いちばん怖い言葉。「なんのこっちゃ」っての、はやってますねえ。子供がときどき言うと、ギョッとしますよ(笑)。 俺のこと言ってるんじゃないかって(笑)。 だから、ぼくは不幸です、毎日(笑)。 山根 作品がどう受け取られるかわからないということに重なって、作品が一つのメッセージになってしまうということがあるんですね。今のテレビの件でいえば、要するに平沢は白か黒かというメッセージになっちゃう。 森崎 好むと好まざると、予測すると予測せざるにかかわらず、効果としてメッセージになってしまう。これがまたイヤ!(笑) 山根 いやなことばっかし(笑)。 森崎 困った商売を始めたといまだに思うことがありますけども、でも、つくってるときはそれとは無縁に、メッセージになろうとなるまいと、楽しい部分がありますからね、ええ。イメージをこねくりまわして、ヤツサモッサヤッサモッサするってのは、けっこう宴会的で楽しいんですよ。 山根 そういう楽しさはとうぜん作品の中に生きているはずで、見るほうはそれを楽しめばいいんですけれど、情報過多の時代だからか、ともすれば受け手は、楽しむことより前に、白か黒かのメツセージを受け取ろうとしてしまうようですね。 森崎 自分の頭が糸鋸で輪切りにされて、パカツとあいた頭蓋骨に何者かの手がヌッと入ってきて、自分のイメージ、脳味噌の中をかきまわすという幻想を、ぼくはときどきするんですけビね。テレビ・ドラマなんかやってると。ある種の軽いノイローゼなんでしょうけれど。ちょっとノイローゼじみてた方がものをつくるのにはいいんだっていう説もああるかもしれませんが、やっぱりない方がいいと思うんですね。 ぼくの美学と便所 山根 もういっぺん整理していいますと、ぼくが関心を持っているのは、森崎さんお映画が常に生活のほうへベクトルを向けていることと、それでも映画は英がなんだということとの関係です。小林秀雄の有名な言葉がありますね。ちょっと引用しますと、「あらゆる思想は実生活から生まれる。併し生れて育った思想が遂に実生活に決別する時が来なかったならば、凡そ思想といふものに何の力があるか」。これは映画にも当てはまるんじゃないでしょうか。映画がいくら生活に根ざしていても、ひとつの虚構の世界として自立してなくちゃ、面白いわけがないと思うんです。そのへんのことについて、森崎さんに聞いてみたいんです。 森崎 うーん……。むしろ、そこいらを山根さんみたいな人に、こう、掌を指すがごとく言ってもらうとですね、今後のぼくの創作活動にとてもいいのではないかなんて、いつも思ってるんですよ。前において失礼ですけど、ですからいちばんぼくの中で問題であるし、あらかじめ結論じみた正確な考えが出てきそうにないっていう予感がするようなもんですけどね。 具体的にいうしかないんですけど、今度の『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』という作品では、ぽくは生活に根ざしながら、今の小林秀雄さんに習うわけじゃないですけど、そこから切れたい。結果的にですけどもそういう、ある種腹の坐ったものを願望として、大胆にっていいますか、生活細部を描くなんていうことをまったく捨てちゃってやりたい、というふうに今思ってますね。 脚本を読んでいただくとわかりますけども、 「俺がイモ食やお前のケツから屈が出るか」なんてことについての喧嘩なんてのはまったく出てこない。生活臭ってのが逆にない。それが大問題なのではないかと、ふと自分では思ったりしてる。ゼニカネがどうのとか、俺が買ってきたものを食っちゃったとかという種類のことでやってる分には、安心できるんですがね。ですから、今度のはひじょうに不安というか、その分だけぼくにとってはある種の飛躍っていうか、ポーンと浮かんでるって状態にあるんですけども……。 ぼくは一脚本家としての生活次元でいいますと、メシはテレビで食ってるわけですね。で、去年(一九八〇年)なんてのは、テレビの二時間ものの演出をただ一本やっただけで、監督としてはゼロに近い。何で食ってるかっていうと、時たまくるテレビのホンを細々と書いてる。テレビに描かれる世界ってのは、もちろんどんなものでも自由だと思わなければいけないんてすが、私なんかにくるジャンルってのは、やっぱり生活にもろに密着したもので まあ、テレビってもののキヤラクターから、そういうものは増えると思うんですけども。だから、生活から切れる切れないでいうと、生活からまったく切れてないドラマの世界ってものを、ぼくはメシを食ってる中で否応なく書かざるをえないんですね。 映画を撮る撮らないは関係ない、むしろ映画を撮る方が年間収入が減るわけで。ですから、今度撮る劇場用映画の世界も必然的にそれを反映せざるをえないということもあって、ひじょうに非生活的になってるってことがありますね。結果的に。だからそれをどう思ってるんだっていわれると、ひじょうに、ええ……。 山根 そのことに関連して、もう何年も前の作品ですけれど、一つ前の『黒木太郎の愛と冒険』がたいへん興味深いですね。森崎さんはずっと松竹という映画会社の中で、それから一本だけ東映で、映画をつくってこられて、この作品をはじめて大企業の外でつくられた。そんなこともあって、ぼくの印象では、森崎映画の流れの大きな節目になっていると思うんです。で、この作品には、おおざっぱに分けると三種類の型の人間が描かれる。一つは生活密着型で、女たちがそうですね。もう一つは、ある観念的な世界に生きてる人間で、田中邦衛の主人人公・黒木太郎、財津一郎の大人のオモチャ屋の親父、それから軍人の亡霊そのままの三国連太郎など。それからもう一つは若者たちで、これは生活ベタベタの密着型と観念世界型のあいだというか、両方に足をかけてるというか、とにかく一種宙ぶらりんのところで生きてて、これが映画をつくろうとしているので、とうぜん森崎さんの自己像が投影されてぃると周えます。ともかく『黒木太郎の愛と冒険』はそんな三つの型が渦を巻ぃてる映画で、その揮然一体ぶりが魅力的でした。 森崎 渾然一体となってたかどうかはともかく、手法としてはですね、それを一体にしようという意識がひじょうにありましたね。 だから生活ベタベタも出てこなくちゃぃけないし、三国連太郎みたいに観念の世界に住んでるような人間も出てくる。過去の戦争という現実は、今はもう観念の世界でしかあり得ないんてすが、ぼくにとってはあの戦争が何だ ったんだろうって思いが、兄の死とぃう問題とモ口に噛んで、ものすごくあるんですね。しかし、そのことと世間の人々の生活ってのはなんにも結びつかない、別世界のことである、というふうにいいきってしまうのは、ぼくにはひどく不安であるんだというふうなことを、ひとつは言いたかったんですね。 山根 そのへんのことが、あの映画の魅力的な混沌ぶりに出ていると思います。 で、今度つくられる映画はたぶんそういうふうなところを踏まえたものになるんじゃないか。とすると、森崎さんご自身のなかで『黒木太郎の愛と冒険』がどんなふうに位置づけられているかは、たいへん興味深い問題です。 森崎 あれをどう位置づけるかってことは、やらなければいけない宿題だって気が、今ものすごくしますねえ。 山根 まあ、実際のあり方としては、今度の作品を作ることが宿題を解くことなんでしょうね。 森崎 どういえばいいんですかねえ……。つまり“新宿芸能社もの”なんてのをつくっているときは、あんまり肩肘はらずに、いわば思想的には無責任につくってればいいわけですよね。無責任さがそこいらの良さを保障してるみたいなところもあったしして……。 要するに裸で暮らしてる女たちなんだから、それを、なんか差別のクソのって、メッセージを入れようとすると、かえっておかしなものになるんで、そこは楽しみながら無責任に、いわば宴会映画ふうにつくればいい、と。宴会映画なんて、そのころは考えてなくて、ひじょうに真面目に考えてたんですけども、やっぱりそういうふうにつくってきたと思うんですね。 『黒木太郎の愛と冒険』っていうのは、宴会映画ふうにはとてもつくれなかつた。そういう気持は今でもないし、そういうのがどこに出たんだって言われると困るんてすが、あのころ、今でもそうなんですけれど、人間の死っててことをどう捉えていいかわからなくて、ものすごく気になつてて、それで王人公が瀕死の重症を負つたり、実際には生ける屍みたいな戦争犠牲者がまた切腹するという形をとるとかして、出てくるわけですね。 そういう、人間の死と生とが、どう裏腹の関係なんだっていう、宗教的ともいっていいぐらいの、ある不安の命題があって、黒木太郎ってオッサンの職業が命がけでやるスタントマンであつた方がいいといった形で出てきたりもする。なんかフロイト的な、ぼくの中にグチャグチャッとあるものが、ある種の夢である映画という形で出てきてる。ぼくが精神分析学をもう少し勉強してれば、自分で、あれはこうなんてすというふうに言えるのかもしれませんが。 だから、今度の映画はそういう意味でいうと、ストリッパーの生活を描くんだっていうふうに つまり死が何てあるとか、戦争がどうだったんだとかっていうことじゃなくて、楽しみとしての映画づくり、という言い方はちょっと不遜ですけビも であらねばならん、というふうに思っているわけで、『黒木太郎の愛と冒険』のような、眼つぶって、ポーンと飛びあがるみたいな作り方は……。なんか語るに落ちるというふうで、よくわからんでつくってるんじゃないかって気がしてきたな(笑)。 しかしここは、自分でもなんとかしておきたいんだなあ。エー、しかし、『黒木太郎の愛と冒険』に似たものになってしまうんじゃやないかつていう不安、なんかそういう感じもしますねえ、今度のは……。何をいってるんだろう。(笑)。 わかんなくなってきた(笑)。 山根 "新宿芸能社もの"の場合、楽しみながら無責任につくればいいと思われたのは、描くものがメツセージではもちろんなくて、はつきりした像、人物像とか生活像とかであつたからで、たしかにそれを豊かに描き出されていたと思うんです。ところが『黒木太郎の愛と冒険』では、生活のイメージ、死のイメージ、戦争のイメージ、いろんな人物のイメージなどが、いくつも散乱してぶつかり合っている世界になってる。その混沌を、今度、もう一度整理しようと思ってらっしやるんですか。 森崎 はあはあ、なるほど、わかってきましたねえ……ある意味では整理の方に向かいたいというか、具体的にいうと『黒木太郎の愛と冒険』で、倍賞美津子さんと田中邦衛さんの夫婦が出てきますけビも、あれは生活という次元で描きながら、つまり夫婦別れの危機だとか出てきますが、なにも描いてないに等しい。むしろ緑魔子さんの方に光が当たっちやって、なんで倍賞さんの嫁はんがいなくちやいかんのか、というふうになっちやつてる。 今度も主人公は倍賞美津子さんを考えてるんですけど、あれであっちやいけないという、大整理ですね、少なくともヒーローとヒロインの関係は、厳然として、ある重さをもってなきやいかんと思います。『黒木太郎の愛と冒険』に関しては、そういう考え、まったくなかつたですね。 このあいだ新聞に、鈴木清順監督がNHKの婦人の時間でお話をなさったときの抜粋みたいのが出てたんですけれど、「監督ってのは、作品をやるときには、ある種ヤケクソにならなきゃやれない、つくろうというところに踏み切れないんだ、監督ってのはだいたいみんなそうだろうと思ってる」というふうなことをおしゃってましたけども、あの『黒木太郎の愛と冒険』てのは、まさにそうだつたんですよね。 松竹をクビになつたとき、俺はもう映画をつくれないんじやないか、それほど甘いもんじやないんだと思ってたんですが、馬道さんという、なんか執念の塊みたいな人のパワーに押されて、「よし、それじゃつくるか」って気になって。でも、おそらくこれが最後の作品になるだろう、と思ってた。あの映画のパンフレットに河原畑寧さんが、ぼくの年賀状かなんかの文を引用して「"もう一本映画をつくって死にます"つて書いてあったんで、大笑いした」っておっしゃってたんですけど、大笑いされちゃ困るんで、もう、モロにそうだったわけですね。それは悲愴でもなんでもなくて、いわばヤケクソで、それの肯定的な部分でつくろうとした、否定的なヤケクソの部分では、「どうでもいいや」と思ってたわけで。というのは、映画がつくれるかどうかにこだわってると、息もできないような状況になってしまうから。 そういうものがぜんぶ反映して、それでもなんかそこいらのフンギリが作品的なものとして出るだろう、と。しかしそれは自分ではまったく予測がつかないという形でつくったもんですから、結果は思ったとおり、バラバラになっちゃった。 今度は、そのヤケクソ性の何かが光るというふうには思わないわけで、やっぱりイメージしたものだけしか出ないんだ、と。それが少し水増しされてフィルムに定着するだけで、インスピレーションがフィルムの中にもぐり込むみたいなことはあり得ないんだ、というふうにつくりたい。整理するっていうか、自分自身にはわかりやすいようにつくりたいと思います。『黒木太郎の愛と冒険』は、自分にわかんなくてもいいと思ったですよ。正直言って。そんなメチャクチャなことがあるのかって怒られると、一言もないわけですけどね(笑)。 山根 そこでぼくの感想を一言さしはさみますと、ぼくは『黒木太郎の愛と冒険』がこれまでの森崎さんの作品の全作品の中で、いちばん美学的にできあがってると思うんです。そこが不思議なとこだなあと思いますね。 森崎 美学的に? 山根 ええ。さっき、美学には反挨するっていう意味のことを言われましたけども、あの作品がいっとう美学的な、いわば高みへ昇ってる、と。 森崎 高みへ? 山根 ええ。むろんそれは、決して悪い意味じゃないんですけど。作り手の意図の問題ではなく、結果としてです。混沌の美学みたいなものがあると思うんですよ。古典的な美学とまったく違うものだから、反美学の美学といってもいいです。 森崎 どんなところにそれを感じますか。 山根 今、パッと思い出すのは、いちばんラストのところで、主人公のガンちやんが血だらけになって歌をうたいながら、いっぺん死んだのか、倒れていたのに、もう一度起き上ってきますね。それで例の歌「砲兵の歌」をうたいながら、短 剣持って向かって来るじやないですか,あのショットなんか、すごく美しい画面だと思うんですよ。 森崎 ちょっと待って下さいね。自分の作品を、あとで実はこうだったんだってのは、最低なんですけども、ぼくはあの 映画をパート・カラーにしたかったんですよ。 山根 白黒作品の一部をカラーにしたかった……? 森崎 あそこのワン・カットだけ。ガンちやんが死んでる俯瞰ののカットがあるんですが、起き上る前の。ここだけは血を赤くしたかった。というのは、山根さんはもう見抜いていらっしやるかもしれませんが、ガンちやんが上衣を脱いだとき、下に着てるのは親父の洋服ですね。 山根 ええ、そうですね。 森崎 シャツもそうなんですよ、実は。で、血だらけになってるのは、親父の血なんですよ。アップで撮ってるんですけども。クソ理屈ですが、犯人が射った弾は腕を貫通していて、胸の血は親父の血の痕。だから、前日か二日前にこびりついた、黒い血でなくちゃならない。それはカラーでないとわかんないから、そこだけパート・カラーでやろう、と。一所懸命やったんですけど、なかなかうまくいかなくて。テストをものすごく繰り返しましたよ。 山根 じやあ、二つの血が区別して見えるはずだったんですね。 森崎 ええ。それであの犯人がビビルのは、死んだ男の固まった血がフワッと出てきたんで、なんだこりゃ、と。しかも軍服の中に。というのは、ぼくの兄貴の軍服が家に送られてきたんですが、海軍第三種軍装のまだ新しいような服でね、カーキ色なんです。それに、あれとそっくりな血がこびりついてたんですよ。それがどうしても、フワッと、出てこなくちやいかん。そのためにあの映画をつくったようなもんですからね(笑)。 だからこのあいだも、あの映画を上映した会場で、そのことを言いたかったんですよ。そんなものクソ理屈だっていわれりゃ、一言もないんですけどね。だけど、ぼくが言いたいのは、ガンちやんが上衣を脱いだヒきに、パン・ダウンして信玄袋になりますけど、そうしないで、親父の血だらけのシヤツをひきずり出して着りゃよかったんですよ。でも、そこで着ちゃうとフワッときたとき、びっくりせんだろう、と。だから脱いで、パン・ダウンして「遺書」って本にいってるんですが。親父のシャツと軍服を着たっていうことなんてすよね。そこのイメージがストーンととんじゃってるから、美的になったんじやないでしょうか。 山根 いやあ、もしパート・カラーになってれば、もっと美学的になったんじゃないでしょうかねえ。 森崎 ぼくはね、そういう意味では、ちょっと使ってらっしゃる言葉が違うかもしれないけども、ぼくの中の美意識ってのを、あんまり大きい声でいうと、ほら、今、励まされて言ってるだけで、実はぼくの美学をやりたかったんですよ(笑)。 山根 何を隠そう……(笑)。 森崎 つまり、三十六年前の血が凝り固まって出てきて、それが三日前の血と重なって、というぼくの美学があるんですね。つまり、ぼくが見た兄貴の血のイメージがあるわけだから、単調な美学じゃないですねえ。でも、俺の美学だっていう、他の奴は美学だと言うなっていう感じがあるわけです。それは狙ったんですよ。だからもう、ほんとうに苦しみました。現像所を泣かせて。 山根 今言われてから思い出すんだから変ですけどね、ぼくは、シャツの血が親父の血であることはわかったような 気がするんだけどなあ。 森崎 うれしいなあ。 山根 それは、なんか当然わかってたような気がするんですけど。とにかくまず服が親父のものであって……。 森崎 あっ、わかりましたっ? 山根 誰だってわかりますよ。ひどい観客不信(笑)。だから当然、血もそうだっていうふうに、ね。 森崎 ああそうですか。そんならいいです。 山根 森崎さんは、戦前の映画におけるような美学と違うものを、戦後の映画の中でつくっていきたい、というふうに最初おっしやいましたねえ。それは、逆にいうと自分なりの美学をつくりたいということであって……。 森崎 そうです! そうですよ。ぼくだってやっぱり、人間は何において死ねるかっていえば、美においてだと思ってますからね。ゼニカネだとかじゃ死ねない。ぼくのいちばん親しい人間の死がそうでしたからね。美的に奴は死んでるわけだから、ぼくだって美的に死にたいわけで、できたらねえ。そういう意味では美ってのはね、要するに死の想念と重ね合わせて、のっぴきならない価値の世界なんですよ。 山根 そのへんのところが、『黒木太郎の愛と冒険』にはいちばん出ていたと思いますね。"新宿芸能社もの"のような生活密着型の映画じゃなく、混沌としているから。で、そこでまた、そういう美学的なべクトルと生活密着型のべクトルとの二つが、森崎さんの中ではどんなふうになってるんだろうと、あらためて思います。 森崎 実はぼくは、文学部の美学へ行こうと思ったこともあったんですよ。絵描きになろうと思ったぐらい絵をよくする少年だったわけだから。今でもほんとうは、絵を描きたいと思ってるんですけれども。 山根 いつか似顔絵を描かれるところを見ましたけど、実にうまいですね。 森崎 人一倍俺は美にクウッとなる、と思ってるわけですよ、実は。何を隠そう(笑)。 たとえばあの森繁久弥が馬鹿みたいなことをやる作品にしたってですね、ルルーシュが気づかないカットがある、なんて思ってるわけですよ(笑)。ありゃせんのですけど(笑)。でも、意図としてはあるわけで。だからルルーシュなんぞは、嫉妬を混えて嫌いなわけですね。そう気楽に極楽トンボで美をやれたらええなあ、と。美、といった場合、こっちはなんかね、刺さってくるものがあって、それは何だろうといつも思うんですけども。 むかし読んだ本にね、強靭な意志と明晰な悟性とほとばしる情熱と、だったかな。悟性と理性と情熱と意志力と、それを一体化したもの、それは行動である、イコール美である、と、こうみごとに書いてるわけですよ。誰を隠そう、小田切秀雄さんだったかな(笑)。 これこれ、これを知ってれば、もうみんな、たちどころに切れるなって思った時代があるんですよ。つまり、語呂がいいから。それにいまだにってことじゃないんですけども、そういう次元のもんだと、美ってのは。パープルとピンクを並べてこうやると美しい、なんていうもんじゃないと思うんですよね。 それで、ぼくの映画が、笑いに寄っかかってしまうってのは、その逆の涙ぐむというのが美的になっていってしまうという意味で、美はこわいっていう意識がありますね。つまり正確でなくなっていく、境界がわからなくなり、酔っぱらったような状態になって、美的だなあというとちょうどぴったりする、みたいなのは、ちょっとヤバいんだという気が、どうしてもあるんですよね。というのは、戦争中に、美的に死ねといわれたくちだからなんですよねえ。 ときたま思い出すんですけど、ドアを開けたらもう、鼻を撲つという言葉がありますけれど、まさに鼻を撲たれたんですよ。撲殺するの撲ですね。水洗便所に糞がですね、山盛りになってるんですよ(笑) 山根 エエッ、糞? 何の話ですか(笑)。糞が流れないで山盛りに? (笑) 森崎 便器の外側に(笑)。中にも、もちろん。その臭気たるや、すごかったですね。それだから、ガーンときたんでしょうけどね、まさに顔を殴られたっていう……それが今でも出てくるんですが。予科練の飛行兵を志願して行った、佐世保海兵団の中の便所なんですが。とにかくあの頃の水洗便所ですからね。真っ白な、きれーいなタイルを、下士官が指でこうやって、なめるようにして検査する。ピッカピカに磨いてあるんですから。 山根 それがどうして糞の山に?(笑) 森崎 ぼくら志願兵がそうしたんですよ。真っ白なパリパリの服を着た下士官が、棒を握って、真っ赤になってどなりましたね、彼にはわかんなかったでしょうが。 ぼくら志願兵は、山の中からも来てるわけですから、水洗便所のやり方がわからない。穴ぼこが前の方にあって、ポトンといわないから(笑)。困っちゃったわけですね。しかし、あれもやらなきゃってんで、外側にするわけですね。そうすると次に行った奴が、足の置き場がないもんだから、こうやって、ぼくも結局それでやったんですが(笑)。物理的な結果として、周りに糞がエベレスト山のごとくですね……(笑)。何百人と志願兵が来ているわけですから、五十人入ったとしても、五十個の糞がうず高くなるわけです。押すとシャーッと流れる便所ってのは、ぼくらの概念にはなかったわけですから。 馬車引きみたいな顔をしたその下士官が言ったですよ。 「お前らは七つボタンに憧れて来たんだろう、海軍の旗をニュースで見て来たんだろう」と。そのとおりですね。海軍というのは当時の少年たちの美的な憧れの的だった。それが、開けたら糞が出てきたわけですね。ぼくは誰かにだまされてると思いましたね、やっはり。本質はこれなんだ、と。なんだかんだといっても、最後は垂れ流しながらね、死ぬわけだから。それがやっぱり見えたっていう…… つまり、当時のぼくの美という概念の中にあったのは、白、制服、金モール、軍艦旗、死をおそれぬ魂、みたいなすべてをひっくるめて、海軍は、美の象徴であったわけですが……。それ以来ですね、美っていうのはヤバイんだと警戒するようになったのは……。 ・ だから、ぼくの映画には便所が出るわけですよ(笑)。 松竹の社長は、 「便所をなぜ出すか」って怒ったんですけど。便所を出すと安心するんですよ、悪魔祓いをしたような気がして(笑)。 山根 さっき涙のことをおっしゃいましたが、森崎さんの映画では、涙に流されることを拒否するところがあって、笑いが涙じゃなくて怒りの方へ結びつくことが多い。それも同じことなんでしょうね。ほのぼのと笑ったり、ほのぼのと涙ぐんだりするだけでは、流されてしまって、それは一種美的な感情なんだろうけれども、そんなふうに流されるのは違うんだ、と。で、そこへションベンやクソの話が出てきたり、あるいは人物が怒りのアクションを るというふうになっていくんだと思いますね。 森埼 ええ、そういうふうにしておくと安心するわけですよ。泣くだけで成立しちゃうと、なんかヤバイなあ、なんか気持悪いって感じがありますね。 篠田正浩って監督が ぼくはわりかし好きなんですけども ぼくのことを何かに書いてて、森崎東、うん、泣かせるのがうまい監督ですね、と一行で片ずけた。ひじょうに怒つたですぬ、ぼくは(笑)。今でもそれを思い出しちゃ怒つてるんだけども、そう言われるとひじょうにいやですね。つまり、笑わせながら、うまくちょっと泣かせてると。篠田に会つたら「あれはないよな、お前。ああいうふうに言うな」って言いたいですけども、そういうふうにとられてるなら、しようがないですからねえ。だからよけいヤバイって気がするんですよ。 ひょつとすると泣かせるのがうまいのかもしれないな、そういう甘っちょろいところが俺にはあるからな、という気がものすごくするわけですよ。だから、プレーキを自分でかけてるのかもしれませんね。 山根 『喜劇・女は男のふるさとヨ』で、緑魔子が売春をやったというので、中村メイコが警察に呼ばれて、刑事が調書を読むのを聞いているうちに、涙を流しながら怒るシーンがありますね。あそこは泣かせるし、実に美しいンーンだと思うんです。その美しさは、場面にみなぎるエネルギーが、単純に涙の方だけに向かうのではなく、怒りの形になってゆくからなんですね。いうなれば、そういう形で映画的な美学になってるということだと毘うんですよ。 森埼 そうそう、原作には「なんであんた方はそんなふうに言うんですか」って言ったというふうに書かれてんですけども、あれをドラマチツクにするために、泣きながら、ほとばしるように涙を吹き出しながら、詰め寄っていって、最後はもう、なんか机にすがって、がっくりきちゃって泣いてしまう、というふうにつくれるわけですね。で、それは、中村メイコさんだから名演技しますよ。 自分が言ってることに衝き動かされて、酔っぱらっちゃって、泣いちゃったっていうふうに撮つたとすれば、醜悪ですね。そういう醜悪なシーンていうのが、現実にありますけどね。 山根 ですから、あの映画では、まさしく現実と違う映画なんだから、彼女は酔っぱらっていて、 「酒飲んでるのか」って言われると、 「ああ飲んでますとも」と居直ってね、ペンをかまえて刑事に突つかかって。そこで、映画だからこその一種の美しさになると思いますね。そこらへんに、森崎東の美学ってのがあるんだというふうに思うんですよ。それは通常いわれる美学というのとはもちろん違いますけどね。 森崎 なにしろ、男の美学だとか男のロマンだとか、なんだか安直にね、新聞をめくると必ず下の方に、広告にあるから、アレルギーになってんですよ。どうしたってこっちは美で飯を食おうと。ねえ、それ以外にないんだから。 山根 で、ぼくが思うには、そういう独特のを描いてこられたのが『黒木太郎の愛と冒険』では混乱の中に突きやられて、別の美学に向かってるんではないかな、と……。 森崎 あのー、ぼくはこのごろ、そういうことがなくて困るんですけども、『黒木太郎の愛と冒険』を撮る前までくらいは、映画を撮ろうな、撮りたいな、という、どういう映画かっていうイメージは別にないんですが、なんかブワーッと水位が上がってくるみたいなことがあったんですよ。 それでそういう瞬間があるのは、小説読んだときとかではなくて、小説読めばよむほど、水位が下がるんですよ、こんなにたくさんの表現があるんだからもういいや、というふうに、それがひじょうに美的につくったテレビのコマーシャルがあるでしょう。もうルルーシュが撮ったんじゃないかという。ああいうのを見ると、むらむらっとして、「ようし、俺の映画を撮ってやろうじゃねえか」と。ただし、三秒ぐらいですよ。コマーシャルが消えちゃうと、ぼくの方も消えちゃうんですけどね(笑)。 「それで美化!」なんてね。「お前らのコマーシャルと違って、俺は一時間半やれるんだからさあ、ようし、やったろうじゃないか」という気になったですね。 で、映画を撮った場合、宣伝部の人から、 「監督、どういうテーマでやるか一筆書いてよ」なんて、よくいわれますけど、それに書けない部分で、実はやろうとしているわけですよね。それ書いちゃうと、なんだかしらけちゃうから。 そういう意味でいうと、今度の作品の場合は、これもぼくの嫌いな、横向きたくなる物語ですけども、男の色気、原田芳雄さんの男の色気をですね、ムッというほど実は出したい。と言うと、みんな、ウツとなるから(笑)。 「森崎が男の色気を? 美しく出したい? ふざけんじゃない。よせ!」とか、出てないじゃないかと言われるといやだから 言いませんけれど(笑)。 ぼくにとって、リングに上がりたいなあという気がするのは、そういうことなんですね。さっきは死とか哲学がどうのなんて、いろいろゴタクを並べましたけども、監督としてのフット・ワークが出るんならばそこで出るんで、原田芳雄君のこう、ぐっと迫りや、俺が女だったら、濡れるようなふうに撮りたい、という欲望なんですよ、実はね。 山根 じゃ、わりあい普通になったんじやないですか(笑)。 森崎 普通? 普通って……。 山根 だって、原田芳雄さんほど男の色気がプンプンした役者はめずらしいくらいですもん。 森崎 それをもう一歩やりたい。もう、イヤ!っていうほど(笑)。 山根 そりゃあもう、原田芳雄だったら、放っておいたって、いやというほど色気を感じさせますよ。 森崎 そうか、ちょっと、ずれてるかな。 山根 それを今さらやるっていうのだから、わりあい森崎さんとしては当り前のところにやっとたどりついた(笑)。 森崎 もろに馬脚をあらわすか、ワハハハハ。俺だけの実字、たった一人の反乱的美学なんて言ってるわりには、ど うってこたあねえな(笑)。 山根 ぼくなんかが森崎さんの映画を見てきて、美学というか、そういうのてひとつだけ悪い例をあげれば、 『高校さすらい派』のラストだと思うんですよ。 森崎 ああ、ラスト・カツト? 山根 いや、ラスト・カットじやなくて、砂丘の幻想のシーンで、変な機動隊のお化けみたいなのが砂丘の向こうから突撃してきて、森田健作が機関銃を乱射するシーン。あれなんか、森崎さんの持ち味とはまったく違うはずで、なんでこんなことするんだろう、と。 森崎 うーん……。 山根 一種美学的にこしらえた画面だと思うんですよ。 森崎 うーん、なるぽどね。 山根 だから、ぼくは『高校さすらい派』っていう映画が森崎さんの全作品の中で、いちぼん観念的に空回りしてる映画だと毘うんですけどね。そこて森崎さんの観念性というのがよく見えてる。それは単純に悪いとは思いませんけども、作品としてはやっぱり空回りしてるって気がするんです。それを象徴してるのが、今のシーンてすね。 森崎 あそこはどうですか。はら、廃船の上て、 「南十字星向け、ヨーソロ!」つて、船出だっていってね。それから三人で結婚式。あれは美か醜か……。 : 山根 いや、美か醜かというふうには思わないですね。まあ、ちょっと恥ずかしいシーンてはありますけれど、ああいうのは、若者の遊戯佳のあらわれというふうに思うから。ちょっとチャチだから、見てて少々気恥ずかしいけども、あの年頃の少年少女たちにとっては切実でもある、と思いますからね。ただいずれにせよ、そういう描き方は、森崎さんの観念的青春像のあらわれという気がするんです。『黒木太郎の愛と冒険』の中には、ああいうシーンはないですよね。 森崎 うーん……。あの若い男三人の半同棲生活みたいな部分が、最初はエ延々とあったんですけどね。 山根 ああ、短くカットする前に。 森崎 ええ。なんか、同性愛ふうのカットがあったりしたんですよ。ぼくは放っとくと、観念青春になりますから、自分でわかるんですよ。だからそれじゃなくいきたいと思っていたことは確かですね。 山根 今度の映画(『党宣言』)は、そのへんはどうなんですか。. 森崎 中学生がが三人出てくるんですが、実はよくわからんのですよ、今野中学生と、こっちとの共通項なんていうのは……。 だけど、『黒木太郎の愛と冒険』は、ガンちゃん役をやった伊藤君の実話をそのままいただいて映画化してということもあって、映画をつくろうと思っている若い人が、あの映画をどう思っているかについては、ぼくはひじょうに興味があるし、意味のあることなんですが、それに関しては、伊藤君はまったく否定的なんですよ、大失敗作であると言ってるわけですね。 どこでそうなのか、あんまり言われるといやになるからね、わざわざ聞くこともねえと思ってるんですけども、ただその言葉を、ぼくはぼくなりに重く受け止めてるわけですね。やっぽりテメエの頭ん中で、勝手に踊らしたというところがあってですね。ても、彼らの中から出てきたものを、たとえば黒木和雄さんの『竜馬暗殺』のポスターが部屋に張ってあつて、俺は竜馬の生まれかわりだって思いこんでるとか そのまま全部入れてはいるんですよ。だけど、ぼくの並べ方になっちゃってて、彼らの生理とはまったくかけ離れたふうになってるんじゃないか、さっきいったように、もうやけくそですから。そんなとこまでつきあっておれねえや、というところがあったりして……。 そういう意味では、今度は、いつもそう思っててだめなんですけども、中学生だから、しかも映画をつくろうなんて思ってない連中だし、彼らの生理が少しでも出なきゃだめだな、とは思ってますよ。 つまり、むこうの都合で撮りたい、と。「十五歳の少年少女たちはそうはやらないんだ、監督」と言われりゃ、ぼくは一言もなく引き下りますね。 たぶん前はね、銃一役の伊藤君も言ったんてすよ、 「監督、違うと思うんだ」って。最後に乗り込んで行く前、ションベンしながら歌を歌い出すシーンで、なぜ彼がしつこくぼくに「違う」と言ったのか、いまだに正直いってわかんないんですよ。 「違う、やりたくない」 「いいんだ、やれ!」なんて喧嘩腰で。でも、あそこにぼくは、えんえんと音楽をブチかませるという、監督としての狙いがありますから、引けないわけですね。ガタガタになつちゃうから。だけど今度の作品では、そこは相対的に考えたいと思います。 山根 でも、どうなんでしょう。中学生はこういうときこういうふうに動くもんだと、たとえ生身の現実世界に即して言ったところで、映画的にリアリティがなければ意味がないんじゃないですか。 森崎 ええ。でも、ぼくらがそれに反対して、リアリテイがあると想定するようなそればど画然としたものはないはずだ、というのがぼくの意見ですよ。映画の作り手の方にはそれはないはずだろう、と。そこはひじょうに流動的で、実はいいかげんなはずだ、と。 「このときはこういう顔をして、こういうふうにしゃべるということに、自信があるか」と聞かれりゃ、「別に」と、みんな言うんじゃないかと思うんですね。で、 「別に」と言い始めると面倒くさくなる、短時間で撮影が終わらなくなるから、やってるだけですよ、みんな。何を隠そう、偉そうに(笑)。原価計算を安くするために監督の権威ってものは機能してるわけですから。 黒沢明さんみたいに、たくさん金をかける映画でも、なおかつ、それを効果的にするために黒沢さんの権威があるわけですからね。ゼニがない人間は、もうそれしかないんで。監督の権威というやつを、おっかぶせるわけですよ。 だから妥協するとかじゃなくて、分業でいい、と思うんですよ。 山根 分業であるからこそ、役割というものが生じますよね。役者としての役割、監督としての役割、というふうに。だから、現実世界ではこうだああだといっても、それをどう取捨選択するかってのは、監督の役割ですよね。 森崎 もちろんそうですよ。無限に言ってりゃ、もう、そりゃあ「今日は帰りたい」って言いますからね(笑)。「意見を言ってみろ、全部とり入れるから」なんて監督はよく言いますけど、口でごまかしてるだけて、 「結局は入れないんだよ」と言うために言ってるわけですからね(笑)。 コンテを描かない、のぞかない 山根 ぼくはまだ現場を見たことがないんですが、森崎さんの演出の仕方は、あまり枠にはめていかないやり方、押し付けじゃないやり方なんじゃないですか。 森崎 ええ、どっちかっていうと、そうじゃないでしょうかね。 山根 一挙手一投足を支持するようなことはしない演出なんでしょう? 森崎 ぼくがついた監督たちに比べると、はるかにそうですね。ぼくのついた監督たちは、もう、自分のイメージにはめていきましたからね。全部コンテが決まっているから、ということは、役者がイメージと違う演技をすると、コンテが違ってきちゃうんですよね。 山根 森崎さんは絵コンテを描かないんですか。 森崎 絵コンテも描きませんし、コンテを立てない、立てちゃいけないと思ってますし、現場で変わっちゃうし、でも、たまには絵コンテを立てますが、それこそ早くやるため、能率のためですね。 山根 じゃ、加藤泰みたいに絵コンテをばっちり描くやり方というのは……。 森崎 全然だめです。いや、やろうと何や、あの方が楽なはずですよ。いや、加藤さん批判じゃないですよ。加藤さんは、あのとおりやるからまたすばらしいと思うんですけども。前の日にあの人は、つくるわけでしょう。するともう、それだけでいいわけですよ。もう翌日は、実に気も軽く何の悩みもなく、光風霜月ね、むしろ自分の絵を、一人で描くようなもの。だからあれはとても楽しいはずだと思いますよ。 山根 いや、楽しいのかどうか知りませんけども、加藤泰の演出の方法は、単純に絵コンテに役者をはめ込んでいくというのとは、まったく違いますね。 森崎 あの人は絵があってですね、動きは自由なんじゃないですか。 山根 そうなんですよ。演技については、もう自由にさせます。 森崎 だから、絵のイメージがあるんですよ。 山根 その点で対照的なのは鈴木清順の場合で、役者が人形かオブジェみたいに使われていますね。 森崎 しかし、ワイド・スクリーンにバチッと決まる絵ということでは、両者とも共通してますね。 山根 ええ、画面がどちらもビシッとしてるんですよ。森崎さんは、そういう絵を考えることはないんですか。 森崎 うーん……。考えないというと嘘になりますけども。のくはぼくなりにやっとるわけですよ。エー、庭の隣には、なんかこう、土管があって…と。 山根 なんかきたないですねえ(笑)、 土管だもの(笑)。。 森埼 屋根の上に鳩小屋があって、なんて、美的なことも考えてるんですよ(笑)。 でも、鳩小屋の中にキャメラがボーンと入って、網の上から見るみたいな発想はまったくないですね。チャチに感じちゃうんですよ。いや、両者の絵がっていうんじゃなくて。すばらしいと思うんですよ、お二人とも。でも、ぼくはそういうふうに絵で考えると、きっとチャチになる、と。だからそれは考えない方がいいんだ、というふうに思ってますね。 山根 もともと絵を描こうと思ってらしたくらいだから、美的構図なんてのは、普通の人よりよくわかるわけでしょう。 森崎 わかるけど、ぼくの好みがありますよね、ても、映画は絵と違うんだって、基本的には思いますよ。動いちゃうんだから。カットがあって積み重なる。あれがひとつの絵だったら、ぼくはものすごく凝りますよね、アタマからケツまで。ワン・カットの絵があるならば。それは誰にも負けないぐらい。 山根 森崎さんの映画は、一般に比べるとカットは長いようですね。 森埼 長いです。カット数が少ないですよ。 山根 それはどういうことでしょうか。 森埼 長回しがあるってことです。 なぜ長回しがあるんですか。 森埼 喜劇だということもあつてずすね、ピシャッと、美的にコンテ割りができないんですよ。すっくと立ちあがる、ポンと寄るとか、バーンと引くとか、あるでしょう。そこでなんか女の子が裸で来て、ぐーっとなったりするのは、前の日に割れないですもの。そうすると、やってみて、しかもその時々の条件で、ツルッとひっくり返ったりしますから、もう見るしかないですよね。ずつと演技をケツまで見さしていただく。それで「別に切るとこないね」 「こんな長くて持つかね」 「いや面白いから持つんじやない」 「じゃ、回そう」つてことで。ひじょうに胸を張って、長回ししてるわけじゃないんですよ(笑)。 ただ、カットを変えた場合に、三十分ぐらい時間経過してるのに、演技だけつながってるみたいにみせかけてるけども、ライティングも変わってるし、肉体的条件も変わってるって、明らかにわかることありますね。あれは耐えがたいですね。それはもう拷問に似たような、ええ……。 山根 やっぱり映画美学的にはしたくないんですね。 森崎 ああ、そういうふうにいえますね。「どうしてもカットを変えたい」と言う人いますからね。「萬屋錦之助がこうやるときは、長回しじゃないんだ、こうだ、こうこうキラリッ」と。それ、わかるんですよ、ひじょうに。楽しいんですよね、実は。 山根 だからでしょうか、森崎さんの映画には、これだよ、ここだよ、ときまるシーンがあまりありませんね。 森崎 名場面、名カット、というのがね。 山根 きまるシーンがなくて、流動的ですね。 森崎 きまりたくない。あまり美しすぎるってのがいやなんですね、なんでしょうかね。ほんとうは、やっぱりね、いやっていうほど美しく撮った方がいいのかと思うんですよ。 山根 でも、そこで思うんですが、森崎さんは女優をたいへんきれぃに撮りますね。 森崎 そうですか。嬉しいですねえ。 山根 『黒木太郎の愛と冒険』で、倍賞美津子が時津一郎の大人のおもちゃ屋に来るシーンがありますね。あそこの ショウウインドーの向こうからのぞいてる顔は、ものすごくきれいでしたよ。 森崎 うん、きれぃだつた。 山根 そんなふうにきれいな顔を撮るということは……。 森崎 しかしそれは、意図的じゃないですね、結果的にそうですね。 山根 意図的であったら、いわゆる部的になっちゃうんでしょうが、森崎映画では城由布さんが、美しいとかきれいとかいうより、いい顔に撮られているんですね。 森崎 それは嬉しいです。そのためにはこういうふうに努力してるということは、まったくないですけれども、ほんとうはそうありたいですね。特に女優さんの場合は。しかもロケーションでね。セットでは、しようがないみたいな気があるんですけど。ロケーションで、なんか空気の中で、こう髪の毛がそっと揺れるみたいな。そこいらはルルーシュのスケベに似てるっていうか……(笑)。 山根 いや、ルルーシュの方は、人工的な美というか、加工された美というか、そういう感じでしょう。やたらスローモーションにするとか。 森崎 うん、スローモーションで走りゃね、逆光で、美しい花でもありゃ、みんなきれいですよ。 山根 森崎さんは、そういうテクニツクでもつて、きれいに撮ってるんじゃないわけでしょう。じゃあ、構図が美しいのかというと、別に普通だと思うんですよ。 森崎 ぼくはあんまり(キヤメラを)のぞきませんから。後でいつも後悔するんですけども。のぞかないかんなあと思うんですけどね、のぞいてる気持の余裕がなくて。だから構図なんてのはもう……。ときたま、こういう構図にしたいという自分のイメージがあっても、前のはのぞいてない、後のはのぞいてない、それだけぼくがのぞくと、カタカタッとなってしまう。だからもう、のぞかない方がつながっちゃうっててこと、ありますね。 山根 一部分だけのぞいたとすると、そこずリズムが崩れるんですね。 森崎 ええ、カメラマンが自分の生理でやつてるときに、監督がのぞいて、 「こうだろう、この辺でどお?」なんて。やっぱり、ちょっと動かすことで微妙に違ってくるんじゃないでしょうかねえ。 だから、のぞくんなら全部のぞいてやらなきゃいけないんでしょうけど、のぞいているあいだ、俳優さんの生理と離れてるんですよね。ひじょうにクールに、もう、つめたーく、なんだかマウスを見てる医者のような感じになりますからね。まったたく切れちゃうんですよ。それはもう、みごとに違うんですよね。こつちは向こうの血管の血の流れと、自分の血の流れをいつしょにしたいなんて思ってるわけじゃないですか。それがバーンと別世界になっちゃつて、だから、よくないんじゃないですかね。 山根 そんなふうに監督である森崎さんの呼吸と役者さんの呼吸とが呼応してる感じが、役者さんを生き生きさせるんですね。だから倍賞美津子の顔がきれいといつたときに、美人をいいアングルで撮って、陰影がよくて美しいという ことじゃなくて、もっともいい顔をしているってことなんですね。 森崎 それは嬉しいですねえ。ぼくは『陽炎座』の本にも書いたけども、加賀まりこさんが、清順映画に出てると監督のカットじりのハイがかかりたくない、と言ったんですね。それはわかりますもん、そういう演技だなあ、加賀まりこさんの演技は。それは、いっぺん言われてみたいセリフですね(笑)。 「監督、よけいな声かけないでよ」と。 「ずっとやらせといてよ」って。それはもうすばらしいことですね。 山根 役者が役を生きてしまうことのすばらしさですね。役や監督の意図を理解したうえで演じる、というのではなくて。 森崎 理解して演ずるというのは、解釈するわけでしょう。俺が理解したのを、お前らに見せるために解釈してわかりやすくしてんだよ、と。その理知的操作ってのは美とは無縁ですね。じゃまですね。 山根 森崎映画では、役者さんたちが役を生きることを楽しんでいる感じがあって、それが独特の美になるんでしょうね。 森崎 たまに、「そこのところ、ちょっとこうやったほうがいいなじゃないか」なんて、言ってみたりするんですよ。必ずよくないですね。だから黒沢さんなんかは、あなまり言わずに、「もう少しやわらかくやって」とか言うそうですね。そうすると見違えるようになるという。そういうことなんじゃないでしょうかね。 |
| (その4 へ行く) III エトスを美的に娯楽的に刺激したい 1983年10月2日 |