ふる里の四季

#山の雑学・転ばぬ先の杖/登山靴選び
たかが登山靴・されど登山靴・ここちよく・足が痛くならない靴選びとは 安全を選ぶことに通じる。
ふじわらみちひろ体験備忘録
山の安全雑学・痛い目に合わないための秘策とは??。安全は足元から始まる。
登山靴は 山中において体の一部となる。
ビブラムソ-ル
#痛い目にあわないための登山靴の選び方・・理屈ぬきの体験版
軽量タイプの登山靴・気になる靴選び
①目的に合わせて使い分けする。。一般的な話として ソ-ルの硬さや形状で使い分けるのがよい。アウトソ-ルがポイント(靴底)。
底の薄型ウレタンタイプは、フィット感もよく歩きよいが劣化も早い。一年ごとに底のヒビ割れをチェックする。底面のフラットタイプは スパッツの装着に難がある。
ゴム製は 強度重視で 履き心地は硬いが耐久性は高い。
日帰りハイクには 歩きやすいウレタン薄底タイプが種類も多くお勧め。履きなれたスニ-カ-でも十分間にあう
靴選びも好みがある(ファッションの一つ)。一言でいうと自分の好みに合う靴を選ぶのが基本。
なぜなら 身に着ける衣服と同じで 自分の足を保護する役目を持つからです。
軽くて歩きよいタイプは・ロ-カット/スニ-カ-タイプが一番。小石の侵入防止にスパッツを用意する。
②サイズと靴底の話
経験的にサイズは一段大きめを選ぶ。ピッタシサイズは、長時間歩くうちに足に圧迫を感じるようになる。特に下りでつま先(足の指先)を痛めやすい。圧迫感などの調整は、ソックスや底敷(インソ-ル)で合わせるとよい。靴ひもの締め具合も重要です。インソ-ルのタイプも多種ある。購入時に装着インソ-ルが厚いタイプは 差し替え調整が比較的楽。
③ウレタン底も改良されてスリップ防止と軽さが特徴。靴は安全道具の一つ(消耗品)。
④ゴアテックスは 表面の撥水性がなくなると性能は極端に低下する。ゴアは万能と思われやすいが 撥水性能の経年劣化は防げない
(経年劣化に注意))。
新しい登山靴の注意点・まず登山前にやる事。試し歩きをする。場所は河原や裏山などの不整地がお勧めです。登り下りの不整地を歩くことで 足首関節周りの当たり加減や圧迫感がよくわかる。日常的に使用して履き加減をみる。
足裏のクッション感覚は個人差があるので 自分で確かめるのが無難。
例えば 地下足袋のような感覚が良いという人もあれば 分厚いアウトソ-ルが良いという場合もある。アウトソ-ルとは
蛇足-- 全体的に造りの硬い靴ほど足首に負担がかかる。最初から硬い靴を選ばない事。登山道具も時代と共に改良され新素材の製品も多い。上手に使えば快適な登山も可能。。
お気に入りの靴なら程度にもよるが修理(ソ-ル張替え)も検討するとよい。
靴ずれ対策・念のために カットバンを数枚用意しておくと安心です。
私の場合・1970年後半から長年革製のものを使用してきた。当時は革靴が主流でロ-バ(独製)のチベッタなどは実に丈夫で、ビブラム底も張りかえたりしてきた。しだいに内張りがすり切れて靴ヅレでついにあきらめていた。が後に修理し 今でも現役(時折革の感触を楽しんでいる)。
登山初期(昭和40年代.1960年後半)の頃 革製の軽い登山靴をはいた事もある。大山を経て大休峠から甲ガ山を越えた下りで片方の底がはがれてしまいタオルでしばり船上山まで下山した記憶がある。靴選びは ザック重量や山行回数等に合わせて選ぶことが大事です。その後、当時流行のナイロン製のキャラバンシュ-ズも試してみた。。これは底の縫い目がすぐに破れてしまった。靴は身体を支えるとともに地面と直接向き合う物なので 目的に合わないとケガにつながる。。足首の保護には 足首用サポ-タ-が使いよい。捻挫等に不安があるばあいは タイプのちがうものを二枚重ねに使うと効果的。
足首の筋トレ
カカト&骨ホルモンで活力をつける。
足首&カカト運動は アキレスけん・クルブシ・脳と連動する。日常的にできる動作なのでおすすめです。
蛇足---体力・筋力づくりは やりすぎに注意。違和感を感じたら休息の時期と知るべし(長続きの秘訣)。
長年(1970年代~)、ヘビ-タイプの革登山靴を使用してきた。ロ-バの他に京都のムラカミでオ-ダ-注文したこともある。ロ-バと交互にはいてきた経緯がある。
ロ-バは カカトの内張りがほころんで靴ズレしだしたので履くのをあきらめていた。。 最近ネットで革登山靴修理のペ-ジを見て 35年以上経つ靴の修理を依頼した。 修理可能と聞いたので 念願の修理に出した(07/10)。。一ケ月ほどで待望のロ-バ靴修理完了(07/11)。早速、ミンクオイルと防水オイルで丹念に磨きをかける。。ビブラムソ-ルは二回目の交換。靴も履きすぎると型崩れはいなめない。
登山靴修理「ナカダ」商会はこちら。
京都・ムラカミの登山靴・古きよき時代の逸品。
ムラカミ登山靴は ロ-バの予備で履く。ロ-バの底が減り始めた時点でオーダ-購入し30年くらい使用。。最近流行のゴア登山靴購入まで常用。底減りと内張り破れで修理(08/11)に出す。。ビブラム底張替えと内張り補強済み。京都ムラカミは時代(革靴全盛)の役目を終え07/春に閉店と聞く。。最近は資源の有効利用もあいまって再生品の時代になり昔の道具がよみがえるようになる。革靴は履くほどに足になじみ愛着ある趣味の靴として価値ある存在。
革の登山靴は水に弱いのが難点、特に残雪期は不向きだが ワックスで磨いた革靴は愛着も出る。状況をふまえながら使用すると楽しさ倍増。。数日前から靴にワックスかけて準備するのも登山の楽しみの一つ。。重さは気にならないが ただ履きなれないと足裏が靴に負けるようになる。。
昨年の夏(02・夏)、始めて流行のゴア軽量靴を購入して無雪期用にはいている。2年もするとサイドのラバ-にヘタリが見れる。接着が離れ始めると限界か。4年目で新しく買い換えることにした(底の薄いウレタン靴は軽くて歩きやすいが3年くらいで底にヒビ割れが出て限界に。軟い薄底ほど劣化(2年)が早い)。。ウレタンは使用と関係なく経年劣化が早いなどの難点がある。素材の特徴を知ることも大切です。ゴアテックスは 油や汚れに弱い特徴があることは良く知られている。
近年 健康思考の高まりとともに 遊歩道やロ-ドウォーキングが盛んだ。よく整備されたハイキングコ-スでは はきなれたスニ-カ-がおすすめ。いわゆるウォ-キング靴が歩きやすい。普段から履きなれた靴が最適・最適です
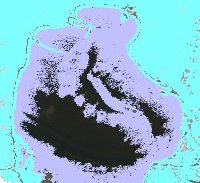 。
。
健康増進にお勧めの歩き方とは
足首・ふくらはぎのケア・自分でやれるふくらはぎのマッサ-ジ・自分で出来るストレッチ
歩きに少しだけ負荷をかけるのが 効果的。最近、インタ-バル歩行が注目されてきた。陸上競技などでは かなり昔(1930年代)から知られる練習法の一つ。脈拍120回/分をめやすに 早歩き・スロ-歩きを体力に合わせて繰り返す。健康ウォ-キングでも注目される歩行方の一つ。次第にレベルアップが可能。。
最近は 認知症予防にウォ-キングが注目されれいる。歩くことは
足の握力・・足指とバランス参考までに。
登山前と登山後の肩周りや足腰・股関節のケアもお忘れなく。両肩や足首のグルグル回しなどは簡単にできる。
股関節周辺だとテニスボ-ルをグルグルと転がしまわす。簡単で効果がある。ふくらはぎは 自分でマッサ-ジできる。ベッドの上で片方のかかとでふくらはぎを押さえるようにもむとより効果的。足首アキレスケンからヒザの裏までもみあげるのがポイント。
捻挫の予防・ケア
ふくらはぎは第二の心臓とまでいわれるほど重要な筋肉群。しこりを残さないよう日ごろのケアが大切。自分でやれるのでいろいろ試してみましょう。近年は 下半身の保護やファションもかねた「ストレッチパンツ」も多種ある。目的に合わせて色々試してみると良い。
蛇足
ヘルメット着用・ためして納得
火山・落石あるなしに関わらず・使い慣れ・かぶりなれると重宝です。頭部の保護以外に まず・風に強い。次に・ヤブなどのブッシュ帯歩きに強い。その他・ヘルメットの下にタオルをはさむと 日よけや汗拭きに便利・虫よけネットも同じく・・形状によっては水バケツにもなる。ETC。。
頭部の保護でヘルメットに勝るものはない。アウトドアにおける事故・ケガに対して 脳の損傷を防ぐ唯一の防具と知るべし。+サングラス(薄色系)も用意する。自分の身は自分で守る。。。
緊急用に粘着テ-プ(布テープ・小巻き)を持参する。止血や擦り傷にも使えるが、靴底が脱落した時に一時的ではあるが、靴底の固定に使うとこともできる。
Copy © TanesaRock