
#だいせん花特選
だいせんのお花たち
#大山の花・大山(だいせん)の
|

ダイセンミツバツツジ
#大山の花はクガイソウが広く知られる。
|
 サラシナショウマ |
 フウロソウ |
 ホソバノヤマハアコ |
 ダイモンジソウ |
 クガイソウ |
 ダイセンヒョウタンボク |
 サカハチチョウ |
 ダイセンオダマキ |
 ヤマジノホトトギス |
 アサギマダラ |
 オオバギボシ |
 リンドウ |
#夏(7月中から8月/中)の花としてオオバギボウシ、
|
 ダイセンミツバツツジ |
 ミヤマカタバミ |
 クロモジ |
 ギンリョウソウ |
 ユキザサ |
 ミヤマハタザオ |
 ツガザクラ |
 ホタルブクロ |
 クサボタン |
 キュウシュウコゴメグサ |
 シシウド |
 ソバナ |
 ダイセンクワガタ |
 ホツツジ |
 ヤマアジサイ |
 ツガザクラ(秋) |
 お花畑・九合目付近 |
 お花畑・ユ−トピア付近 |
コブシとタムシバ(モクレン科)
|
 コブシの花 |
 タムシバの花 |

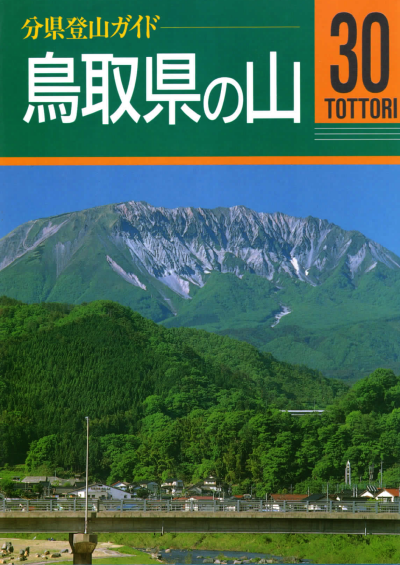
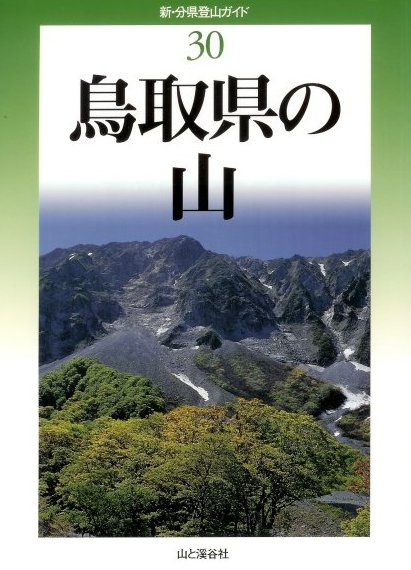
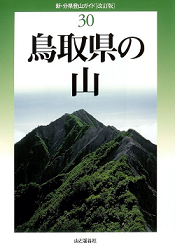
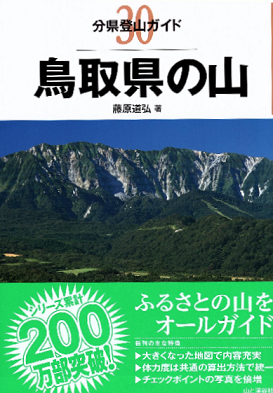
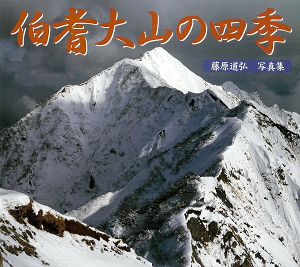
Copy© Tanesarock





