

#鳥取県の山・大山(だいせん)は 別名・#伯耆大山(ほおきだいせん)、 伯耆富士とも呼ばれる。鳥取県の中部から西部地域は かつて「伯耆の国」と呼ばれた時代もあった。大山(だいせん)は 他県の大山(おおやま)と混同されることがある。 ここで伯耆大山とするのは ルビの混同を避ける意味合いもあります。その昔 9世紀(平安時代)には 伯耆国大山(ほおきのくにだいせん)ともよばれていたらしい。昔は 大神山(おおがみやま)とも呼ばれ山岳信仰の霊場として名高い。中でも大山寺の僧兵は3000人規模ともいわれ地領内外をかっ歩していたらしい。開山は古く 養老年間までさかのぼる。大山は 数200万年前の火山で出来た独立峰。外輪山は 船上山まで続く。火砕流は日本海まで延び 海岸に近い名和地域にその痕跡を見る。特徴として 火山砕石の風化が進み崩落が激しい。1980年代に入り稜線の崩落で縦走登山が困難となる。。一方、 山頂からの眺望が良いことから人気ある山として知られている。大山・隠岐国立公園の中心地。夏場は 学校登山や観光ツア−でにぎあう。
点在する峰(ピ−ク)の名称は #山岳信仰に由来する箇所地名が多い。。山頂のある弥山・天狗ガ峰・三鈷峰や行者谷などはその代表。大山寺周辺では 寂静山や宝珠山。僧侶の名・豪円山などがある。。
登山基地となる大山寺には 天台宗・大山寺や大神山神社(奥の院)がある。ちなみに大山の最高地点(国土地理院)は「剣ガ峰」1729m。山頂登山は「弥山」1709mをさす。
#鳥取県の山・大山(だいせん)・#四季の特徴。。
春は 3月の雪解けから始まる。3月下旬には スキ−場も終る。登山では残雪期に入りますが 3月中旬頃まで雪の降ることもあり冬山の装備で登山することになる。夏山登山道では六合目から上はまだ冬の景色です。。この時期は凍結でスリップしやすい時期なので要注意。天気の良い日などは 写真ポイントでもある 六合目付近から北壁の絶景が楽しめる。晴天だと登山者も多く足跡をたどって山頂まで上れるが足元はアイゼンも必要。特に下りの八合目付近は要注意。スリップで身体が横に寝てしまうと止める手立てがありません。。
元谷周辺の早朝などは 雪面も硬く氷化してどこでも歩ける時間帯もある。。
宝珠尾根では 雪溶けとともに雪面は不安定になる。夏とは別のル−トを取ることもあり 慎重を要する。。特に上宝珠周辺は雪崩の注意もいる。壁周辺や沢筋に入ると落石もある。残雪上の落石は 無音で巨石が落ちてくる。周囲の地形に目配りも大切です。
山歩きをすると「五感」が磨かれるとも言われる。「五感」は危険予知にも大いに関係する事と思っている。現代風に言うと「センサ−」である。感度は高レベルに越したことはない。
4月以降は天候しだいで登山は快適な季節を迎えます。。4月中旬を過ぎると山頂付近も芽生えが始まり 下旬には一足早くダイセンヒョウタンボクの花が咲く頃となる。
 5月以降新緑の季節。大山でサンカヨウの花が咲くのは 5月中旬頃です。サンカヨウはユ−トピア周辺のガレ場でも見れますが 大群落は鳥越峠周辺がビュ−ポイント。5/20前後が写真や観賞のねらい目でしょう。谷間の湿地帯では ブユの発生も見られるので 防虫ネットが重宝です。。
5月以降新緑の季節。大山でサンカヨウの花が咲くのは 5月中旬頃です。サンカヨウはユ−トピア周辺のガレ場でも見れますが 大群落は鳥越峠周辺がビュ−ポイント。5/20前後が写真や観賞のねらい目でしょう。谷間の湿地帯では ブユの発生も見られるので 防虫ネットが重宝です。。
ブナの新緑は 葉の広がる頃の透明感がねらい目の一つ。。葉の広がり始める時期を見届けて撮るとGOOD。。5/中旬には ダイセンミツバツツジも開花する。。花数の多い大株がねらい目。
ブナは自分の写真ポイントを作るとおもしろい。樹木も人間と同じで人相ならぬ樹相がある。。お気に入りの樹相に当たると恋人を探し当てたようなもの。。マイポイントは季節を変えて丹念に撮り続けるのがコツ。。。。
5月下旬ともなると、湿気のある木谷のブナ林などで風のない日は ブユの発生も多い。虫除け対策も忘れずに。。
6月に入るといよいよ#夏の季節です。。6月上旬までは ブナの緑も落ち着いてきて重厚な感じになってきます。。モスグリ−ンは撮るのに難しい素材だが光を上手にコントロ−ルするとおもしろくなる。。

ブナの大木は 夏山道4合目・元谷・下〜中宝珠・大休峠周辺に多く見られる。四季の変化はそれぞれに趣きがある。
登山道では山野草も咲き野草登山も可能。。この時期は梅雨がいろいろと影響してくる。。まず雨の準備。登山や写真も天気で決まりますので難しさも出てくる。
夏山の午後は 雷雨も多い。。そこで最小限の雨具が必要。。一番手軽な雨具としてポンチュがある。。夏場はこれ一枚でも足りますが 他に薄手のオバ−ズボンと 念のためにウインドブレ−カがあれば十分。。
夏の大山で特徴的なものとして雲海がある。。周辺の山々は島に見立てるが 大山をとりまく山は 高くて烏ガ山くらいですから一面雲海だけになることもある。。
雲海を上手にあしらうと雰囲気のある写真も可能です。。雲海だけだと単調になる。写真集を参考にしてみて下さい。。デジカメはレンズの角度や光の角度で色調が変化するのでそのつどビュ−確認がいる。。青空を逆光で撮る景色はデジカメの場合大変に難しい(逆光の空や雲はフィルムが有利)。山の上では 二度目はありません。
 梅雨明けとともに7月下旬〜8月上旬にかけては お花畑の季節です。ポイントは 山頂周辺・三鈷峰周辺。あらかじめポイントを絞っておくと撮りやすくなる。
梅雨明けとともに7月下旬〜8月上旬にかけては お花畑の季節です。ポイントは 山頂周辺・三鈷峰周辺。あらかじめポイントを絞っておくと撮りやすくなる。
山はお盆を過ぎると秋の気配。。9月は写真も一段落して少し休息も必要な季節。。写真や登山具の整理や整備にあてるとよい。
登山の合間は 体力づくりも重要です。やりすぎない程度にウオ−キング+ジョギングなども取り入れてみましょう。
#大山(だいせん)の秋・ 10月中旬以降〜11月中旬頃まで。大山では 10月中旬から山頂・ユ−トピア周辺で紅葉が始まる。三鈷峰周辺では20日前後がピ−クになる。。弥山山頂では草紅葉が美しい季節。

山の秋は短い。どこを撮るにしてもポイントを絞る必要がある。。天気を見ながら計画をたてましょう。。ポイントは大きく絞ると鳥越峠・三鈷峰・弥山山頂・元谷と南壁側の沢筋になります。。11月上旬に入ると大山寺周辺もねらい目の一つでブナやクロモジ・カエデが美しい。大山滝周辺は 11月中旬頃。。大山の紅葉は 日当たりの良い南大山から大山寺に向けて色の景色が移動し一週間単位で稜線からふもとに向かう。。
秋の特徴は 新緑とちがいチャンスの期間が短いこと。。ポイントを欲張ると失敗の元になる。天気を読みながら手際よく行動する季節。。晩秋などは一荒れで紅葉が終わることもしばしある。。ガスや小雨の紅葉もねらい目ですが防水の準備必要、日陰では気温も下がるので防寒対策も忘れずに(薄手の手袋は使いよい)。
 大山の本格的な冬は12月中旬以降。11月は条件にもよるが稜線の霧氷もねらい目の一つ(写真集参考)。。初雪などのうっすらとした雪景色も悪くはないがコントラストが強く表情が出しにくい。12月中・下旬の降雪を狙うとエッジの効いた写真も可能(写真集参考・表紙)。。
大山の本格的な冬は12月中旬以降。11月は条件にもよるが稜線の霧氷もねらい目の一つ(写真集参考)。。初雪などのうっすらとした雪景色も悪くはないがコントラストが強く表情が出しにくい。12月中・下旬の降雪を狙うとエッジの効いた写真も可能(写真集参考・表紙)。。
冬の雪景色は 弥山山頂がビュ−ポイントの一つ。。ガスの切れ間の稜線は見逃せない。。宝珠尾根から見る北壁は逆光でしかもキャチライトが少ない季節(写真集参考・北壁黎明)。太陽が東に移動しかつ冬ギリギリの2月中・下旬まで待つことになる。。冬の山頂や北壁の写真は 天気や太陽の動きを読むのが決め手。。外すと次年まで持ち越しに。。宝珠尾根だと2月中・下の晴天がねらい目。雪のブナ林は 4・5合目周辺がベストポイント。
雪の宝珠尾根は魅力的で何度となくトライしてきた。 このコ−スは雪崩の危険もあるので状況判断が難しい。。ポイントとしてはおもしろいが危険もある場所。。特に中宝珠手前で冬場は大きな雪庇(せっぴ)が張り出す場所もある。
昔のことだが参考までに。
一度だけ冬の中宝珠で雪庇崩壊に遭遇した経験がある。足元で大きな雪庇が切れると「スパッ−」切り裂き音がする。。安全か否かは意外と足元にある。樹林帯といえども強風が吹きつける場所には 大小に関わらず「雪庇」ができやすい。降雪地帯だと雪の積もった民家の屋根下で雪の張り出しが見てとれる。危険予知とは 登山のみならず身近な行動の中から始まるのです。撮影中に 三脚の雲台で指を挟まる。そのためには薄手の手袋も必要ETC。
 #大山(だいせん)・#冬山と写真 大山の撮影で冬は欠かせません。が天気の良い日は少なく難しい一面もあります。大山の本格的な冬は12月中旬以降。11月は条件にもよるが稜線の霧氷もねらい目の一つ。。初雪などのうっすらとした雪景色も悪くはないがコントラストが強く表情が出しにくい。12月中・下旬の降雪を狙うとエッジの効いた写真も可能。
#大山(だいせん)・#冬山と写真 大山の撮影で冬は欠かせません。が天気の良い日は少なく難しい一面もあります。大山の本格的な冬は12月中旬以降。11月は条件にもよるが稜線の霧氷もねらい目の一つ。。初雪などのうっすらとした雪景色も悪くはないがコントラストが強く表情が出しにくい。12月中・下旬の降雪を狙うとエッジの効いた写真も可能。
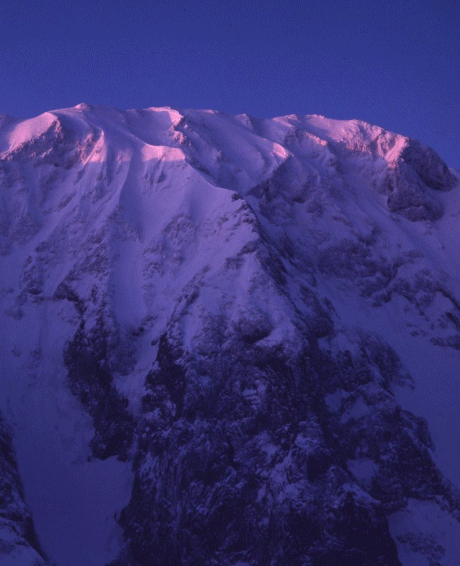 冬の雪景色は 弥山山頂がビュ−ポイントの一つ。。ガスの切れ間の稜線は見逃せない。。宝珠尾根から見る北壁は逆光でしかもキャッチライトが少ない季節(写真集参考・北壁黎明)。太陽が南から東に移動し かつ冬期ギリギリの2月中・下旬まで待つことになる。。冬の山頂や北壁の写真は 天気や太陽の動きを読むのが決め手。。外すと次年まで持ち越しに。。冬の山頂付近の撮影チャンスは限定的でチャンスは少ない。天気予報と相談しながら一発を狙う。宝珠尾根だと2月中・下の晴天がねらい目。雪のブナ林はポイントが限定される。
冬の雪景色は 弥山山頂がビュ−ポイントの一つ。。ガスの切れ間の稜線は見逃せない。。宝珠尾根から見る北壁は逆光でしかもキャッチライトが少ない季節(写真集参考・北壁黎明)。太陽が南から東に移動し かつ冬期ギリギリの2月中・下旬まで待つことになる。。冬の山頂や北壁の写真は 天気や太陽の動きを読むのが決め手。。外すと次年まで持ち越しに。。冬の山頂付近の撮影チャンスは限定的でチャンスは少ない。天気予報と相談しながら一発を狙う。宝珠尾根だと2月中・下の晴天がねらい目。雪のブナ林はポイントが限定される。
積雪期・ 6合目から7合目周辺が北壁のベストポイント。ブナ林は3合目から4合目付近。
冬期の晴れた日は風も強い。防寒・風防対策も大切です。手袋は薄手・厚手あると重宝です。
冬は寒さや降雪で事故も起きやすい。雪の宝珠尾根は魅力的だが せっぴの踏み外しや雪崩の危険もあるので状況判断が難しい。難しい一面もあるがそれが又魅力でもある。。
山の写真は お天気しだい・体力次第・生活環境しだい ということになる。したがって 今年だめなら 来年がある。大山は 海に面した独立峰であるがゆえに天気変化が激しい。 したがって 気長に構えることも大切です。
何故、大山・だいせんなのか?。一言で言うと身近に山があった。単純な話だが登るたびに新らたな「発見」がある。だからつながる。発見の仕方は個々にちがう。個々の違いを感性と言うらしい。風景写真は、山に限らず幅広く撮り歩くと長続きする(経験的に)。草花のクロ−ズアップも面白い。
Copy © Tanesarock