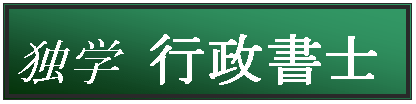
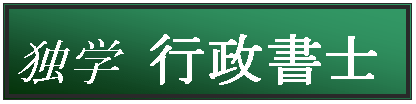
独学・学習方法
独学で、全く初めての方は参考にしてみて下さい。
★始めに用意するものなど★
★副教材について★
★管理人が使用した教材★
★管理人がすすめる学習方法★
★模擬試験は必ず受けよう★
★スランプ脱出方法★
始めに用意するものなど |
基本書・六法・過去問題集。まずは、この3つを最低用意してください。 |
| ●基本書 |
|---|
| 基本書はご自分にあったものを選択 よく基本書はどれがいいのですか?という質問を見受けますが、個人的にはどれでもいい、すなわち、ご自分が使いやすいものを購入すればいいのではないでしょうか。図解入りのものがいいとか、漢字に、ひらがながうってあるのがいいとか、1冊にまとめられたもの、あるいは何冊かに分けてあるものなど、いろいろな選択肢があると思います。 最近は、行政書士資格が話題になってきたせいか、その種類も増えてきているようです。 週間住宅新聞社の 2013年版うかるぞ行政書士 

 は、コンパクトながら法令、一般とも載っており、まずまずの基本書ではないでしょうか。民法、商法、地方自治法が、やや手薄な感じがありますが、条文の多い法律であり、問題集の解説と六法との確認で十分対応はできると思います。
は、コンパクトながら法令、一般とも載っており、まずまずの基本書ではないでしょうか。民法、商法、地方自治法が、やや手薄な感じがありますが、条文の多い法律であり、問題集の解説と六法との確認で十分対応はできると思います。試験内容の全てを網羅している基本書はないと思うので、必要に応じ 口語 民法 
 や
はじめて学ぶプロゼミ行政法など、自分の弱点を補う教材を、その都度、購入していくことも必要だと思います。 や
はじめて学ぶプロゼミ行政法など、自分の弱点を補う教材を、その都度、購入していくことも必要だと思います。 |
| ●六法 |
| 六法は、民法がひらがなのもの 六法は、民法などカタカナの条文がひらかなに書き換えられているものがいいと思います。 特に初学者にとっては、あのカタカナ条文は見るだけでもいやになりますよね。 「行政書士受験用」と書いてあるのものなら、大体、ひらがな表示になっているようです。 (平成17年の民法改正で、カタカナ表記ではなく、全て口語体になりました。) あと、書き込みができるスペースがあるものが、使い勝手はいいと思います。 模範六法や小六法よりも、やはり行政書士試験に関係のある法律だけを掲載している六法のほうが便利だと思います。 東京法経学院の行政書士必勝六法 
 や、東京法令の平成25年対応版
行政書士受験六法 や、東京法令の平成25年対応版
行政書士受験六法
  が評判がいいようです。 が評判がいいようです。私は、東京法経学院の行政書士必勝六法を使いましたが、ご自分の目で実際に確かめて購入して下さい。私が受験した時とは編集方法も変わっていると思います。 |
| ●過去問題集 |
| 解説に必ず根拠条文の載っているもの 過去問題集も基本書と同様、ご自分が使いやすいものを選んでください。 問題の載っているページに解説があるもの。次ページに解説があるもの。巻末に解説があるものなど、いろいろあります。 ただ、いずれの場合も、解答、解説に根拠条文が必ず載っているものを選んでください。 たまに見受けるのですが、解説も根拠条文もなしに「その通り」みたいな解答がある場合があります。 このような表現が多用されている問題集は避けて下さい。 また、10年分の試験が年度別に載っている過去問題集よりも、科目別に過去問を載せている問題集の方が私はいいと思います。 一度に全ての科目を同時に解答する力は、本試験当日にあればいいのです。 それよりも、科目別に単元を区切りながら、繰り返し繰り返し解く方が、実力が着実につくと思うからです。 東京法経学院の行政書士過去問マスターDX〈1〉業務法令・上〈2013年版〉 
 、行政書士過去問マスターDX〈2〉業務法令(下)・一般知識〈2013年版〉
、行政書士過去問マスターDX〈2〉業務法令(下)・一般知識〈2013年版〉

 は、受験生が総じて高い評価をしている過去問題集です。 は、受験生が総じて高い評価をしている過去問題集です。私は、法学書院の科目別問題集 行政書士重要過去問 法令編・一般教養編を使用しました。 (現在は、行政書士過去問セレクト〈2013年版〉  になっているようです)
になっているようです)これも、なかなかよい過去問題集だと思います。 問題集は、年度別のものと科目別のものがあるので注意して下さい。 お勧めは、科目別の方です。 |
副教材について |
学習の進展具合にあわせて購入 |
| ●副教材など |
| 一通りの学習がすんでからでも遅くない 副教材は、自分の弱点を補うために、又は、基本書に載っていなかったことをさらに補強するためのものです。 ということは、全く初めて学習するのなら始めに買わないほうがいい場合もあります。 なぜなら、全く初めての場合、自分の得意なところ、苦手なところ、理解できないところ等がわからないです。 そして、基本書で何度読み返してもわからない場合などに購入するべきだと思います。 副教材と基本書との出版社を変えることで、別のを見方ができ理解が深まるケースもあるでしょう。 いずれにせよ、一度、基本書を読み、過去問題集を解いてから購入しても遅くはないと思います。 |
| ●予想問題集 |
| 過去問題集を3回解いてからにしたほうがいい 予想問題集を解くことも、行政書士試験合格には欠かせません。 しかし、多くの予想問題集はかなり問題の難易度が高くなっています。言い方を変えれば、重箱の隅をつつくような問題が多いのも事実です。 もちろん、本試験においても、重箱の隅をつつくような問題は出ていますし、今後もこの傾向は続くような気もします。 ところが、全くの初学者の方が、このような問題に早くから取り組むことは、かえって混乱を招き、基本を押さえることの弊害にならないかと思うのです。 多くの過去問題集は、基本事項を押さえるために過去の良問を選択し掲載しています。 私は、早い段階で予想問題集に取り組まず、過去問題集を3回ほど解いてから取りかかった方がいいと思います。 |
| 模擬試験の受験校以外の出版社もの。できれば2冊以上の予想問題集 では、実際に予想問題集を購入する場合、どういう点に気をつけるか。 それは、ズバリ出版社を代えて2冊以上を購入することをお勧めします。 そして、模擬試験を受ける予定があるのなら、その受験予定の予備校以外の予想問題集がベストと思います。 なぜなら、本試験では、どのような角度で問題を出すか、それは全く不明です。 よく、予備校の広告に「また、また的中!予想問題」などとありますが、実際の受験生の感想は、「えっ、どこが的中なの?」といった具合です。 そのままズバリ的中する問題など作れません。それより、いろいろなタイプの問題をいかに数多く解くかに重点をおいて下さい。 その意味で、予想問題集購入の際、出版社を代えるといういことは、お分かりいただけると思いますが、ではなぜ模試の受験予定の予備校のものは避けるのか? 私も、ある学校の模試を受けましたが、驚いたことに論述試験の題材(現在は、論述は廃止されています)は、その予備校の出版している予想問題集で出題されているものと同一でした。 模試を受けたあと書店で、それに気づき非常に驚きました。 これから私の予測ですが、予備校の予想問題集と模試の内容は非常に似ていると判断できます。 同じタイプの問題を解いているのだから、模擬試験で高得点が取れるのは当たり前で、極端な言い方をすれば購入した予想問題集と同じ予備校の模試は受けないほうがいいです。 もしも、ある予備校が非常に気に入り、そこの教材、模試を利用したとしても、必ず他社の予想問題集を別に購入してください。 繰り返しますが、そのままズバリ的中する問題は絶対に作れません。 2~3社の予想問題集と、別の予備校主催の模試。 こうすることによって、いろいろな角度からの問に答えることが出来る応用力が身につくと思います。 |
管理人が使用した教材一覧 |
| カテゴリー | タイトル | 出版社名 | 評価 |
| 基本書 | 合格うかるぞ行政書士 | 週刊住宅新聞社 | AA |
| 過去問題集 | 行政書士過去問350題(法令編) | 法学書院 | AAA |
| 行政書士過去問300題(一般教養編) | 法学書院 | A | |
| 六法 | 行政書士必勝六法 | 東京法経学院出版 | B |
| 参考書 | 行政書士合格ノートⅠ 業務法令編 | 東京法経学院出版 | A |
| 行政書士合格ノートⅡ 一般教養・論述編 | 東京法経学院出版 | A | |
| 電車でおぼえる行政書士Ⅰ(憲法・地方自治法編) | 大栄出版 | B | |
| 電車でおぼえる行政書士Ⅱ(民法・行政書士法編) | 大栄出版 | B | |
| 電車でおぼえる行政書士Ⅲ(行政法・その他の法律編) | 大栄出版 | B | |
| 電車でおぼえる行政書士Ⅳ(一般常識編) | 大栄出版 | A | |
| 電車でおぼえる行政書士 直前総チェック | 大栄出版 | A | |
| 電車でおぼえる行政書士 記述式対策 | 大栄出版 | AA | |
| 予想問題集 | パワーアップ行政書士予想問題集Ⅰ(業務法令) | 東京法経学院出版 | AAA |
| パワーアップ行政書士予想問題集Ⅰ(一般教養) | 東京法経学院出版 | A | |
| 2000行政書士合格レベル問題法令編 | 大栄出版 | AAA | |
| 2000行政書士合格レベル問題一般教養編 | 大栄出版 | AA |
模擬試験は必ず受けよう! |
独学でも予備校等の模擬試験には参加 |
| ●10月に照準を合わす |
| 試験日を11月中旬と思わないこと 私は独学でも、予備校等が主催する公開模擬試験は必ず受けるべきだと思います。 理由の一つは、独学が故に自分自身の実力が相対的にみてどの程度なのかは、なかなか判断がつきにくいからです。 予備校の主催する模擬試験では1000人近く受験するものもあり、他流試合を経験することにより、試験に対する慣れ、自分の実力がどの程度の判断がつきます。 多くは10月中に実施されるので、11月中旬の本試験に向け、弱点分析、そしてモチベーションを高めることもできるでしょう。 マンネリを打破するためにも、10月の模擬試験に向け学習を進めてください。 そして、繰り返しますが出来れば自分が使っている予想問題集とは別の予備校の模試を受けることを私は勧めます。 |
スランプ脱出方法 |
100%完璧な人はいない |
| ●いつ勉強するのか? |
| 日々の学習時間は同じにする 独学での学習の場合、自己管理ができるかどうかにかかっています。社会人の方は仕事が終わって夜の学習になるでしょうし、主婦や学生さんは昼間に時間が取れるかもしれません。あるいは、通勤・通学時間を利用される方もいるでしょう。 大切なことは、日々、学習する時間をできるだけ同じにすることです。今日は夜して、明日は昼、あさっては・・・となると人間どうしても弱いので、ついつい勉強から逃げてしまいます。 学習リズムをつくることにより、独学でのデメリット、すなわち自己管理の難しさを克服してください。 |
| ●どうしても勉強したくない時 |
| イライラは学習することで止まる 勉強を始めて何ヶ月がすると、非常に精神状態が不安定になるときがあります。受験に対する不安、孤独感、嫌悪感。「こんなことして、何になるんだ!」ひどい時には、「行政書士なんて資格とっても仕方ない」なんて思い始めることもあるかもしれません。 しかし、これは、誰もが経験することです。 試験範囲の広さ、迫ってくる試験日など、様々な要因が受験生の気持ちを不安定にさせます。 そんな時、騙されたと思って30分ほど問題集を解いてみて下さい。基本書を読むのではなく、問題集を解くのです。気持ちが落ち着くこともあります。 勉強に集中しているときは、余計なことは考えないことが多いです。 |
| ●それでも勉強に集中できないとき |
| 思い切って土・日は完全OFF どうしても勉強をしたくない、集中できない時期があれば、思い切って土・日は完全OFFにしてみるのも一つの方法です。私も3回目の受験の時は、8月までは土・日は完全にOFFにしました。どうしても集中できなかったのです。 9月になると模試や本試験が近くなるので自然に勉強し始めますが、特に、何回目かの受験の方は、こういう方法で気分転換を図るのも方法かもしれません。 また、図書館や勉強する部屋をかえてみるのも一つの手です。 |

2回も試験に落ちた人間が生意気いいますが、少しでもお役に立てれば幸いです。