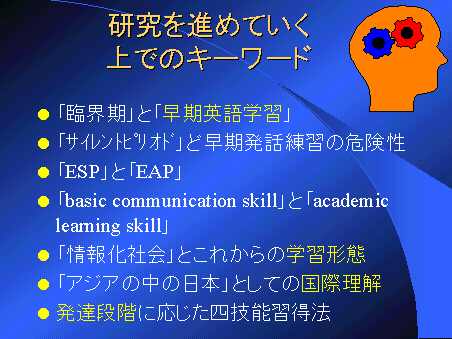 |

|

|

|

|
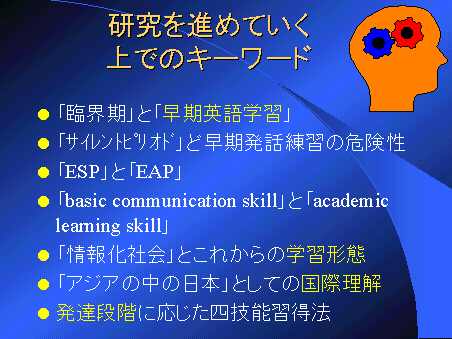 |

|

|

|

|
・英語早期、入門期では「音声指導」から入るのが常道である。しかし、現状では週3時間の環境でEnglish showerは不可能。
・output 以前に十分な input 活動を試みる。
・英語の必要性は現状では生徒に実感されていない懸念がある。高校・大学入試があるため「教科としての英語」が生徒側の実際の必要性である。入試が変われば多少は変わるかもしれない。
・英語は技能面先行だけではなく、知識面の育成も忘れてはならない。学習の側面として「知識・技能・情意」とありその本質は昭和22年の改定以来変わっていないと言われる方もおられる。確かに現行指導要領(平成元年)の「コミュニケーション」の言葉以外熟読してみると何ら内容的には大きな差異は無いように感じられる。時代とともに本質の周辺が変化したり脚光を浴びたりしているのかもしれない。現行のものでは「情意面」に指導の焦点があてられている。情意面(関心意欲態度)を重視したとしても、技能・知識も大切であることに変わりない。特にこれらは発達段階に合わせて指導されれば解決することではないだろうか。英語学習のゴールに向かって、中学英語はその過渡期であり、入門期である。まずは基本的に全てを取り扱いつつも情意面を伸ばしていくことが必要だろう。段階的指導法を私は重視している。中学ではまず基本である。もし小学校に英語科が入って一般化したならばまた中学英語の役割も変わるだろうが、現時点では情意面を重視しながらも知識面も回避せず(『文法指導』という言葉が教育界でtaboo化している感じが個人的にしている)に指導していく必要があると思う。「まずやってみて体で覚えて、理論的裏付けをとる」という方法も必要かもしれない。sports界で良く行われる方法である。指導要領も戦後11回目の形に間もなく変わろうとしている。
・英語を「tool」として何に使うか。と言えば私の場合「国際理解」に使う。 そしてEFL/ESLとしている国と交流しても良い。私の場合アジアとの交流を試みたい。その理由は今後アジア圏との交流が大切になってくるのではないかと思っているからである。