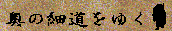
<小松>
(こまつ)石川県小松市
旅行日 97/7
地図を見る(ここをクリック)
 七月二十四日(陽暦9月7日)の申の上尅(午後4時頃)芭蕉に曽良、そして金沢の門人北枝(ほくし)は小松の町に到着します。翌日は・・
七月二十四日(陽暦9月7日)の申の上尅(午後4時頃)芭蕉に曽良、そして金沢の門人北枝(ほくし)は小松の町に到着します。翌日は・・
この所、太田(ただ)の神社に詣づ。斉藤別当真盛(さねもり)が甲(かぶと)、錦の切れあり。
倶利伽羅峠に続き、ここも源平合戦ゆかりの地。(『安宅の関(あたかのせき)』ってゆーのもあるけどここではパス)
 小松の駅から歩いて15分ほど。多太(ただ)神社の宝物館には「実盛(さねもり)の兜」が展示されている、そうです。私が行ったときは閉まってた・・・(悲)
小松の駅から歩いて15分ほど。多太(ただ)神社の宝物館には「実盛(さねもり)の兜」が展示されている、そうです。私が行ったときは閉まってた・・・(悲)
とりあえずは参道の鳥居脇に、石製の兜(左写真)が見られたのでありました。
目庇(まびさし)より吹返しまで、菊唐草(きくからくさ)の彫物、金(こがね)を散りばめ、竜頭(たつがしら)に鍬形(くわがた)打つたり。
 以下『平家物語』より。
以下『平家物語』より。
寿永二年(1183)五月二十一日、倶利伽羅の一戦で大敗した平家軍は、加賀国の篠原(しのはら:小松市街から南西に10kmほど)で再び源氏軍と戦うことになる。
七十歳を越えた老武者実盛(さねもり)は、若武者に侮られぬよう白髪を黒く染め、決死の覚悟で戦いに臨むが、ついには首を打ちとられてしまった。
実は源氏方の大将木曽義仲(きそのよしなか)は幼い頃、実盛に命を助けてもらったことがあった。実盛と旧知の樋口次郎とともに、この雄々しくも哀れな敵将の最期に、はらはらと涙を落とすのであった・・・。
上は『平家物語絵巻』実盛最期の事(林原美術館編著)より
続けて、芭蕉の句(↓)へ。
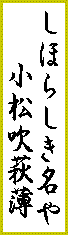 <芭蕉の句>
<芭蕉の句>
しほらしき 名や小松吹 萩薄
(しおらしき なやこまつふく はぎすすき)

<句意>
- (小松とはいかにも)実にかわいらしい地名であることよ。(見ればその名の通りにあたりの野に生えている)小松の上を吹き渡る秋風が萩や薄も吹きなびかせていることだ。
右写真は多太神社にほど近い本折日吉神社に建つ碑。中央には「芭蕉翁留杖の地」、その右には「しおらしき〜」の句が刻まれています。
ここではもう一句紹介します。
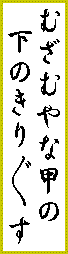
むざむやな 甲の下の きり/″\す
(むざんやな かぶとのしたの きりぎりす)

<句意>
- 実に痛ましいことであるよ。(実盛が白髪を染めて奮戦したという)甲の下で(実盛の亡霊の化身かとも思われる)こおろぎが(寂しい声で)鳴いている。
三省堂・新明解シリーズ「奥の細道」(桑原博史監修)より
この句は、謡曲『実盛(さねもり)』の「(実盛の首を検分しに)樋口まいり、ただ一目みて、涙をはらはらと流いて、あなむざんやな、斎藤別当(実盛)にて候ひけるぞや」の文句から一部とったもの。
左は、多太神社境内に建つ句碑。

 金沢の頁へ
スタート頁(地図)へ
金沢の頁へ
スタート頁(地図)へ
ホームページへ |「奥の細道」目次へ | メールはこちら
![]()
 七月二十四日(陽暦9月7日)の申の上尅(午後4時頃)芭蕉に曽良、そして金沢の門人北枝(ほくし)は小松の町に到着します。翌日は・・
七月二十四日(陽暦9月7日)の申の上尅(午後4時頃)芭蕉に曽良、そして金沢の門人北枝(ほくし)は小松の町に到着します。翌日は・・ 小松の駅から歩いて15分ほど。多太(ただ)神社の宝物館には「実盛(さねもり)の兜」が展示されている、そうです。私が行ったときは閉まってた・・・(悲)
小松の駅から歩いて15分ほど。多太(ただ)神社の宝物館には「実盛(さねもり)の兜」が展示されている、そうです。私が行ったときは閉まってた・・・(悲) 以下『平家物語』より。
以下『平家物語』より。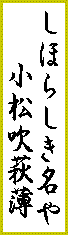

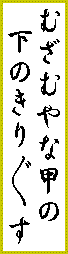


 金沢の頁へ
金沢の頁へ