(1967)
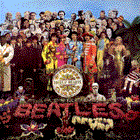
Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band
・出だしのまるでコンサート会場にいるような「ざわざわ...」だけで期待感一杯。わくわくしてしまいます。実際の演奏は2分弱のとっても短い曲で、これから始まる一大スペクタクル・アルバム(?)の単なるオープニング・アクトだったりします。
With A Little Help From My Friends
・Ringoのボーカル曲の中で一番評価が高いのがこれでしょう。かわいそうだけど歌だってドラムだって、決して上手くない彼の心境をPaulが代弁してくれているようで、健気に歌う姿に、ちょっとかわいそうな気もします。逆に説得力があるとも言えますが...。
Lucy In The Sky With Diamonds
・タイトルの頭文字が「L・S・D」となることから、あれやこれやと憶測を呼んだ曲。曲の構成も転調とリズム変化を繰り返していてとても複雑。この曲の譜面って何が何だか分かりませんよ...(汗)。後の名曲<Strawberry...>にも通じる摩訶不思議な世界が展開される曲です。
She's Leaving Home
・ストリングス・アレンジが当時の私にはとても退屈でした。今聞いても印象は大して変りませんが(^^;;)、楽曲の良さは中々のものだと思います。別アレンジで誰かがカバーしていたように思いますが、ゆったりとした中で謳い上げられる悲しい別れの一こま。いい雰囲気です。
Being For The Benefit Of Mr.Kite !
・途中三拍子を織り交ぜながら繰り広げられる音の万華鏡...そんな雰囲気の曲です。当時のアルバム作りで、こんなアプローチをしているミュージシャンはいなかったでしょうね。あるテーマに基づいて、その世界を自らが持つ様々な手法を駆使して展開する...この『Sgt. ...』が、いわゆるコンセプト・アルバムの走りだといわれる理由が良く分かります。
Within You,Without You
・Georgeお得意のインドの世界。西洋のミュージシャンは音楽的に行き詰まると、何故かインドに向かってしまいますよね。日本のミュージシャンの場合は沖縄だったりしますが...。独特の音階をもつこれらの地域の音楽。これと異種混合をはかろうという試みは理解できないでもないですが、それは邪道だと言いきってしまいましょう。インド音楽でもない、ロックでもない、なんだか中途半端な単なる際物以外の何物でもなかったりします。
When I'm Sixty-Four
・Paulお得意のほのぼのポピュラー風曲。これって完全にロックじゃないですね。でもアルバムの中にこんな曲が挟まると、逆にメリハリが効いて違和感無く収まったりするのがPaulのマジックなのだと思います。
Good Morning Good Morning
・オーケストラをバックに歌うロック・ミュージシャン...そんなスタイルが完全に確立したのがこのから曲でしょう。途中のアバンギャルドなギターが妙なコントラストで格好良いです。エンデイングの動物の鳴き声のエフェクトの連続が、アニメのドタバタなワン・シーンを思い出させるようで、とても楽しいです。
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)
・同じ曲をアップ・テンポにしてロック・アレンジにする...あれ、そういえばこの手法ってQueenの<We Will Rock You>がそうですよね。そして続く<A Day...>はQueenなら<We Are The Champion>って訳か...なるほどと感心ししてしまいました。
A Day In The Life
・スペクタクル・ショーのラストを飾る超大作。この曲の聞き物はフル・オーケストラの4回重ね。そんなことなんて今でもBeatlesぐらいしか出来ない技でしょう。この曲の最後に動物にしか聞こえない2万ヘルツの音が入っているそうです。しかし残念ながらCDフォーマットではその音域の音はカットされているはずです。LP盤は物理的に音を溝に刻み込んでいるはずですから、確かめたい人はレコードを探してください。あとレコード盤の最後のループする溝に音を入れるなんて、そんなこと考えたのも彼らくらいでしょう。しかしオートリバースのプレイヤーが出てくるとは彼らでも想像していなかったようで、途中でブツッとアームが戻ってしまい、逆に悔しい思いをした人も多かったはず。いろいろと手の込んだ事をやってくれます。
※よく考えると、このアルバムが出たのは彼らがデビューしてからまだ5年しか経っていないのですよね。田舎の港町でロックン・ローラーを気取っていた不良少年達が、5年後にこんな凄いアルバムを創作してしまうなんて...。彼らは生き急いでいるような気がします。このアルバムのいたるところで見え隠れするドラッグの世界。ドラッグ無しにはあんな尋常ではない世界は描けないって、妙な説得力はありますが、一方では猛烈なスピードで生きていた彼らには、並の精神ではとても耐えられないというのも分かるような気がします。
このアルバムが出た頃は彼らがツアーをしなくなってしばらく経ち、人前に登場する機会も物理的に減っていて、彼らの謎めいた言動とも合わせて様々な憶測が飛び交うようになっていきます。ドラッグ話もしかり、そしてPaulの死亡説もしかり。こうしたオカルト・チックな対象としても彼らは見られるようになってしまいます。でも実際はマスコミに乗らないだけで、案外飄々と暮していたのかもしれませんが...(^^)。
(1967)
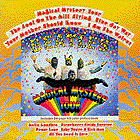
Magical Mystery Tour
・サウンドの基本的なコンセプトは前作と同じように感じます。ただこのアルバムはアメリカ編集盤とのことで、Beatles本人達の意思は全体としては反映されきっていないのだそうです。
そんなアルバムのトップを飾るこのタイトル曲は「(架空の)バス・ツアーにさぁ出かけましょう」というまさに『Sgt. ...』と同じアプローチ。レコーディング・アーティストとして定着した彼らが誘うバーチャルな「With The Beatles体験」という嗜好だ。ジャケットからも彼らのサイケデリックな非日常世界世界が存分に表現されています。
Fool on the Hill
・牧歌的な曲調とは裏腹に、ブッ飛んだ世界が展開されている曲。リコーダーによるテーマが実に印象的。その難解な歌詞から深い精神世界が表現されていると言われていますが、案外単純な内容だったりして...。
Flying
・Beatles風プログレ曲。これでも聞きながら皆さん飛んでくださいと言わんばかりの危ない曲です。続く<Blue Jay Way>も怪しい魅力に溢れる妙な曲(^^;;)。
You're Mother Should Know
・まさにPaulらしいメロディ抜群の佳作。そんなメロデイの魅力を十分に引き出す抜群のベース・ライン。こんなラインは並のベーシストには考えつきません。このライン取りって研究の価値有り。
I'm The Walrus
・このアルバムの中で最も危なく怪しい曲。Johnらしい風刺タップリの曲。途中のオーケストラ・バースの挿入などはPaulの志向を感じます。この曲も「ああ、Sgt.の後に出たアルバムなんだな」と感じさせてくれます。
Hello Goodbye
・さあ後半はヒット曲集ですよ...って感じ(^^)のポップチューン。
Strawberry Fields Forever
・そんなヒット曲集が始まったとたんに出てくる、収録中最も飛んだ曲。世のレコーディングに初めて使用されたメロトロンが効果抜群。この曲の前半と後半とは別々にレコーデイングされたもので、そのピッチのズレを調整して途中でつなげるという荒業により作られた話は有名で、おかげで全体にダイナミックレンジの低い平坦な感じに聞こえるけれど、それがまたこの曲の雰囲気と合って結果オーライの出来となりました。やりたい放題の作品です。どこで繋いだか知りたい方は こちらへ。
Penny Lane
・かつて彼らが過ごしていた土地のご当地ソング。<Strawberry ...>もJohnが子供の時に過ごしていた場所を歌ったものだし、何だか回顧趣味に溢れた作品が続いています。彼らがバスに乗って行きたかったのは、そんな古き良き時代のあの場所だったのでしょうか。
Baby You're A Richman
・単純なメロディとは裏腹に複雑怪奇なオケが、摩訶不思議な極彩色のサイケデリック・サウンドを聞かせてくれます。
All You Need Is Love
・BBCの衛星中継による全世界同時中継の特別番組(1967年6月25日)での目玉企画として制作された曲で、この曲の公開レコーデイングという趣向だ。当時のイギリスといえば、やはり彼らしかいなかったのでしょうね。Aメロの3/4拍子も実に自然に聞こえてしまうのは不思議。Beatles版We are the Worldってところでしょうか...チャリティじゃ無いけど。
(1968)
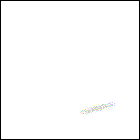
< Comming Soon ! >
(1969)
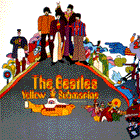
< Comming Soon ! >
Get Back to Beatles Index