(1969)
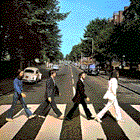
Come Together
・アルバムそのものは同年初頭からの『Yellow ...』のセッションと同時に進められており、途中お蔵入りした『Get Back』セッション(後にリミックスされてアルバム『Let It Be』としてリリースされる)を挟んで仕上げられていきます。4人で進めてた最後のアルバムということになります。
さて、この<Come...>は気だるくも生き生きと歌い上げるJohnのボーカルはまさに入魂の1曲。レコーディングでもテイク1から素晴らしい出来だったとのことで、実質的に崩壊していた4人の関係から、Johnにしてみれば久し振りのBeatlesでの活動復帰作だそうです。そんな意気込みが十分伝わります。歌詞に「1足す1足す1は3...」とあって、「あれ、もう一人は...?」ということでPaul死亡説の理由の一つにもあげられ曲です。またこの曲でも例の「walrus」が登場します。
Something
・こちらはGeorgeの入魂の1曲。当初はこの曲に約4分間ほどのエンディング・バースがありましたが、だらだらしてるとの理由でその部分は大胆にも全てカット !!(^^;;)。途中のギター・ソロはGeorgeのものとしては過去最高の出来と言えるでしょう。あと、この曲のPaulのベースラインはまさに芸術的。フルコピーなど絶対に出来ません。オクターブ・ノートをこんなに上手に使いこなすなんて...凄いです。私の拙い経験上、最も難易度の高いフレーズだと思います。
Maxwell's Silver Hummer
・Paulの実に彼らしいポップ・チューン。ハンマー音のSEは映画「Let It Be」でも、鉄の塊を叩いている光景が写っていましたよね。ジョージ・マーチンによるハモンド・オルガンが実に効果的に用いられています。ちなみにJohnはこの曲は大嫌いだそうです(^^;;)。
Oh! Darling
・この曲のボーカル録りにかけるPaulの意気込みは相当のもので、こなれた上質の声ではなく、地声の自然の擦れ声を採用したくて幾度も録り直しをしたそうです。初期のRockn' Rollな頃の荒々しさが欲しかったようです。こちらもPaul入魂のボーカル・チューンが聞き物だといえます。みんな本気でこれが最後だと思っていたのでしょうかねぇ。力の入れ様が違います...。
Octopus's Garden
・RingoがBeatlesに提供した曲の中では、最も完成度の高い作品。おぉ、Ringoあなたもかい!?。全員の意気込みがイヤというほど伝わってきて涙がでちゃいます。
I Want You
・当初は『Get ...』に収録するべく準備が始められた曲だそうです。途中のブルース・ギター・ソロはBeatlesの楽曲では珍しく長時間(^^;)収められています。また後半のハモンド・オルガンもボーカルがかぶっているとはいえ、やはり珍しく即興っぽいフレーズが聞けて、まさに異例ずくめの曲。
異例といえば曲の後半のリフレイン部で聞ける嵐の音はムーグ・シンセによるホワイトノイズ。普通はこの手のノイズ(音ではない)は、レコーデイングでは最も嫌われるもので、このアルバムのCD化にあたっては結構問題になっていたそうです。そして最も凄いのはエンデイング。フェイドアウトするでなく何かフレーズがあるでもなく、唐突に切れる...。これはJohnのアイデアだそうです。
こんな何から何まで異様なまでのテンションで仕上げられたのこの曲。それもそのはず、この曲の最終レコーディングの行われた1969年8月20日が、John、Paul、George、Ringoの4人がAbbey Road Studioに全員揃った最後の日になったのだそうです。Beatles最期の日の(ミキシングやオーバーダブを除いた)録音がこの曲だったとは...。改めて聞きなおすと、彼らの情念というか怨念のような鬼気迫る雰囲気が伝わってきます。
この曲にまつわる有名なエピソードがあります。曲の4分半を過ぎたあたりでJohnの「Yeah....」と振り絞るようなシャウトの後に、何者かの声が聞こえるというもの。確かに叫び声の直後に左チャンネルから微かに聞こえます。当初はコンソールのスタッフの誰かからの指示だと言われていたそうですが、当時は誰も彼らに指示なんて出せるはずがありません。結局はベーシックトラックを録音中にオフマイクでメンバーの誰かの声を拾っていたというのが真実らしいです。本当にこの声は聞こえますよ。ちょっと不気味(^^;;)。
Here Comes The Sun
・Georgeの入魂の曲がもう1曲。魑魅魍魎がドロドロと渦巻く曲から一転して、心が洗われるようなコントラストが実に見事です。
Because
・3声による究極のコーラス・ワークが実に美しい。イントロのハープシコードのような音はムーグ・シンセによるもので、途中のフレーズもムーグによるもの。ここまで大胆にシンセサイザーが採用されている曲もBeatlesでは珍しいのでは。
さて、ここから始まる世紀の大メドレー。レコーディングの時には「The Long One / Huge Melody」と呼ばれていたそうです。実は当初はリリースされた曲順と一部違っていたそうです。アルバムの最後に取って付けたように入っている<Her Majesty>が実はこのメドレーの一部だったそうです。ではどこに入っていたか...。当初の曲順は<You never Give Your Money>〜<Sun King>〜<Mean Mister Mustard>〜<Her Majesty>〜<Polythene Pan>〜<She Came in Through The Bathroom Window>〜<Golden Slumber>〜<Carry That Weight>だったそうです。このメドレーのラフ・ミックスが出来あがった時にコンソールでこのテープを聞いていたPaulが<Her ...>が邪魔だからカットしてくれとエンジニアに指示をだしたそうです。まだラフの段階なので「適当に切って繋いどいて...」程度のもので、<Mean ...>の最後のディストーション・ギターの最後がかぶったまま切り落とし、<Her...>の最後のアコギの余韻が消えぬ間に<Polytheen...>の頭とつないだのでした。しかもそのエンジニアがスタジオの上司からの指示で、Beatlesの音源はいかなる部分であっても全て残すようにと言われていて、切り取ったテープの処置に困って数秒分(20秒間)のリーダー・テープをつけてそのラフ・ミックスのテープの最後につなげておいたというのです。ところが最終ミックスまで残ったテイクは、なんとその時のもの !!。ご丁寧にカットされた<Her...>までが生き残ったというのです。<Sun...>と<Mean...>の繋ぎの虫の音など、途中何度も手が加えられていながら、こんな偶然が生み出したテイクを採用してしまうなんて...。アルバムが完成して一番驚いたのは、その時のエンジニア君だったでしょうね。
CDのライナーには、こんな世紀の偶然が起きた69年7月30日がBeatlesの最後のレコーディングセッションと記載されていますが、これは間違い。正しく8月20日だとのことです。個人的にはこの日がビートルズの解散記念日だと思ってます。
The End
・実質的なアルバムの最後を飾るのがこの曲。初公開のRingoのドラム・ソロが最後の最後で初めて聞けました。ここではJohn、Paul、George三人のギター・バトルも聞けます。本当はこの曲は「in the end..」ということで、「(前向きな意味で)人生は結局チャラ」みたいな内容の歌だと勝手に解釈していますが(^^)、これほどまでに壮絶な生き方をしてきた彼らからそんなこと言われちゃうと、何だかなぁ...って考えてしまいます。
(1970)
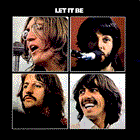
Two Of Us
・アコギ中心のシンプルな構成で、よく聞くとベースがいない !!。ベースラインに相当するフレーズはGeorgeのギターにより延々演奏されています。このアルバムにはそんな構成の曲が他にもあります。さらに主要な部分でのリズムもスネアがない !!!。しかも結構複雑なテンポ・チェンジが行われていたりします。John & Paulの3度ハモリが主で、スネアによる繋ぎでサビの部分はPaulの独唱です。ベーシック・トラックは69年のスタジオ録音のものだそうです。何気ない曲に聞こえてしまいますが、案外複雑なことやっている...こんな曲をやっているって、やっぱり只者ではないですね。
Dig A Pony
・伝説のAppleビルの屋上でのパフォーマンスの時のものです。さぁ始めるぞとして「ちょっと待ったぁ」と演奏を止めているのはRingoです。映画でも見られるように当日はかなり寒かったようで、4人とも寒さ対策のためかなり妙な服装をしていますよね(^^;;)。ギターは左がJohnで右がGeorge。曲の雰囲気はまさにJohnのもので、元々は「All I Want Is You...」のフレーズが曲の最初と最後に入っていたものを、プロデューサー氏が勝手にアレンジしてアルバムに収録されている...そんなのって、ありでしょうか。メンバーが怒るのは当然ですね。
Across The Universe
・収録されている曲の中では結構古くて68年には原型はできています。もともと「野生動物保護基金」のためのチャリティ・アルバムに収録されるために制作されていたもので、その時のものは『Past Masters2』に収録されている鳥の声入りバージョンとして古くからマニアの間では有名でした。曲のテンポを落とすために何とキーを半音下げて収録されています。野鳥バージョンは逆に半音上げられているので、比較して聞くと「おいおい」って感じです。なおPast...に収録されているバージョンでコーラスを取っているのは、たまたまスタジオに見学にきていた素人の女性2人だそうです。何たる大胆さ...!!。こちらのアルバムでは当然のように(!?)カットされて、新たにプロによるコーラスが追加されています。
I Me Mine
・<Across...>と逆でベーシックトラックが一番新しいのがこの曲で70年1月に録音されているとのことです。Beatlesの4人が全員揃ってのレコーディング・セッションは前述のように69年の8月20日なのですが、この曲が録音された1月3日には休暇中だったJohn抜きの3人が集まっています。映画「Let It Be」のシーンの中でこの曲のデモ・テイクを演奏するシーンが採用されていたにもかかわらず、きちんとしたテイクのレコーディングがなされていないので、「それならば...」とメンバーが集まったと言う何とも「??」な理由でこの曲が世の中に残りました。オリジナル・テイクは1分半ほどのものが出来あがって見ると2分25秒の曲になっていた...「I , I , Me,Me,Mine...」のリフを使いまわしたのでしょうか...。プロデューサー氏もやりたい放題ですね。
Dig It
・オリジナルは12分を越える超大作。アルバムに収録されたのはたった50秒という何とも継子の1曲。まぁ12分といってもほとんど即興でジャムってるものなので仕方ないかなぁとも思いますが、でも何とも大胆なカットだこと...(^^;;)。
Let It Be
・ピアノを習いたいの少年少女は必ず1回はチャレンジする曲ではないでしょうか。アルバム版とシングル版でギター・ソロのフレーズが違うので、いわゆる「別バージョン」という悪魔のような業を意識した最初の曲だと思います。ところが真実は意外と、この2つのバージョンは同一テイクのミックス違いというのが真実だそうです。つまりあのギター・ソロは同じテープの異なるトラックに収録されているということなのです。両方のソロが同時聞けるミックスは未だに発表されていないけれど、何だか想像できませんねぇ...。そしてこのレコーディングが行われた70年1月4日が、全員揃っていないもののBeatlesがバンドとして録音した最後となります。
Maggie Mae
I've Got A Feeling
・この曲もルーフトップ・パフォーマンスのテイクが聞けます。映画の中で途中のギターのアーム・ダウンのところをJohnがGeorgeに何度も説明しているシーンは結構印象に残っています。
One A fter 909
・今回の収録曲の中で最も古いのがこれで、何と63年には一度録音されています(『Anthology1』に収録)。『Let...』で採用されているのは当然当時のものではなく、ルーフトップ・パフォーマンスの時のものがベースになっています。Billy Prestonのエレピが効いていて、完全に5人目のバック・アップ・メンバーとして存在感が感じられます。ライブ感抜群のテイクは、彼らは何だかんだと言いつつもライブ・パフォーマーだったという面目躍如といったところでしょうか。
The Long And Winding Road
・プロデューサー氏のオーバー・プロデュースにさすがのPaulも怒ったと有名な曲。オリジナルは実にシンプルです(『Anthology3』に収録)。映画でも見られたようにPaulが生ピアノ、Johnがベース、ビリーがエレピを担当しています。しかしこの曲はJohnの最も嫌うタイプの曲で、とてもまともにプレイしているとは思えませんよね。はずしてはいないものの気の無いフレーズが続きます。Paulにしても単なるデモ・テイクつくり程度にしか思っていなかったのかもしれませんが...。ところがベースとなるトラックはこの時のものしか残せなかったというのだから、何という神の悪戯でしょうか。こんな極上のバラードの最悪テイクを修復するにはオーケストラを目一杯乗っけてオーバー・プロデュースするしか無かった...と逆に同情しますです。
Get Back
・彼らはどこに戻りたかったのでしょうか。「かつて居た場所とは」...そんな謎かけのようなエンデイングです。アルバム・バージョンはルーフトップ・パフォーマンスの時のもののような雰囲気ですが、それは最初と最後の語りのみで、ベースはその数日前のスタジオで収録されたもの。実際、屋上ライブの最後はこの曲で、突然のパフォーマンスに周囲の混乱を警戒した警察官が演奏の中止を申し入れる...という映画「Let...」の緊張感たっぷりのラストシーンでも見ることができましたよね。この時のめろめろなテイクは『Anthology3』に収録されています。アルバム作りを彼らが放棄しため、結局幻の先行シングル扱いになってしまいますが、とりあえずこの曲のシングル盤がリリースされることとなります。このシングル・バージョンは、趣旨もプロデューサーも異なるのでまるで違う印象を受けますが、『Let...』に収録されたものと同じテイクで、単にミックス違いだと思います。
※バラバラになってしまった4人が「原点回帰」をテーマに、デビュー当時と同じ手法でオーバー・ダブなど一切無しに生のBeatlesを表現しようと始まったのですが、その溝は埋まることなく、暗く重苦しい雰囲気に包まれたセッションが続いてしまいます。映画化のため常にカメラが彼らを追っているというプレッシャーも手伝って、とうとう修復不可能なところまで追い詰められてしまいます。少なくとも映画「Let It Be」のビデオ(DVD)が日本国内ではリリースされていないところにも、当時の状況は残したくないという彼らの意思が表れているのだと思います。当初の企画のまま世の中に出ても、かつての英雄の醜態だけがクローズ・アップされるだけだっでしょう。
とにもかくにも、このリアル「Let It Be」といえるアルバム『Get Back』は結局リリースされませんでした。原点回帰がテーマだったので、アルバム・ジャケットもデビュー・アルバムと同じものを...ということで撮影されたのが、2枚組みコンピの青盤で使われたものです。ちなみにお蔵入りした『Get ...』には以下のような曲が収録されていました。
Side A : The One After 909 / Rocker / Save The Last Dance For Me / Don't Let Me Doen / Dig A Pony / I've Got A Feeling / Get Back
Side B: For You Blue / Teddy Boy / Two Of Us / Maggie Mae / Dig It / Let It Be / The Long And Winding Road / Get Back(Reprise)
これらのテイクはブートレッグなどで全て入手することができます。それぞれのテイクをこの曲順につないで聞いてみても、正直まとまりのない印象しか受けません。ましてや後にでるAnthologyシリーズのような「記録集」としての意味合いでリリースされるのではないのですから、お蔵入りは当然です。この作品集は放ったらかしにされたまま彼らは、皮肉なほど完成度の高いAbbey Roadセッションへと向かうのでした。
※DVD"The Beatles Anthology"を見ていたら、このアルバムのセッションの途中でGeorgeが「もうやってられない」と言ってスタジオを出てしまったそうです。"White Album"のレコーディングの途中でRingoが脱退宣言して以来、二度目の解散騒動がこの期に及んで起きていたとのことです。リハーサル〜撮影のスタジオをApple Studioに移してから、ゲスト・ミュージシャンとしてキーボード奏者のBilly Prestonを迎えます。同じくGeorge曰く「皆、格好付けたがりだから、外部の人がくると、口論や仲違いはしなくなるんだ」と。これで暫くは保つ...Georgeの苦肉の策って感じでしょうか。絶大なカリスマ性をもつ彼らの、実に人間らしいエピソードです。でも、こんなエピソードが今頃語られるなんて、やっぱり彼らは凄いということでしょうね...。
Get Back to Beatles Index