(1964)
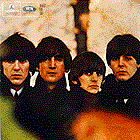
No Reply
・不思議な落ち着きを感じさせてくれるこの時期の曲。この曲も激しくシャウトするブリッジの部分とは対照的に、激しいけれど秘めたような歌を聞かせてくれています。途中のスネアのパターンは、これちゃんとコピーしようとすると、エライ難しいと思います。不思議なタイミングでパツパツ聞こえてきます。
I'm A Looser
・Johnによるミディアム・ロックンロール・パターンの曲です。相変わらずのGeorgeの8小節ソロが頼りなさげでよいです(^^;;)。エンディングのハーモニカソロの部分に音飛びというかリズムが転がっているところがあります。原因は...謎です。
Rockn' Roll Music
・お得意のカバーで、C.Berryの名曲です。Rockn' Roller Johnの真骨頂を聞かせてくれます。
I'll Follow the Sun
・中期の彼らの代表曲と言ってよいでしょう。アコギとJohn & Paulのコーラスがめちゃくちゃ美しいです。
Mr. Moonlight
・出だしのJohnのシャウトが印象的。途中のオルガンも結構珍しいかなと思いますが、マニアの間では手抜きのボーカルとあまり評判が良くないらしいです。そんなものでしょうかねぇ...。
Eight Days A Week
・唐突なF/Iで始まる曲。「一週間が8日あれば...」などと、当時の彼らがとてつもなく多忙だったということを訴えている曲だそうです。確かにこの時期の彼らは殺人的なスケジュールで世界中を飛び回っていたのですから。自分達が本当に何をしたいかと考え出した時期でもあるようです。苦悩の制作活動ってニュアンスが実によく伝わってきます。
Honey Don't
・こちらはカバー曲。殺人的なスケジュールの中でレコーディングが進んでいたのを如実に示している曲です。ワン・コーラス目の「Honey Don't 〜」と繰り返しているJohnのボーカルで明らかに声がひっくり返っているところがあるのにOKテイクになっているなんて、ちょっと信じられません。
Every Little Thing
・中学生時代にこの曲のメロをピアノでコピーした記憶があります。何故そんなことにトライしたのかまるで覚えていませんが、とても印象的なメロディであると感じるのは今でも変りありません。
※この時期の彼らの曲って、時代が生み出した継子のようなものなのかもしれません。いつか違うミュージシャンによって新たな解釈が加えられて、蘇るような気がしてなりません。
(1965)
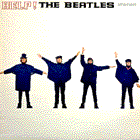
Help
・言わずと知れた映画「Help!」のタイトル曲。改めて聞くと番組のテーマ曲に採用した「開運、何でも探偵団」が浮かんでしまうのは、ちょっと悲しい現実。アルバムは前半が映画のサウンドトラック、後半は新作集という構成。
主旋律を歌うボーカルとバックコーラスが歌詞で掛け合いをしたり、サビの後半部でのハモリが実に印象的。複数鳴っているギターのリズムの刻みが細かな部分で合わず、不安定なドラム・ロールと重なってリズムが転がるあたりはご愛嬌か。当時のボーカル主導の彼らのサウンドをある意味で象徴している曲なのかもしれません。個人的にこの曲は現在正規盤としてリリースされているテイクよりも、US盤でリリースされた007風のオーケストラ・スコアで始まるものに馴染みがあります。このテイクは現在ではBootlegでしか入手できず劣悪な音質のものしか手に入りません(泣)。LP探すか...。
The Night Before
・この頃の作品は録音技術がとても未熟。この曲のイントロも頭のコンマ数秒が絶対に欠けてます。音の立ち上がりがクリアじゃないです。しかも後ろで誰か(たぶんPaul)が唸ってますもの。リズムギターの重ねも甘くて、それが雰囲気を作っているといえばそれまでだけど、忙しくて時間が無い中で取り急ぎ作りましたって感じの仕上がり。ただポップス調ロック・チューンとしての楽曲のレベルは一級品ですけどね。
You've Got to Hide Your Love Away
・フォーク・ソングです。ギターとタンバリン、そしてセッション・ミュージシャンによるフルートのみという、至ってシンプルなアレンジ。その分Johnのボーカルが立ってます。歌い方がまるでBob Dylanみたいで、ちょっと笑えます。
I Need You
・今なら小学生だって出来ると思ってしまうほどのボリューム・ペダルによるギター・アンサンブルがアレンジの胆となっているGeorgeのラブソング。カウベルが入るブリッジの部分のテンポが実に不安定で、ちょっと気持ち悪い。エコー効果をペダルだけで実現しようとしているあたりは、お小遣い不足でエフェクターの十分買えないアマチュア・バンドの方には参考になるかも。この時期の彼らの曲全てに言えることだけど、曲が良いのにアレンジが録音が...と、時代の未成熟さが気になっちゃいます。
You've Going to Loose That Girl
・おいおい、ボーカルの出だしのキーがズレてないかい?(^^;;)。と言うよりも途中でマスターテープの再生速度そのものをテンポダウンしてキーが不安定になるのかなぁ...随分と乱暴なテイクですね。あとRingoのボンゴも随分といい加減じゃありません?。こんなパーカッションならノブの方がまだましかしらん(笑)。ボーカル&コーラス・ワークスが完璧なだけに、このアンバランスはどう聞けばよいのか迷ってしまいます。でも私は好きです、この曲。
Ticket to Ride
・「涙の乗車券」とはよくぞつけたという感じの邦題。この時期の彼らを代表するヒット曲の一つ。彼らに言わせれば当時最もヘビーな曲だそうです。今聞くとめちゃくちゃポップスですけどね。
It's Only Love
・Johnにしてはベタ甘のバラード。本人は嫌いだそうです。2001年にリリースされた元ChicagoのPeter Ceteraがカバーしました。アレンジが洗練されると60年代ポップスの名曲に聞こえて良い感じです。ぜひ聞き比べてくださいませ。
I've Just Seen A Face
・Paul作のカントリー&ウエスタン調の曲。Wingsの世界ツアーで取り上げられて場内は大受け。好きで聞いていた私は、どのアルバムに入っているかが分からずに大焦り(^^;;)。楽しい気分にさせてくれる曲です。
Yesterday
・このアルバムに入っていたんですねって感じのBeatlesを代表する、いや20世紀を代表すると言っても過言ではないほどの1曲。髪を伸ばした不良青年にしか見られていなかった彼らの評価も一変させた。実際にはPaul以外の誰もレコーディングには参加していないとのこと。Paulのもつ万人受けする音楽センスが花開いた作品といえるでしょう。弦楽四重奏を重ねたGeorge Martinのアイデアには脱帽。おかげでステージでの完全な再現ができなくなった最初の曲となってしまったとのこと(^^;;)。人類の宝と言うのは大袈裟?。
(1965)
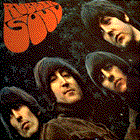
Drive My Car
・イントロ部、ギターだけでリフが始まり絶妙なタイミングでベースが追いかけ、さらにドラムが入る....なんともスリリングなイントロだろうか。何気ないフレーズが、実は再現するのがめちゃくちゃ難しい...Beatlesサウンドの魅力の一つ。偶然か勢いか、当時の彼らには神業に近い所業が多くみられる。レコーディングに夢中になっていてJohnのコーラス部分のフレーズ間違いにも気付かなかったなんてコメントがでるほど、彼らには時間が無かったようです。フレーズは大した事無いけれど(^^;;)、Georgeのギターも結構フューチャーされてます。
Norwegian Woods
・この曲で初めてシタールが登場する。当時Georgeはまだこの楽器に慣れていなくて相当なフラストレーションが溜まってしまったらし。そもそもJohnのギター・カッティングそのものがシタールの奏法の模倣であり、それに本物のフレーズを被せるというのが本当の狙いのようです。Georgeとインド音楽への傾倒は有名な話だけれど、ことのきっかけは、バンドの先輩からムリヤリ押しつけられたものだったとは、何とも...。歌詞の表現方法が抽象的で婉曲的なものだったことから様々な解釈を呼んだ。自然保護、自然回帰、果てはイギリスの古典文学の影響などともっともらしく語る評論家まででたようですが、実際は妻に悟られず彼女のことを歌いたかったなんて、実に人間味あふれる理由です。英語の歌詞をじっくり眺めながらお聞きくださいませ。
Nowhere Man
・オープン・スケールにハーモニクスと当時のGeorgeにしては秀逸のソロが聞ける。自分の居場所を探し続けるという実にJohnらしい精神性豊かなテーマの曲。歌詞が抽象的になればなるほど聞くものの勝手な解釈を生みやすいもの。作った本人は案外違うことを考えていたのかもしれませんけどね。
Michelle
・日本人にしてみれば歌詞に英語を混ぜるとそれなりに格好良く聞こえるものだが、もともと英語圏の彼らにしてみれば、エラ振る大人達?を騙すために、ちょっと上品に聞こえるフランス語でも混ぜておこうか...その程度で作られたのがこの曲だそうです。前作の<Yesterday>と並び評される名曲が、何てことはない、そんな理由で作られたなんて...さすがです。ただしこの曲のコード進行を解析すると、その複雑怪奇な構成には驚かされます。よく聞けば転調しまくりだしシンプルなアレンジと対比して、作曲家としてのPaulの才能がいかんなく発揮されている、やっぱり名曲かと思います。
Girl
・マンドリン風に奏でられるギターが何ともいえないヨーロピアンな雰囲気を作っています。ブレスまでSEに使ってしまう、ある意味実験ともいえるアレンジは、ボーカリストの表現方法を模索するアーティステックな手法と考えられなくもないですが、正直貧乏臭く感じるのは何故でしょうか(^^;;)。
In My Life
・彼らの曲の中で実は私の大好きな曲の一つ。中間部のハープシコードのような音色のバロック調のソロが実に印象的です。このソロはプロデューサーのGeorge Martinによるものだそうです。しかもわざわざ半分の速度でテープを回して録音して、このスピードで再生して挿入したという凝りよう。当時中学生だった私が初めてこの曲を聞いた時の衝撃は忘れられません。具体的な出来事とリンクしているわけではないけれど、懐かしく甘い思い出...この曲はそんな雰囲気に浸らせてくれます。
※このアルバムの制作を始めたのがこの年の10月。リリース予定はクリスマス!というなんとも過酷なスケジュールだったにもかかわらず、このレベルの高さは、彼らの並外れた才能を感じざるを得ません。しかも全曲オリジナルで、出来あがって見れば後に彼らを代表するような名曲がゾロゾロ収められている....いやはや凄いです。
(1966)
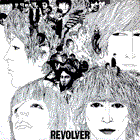
Taxman
・このアルバムをレコーディングしている頃から、彼らはコンサート活動休止の意思を固めていたようです。このアルバムには、そんなライブ・パフォーマンスを前提としない曲作りがあちらこちらに見てとれます。例えばこの曲のPaulのベースラインはまさに芸術的。こんな曲のベースを弾きながらJohnとのユニゾン&コーラスでボーカルをとるなど、さすがのPaulでも無理でしょう。続く<Eleanor Rigby>なども、当時のワー・キャー状態のコンサート会場には相応しくないアレンジです。そんな「ライブでの再現」という制約が無くなったということは、今後の彼らの創作活動のうえで重要な意味を持っていきます。
I'm Only Sleeping
・曲の雰囲気から初めのうちはGeorgeの曲かと思っていました。Bメロのコーラス・パートの作り方などは、まさに一つのパターンとしてその後のアレンジ・ワークに定着していきます。ソロ・パートでの逆回転録音の使用など、当時のレコーディング技術(と言っても、今から考えるととてつもなく幼稚だけれど)の最先端をいくものだったようだし、そんな技を遊び心タップリに取り入れるところなど、まさにやりたい放題の当時の彼らの様子がよく分かります。
Here, Ther and Everywhere
・中期の彼らの代表曲の一つ。三声による抜群のハーモニーもそうですが、甘く語りかけるようなPaulのボーカルが実に美しい名曲です。(たぶん)Johnによるフランジャー効果たっぷりのシンプルなギター・カッティングも良いです。
Yellow Submarine
・おそらくRingoのボーカル曲の中で、最も有名な曲なのかもしれません。Beatles版「みんなの歌」というところでしょうか(笑)。以前、Ringoが来日した際に、「We all live in a ...」なんて大合唱で盛り上がったのを思い出します。単なるロック・アーティストという枠を越えた、まさに20世紀のポピュラー・ミュージック王としての底力を見るような思いがします。
She Said She Said
・高域を強調した、まるでシタールのようなギター・リフが印象的な曲。何てことのない曲だけれど、何故かBメロの気だるさが何故か心に残る佳作です。
Good Day Sunshine
・いかにもPaulらしい牧歌的な雰囲気タップリの曲。スネア四つ打ちとシンバルの微妙なタイミングは、残念ながら多重録音でした。これってS.Gaddでも無理です(^^;;)。
And Your Bird Can Sing
・ギター2本重ねによるテーマが実に印象的。Jay Graydonのフレーズ・パターンの超原型を見るような気がします。ブリッジ部分の半音下がりも気持ち良い。割とこの曲って好きなんです、はい。
For No One
・続くこの曲も何だか分かりませんが好きです。いかにもPaulらしい曲で中間部のオーボーエのソロも雰囲気にばっちり。こんなメロディがどんどん出てくるなんて、やはり彼らは天才?。
※その他に<Doctor Robert>、<I Want to Tell You>、<Got to Get You into My Life>なども魅力だっぷり。このアルバムって全曲良いです。で、実は問題の(笑)<Tomorrow Never Knows>。サイケ音楽のはしりとして位置付けられているこの曲が、このRevolverのレコーディング・セッションで最初に録り始めたというのは驚きの事実。この曲はオーバーダブによる様々な効果音により成立しているけれど、ではそんな効果音無しのベーシック・トラックのレコーディングの時は...なんて想像すると、それだけで鳥肌というか悪寒というか、壮絶な光景ですよね。こんな曲って、イッちゃってなければとても演れないな...と思います。
Get Back to Beatles Index