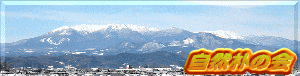
「自然朴の会」山行記録
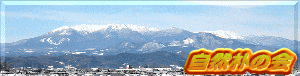
山行記録
2007年09月23日(日) 晴れ
コース ヒュッテ玄関 6:20 → 6:31 蝶ヶ岳最高点 6:40 → 6:44 下山口 → 6:47
大滝山分岐 → 8:25 まめうち平 → 9:21 力水(水場) → 9:31 つり橋 → 9:43
登山口(補導所) → 9:58 登山口駐車場
2007年09月24日(月) 晴れ
弥彦山スカイライン(多宝山登山口) 8:07 → 8:25 多宝山山頂 → 8:42 登山口
⇒
車で移動 ⇒ 弥彦山スカイライン駐車場 8:50 → 9:01 ケーブル終点広場(九合目)
→ 9:15 弥彦山山頂 9:26 → 9:40 レストハウス 10:20 → 10:30 駐車場(この後帰宅)
朝一番の食事は5時半、ツアーの一行は4時半に並んで一番目の食事に付くと言っていた、私らは5時過ぎに食堂に行って見たら朝一番の組はもう食事が始まっていて間もなく次の番になるとの事なので待つ事にした。 5時半に2番手の食事が始まった、食事が終わった荷物をまとめ出発するため玄関に下りる。 今朝は蝶ヶ岳の最高点に寄ってそれから下る事にする、最高点は小屋の南側になるのでテント場の方に回りこむ、昨夜のいいの君も一緒に行って見ると言うので同行しカメラのシャッターを押してもらう、昨日はガスで展望が得られなかった槍穂高の峰々も今朝は薄モヤはかかっているが顔を見せてくれている、ここからの展望では槍ヶ岳がだいぶ遠くに見えて穂高が直ぐ目の前になる、この景観を目に焼きつけ下山開始であるがその前に下山口の三俣にタクシーの予約と今夜の宿への連絡を携帯電話で行ってから出発する。 携帯電話はMOVAを使用しているが蝶ヶ岳のテント場の所からはアンテナ3本で繋がった。 タクシーには三俣に10時でお願いした、1200mほどの下りなのでのんびりもしていられない、テント場の所が三俣への下山口になる、下り始めて間もなく三俣と大滝山の分岐が有る、三俣への道に入ると正面に昨日越して来た常念岳が大きな山容を見せている。 道は朝露で濡れた石で足場が悪いので注意しながら下る、大分下の方からにぎやかな声が聞こえる、おそらく先に出たツアーの一行の声と思われる、3/4が女性との事なのでにぎやかな様だ。 途中から登ってくる人とすれ違う様になってくる、下りながら登りの人を見ると大変そうで自分らの一昨日を思い出す。 途中で水音が聞こえるが水流が見えない空沢の所でツアーの一行が休憩しているのに追いつく、その先で水分補給の立ち休みだけを取り先に出発する。 まめうち平の休憩ポイントを過ぎ登山道が歩きやすくなる、やがて水場「力水」に出る、ここの水はそれほど冷たくは無いので湧き水ではなく沢水なのかもしれない。 つり橋を渡り間もなくすると三俣の所以となる蝶ヶ岳と常念岳へ分岐に出る、登山口までは間もなくのはずなので皆の足取りも気持ち軽くなる。 登山指導所の有る登山口に到着して、下山届けをポストに入れる、これで歩くのも終わりかと思ったらタクシーが待つ登山者駐車場は500m先になる、一気に足取りが重くなるが最後の頑張りと歩を進めると駐車場が見えやっと駐車場に到着する、駐車場にはタクシーが待っていてくれた、時計を見ると9時58分と予約した到着時間の2分前、タクシーの運転手さんも時間通りわれわれが到着したので驚いていた、タクシーで移動しながら話を聞いたら結構遅れて来る人が多いそうで、1時間以上待つことも有ると言っていた。 タクシーで中房温泉の登山者駐車場まで送ってもらう、料金は約1万円と少しかかった。 車に戻りまずは登山靴から足を開放してやる、その後車で中房温泉の日帰り入浴者用駐車場に移動して、合戦尾根登山口の前にある温泉で3日間の汗を流す。 その後途中の小さくあまり目立たない蕎麦屋(この蕎麦屋が見かけによらず、手打ちをしていて打った蕎麦が無くなったら終わりの店で、昼時だったが私らの後3食ほど出たところで終わりになった)で盛蕎麦を食べ、予約をしていた角田浜の民宿(寿館)に向った。 寿舘は今年の5月に奥秩父(甲武士岳、瑞牆山)に遠征した時もお世話になった常宿になっている。 寿館での夕食はいつもそうだが、食べきれないほどの料理(浜なので新鮮な海の幸)が並び、残さず食べるのは合戦尾根を登るのと同じくらい大変である、しかしせっかく心を込めて出してくれているので頑張って食べる、部屋に戻ってからは腹がいっぱいで飲める状態ではないので横になっているうちに寝てしまった。
翌朝、予約をした時に宿の女将から翌日は久しぶりの旅行に出かけるのでと本当は断られたのだが、朝は早くに出ても良いのでと無理を言って泊めてもらったので早めの朝食を出してもらい7時半には宿を出た、宿を出たのが早い時間なので車の中でこれから真っ直ぐ帰るかどうしようかと話をしているうちに、視界に入ってきた弥彦山に寄って行こうかとなり、下から登るのでは時間もかかるししんどいので弥彦スカイラインを車で登り、峠から多宝山と弥彦山を往復しようと言う事になった。 NAVIを弥彦スカイラインの峠にセットし方向転換する、スカイラインのほぼ最高点の峠に多宝山への登山口が有り車が2台ほど止める事が出来そうなスペースも有った。 車を止めると取り合えず服を山歩きモードに取替え(宿を出る時は山登りは全然考えていなかったので服装は普通のレジャーモードだった)登山靴に履き替える。 支度が出来たところで水だけ持って多宝山の山頂を目指す、山頂までの道は歩きやすく15分ほどでレーダードームの有る山頂に到着する、山頂には一等三角点が有りその前には「天測点」の名盤が付いているコンクリートの台座の様な物が有った、山頂から日本海が望めるが山側は樹木があり展望はあまり無い、早々に下山し次の弥彦山に向う事にする。 車に戻ったらそのままの支度で車で弥彦山の方に移動する、多宝山から弥彦山までは登山道がつながっているが、時間を短縮するため弥彦山の下まで車移動にした。 スカイラインの弥彦山の下には大きな駐車場が有り、弥彦山九合目まで10分ほどで行ける、。 九合目は下の弥彦神社の所からのケーブルの山頂駅になっていてレストハウスが有る、レストハウスの前を通り弥彦山山頂に向う、道は広く階段状になっていて一般の観光客でも普通の靴で問題なく歩ける、山頂に近づくとNTTや放送局のアンテナが沢山立っている横を通る、山頂には弥彦神社の奥の院が有りその周りからは各方面の展望を得る事が出来る、西には日本海が広がり佐渡ヶ島も大きく見える、東には黄金色に実った田んぼが広がっているのが見渡せる。 帰りにレストハウスの屋上展望台に上って多宝山と弥彦山をもう一度眺めた後、車に戻り帰路に着き今回の山行も無事終了となった。
.files/jyonen200709_076.jpg) |
.files/jyonen200709_077.jpg) |
.files/jyonen200709_078.jpg) |
| 出発前にヒュッテ入口で記念写真 | ヒュッテのテントサイトの上の蝶ヶ岳最高点、ま新しい標柱が立っている | 最高点の標柱前から槍穂方面を見渡す、朝霞が少しかかっていたがその姿を見せてくれた、中央の窪みが大キレット |
.files/jyonen200709_079.jpg) |
.files/jyonen200709_080.jpg) |
.files/jyonen200709_081.jpg) |
| いよいよ縦走のフィナーレ、三俣への下山開始 | 下り始めると三俣と大滝山の分岐がある、三俣は左へ、うっかりすると右の大滝山へ下ってしまいそう | 大滝山への分岐を過ぎてまもなく、正面に常念岳が見える、左の尾根は前常念 |
.files/jyonen200709_082.jpg) |
.files/jyonen200709_083.jpg) |
.files/jyonen200709_084.jpg) |
| どんどん下って膝も笑い始めるころ広場(まめうち平)に出る、登りにも下りにもちょうど良い休憩ポイントになる | 力水と表示が有る水場になると三俣も後少しになる | 沢を越すつり橋 |
.files/jyonen200709_085.jpg) |
.files/jyonen200709_086.jpg) |
.files/jyonen200709_087.jpg) |
| 三俣の所以となる常念岳と蝶ヶ岳への分岐、登山口までは後少しだ | 登山口の登山補導所に到着、下山届けをポストに入れて、駐車場に向う | 登山口から10分ほど歩いてやっと駐車場に到着、山頂出発時に予約したタクシーが待っていてくれました |
| ************************ | ***ここからはおまけのコーナー*** | ************************ |
.files/yahiko200709_001.jpg) |
.files/yahiko200709_002.jpg) |
.files/yahiko200709_003.jpg) |
| 弥彦山スカイラインの最上部に差し掛かった所に多宝山の登山口があります | 登山道は刈り払いされた木立の道です | 多宝山山頂は一等三角点の山です、すぐ脇にはレーダードームが有ります |
.files/yahiko200709_004.jpg) |
.files/yahiko200709_005.jpg) |
.files/yahiko200709_006.jpg) |
| 一等三角点 | 三角点の側には高さ1mほどのコンクリートの柱(台?)が有り「天測点 地理調査所」と名盤がはめ込まれていた | 下山路、木立の向こうに日本海が望める |
.files/yahiko200709_007.jpg) |
.files/yahiko200709_008.jpg) |
.files/yahiko200709_009.jpg) |
| 車で少し移動してや弥彦山に手抜き登山開始 | スカイライン沿いの駐車場から10分ほど歩いてロープウエィの終点の前に出る | ここは弥彦神社から登った場合の九合目に位置する、残りは一合分の登りだけになる |
.files/yahiko200709_010.jpg) |
.files/yahiko200709_011.jpg) |
.files/yahiko200709_012.jpg) |
| 弥彦山山頂から平野部を見下ろす、田んぼが黄金色に見えている | 山頂にある奥宮の前で、後ろは日本海 | 南の海岸線、奥の出っ張りは能登半島 |
.files/yahiko200709_013.jpg) |
.files/yahiko200709_014.jpg) |
.files/yahiko200709_015.jpg) |
| 目を移せば佐渡島が見える | 山名を刻んだ大石の前で記念写真 | 九合目に有るレストハウスの屋上展望台、後ろは多宝山 |
.files/yahiko200709_016.jpg) |
.files/yahiko200709_017.jpg) |
.files/yahiko200709_018.jpg) |
| 弥彦山から多宝山への登山道、正面のジグザグを登って向こうに一旦下ると先ほど車を止めて登り始めた登山口になる | 弥彦山の山頂部は放送局やNTTなどの鉄塔が沢山建っていて何か異様だ | 歩道の脇のアジサイの生垣に、時期はずれのしかも白のアジサイが数輪咲いていた |