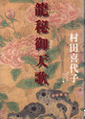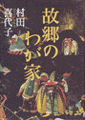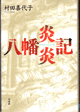収録8篇中、5篇が何らかの文学賞を受賞しているという、贅沢な短篇集。まさに“傑作短篇集”というに相応しい。
平明で穏かな文章、そのうえに肌の温もりのような温かさ、明るさがあります。
冒頭の「熱愛」からしてお見事。予想もしない事態で突然に親友を失った若者の、底の抜けたような喪失感、焦燥感が見事に描かれています。それなのにこれは、何の賞も受賞していない篇。
本書中で格別素晴らしいのは、「鍋の中」「白い山」の2篇。
「鍋の中」は、夏休みを一緒に過ごすことになった4人の孫からみた祖母を描いた作品。そして「白い山」は、幾人もの“おばあさん”を登場させた作品。
両作品とも、おばあさんたちに対する温かい目線が素晴らしい。
ただ年老いたのではなく、多くの苦労を重ねてきた果ての姿という目でみれば、そこには温かい気持ちが溢れてくるのを禁じ得ません。
しかし、村田さんはただそのままでは済まさない。幼稚園児たちをわざわざ登場させ、老人たちと園児たちの姿を見比べるようなことをしてみせます。するとそこでは、老い果てた老人たちという現実の姿も露わになってしまうのです。なんとも心憎い仕業ではないでしょうか。
間に入る「百のトイレ」では、2歳の女の子についてしまったヘンな癖に奇妙な可笑しさがあり、その後にもってくる爽快さとの組み合わせが絶妙の味わい。
「蟹女」では、あれよあれよという間にこれって人間のこと?それとも蟹のこと?と戸惑わせられてしまうのですが、その戸惑いにこそ楽しさがあって、何とも愉快な気分になります。
「望湖」に登場する、磯のカニのようにぞろぞろ這い出してくるというおばあさんたちの姿には、楽しく絶句。
そして最後の「茸類」には、頭をガツンと一撃された気分。
短篇であるのにまるで長篇の如く局面が次々と転回していく様子には、まるで息を呑むよう。
そのうえ、ちょっぴりドキッとさせたり驚かせたりと、読み手を面喰わせて手玉にとるようなところさえある。でもそれが何とも楽しく、愉快なのです。
それが村田喜代子さんという作家独自の雰囲気だと思います。
※それにしても“じーさん”はまるで出て来ませんねぇ。じーさんが出てくると、竹内真「じーさん武勇伝」のように滑稽劇になってしまう所為なのでしょうか。
熱愛/鍋の中/百のトイレ/白い山/真夜中の自転車/蟹女/望湖/茸類
|