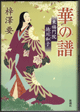戦国時代に舞台を置いた小説は当然のごとくにして武将たる男性を主人公にしたものが多いのですが、珍しく女性の立場から描いた歴史小説。
ただし、女性といっても女らしい生き方を送った人とはちょっと違う。領主の一人娘として生まれながら早くに出家し、出家したにもかかわらず否応なく家名の存続、領地支配と支配される側の苦衷を味わってきた女性。後に徳川四天王の一人に数えられた井伊直政の養母でもあり、先代の井伊家当主でもあったその女性の名を、井伊次郎法師直虎という。
祐は井伊谷の領主・井伊直盛の一人娘。井伊は小国故に今川氏による属国扱いを受け入れてきた。その今川氏から謀反を疑われ、一族の武将を殺されたうえにその息子であった祐の許婚者も領外へ逃亡させられます。更に今川氏より、主家を裏切って通じた家老の息子を婿取りせよと命じられる。
そこからが本書の主人公、祐の真骨頂。
女なればこそ敵の息子を娶らされ、その子供を生まされる。自分の身体が家も自分をも裏切る。そんな女である自分の身体がおぞましい、憎いと訴え、祐は自ら決断して出家してしまう。
父親と大叔父である僧・南渓が押し問答の末に妥協の産物として付けられた名前が、井伊家の惣領名である「次郎」と「法師」を組み合わせた「次郎法師」。
その祐(祐圓尼)の人生をさらに大きく狂わせることになったのが桶狭間の合戦。生き延びてその後勢力を急拡大した徳川家康と対照的に、直盛を亡くした井伊家は困難な道を辿ります。直盛の後を継いだ元許婚者の直親も討たれ、苦衷の策として祐が井伊家当主(=領主)の座につき次郎法師直虎を名乗ります。
支配する側の苦労と支配される側の苦衷、領地を失う衝撃。女で出家した身であるからこそ生き延び得た一方で、子を持てなかった痛みをもつ。そうした祐という主人公像には惹きつけられて止まない魅力があります。
数奇な人生という月並みな言葉が浮かびますが、そんな暗い雰囲気はありません。むしろ辛苦を越えて井伊家を守り通し、俯瞰的に世の中を見る目を持つに至った祐に、清々しささえ感じるのです。
祐と直政の関係だけでなく、祐と父・直盛および母、直政と実母の関係、祐と交わりのあった瀬名(家康の正室・築山御前)と信康の親子関係も濃く描かれていて、戦国ドラマと思って読んでいたら実は家族ドラマでもあった、という驚きもあり。
見事な筆の冴えと称賛したいところですが、そんな理由付けは必要なく、読んでいて楽しい作品なのです。
歴史小説に興味を惹かれている女性の方には是非お薦め。
|