| 蘇聯軍樂 | 〜 リンゴの花ほころび |
| SAKURA | 〜 友情ギフト |
| エレクトリックパーク | 〜 気分は電器屋さん |
| お雇い外国人の見た日本 | 〜 明治初期のジャポネスク |
| 鍵盤上の子猫 | 〜 指何本あるんだ |
| 靖國神社の歌 | 〜 中村メイ子初吹き込み |
| [禁] 放送禁止歌謡 | 〜 マスカット切る! |
| 日本の信号ラッパ | 〜 とてちてたー |
| 軍艦マーチのすべて | 〜 じゃんじゃんばりばり |
| 君が代のすべて | 〜 起立!(しない人もいる) |
| 懐かしのCMソング大全1〜5 | 〜 ああ、あの頃…… |
| 千古絶響 | 〜 中国四千年の響き |
| Selektib Musik der Drittes Reich | 〜 ハイル! ヒッ(自粛) |
| BRUCKNER SYMPHONIES ZERO ET DOUBLE ZERO | 〜 ブルックナーの習作 |
| ブルックナー 完成版/交響曲第9番 | 〜 ブルックナーの最終作 |
| ベートーヴェン 幻の交響曲第10番 | 〜 これってば、う〜ん |
| チャイコフスキー 交響曲第7番 他 | 〜 紆余と曲折の果て |
| マーラー 交響曲第1番 <花の章付き> | 〜 カットされた楽章 |
| マーラー 交響曲第10番 | 〜 奥様も感激 |
| シベリウス 交響曲第8番 | 〜 ついに発見! |
 演奏者とか:中國人民解放軍軍樂團
演奏者とか:中國人民解放軍軍樂團| 収録曲 | |
|---|---|
1 光榮的近衛軍 The Glorious Garrison Army 5:20 2 近衛軍士兵進行曲 March of the Garrison Soldiers 2:58 3 近衛軍砲兵進行曲 March of the Garrison Artillery 2:56 4 近衛軍禮号進行曲 March of the Garrison Rite Bugle 3:31 5 近衛軍騎兵進行曲 March of the Garrison Cavalry 3:17 6 古老的出征 Going out for Ancient Battle 2:18 7 出征進行曲 March of Going for Battle 3:11 8 進軍進行曲 March of Advancing 4:14 |
9 光榮的戰門進行曲
March of Glorious Fighting 3:56
10 蘇軍進行曲
March of USSR Army 2:59
11 黒海海軍進行曲
March of the Black Sea Navy 3:34
12 阿塞爾拜疆英雄進行曲
March of Azerbaijani Heroes 2:28
13 斯大林格勒英雄進行曲
March of Staligrad Heroes 2:09
14 卞秋莎
Kaqiusha 2:45
15 紅軍節日進行曲
March of the Red Army Festival 1:27
16 一個斯拉夫女人的告別
Farewell of a Slav Women 2:39
|
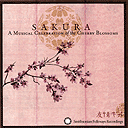 演奏者とか:Center for Forklife and Cultural Heritage
演奏者とか:Center for Forklife and Cultural Heritage| 収録曲 |
|---|
1. Sakura 3:09 2. Yasugi Bushi (Song of Yasugi) 5:00 3. Asadoya Yunta of Okinawa 1:57 4. Hachigaeshi (Returning of Bowl) 5:44 5. Akita Nitaka Bushi 4:56 6. The Song of Rice-Husking 3:53 7. Songs of the Stonemason 2:46 8. Soran Bushi (Soran Song) 2:46 9. Rokudan No Shirabe (Music of Six Steps) 5:36 10. Yuudachi (Evening Rainstome) 11:12 |
この友情ギフト、他には桜の枝の絵をあしらったどピンクのTシャツとか、桜の木栽培キット、石けん、タオル、カップ、蝋燭など、いろいろありました。ただ、この「フト」を一文字だと思ってる節があって、こちらのタオルみたいな(ピンぼけでごめんにゃ)書き方になってたりします。よく見ると「友青」だし、日本語が縦書きになってるだけ上出来ですかね。
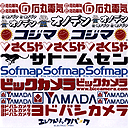 演奏者とか:不詳
演奏者とか:不詳| 収録曲 |
|---|
01. 石丸電気の歌 02. オノデンボーヤCMソング 03. コジマ It's a Happy "YASUI" World! 04. ハートでさくらや 05. サトームセンCMソング 06. HELLO SOFMAP WORLD 07. ビックカメラのCMソング 08. ヤマダ電機の唄 09. ヨドバシカメラの歌 |
ASCII24のAkibaGO!によるインタビューを受けた制作者によると、収録順は五十音順で恨みっこなし、てことみたいですね。ジャケットのロゴなんかも同じ面積になるように配慮したとか。
ずっと昔、ソフマップなんかは自前で店内ソングのCD作って売ってたりしましたけどね。そう言えばソフマップやヨドバシカメラは英語版とかいろいろバリエーションがあるはずなんですけど、このCDでは各社一曲のみってことで日本語版しかありません。オノデンも「未来と遊ぶ」バージョンだけで「宇宙を散歩」しないし。残念。
それにしてもコジマのやつはこれで初めて聴きました。ただ最後の「コージマ」のとこだけ聞き覚えがありました。
 演奏者とか:前田健治(ピアノ) 三森茜(12の三手連弾部分)
演奏者とか:前田健治(ピアノ) 三森茜(12の三手連弾部分)| 作曲者/収録曲 | |
|---|---|
フランツ・フォン・シーボルト(1796-1866) 7つの日本のメロディ 1 第1曲 アレグレット・ヴィヴァーチェ [0'42"] 2 第2曲 ポコ・レント(かっぽれ) [2'26"] 3 第3曲 アンダンテ・コン・モト [0'09"] 4 第4曲 ヴィヴァーチェ・コン・フォーコ [0'35"] 5 第5曲 アレグロ [0'27"] 6 第6曲 レント・クワジ・アダージョ・ラメントーソ [0'16"] 7 第7曲 アンダンテ・コン・モト [0'51"] シャルル・ルルー(1851-1926) 8 扶桑歌 [5'22"] 日本および中国の歌 9 第1巻 [6'38"] 10 第2巻 [5'30"] 11 第3巻 [3'42"] 12 小娘 [3'42"] フランツ・エッケルト(1852-1916) 13 東京の思い出 [2'52"] |
ルドルフ・ディットリヒ(1861-1919) ニッポン・ガクフ[全17曲] 14 さくら [2'53"] 15 祭ばやし [1'21"] 16 権兵衛が種播く [1'50"] 17 婚姻の歌 [2'29"] 18 琉球節 [1'13"] 19 落梅 [3'07"] 20 地搗歌 [1'30"] 21 こいと言うたとて [1'39"] 22 どっこいしょ [0'55"] 23 せっせっせ [1'06"] 24 山寺 [0'39"] 25 姫松 [1'19"] 26 ちゃちゃらつばやし [0'49"] 27 花競 [1'50"] 28 はうた [1'39"] 29 地搗歌第2番 [1'31"] 30 お江戸日本橋 [1'32"] ハインリヒ・ヴェルクマイスター(1883-1936) 私の日本の鞄から 31 フモレスケI [3'18"] 32 フモレスケII [3'54"] 33 フモレスケIII [3'40"] |
ルドルフ・ディットリヒはオーストリアのハプスブルク家最後の宮廷音楽家ですが、俳優の根上淳の祖父にあたるそうです。そんな縁でブックレットに「幻の祖父ディットリヒのこと」って序文を寄せてます。ディットリヒ本人が残した「日土理非」って当て字のサインも載ってておちゃめです。
本CDに一曲だけ入ってるエッケルトは、下の方の『君が代のすべて』に書いた、明治十三年改訂になる現行の君が代にも関わってます。メロディに和声を付けたと言う話ですけど、作曲からやったんじゃないかみたいな説もあるようですね。『軍艦マーチのすべて』に出てくる瀬戸口籐吉もエッケルトの生徒です。
うーん、なんだかここに来てアルバム間相互の関連が出てきたにゃー。
どの作品も、お世辞にも名曲だーすばらしーとは言いがたいです。『お江戸日本橋』とかの耳慣れたメロディも出てきますが、意外に日本的な感じは受けなかったりします。ただ、プッチーニの『蝶々婦人』にこれらの曲からの引用があったりするそうで、その意味では名曲の母胎となったとは言えるのかも。
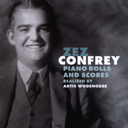 演奏者とか:ゼズ・コンフリー(ピアノロール) アーティス・ウッドハウス(ピアノ演奏*) ヤマハ・ディスクラヴィアによる自動演奏の録音
演奏者とか:ゼズ・コンフリー(ピアノロール) アーティス・ウッドハウス(ピアノ演奏*) ヤマハ・ディスクラヴィアによる自動演奏の録音| 収録曲 | |
|---|---|
1 目まいする指 2:35 2 赤いランタン 2:31 3 ミネトンカの水辺に 2:48 4 短編小説* 1:47 5 ワルツ・ミラージュ 2:36 6 グリニッジの魔女 2:22 7 アフガニスタン 2:43 8 ちょっとした不注意* 2:16 9 鍵盤上の子猫 2:41 10 アラブのシーク 3:18 11 天国の庭* 1:46 12 つまずき 3:14 |
13 信号無視 2:30 14 チャイムのタップダンス* 2:22 15 せかせかしたユーモレスク 2:53 16 愛と呼ばれるもの 3:09 17 真夏の夜の悪夢* 2:33 18 トリック[かわいい女の子] 3:08 19 ピアノをなだめる* 2:11 20 演奏会用練習曲* 2:08 21 私のペット 2:34 22 リラクゼーション* 1:50 23 ファンタジー・オブ・トゥデイ (クラシック&ジャズ版) 4:22 |
まだレコードによる録音が普及してない時代なので、音楽の再生と言えば一枚物の楽譜で売ってる「シート・ミュージック」を自分で演奏するか、自動ピアノ用に売ってる孔のあいたロール紙を買ってきてかけるかくらいしか方法がないわけです。もっと規模が大きくなるとオーケストリオンとかのオルゴールのお化けみたいなのもありますけど、アメリカでは国民的なピアノ好きもあって、自動ピアノが一般家庭にもわりと普及してみたいなんですね。
ピアノロールの制作方法は、当初はオルゴール同様に作曲された楽譜に合わせてロール紙に手作業で孔をあけていたのが、やがて普通にピアノを演奏するとそれに応じて自動的に孔をあける仕掛けが導入されて演奏の記録/再現みたいな方向に進みます。前者では指使いなんか無関係に孔さえあければ音が出ますし、後者でも出版前に多少の修正(同時に鳴る音を増やしたり)が入るのが普通だったみたいで、とても一人の手では演奏できないような派手な音響になってます。
自動ピアノはロール紙の孔を通ってくる圧縮空気で鍵盤を動かすことで演奏するんですけど、ここではピアノ・ロールの孔の位置と長さを電気的に読みとってコンピュータに取り込み、MIDIファイルに置き換えて、コンピュータ制御のグランド・ピアノであるヤマハの Disclavier Pro で再生させて録音、て言う手順を踏んでます。(一部ロールではなく楽譜から手で演奏してるのもあり)
雰囲気としては、ディズニーランドの門を入ったところにある土産物商店街(なんて言っちゃいけないのかにゃ)に流しておくとよく似合いそうな感じですね。私は2曲目の「赤いランタン」がお気に入りです。
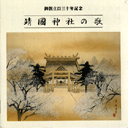 企画・制作:靖國神社 社務所
企画・制作:靖國神社 社務所| 収録曲 | ||
|---|---|---|
【礼式曲 吹奏楽】 1. 国の鎮め 1:20 2. 水漬く屍 1:10 3. 山の幸 1:21 4. 海の幸 1:02 5. 吹きなす笛 1:29 6. 命を捨てて 1:20 【礼式曲 ラッパ譜】 7. 君が代 0:42 8. 足曳 0:23 9. 海ユカバ 0:11 10. 皇御国 0:11 11. 吹キナス笛 0:29 12. 命ヲ捨テテ 0:31 13. 水漬ク屍 0:24 14. 国ノ鎮メ 0:23 |
【歌謡】 15. 九段の桜花 3:28 16. 戦友の唄 2:54 17. 九段の誉 3:09 18. 九段のさくら 3:08 19. 父は九段の桜花 2:42 20. メイコチャンと 社頭の対面 3:18 21. 九段の母 3:13 22. 東京だヨおっ母さん 3:34 23. 靖國神社の歌 4:21 【唱歌】 24. 招魂祭 1:14 25. 靖國神社 1:49 26. 靖國神社 1:32 |
【声楽曲】 27. 海ゆかば 4:24 28. 英霊賛歌 3:21 29. 奉頌歌 靖國神社の歌 3:13 30. 鎮魂頌(独唱) 4:38 31. 鎮魂頌(合唱) 5:01 【神楽歌】 32. 靖國の舞 4:00 33. みたまなごめの舞 2:13 34. 奉頌歌 3:02 |
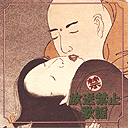 作曲者とか:つぼいのりお 他
作曲者とか:つぼいのりお 他| 収録曲 | |
|---|---|
1.金太の大冒険 ある日金太が歩いていると… 2.極付お万の方 夜のとばりのその中に… 3.トルコ行進曲 嵐吹く 雨ぞ振る… 4.吉田松陰物語 吉田松陰は夜更けまで… 5.快傑黒頭巾 真紅な夕陽が消え落ちて… 6.悲惨な戦い 私はかつてあの様な… 7.ムーンライトセレナーデ 月夜の夜 柳の下… | 8.おっぴょ節 一つ 一人でするのを… 9.ヨサホイ数え唄 一つ 出たホイのヨサホイのホイ… 10.チャンコ・チャンコ あまりしたさにお巡りさんに… 11.おこさ節 可愛いあの娘に着せたい着物ョ… 12.炭坑節 痛いのよ 痛いのよ 痛いのよ… 13.秋田音頭 ヤァーとコリャセ コリャ小便して… 14.ソーラン節 姉ご十七、八 おへその下に… 15.串本節 チンの頭に飯つぶのせて… |
 演奏者とか:谷山節夫、富田道宏、佐々木久登 (陸上自衛隊第1音楽隊)
演奏者とか:谷山節夫、富田道宏、佐々木久登 (陸上自衛隊第1音楽隊)| 収録曲 |
|---|
1陸軍喇叭譜 数ノ部/敬礼ノ部/軍隊・学校ノ部/号音ノ部/招呼ノ部/行進ノ部 2海軍喇叭譜 礼式ノ部/集合整列ノ部/戦闘関係ノ部/陸戦関係ノ部/ 日課・週課・艦内作業ノ部/行進ノ部 3陸上自衛隊らっぱ譜(制定譜) 日課号音の部/警報号音の部/礼式譜の部/行進譜の部/付録 4海上自衛隊らっぱ譜 礼式の部/部署関係の部/日課等の部/行進の部 5航空自衛隊のらっぱ譜(制定譜) 日課号音の部/らっぱによる儀礼譜 6消防らっぱ譜 敬礼/集合/消防行動/行進/日課/数 7明治初期のラッパ譜(三重奏) 陣営 |
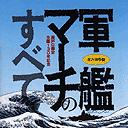 演奏者とか:省略
演奏者とか:省略| 収録曲 |
|---|
1. 岩手県立盛岡第一高等学校校歌 2〜6. 軍艦行進曲 7. ミャンマー・ドゥーイェ・タッマドゥ(ミャンマー国軍) 8〜12. 軍艦行進曲 13. 行進曲「軍艦」 14〜21. 軍艦行進曲 22. 2台のピアノのための軍艦マーチによるパラフレーズ(中田喜直作曲) 23.24. 軍艦マーチ 25. ラグ・アンカタン・ラウト・ジュパン(日本海軍の歌) 26. 軍艦マーチ |
とにかくこれだけ軍艦マーチづくしだと、壮観というか、もう勘弁というか、興味深い一方でちょっとくたびれる一枚です。
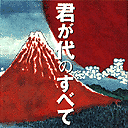 演奏者とか:省略
演奏者とか:省略| 収録曲 | |
|---|---|
1. 君が代[英語版?] 2. 君が代 3. 君が代[初代] 4. 君が代[和歌披講] 5. 君が代[雅楽版] 6. サザレイシ[保育唱歌] 7. 君が代[小学唱歌] 8〜13. 君が代 14. 君が代[雅楽版] 15〜16. 君が代 10,15はラッパ譜付き |
発展と変革… 17. 君が代変奏曲 18. 大日本帝国国歌行進 19. 君が代行進曲 20. 日本のメロディによる即興曲 21. 君が代変奏曲より 22. 君が代 23. 歌劇「蝶々夫人」第一幕より 24. 歌劇「戦争」第三幕より 25. 御大典奉祝前奏曲 ―「君が代」を主題とせる― 26. さとわの夢 |
まずケースを開けるとこんな状態です。ふにゃ。日の丸。
構成は前作を踏襲してます。まずヘンなので一発かましてから、歴史的な録音とか資料的なのを並べて、その後に君が代を引用したりしてる作品が続きます。
前回のヘンなのは盛岡一高のやつでしたが、今度のは明治三十六年生まれの前場コウというおばあさんが歌う英語版らしき君が代です。口伝で覚えてるものらしくて、正確な歌詞は不明でブックレットにも書いてない上に途中で終わってます。メロディは同じなんですけど、最後の「こけのむすまで」にあたる部分が歌われてないです。歌詞を聴き取ってみるとこんな感じ。
えっとーみかどーすえたやっさんど、ちるえるさっさぇんど、やってんさ、さんどやっしゃろや。あーんでずのー、いんざーぶるっくれす、ろっつすとん。
歴史的なのでは、現在のメロディが決まる前にとりあえず付けといた初代の君が代が珍しいです。これは明治二年に、英国王子エジンバラ公が来日するのに、むこうの国歌と一緒に演奏する国歌がないってことで、間に合わせに英国軍楽隊長のフェントンさんに「君が代」の和歌を示してメロディを付けてもらったものだそうです。
ちなみに現行のやつは明治十三年に改訂されたものです。
このCD、ブックレットが縦書きでちょっと厚めの(55ページ)解説書になってて、楽曲分析や歌詞の来歴なんかがそれぞれの専門家によって綿々と綴られてます。けど、どれもこれも最後は「君が代」絶賛してるんですよ。私は別にこれといって思い入れなんかないんですけど、こんなにベタ褒めされると……なんかちょっとわけもなく反感が。
とにかく「君が代」反対派の人は血圧上がるCDですね。
 作曲者とか:省略
作曲者とか:省略| 収録曲 |
|---|
| 省略 |
さて収録曲ですが、1巻と2巻の年代は、そもそも私がこの世に存在していなかったりする時代なので、懐かしいどころじゃないです。
ちなみに1巻の最初の曲はコニカの「ボクはアマチュア・カメラマン」です。知りません。1巻で知っているのは「ミツワ石鹸テーマソング」(わっわっわー、わがみっつ)「明るいナショナル」森永製菓の「エンゼルはいつでも」ヤンマーの「ヤン坊マー坊の歌」など後々までかかっていたものが数曲あるだけで、それもここに収録されているのとは別のアレンジだったりします。しかし「牛乳石鹸よい石鹸」など、後に省略されて断片しか使われなくなった歌がフルコーラスで聴けるのは面白いですね。
2巻も事情は似たようなものですが、多少知っている曲が増えてきます。「伊東に行くならハトヤ」佐久間製菓の「キャンロップの歌」黄桜酒造の「かっぱの唄」レナウン「ワンサカ娘」あたりがここに収録されてます。「タケダ オープニング・テーマ」(たけだたけだたけだ〜)はCMなんですか?
3巻になるとちょうど懐かしさ炸裂のラインナップになってきます。「サントリーオールド(人間みな兄弟)」篠崎製菓「ライオネス コーヒーキャンディ」(雷尾根素と変換されました)丸大食品の「わんぱくでもいい」マスプロ電工「見えすぎちゃって困るのオ〜」中外製薬「ガンバラナクッチャ」カルビーの「かっぱえびせん」オリエンタルの「ハヤシもあるでよー」「明治チェルシーの歌」カシオ計算機「答一発!カシオミニ」など、書き出すとキリがないくらいあります。少し前に作曲者の小林亜星が(阿世と変換されました(苦笑)曲を学んだ?)盗作されたって騒いで裁判でモメたブリジストンの「どこまでも行こう」もあります。富士写真フィルムの「お正月を写そう」はこの頃からだったんですか。
4巻だと記憶には残ってても懐かしさの点では少し落ちます。ライオンの「ブルーダイヤ」(金銀パールプレゼント)「東ハト キャラメルコーン」「タイガー電子ジャー炊きたて」と言ったところが懐かしめですか。あと、今でもやってる「石丸電気のうた」や「日立の樹」はこの頃からなんですね。
5巻になると、もう、ついこないだのような感じ。「明治カール」「東ハト ポテコ」ニベア花王「8×4」(エイトフォー)サンヨー食品「サッポロ一番塩ラーメン」「カメラのさくらや」「ホテルニュー岡部」「サントリーゴールド900(ソクラテスの唄)」などがここに入っています。しかし国際秘宝館の「秘宝館小唄」ってのはなに?
それにしてもTVのCMだけにやはり絵が欲しいです。古いのはおそらく残ってないでしょうが、あるものだけでもビデオなりDVDなりで出して欲しいです。このCDも含めて、適当なプロモーションをすればきっと売れると思います。少なくとも私は買います。
5枚分なんで長くなりましたが、総じて言うと全国に広く流されていた(であろう)CMが主に収録されてるようです。まあ商売だから全国に広く売ろうと思えばそうなるのは当然でしょう。同じ会社の名前が繰り返し出てくるのも、企業側のこうした企画に対する姿勢とか、あるいは収録の許可をもらう手間の問題でしょう。倒産でもしていた日には交渉もできないでしょうし。
しかし! 懐かしさ爆発のやつはローカルCM(千葉出身なので関東ローカル)にも結構あるのでした。崎陽軒(あのシウマイも崎陽軒)や山桜名刺(紙のことなら山桜)大塚角萬(おーつかー、かどまーん)あたりはおそらく関東ローカルでしょう。ひよ子(ひよこ〜持ってこね)は関東ローカルだったんですか?
他にもここに収録されてないもので思い出すままに書いてくと、キンカン(かんかん鍛冶屋のおじいさん)ロバ製菓(潰れた)のぽんぽこ(ぽんぽこタヌキのおまんじゅう)有明製菓(潰れた)のハーバー(ありあけーの〜ハ〜バー)亀屋万年堂のナボナ(森の詩もよろしく)青柳ういろう(白黒抹茶小豆珈琲柚子桜)マルコメみそ(マルコ〜メみそ)日本海味噌(あ〜あ越中)信州一味噌(信州一、信州一、おみおつけ)味噌ばっかりですがハナマルキみそ(おかーさーん)ゴホンと言えば龍角散(歌ではないですが笑点の前後にやってた気管の繊毛運動の顕微鏡撮影が印象深いです)どこかの電卓のCM(例えば、ルート2は、ヒトヨヒトヨニ……)どこかのカメラ(ぼ〜えんだヨ)東芝のテーマ(ひかっる、光る東芝)永谷園(あなたとー食べた〜い、さけーちゃ〜ずけー)ロート製薬(ローォト、ロートローォト)チロリアン(ちろ〜りあ〜ん)ボアジュース(ごーっくーりごっくりこんと)あれ?
 演奏者とか:王原平指揮 湖北編鐘楽団
演奏者とか:王原平指揮 湖北編鐘楽団| 収録曲 |
|---|
1. 竹枝詩 2'40" 2. 春江花月夜 11'05" 3. 屈原河渡 5'59" 4. 楚商 4'18" 5. 幽蘭 7'32" 6. 国殤 7'58" |
これはジャケットにある中国の古楽器『編鐘』(へんしょう)による音楽です。銅鐸みたいな鐘をたくさん並べて吊したやつを、棒というか撞木で撞いて鳴らすわけです。
なんでも1978年に湖北省で発掘された、戦国時代早期にあたる紀元前433年前後の曽国の君主、乙の墓から、この編鐘のフルセットが木の台(鐘架)に吊されたままの、とってもよい保存状態で出土したんだそうです。博物館には出土した実物が展示してある他に、湖北編鐘楽団がその複製品を使った生演奏を踊り付きで聴かせてくれます。それを収録したのがこのCDなのでした。あと内容は不明ですがCD-ROM版も売ってました。
ちなみに踊りの方は、袖がやたらに長い服を纏った女性二人が、その袖を振り回しつつ舞い踊る『長袖舞』(そのまんまにゃ)です。
楽器編成は編鐘の他に、音階に調律したよく響く石の板を編鐘とおんなじように並べて吊して叩く編磬(へんけい)、鼓、琴、瑟、笙、笛などです。編鐘と編磬はふつう一緒に使うものみたい。
曲目は戦国時代の楚の人、屈原の詩に題材を取った作品や、古楽を編鐘向けにアレンジしたものらしいです。なかなかオリエンタル。でもCDに収録されてる水墨画みたいに幽邃な響きの曲より、生演奏で聴いた「王様がおでましになるときの音楽」ってファンファーレの方がかっこ良かったかな。
 演奏者とか:不明
演奏者とか:不明| 収録曲 | |
|---|---|
1 Die Fahne hoch (Horst Wessel Lied) 2:40 2 Badenwiler Marsch 3:00 3 Wenn alle unter werden 2:32 4 Marsch der Leibstanderte Adolf Hitler 2:30 5 Der Fuhrer Ruft: SA Voran! 2:18 6 Westerwald 3:04 7 Erika 3:12 8 Lore, Lore 3:36 9 Und Wenn Wir Marschiren 2:44 10 Edelweiss 3:16 |
11 Panzerlied 2:59 12 Unser Rommel 3:17 13 Pariser Einzugmarsch 4:02 14 Wir fahren gegen Engelland 3:11 15 U-Boote Lied 2:44 16 Rot scheint die Sonne 3:20 17 Bomben auf Engelland 3:11 18 Ich hatt' einen Kameraden 2:55 19 Lili Marlen 2:51 20 Deutschland, Deutschland uber alles 3:02 |
さすが宣伝を重視したナチスドイツの音楽だけあって、景気よくかっこいいです。でも基本的に新しい録音はなく、当時のSPレコードかなんかから起こしたものらしくて、ほとんどがモノラルでノイズもひどいです。
あと軍歌じゃないけどリリー・マルレーンが入ってるのは良いですね。
細かいことですけど、ドイツ語なんで5曲目のFuhrerのuは、ほんとはウムラウト付いてます。
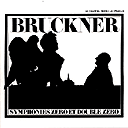 演奏者とか:ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮 ソビエト国立文化省SO
演奏者とか:ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮 ソビエト国立文化省SO| 作曲者/収録曲 | |
|---|---|
CD 1 |
CD 2 |
ブルックナー/交響曲第0番 ニ短調 (1869年版) 1. ALLEGRO 15.07 2. ANDANTE 12.47 3. SCHERZO. PRESTO 6.52 4. FINALE. MODERATO 9.45 |
ブルックナー/交響曲第00番 ヘ短調 (1863年版) 5. ALLEGRO MOLTO VIVACE 19.06 6. ANDANTE 15.06 7. SCHERZO. SCHNELL 6.13 8. FINALE. ALLEGRO 11.03 |
もう一曲のヘ短調のは番号も名前もなしのままなんですが、ときどき0番になぞらえて00番と呼ばれることがあります。そんなカジノのルーレットじゃないんだから。
ここで紹介するCDもそんなルーレット派の一枚です。フランスからの輸入版ですが、秋葉原の石丸電気三号店で見つけて「あら珍しい曲が」とレジに持ってったら、「この曲のCDでは日本で最初の発売なんですよ」と言われました。今では他にも出てますけどね。
え? 曲の内容は? ……つまんないです。
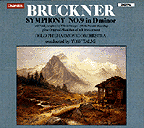 演奏者とか:ヨアフ・タルミ指揮 オスロPO
演奏者とか:ヨアフ・タルミ指揮 オスロPO| 作曲者/収録曲 |
|---|
ブルックナー/交響曲第9番 ニ短調 DISC 1 1. I - 神秘的で荘重に (23:35) 2. II - スケルツォ:軽く快活に (10:53) トリオ:速く 3. III - アダージョ:遅く荘重に (25:26) DISC 2 4. IV - 終局:アレグロ・モデラート (21:55) (ウィリアム・キャラガンにより1979・1983年完成) 5. 終局のためのオリジナル・スケッチ (15:51) |
この9番、ブルックナーが愛する神に捧げた遺言的作品なんですが、いかんせん未完に終わってます。死の床についてからも、ついに完成されずに終わる第4楽章を最期まで作曲していたと言います。なので普通は完成された第3楽章までが演奏されますが、それでもこの曲がブルックナーの最高傑作と言って間違いないでしょう。これを聴かずに一生を終わるのは絶対に損です(断言)。
未完の第4楽章については、スケッチや部分的に完成された総譜など、断片的な譜面が多数残されました。それらは1934年に一度国際ブルックナー協会から出版されています。これを元にして、1983年にアメリカのW・キャラガンが、コーダ(終結部)を書き足して、全曲通して演奏できる形にしたのが、このCDのいわゆる「キャラガン版」です。
キャラガン版ではこのCDが世界最初の録音だそうです。面白いのはスケッチをそのまま演奏したものがDISK2に収録されているところですね。なにせ断片なので、ふっ、と始まって、はた、と終わります。
このCDからちょっと外れますが、この曲を完成させる試みはキャラガン版の他にもいくつもありまして、大きなものでは1985年のニコーラ・サマーレとジュゼッペ・マッツーカによる復元と、さらにジョン・A・フィリップスが加わって行った1992年の補足版があげられます。それらは1934年の出版資料の他にも、そこから漏れた現存するスケッチとかをできる限り参照して完成したものです。
後者の演奏はクルト・アイヒホルン指揮のリンツ・ブルックナー管弦楽団による初録音が出ています。(カメラータ・トウキョウ30CM-275〜6) こっちには断片の演奏なんかはありませんが、ブックレットに手稿楽譜の写真とか復元過程の説明みたいな資料が豊富です。
この「現存するスケッチ」のうちいくつかは、もとはベートーヴェンの第九やモーツァルトの魔笛の自筆楽譜なんかと一緒に、ベルリンのプロイセン国立図書館(現ベルリン国立図書館)にありました。それが第二次大戦中、空襲を避けるためにシレジアのグリュッサウ(現クシェシュフ)の修道院に疎開されて、ドイツの敗勢とともに謎のトラック部隊に持ち去られて行方不明になってしまいます。どうやら大戦初期にナチス・ドイツによって美術品などの組織的略奪を受けたポーランドが、いわば報復的な意味で持ち去ったまま、1977年に存在を公表するまで隠し持ってたみたいなんですね。今はポーランドのクラクフにあるヤギェウォ図書館に保管されてます。
このあたり、ナイジェル・ルイスの『ペイパー・チェイス』(白水社、中野圭二[訳])って本に詳しいです。戦争なんてするもんじゃないですね。
さて、完成された終楽章です。第1、第3楽章に出てくる、ブルックナーが「生への別れ」と呼んだ陰々滅々とした下降音形が、まるで勝利のファンファーレのように鳴り響いたりして驚きです。キャラガン版ではこれをベースにしてコーダを補筆してますし。でもなんかこう、これを捧げられた神様が「第3楽章まででやめとけ」って言ったんじゃないかなって気もしてきたり。
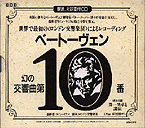 演奏者とか:ウィン・モリス指揮 ロンドンSO
演奏者とか:ウィン・モリス指揮 ロンドンSO| 作曲者/収録曲 |
|---|
ベートーヴェン(クーパー補筆)/幻の交響曲第10番 パート1:19分52秒 第一楽章 変ホ長調 (アンダンテ−アレグロ−アンダンテ) ポーズ :15秒 パート2:28分50秒 バリー・クーパーの解説 |
音楽そのものはとてもベートーヴェンとは思えない仕上がりなので置いといて、ほかんとこのレビューします。
まず、CDそのものはイギリスの聞いたことないレーベル(IMP CLASSICS)から出てるものみたいで、それに日本語の解説書を付けて箱に入れて売ってるものです。普通のレコード屋さんでは見かけなくて、なぜかダイクマ(神奈川県を中心に展開するディスカウント・ストア)が、大々的に宣伝して売ってました。ちなみに中のCDについてるジャケットはこれ。
解説書を開くと、最初に出くわすのがポエム。「夢の波動 シンフォニー第10番に寄せて」だって……ふにゃ、力抜けた。
解説書のメインは録音されてるクーパー博士の講演を活字に起こして、日本語訳したものです。これは親切、というか必要ですね。それからベートーヴェンの簡単な伝記と年譜も付いてます。
あとは博士の挨拶文とか、博士、指揮者、オーケストラとポエムの作者の紹介とか。「ロンドン交響楽団を指揮した巨匠たち」と題して、このCDと全然関係ないフルト・ヴェングラー(ママ)やクラウディオ・アバドなんかを引き合いに出したりもしてます。
解説はともかく紹介文とかを読んでると、なんかこう音楽の内容を補うためなのか、一所懸命にハク付けようとしてる様子がうかがえて微笑ましいです。巨匠たちの件もそうだし、箱には「世界の名盤」とか「保存盤」とか書いてあるし。そもそも上の画像では黒く潰れてる枠とか数字に、実際に金箔が押してあるし。
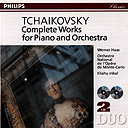 演奏者とか:エリアフ・インバル指揮 モンテカルロ国立歌劇場O ウェルナー・ハース(pf)
演奏者とか:エリアフ・インバル指揮 モンテカルロ国立歌劇場O ウェルナー・ハース(pf)| 作曲者/収録曲 | |
|---|---|
CD1 |
CD2 |
チャイコフスキー/
ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23
1 1. Allegro non troppo e molto maestoso -
Allegro con spirito 19:53
2 2. Andantino simplice - Prestissimo -
Tempo I 7:02
3 3. Allegro con ffuoco 6:30
ピアノ協奏曲第3番 変ホ長調 作品75(未完)
4 Allegro brillante 15:19
アンダンテとフィナーレ 作品79
(オーケストレーション:S.I.タニェエフ)
5 1. Andante 11:45
6 2. Finale (Allegro maestoso) 8:53
|
チャイコフスキー/ ピアノ協奏曲第2番 ト長調 作品44 1 1. Allegro brillante 21:48 2 2. Andante non troppo 15:31 3 3. Allegro con ffuoco 7:19 コンサート・ファンタジー 作品56 4 Quasi Rondo (Andante mosso) 14:46 5 Contrastes (Andante cantabile) 13:30 |
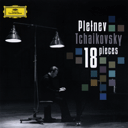 演奏者とか:ネーメ・ヤルヴィ指揮 ロンドンPO ジェフリー・トザー(pf)
演奏者とか:ネーメ・ヤルヴィ指揮 ロンドンPO ジェフリー・トザー(pf)| 作曲者/収録曲 | |
|---|---|
| チャイコフスキー/18の小品 作品72 (ピアノのための) | |
第1曲 即興曲 [3:45] 第2曲 子守歌 [5:43] 第3曲 穏やかな叱責 [2:09] 第4曲 性格的舞曲 [3:17] 第5曲 瞑想曲 [5:14] 第6曲 踊りのためのマズルカ [2:18] 第7曲 演奏会用ポロネーズ [4:50] 第8曲 対話 [3:30] 第9曲 シューマン風に [2:58] |
第10曲 スケルツォ・ファンタジー [6:06] 第11曲 きらめくワルツ [2:23] 第12曲 いたずらっ子 [1:51] 第13曲 田舎のこだま [2:12] 第14曲 悲歌 [6:20] 第15曲 ショパン風に [2:02] 第16曲 5拍子のワルツ [1:36] 第17曲 遠い昔 [3:37] 第18曲 踊りの情景(トレパークへの招待)[4:50] |
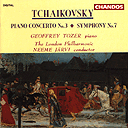 演奏者とか:ネーメ・ヤルヴィ指揮 ロンドンPO ジェフリー・トザー(pf)
演奏者とか:ネーメ・ヤルヴィ指揮 ロンドンPO ジェフリー・トザー(pf)| 作曲者/収録曲 |
|---|
チャイコフスキー/交響曲第7番 変ホ長調 1. Allegro brillante (12:50) 2. Andante (11:18) 3. Scherzo. Vivace assai (7:22) 4. Allegro maestoso (9:04) ピアノ協奏曲第3番 変ホ長調 (16:21) 5. Allegro brillante - Allegro molto vivace - Vivacissimo |
まず一番上のフィリップス盤で珍なのは二枚組の一枚目、『ピアノ協奏曲第3番』と『アンダンテとフィナーレ』です。ピアノ協奏曲は下のシャンドス盤にも入ってますね。
この二曲にもう一つ真ん中のCDに収録されてる別のピアノ曲、『18の小品集』(作品72)の中にある第10曲『スケルツォ・ファンタジー』を合わせて、もともとは一つの4楽章制交響曲、第6番になるはずでした。
これらを交響曲として作曲してたのは晩年の1891年から1892年ですが、チャイ様(壇ふみの声で)どうも気が乗らない。そのうち別の交響曲のアイディアが浮かんできて、どうやらそっちのがものになりそうだってことで、どんどん作曲が進んで有名な『悲愴』が交響曲第6番として完成します。
そうして6番になりそこねた交響曲のあまったスケッチはリサイクルに回されます。まず第3楽章が『スケルツォ・ファンタジー』になり、残りの第1、2、4楽章がピアノ協奏曲に作り直されます。
ところがチャイ様、この協奏曲がまたあんまし気に入りません。第1楽章をなんとか書き上げたところで「あの協奏曲は不格好に長すぎるので、私は単一楽章だけに止めることに決め、アレグロ・ドゥ・コンセール、またはコンツェルトシュトゥックと名付けるつもりです」とか手紙に書いてます。
そうこうしてるうちに1893年10月、チャイ様は謎の死(一応コレラってことになってる)を遂げてしまいます。結局この協奏曲は、完成した第1楽章だけで『ピアノ協奏曲第3番』として扱われることになりました。
さて、あとにはピアノ協奏曲の第2、第3楽章のスケッチが残されました。これをもったいないと思ったのが弟子のタニェエフさん。チャイ師匠の死後にスケッチをオーケストレーションして、『アンダンテとフィナーレ』を仕上げます。作品番号は師匠の通し番号で79を打ってます。これを第1楽章の後にくっつけて3楽章制協奏曲として扱うこともあります。
そしてさらに年代が下って1955年、ロシア改めソ連の作曲家でボガトリリェフという人が、せっかく材料は揃ってるんだからここは一つ、一番最初の構想に戻って交響曲としてまとめてみよう、なんてこと考えたわけです。
それでチャイ=タニ師弟によって完成された三曲や、それらの元になったスケッチを寄せ集めて再構成したのが、下のシャンドス盤『交響曲第7番』になるのでした。ああ長かった。
さてそれでは聴いてみましょう。まずはピアノ協奏曲第3番。これはなかなかいいです。なんとなく後のシベリウスや、バーンスタインのウェストサイド・ストーリーを思わせるようなとこもあったりして。
次はタニェエフ補筆のアンダンテとフィナーレ。これはチャイコフスキー自身の手で完成された協奏曲と比べると、がく〜と落ちますね。まずオーケストラの音に厚みがなくて。アンダンテなんか最初はいいけど、途中で独奏ヴァイオリンと独奏チェロとピアノの三重奏に毛が生えたみたいになっちゃうし。
最後に交響曲第7番。第1楽章はだいたいピアノ協奏曲と同じで、ピアノのパートが他の楽器に展開されてるみたいな感じ。第2、4楽章もタニェエフのよりずっと充実した響きです。チャイコフスキーらしいかと言われるとなんですが、まあしかたないとこでしょう。第3楽章もチャイ様によるピアノ版完成品(スケルツォ・ファンタジー)とは雰囲気がちょっと違いますけど、まあまあの出来です。ただ後半の2つの楽章はちょっと散漫な印象がありますかね。
てことで、他人の手が入ってることを承知で聴くんなら、わりといいです。
 演奏者とか:ズービン・メータ指揮 イスラエルPO
演奏者とか:ズービン・メータ指揮 イスラエルPO| 作曲者/収録曲 |
|---|
マーラー/交響曲第1番 ニ長調 1. 第1楽章:ゆっくりと、引きずるように 15'45" 2. 第2楽章<花の章>:アンダンテ 7'15" 3. 第3楽章:力強く躍動的に、しかし速すぎず 7'43" 4. 第4楽章:厳かに重々しく、引きずらずに 11'19" 5. 第5楽章:嵐のような動きで 20'25" |
第1部 若き日に、花とバラ
第1章 永遠の春、暁の自然の目覚めの描写
第2章 花の章
第3章 帆を張って
第2部 コメディア・ウマナ(人間喜劇)
第4章 カロ風の葬送行進曲
第5章 地獄より天国へ
でも評判が今ひとつだったんで、この第2章「花の章」を外して他の副題も無くし、内容も改訂して4楽章制の交響曲に仕立て直しました。この時、曲名にジャン・パウルの小説の題をそのまま借りて、交響曲第1番『巨人』とします。
その後『巨人』の名前も取り消しちゃうんですが、現在でも大抵は巨人と呼ばれてますね。その方が呼ぶのに手軽だからでしょう。
このCDは外された花の章を復活させて、第2楽章として割り込ませたものです。でも他の楽章は改訂後の内容なんで、一番最初の姿にはなってなくてちょっと中途半端かも。
実はこのスタイルのCDはわりとたくさん出ていて、あんまり珍じゃないです。これと同じく第2楽章にしてみたり、普通の4楽章版とは別にして花の章を付けたり、その辺は演奏家の見識次第でしょうけど。
最初の形の初稿版(ハンブルク版とも)による演奏もいくつか出てるはずなんですが、こっちはずっと珍度が高くて入手難です。若杉弘のマーラー全集に入ってるみたいなんですが、これだけのために全集ってのもねえ。
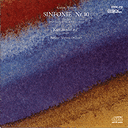 演奏者とか:クルト・ザンデルリンク指揮 ベルリンSO
演奏者とか:クルト・ザンデルリンク指揮 ベルリンSO| 作曲者/収録曲 |
|---|
マーラー(クック補筆)/交響曲第10番 ニ長調 1. 第1楽章 アダージョ <23:09> 2. 第2楽章 スケルツォ <13:04> 3. 第3楽章 プルガトリオ(煉獄)、アレグレット・モデラート <4:02> 4. 第4楽章 (スケルツォ)、アレグロ・ペサンテ <11:14> 5. 第5楽章 フィナーレ <21:48> |
マーラーが1911年に亡くなったとき、交響曲第10番は全5楽章の第1楽章がほぼ完成、第3楽章が少し手を入れれば演奏可能なところまで来ていて、残りの楽章のスケッチもできていました。自らの死を予感しつつ作曲していたマーラーは、未完の草稿の処置を奥さんのアルマにまかせました。しかし以前に「もし完成できなかったら草稿は破棄するように」と語ってたとか、弟子のワルターが公開に反対したとかの事情もあって、アルマはその後十二年間楽譜を隠し続けます。
音楽学者のシュペヒトの勧めでアルマが自筆草稿を公開すると、まず第1、第3楽章の補筆が1924年に作曲家クルシェネックの手で行われ、ついで草稿の全体が写真版で出版されます。その後ショスタコーヴィチやシェーンベルクに全曲完成の話が持ち込まれますが、これらはいずれも実現しません。その一方で何人かの音楽学者が全曲版を作ったりしてます。
このCDのクック版の場合、マーラー生誕百周年の1960年に向けてBBCが記念番組を企画したことに始まります。以前にBBCの仕事をしていたデリック・クックに第10番の解説が依頼され、クックは自筆草稿の研究を始めます。そのうち全曲完成に自信を持ったクックは補筆作業をはじめ、1960年12月19日に第2、第4楽章が不完全な形(写真版からして不完全だった)ながらも全曲の演奏が放送されました。
ところがこれがアルマ夫人に無断でやったもんだから、奥さん怒っちゃうんですね。でも周囲の説得によって放送のテープを聴くと、アルマさんは感動のあまり終楽章を繰り返し聴き、「すばらしい」とつぶやいてこのクック版を承認しました。
その後も写真出版稿では欠けていた第2、第4楽章の残りのスケッチが発見されたりして、改訂された第3稿が最終的なクック版として完成しました。
完成した曲は確かにいい出来で、奥さんが感激したのもよくわかります。特に第4楽章から大太鼓の打撃によって移行する終楽章がなんとも言えずすばらしいです。本当にぜひマーラー本人に作曲させてあげたかったと思います。
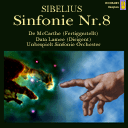 演奏者とか:D・タラ=メーヤネン指揮 ウンベシュピールトSO
演奏者とか:D・タラ=メーヤネン指揮 ウンベシュピールトSO| 作曲者/収録曲 |
|---|
シベリウス(マッカーセ復元)/交響曲第8番 ハ長調 1. I: Allegro moderato 10'17" 2. II: Andantino con moto, quasi allegretto 9'48" 3. III: Moderato - Allegro(ma non tanto) 8'31" |
シベリウスが最後の第7番を書いたのは1924年で、その後1929年に小品を発表して以降、1957年に91歳で亡くなるまで、28年間ものあいだ新作を一切発表しなくなります。人呼んで「シベリウスの沈黙」。
筆を折ったかに見える彼がアイノラでいったい何をしていたかというと、どうやら第8交響曲を書こうとしてたみたいです。結構あちこちに第8番の予告をしたりしてますし、本人も「第8交響曲は何回も完成しているが、まだ満足の行く出来ではない」と手紙に書いたりしてます。
しかし奥さんのアイノによれば、シベリウスは1940年代に自筆譜をだいぶ燃しちゃったらしくて、秘書のレヴァスにも「第8番は全部燃やした」と語ったとか。彼は芸術に対して、そして自分に対しても、とっても厳しい人だったんですね。
それでなくとも彼の作風は幽玄な交響曲第4番を境にどんどん静寂へと向かっていました。そして宇宙の深淵に沈んでいくような7番でその頂点を極めて、第8番はついに本物の沈黙になったのだと、長らくそう思われていました。実際、書いたにせよ発表されなかった以上、それは沈黙以外のなにものでもないですね。
ところが1999年7月、アイノラに隕石が落下して破損したため、修理が必要になりました。その修理のための調査によって、思わぬ発見がありました。暖炉の灰の中から燃やされた交響曲の総譜が見つかったのです。それはアメリカのNASAに持ち込まれ、マッカーセ博士の最新の分析技術によって、演奏可能なまでに復元されました。その世界初のCDがこの一枚です。
最晩年のシベリウスらしく、恐るべき静謐に満たされた音楽です。3楽章制ですが、切れ目はあいまいです。なにか北極圏のオーロラのような(見たことないけど)そこにあるのに全然とらえどころのない、まるで幻みたいな交響曲です。まさに沈黙と呼ぶにふさわしい。こりゃ演奏も困難を窮める難曲でしょうねえ。