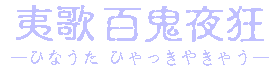
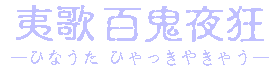 |
| [帶取が池]は、盜賊に母を殺されたお姫樣の復讐譚で、歌舞伎などにも取り上げられた。 「利上げ」は、質草の期限が來て利息だけ拂ひ、期限を伸ばすこと。土師掻安(はじのかきやす)の歌は、いつまでたつても質流れしない帶を怪しんでゐるのである。 |
 [おさかべ](長壁とも書く) は、姫路城の天守閣の上層に住むといふ妖怪。城中の人はみなこれを怖れて天守閣にのぼらなかつた。ある時若侍が火を借りに行つたところ、簾を上げてすがたを現はしたが、十二單を着た老婆であつた。ところが城主がやつて來た時には座頭に化けて出たといふ(「諸國百物語」による)。 [おさかべ](長壁とも書く) は、姫路城の天守閣の上層に住むといふ妖怪。城中の人はみなこれを怖れて天守閣にのぼらなかつた。ある時若侍が火を借りに行つたところ、簾を上げてすがたを現はしたが、十二單を着た老婆であつた。ところが城主がやつて來た時には座頭に化けて出たといふ(「諸國百物語」による)。「香炉峰」は、唐の國は江西省盧山にある峰で、白樂天の詩「香炉峰の雪は簾を撥(かか)げて看る」で知られる。 [蛇足]「ふる城」に「降る城」「古城」の両意を掛けてゐる。 |
| [山鳥]は、山に住むキジに似た鳥。雄は翼で胸を打つて音を出し、この音からホロホロ鳥とも呼ばれる(アフリカ原産のホロホロ鳥とは別物)。古來、雌雄は峰をへだてて棲むと信じられ、「ひとり寢」の例にひかれて多くの歌に詠まれた。「あしひきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寢む」(百人一首の人麻呂歌)。金埒の歌によれば、人を化かしては、獨り寢の慰め草にしてゐたらしい。 |
| [狒々]は、山奧に棲む怪獸。スネが異樣に長くて大柄、性格は獰猛。山猿の年を經たものともいふ。明治時代に至るまで、よく目撃・捕殺され、新聞紙上を賑はせたやうである。 |
| [古榎]深山を歩いてゐると、時に「しねしね」とうるさく囁く物の聲が聞える。死者の靈が榎にばけたものだらうか。なお榎は江戸時代、街道の一里塚として植ゑられた。 |
| 「草摺」(くさずり)は、草花で染めた衣服などをいふ。「いかのぼり」は凧のこと。「いと目」は凧の表面に付け、あがり具合などを調節する糸。「いと」に「非常に」の意を掛けてゐることは言ふまでもない。 |
| [戸隱山の鬼傳説]は、謠曲「紅葉狩」などに見える。戸隱山へ紅葉狩に出かけた平維茂(たいらのこれもち)が、美女にばけた鬼に誘はれ酒宴に引き込まれるが、醉ひながらも鬼を退治する、といつた話。 |
| [一條戻り橋の鬼退治傳説]戻り橋付近に鬼が出るといふ噂が立ち、源賴光の四天王の一人、渡邊綱は寶剣「髭切」を携へて出かけていつた。寶剣の威力を恐れたか、鬼は現はれなかつたが、歸り道、東の橋詰にうら若い美女が立つてゐるのに出くはした。「五條まで行きたいのだが、送つて頂けないか」と嘆願する女を、綱は馬に乘せてやり、五條へと向かつた。途中、女は突然鬼に變じ、綱のもとゞりを攫んで空へ飛び上がる。綱は寶剣で鬼の腕を切り、自分は北野神社の回廊に落ちた、といふ。 |
| [宇治の古戰場]は、源平の合戰が行はれた宇治河畔の古戰場をさす。「伊勢武者」は伊勢平氏の武者。「ひをどし」は緋色に染めた革鎧。 |
| [土蜘蛛](つちぐも)は、日本書紀などにも記述が見え、日本古來の物の怪である。もとはわが列島に土着した異民族をかう称したものらしいが、のち蜘蛛の妖怪と考へられるやうになつていつた。さまざまな姿に變化し、強力な靈力でもつて人々を苦しめた。 蜘蛛の化物なら女郎にも變化したらう(女郎蜘蛛)。いとしい人を罠にかけて奪つたなんてこともあつたでせう。 |
| [安達が原]は、福島県の安達太良(あだたら)山麓の原野。ここに籠つてゐたといふ鬼の傳承は、「今昔物語」「大和物語」など多くの説話集に取り上げられてゐる。 謠曲の「安達原」ではこんな内容の話になつてゐる。供を連れて行脚の旅をしてゐた山伏が、安達原に一軒の家を見つけ、一晩の宿を請ふ。あるじの女は承知して山伏を家に通すが、「隣の寢室は絶對に見てはいけない」と言ふ。やがて女は山に薪を取りに出かけ、山伏はぐつすり寢て仕舞ふ。しかし供の者は隣室が氣になつて仕方なく、たうとう中を覗いて仕舞ふ。そこには山と積まれた死骸があつた。山伏と供の者はあはてて逃げ出すが、山から戻つた老女が鬼の本性を顯して追ひかけて來る。山伏は遂に鬼を祈り伏し、鬼婆はすさまじい恨み聲を殘して消え去つた。 |
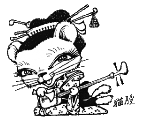 [猫又]「奧山に、猫またといふものありて、人を食らふなる」(徒然草)。猫又はもともと山に住む大猫をいつたやうである。それがいつからか、普通の飼ひ猫の中にも、年を經ると猫又に變化するものがあると信じられるやうになつた。尾の先が二またに分かれてゐるので、容易に見分けがつく。 [猫又]「奧山に、猫またといふものありて、人を食らふなる」(徒然草)。猫又はもともと山に住む大猫をいつたやうである。それがいつからか、普通の飼ひ猫の中にも、年を經ると猫又に變化するものがあると信じられるやうになつた。尾の先が二またに分かれてゐるので、容易に見分けがつく。徒然草の「連歌しける法師」は暗闇と臆病風のために飼ひ犬を猫又と間違へ、大いに恥をかいたが、猫又の大きなものは大犬を優に超えたとのことである。 |
| [海坊主]は、古來さまざまなタイプが報告されてゐる。琵琶を脊中にかつぎ、杖を持つて海上に現はれる盲目の巨人、海座頭。波間に丸い頭をちよこつと出し、船が近づくと沈み、またひよこつと頭を出すといふ、お茶目なぬらりひよん。なんだかわけの分からない、ぬるぬる坊主。 |
| [葵の上]は、ごぞんぢ源氏物語の登場人物。光源氏の正妻であつたが、賀茂神社參拜の折、車爭ひで恥をかかされた六條御息所の恨みをかひ、その生き靈に取り殺された。 |
| 何はさておき南無阿彌陀佛。 |
| [羅生門の鬼傳説]渡邊綱が馬にのつて羅城門の前を通り過ぎたとき、うら若い美女が一人歩いてゐた。綱は女を馬に乘せ、送つてやることにした。道中、女は突然鬼の本性を顯はし、綱の腕をつかんだ。綱が太刀を拔いてその手を斬り落としたところ、鬼は叫び聲を殘して去つていつた。 さて、綱は鬼の腕を持ち歸り、処置に困つて占ひをさせたところ、「七日間の物忌みをせよ、さすれば祟られることはあるまい」と言はれ、その言葉に從つて門を閉ざし、誰にも會はずに六日を過ごした。ところが七日目になり、綱の乳母が訪ねてきて、ぜひ會ひたいと懇願する。綱はやむなく門を開けて入れてやつた。乳母に物忌みの理由を問はれた綱は、鬼と出くはしたいきさつを説明し、斬り取つた腕を見せた。すると乳母は突然鬼に變化し、「我は茨木童子なり。これぞ我が腕!」と言ふや否や、綱から腕を奪ひ取つて飛び去つた。 「井戸替へ」は、井戸の水をすべて汲み上げ、井戸の中をすつかり掃除すること。旧暦七月七日に行はれることが多かつた。「綱を引く」には、井戸水を汲むための桶を結びつけた綱を引く意を掛けてゐる。 |
 [一つ目小僧]については、さまざまな傳承が各地に殘つてゐる。岡山県に傳はる怪談によると、古松の枝の上から青白い光を發しながら飛び出してきて、腰を拔かした人のあたまを長い舌でぺろりと舐める、といふ。一つ目であるばかりでなく、片足のものが多いやうである。その來歴は、柳田國男によつて見事に解明された。 [一つ目小僧]については、さまざまな傳承が各地に殘つてゐる。岡山県に傳はる怪談によると、古松の枝の上から青白い光を發しながら飛び出してきて、腰を拔かした人のあたまを長い舌でぺろりと舐める、といふ。一つ目であるばかりでなく、片足のものが多いやうである。その來歴は、柳田國男によつて見事に解明された。[蛇足]「ふり出だし」に賽子(サイコロ)を振る意を掛けてゐる。一つ目は六の裏。 |
| [平維茂](たいらのこれもち)は、繁盛の子。余五將軍と呼ばれ、陸奧鎮守府將軍としてさまざまな武勇傳を殘す。鬼や妖怪を退治したといふ話も多いから、もののけの恨みつらみを一身に集めてゐたのである。 |
| [産女]は、出産時に亡くなつた婦人の靈が化したものといふ。海や川の中から、乳飮み子を抱いて現はれることが多い。その場を通りかかつた人は「念佛をとなへるので子供を抱いてゐてくれ」などと賴まれる。赤子を抱いてやると、産女は念佛をとなへ始めるが、念佛のすすむにつれ、赤子はやがて石のやうに重くなる。 恐ろしい話であるが、くれぐれも産女の申し出をことわつてはならない。そんな非情の者を、産女は何處までも執念深く追ひ掛けてゆくだらう。反對に、無事赤子を抱き通した者は、褒美として怪力を授かつたり、金銀財寶をもらへたりするのである。 ウブメは姑獲鳥とも書く。これは唐國(からくに)から傳はつた人鳥二身の妖怪、姑獲鳥と混乱したもののやうである。怪鳥となつたウブメは、子供の泣き聲に似た聲を發しながら夜空を飛行し、他の子供を害したといふ。 |
| [實方雀](さねかたすゞめ)藤原實方は、平安中期の歌人。一條天皇の時、陸奧に配流されてその地で果てた。都へ歸りたい一念から、その亡魂は雀に化し、つひに内裏へ飛び入つて、臺盤所の飯をついばんだといふ。それで奧羽地方の雀を「入内雀」と呼ぶのである。 入内雀は、秋、全國に飛來して越冬する。秋の渡りの時、大群をなして稻に被害を與へることがある。 |