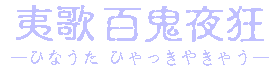
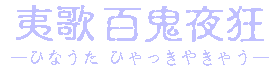 |
| [油なめ]は、夜になると何處からともなく火の玉のすがたで現はれ、赤ん坊に變化して行灯の油を舐める。すつかりなめて仕舞ふと、また火に戻つて何處ともなく消え去る、といふ。 「もゝんが」は、例の滑空する栗鼠科の小動物であるが、江戸時代、子供をおどかす時に使はれた言葉でもある。両手を廣げて襲ひかかるやうな素振りを見せながら、ももんぐわあ! と言つて驚かすのである。そしたら油なめもビツクリして、はつと消えた、といふのである。なほ、「もゝんがはらけ」は、「かはらけ」(油を入れた素燒の土器)と掛詞になつてゐる。 |
| 眼はよく太陽と月に譬へられるが、それが三つあるといふことは、星が一個餘分に入つたのだらう。 |
| [片輪車](かたわぐるま。片車輪ともいふ)は、近江國(滋賀県)甲賀郡に現出した怪異現象。夜、片車輪の車が火焔に包まれて通りを過ぎてゆくが、その車には美しい女が一人乘つてゐる。これに出會ふと子をさらはれるなど災難に遭ふので、人々は夜は固く戸を閉ざして身を潜めてゐたといふ。 東作の歌は、引き潮の潟のあちこちで鳴くさ夜千鳥をよんだ情景に、さりげなく物の怪の名を挾んだのである。本歌は「遠くなり近くなるみの濱ちどり鳴くねに潮のみちひをぞしる」(新古今集)。 |
| [古寺]は物の怪出現の定番スポツト。 |
| 天井裏もまた物の怪がひそむ定番スポツト。 「三浦屋」は当時有名だつた遊郭。天井からのびる物の怪の手よりも、傾城(遊女)の出す手の方が恐い、らしい。 |
| [船幽靈]は、夜行する船を沈めようとする幽鬼。初め白い綿のやうなものが一つ波間に浮んだかと思ふと、やがてそれが人の顔の形になり、次々に幽靈となつて船のまはりを取り圍む。柄杓で海水を汲み入れたり舟底に取りついたりして、何としても船を転覆させようとする。 |
| 天明から文化文政の頃にかけて、江戸では金融資本家が臺頭し、金貸しが盛行した。特に、座頭(有官の盲人)はおほやけに高利貸の許可を得て、「金貸座頭」と呼ばれ、威を誇つた。なにしろバツクには幕府權力がついてゐたのだから、金に窮した庶民にとつて、壁に貼りついた座頭の強催促の恐しさ、化け物の比ではなかつたのである。 |
| [大魔が時]は、逢魔が時。禍事(まがごと)が起こりやすいとされた、夕暮時のことであるが、逢魔を大魔と書くと何やら一層物凄い……。 |
| [おいてけ掘]夜、釣人が堀端を通りかかると現はれて「おいてけ、おいてけ」と魚をねだり、全部置いて行くまではその聲を決してやめないといふ妖怪。江戸本所が出現名所。 |
| 氣がつくと脊中に子供をおぶつてゐる。言葉つきは大人で、時々うす氣味の惡いことを言ふ。捨ててしまはうと思つて暗い森の中へ入つてゆくと、雨が降り出してくる。話を交はしてゐるうち、脊中の小僧はどうやら自分の過去現在未來をすべて見通してゐることが判り、ますます氣味が惡くなる。とある杉の根に通りかかつた時、小僧は「こゝだ、こゝだ」と言ひ、文化五年辰年、此處でお前はおれを殺したのだ、と告げる。さうだつたのか、と氣がついた途端に、脊中の子は急に石地蔵のやうに重くなつた…。 歌とはあまり關係ないが、漱石の「夢十夜」の一挿話である。 |
| [むじな]は穴熊のことだが、狸と混同され、狸を貉といふこともあつた。でも穴熊は鼬科、狸は犬科で、もちろん違ふ動物である。 貉や狸は人を化かすと信じられた。よく美女の姿に化けて男をたぶらかしたりしたやうだが、一陣の風のおとづれと共に、ふと氣づくと影も形も消えてゐた。それで自分が化かされてゐたのだと分かり、夢から醒めたやうに我に返つた、といふパターンの話が多かつたやうである。 |
| [姥が火]大阪平岡神社付近に住むといふ怪火。平岡神社の神灯を毎夜盗んでゐた姥の亡靈なのだといふ。 恐怖にかられると、人は齒の根も合はず、腰も立たなくなる。確かにこれは年老いた状態と似てゐるのかもしれない。 |
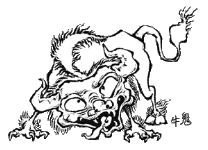 [牛鬼]は、ずいぶん昔から怖れられてゐた妖怪らしい。『枕草子』にも、「名おそろしき物」の一つに「うしおに」を擧げてゐる。これはもともと地獄にゐるとされた鬼、牛頭(ごづ)のことかと言はれてゐるが、南北朝時代の『太平記』等になると、源賴光に退治されたことになつたりもしてゐる。 [牛鬼]は、ずいぶん昔から怖れられてゐた妖怪らしい。『枕草子』にも、「名おそろしき物」の一つに「うしおに」を擧げてゐる。これはもともと地獄にゐるとされた鬼、牛頭(ごづ)のことかと言はれてゐるが、南北朝時代の『太平記』等になると、源賴光に退治されたことになつたりもしてゐる。その後、牛鬼はさまざまなヴアリエイシヨンで登場するやうになり、海中からあらはれて角で突き刺すともいひ、山中に棲んで、人と出會ふとじつと見つめて去らず、見つめられた者は疲勞困憊の擧句死んで仕舞ふ、ともいふ。 參和の歌では、朧車のやうな、異形の者を載せた牛車を連想させもする。 |
| [肉吸]山中に現はれる妖怪。十七、八の美女の姿をとり、ホーホーと笑ひながら人に近づいてくる。「火を貸してくれ」と言ふが、油斷すると食ひつかれ、肉を吸はれて仕舞ふ。 [蛇足]唐傘は竹の骨に紙を貼つた傘。暴風で紙を飛ばされてしまひ、あら憎々しい、骨だけが殘つたのである。 |
| [龍灯](りうとう)は、海上などにあらはれる怪火。暮方、水面に火の玉のやうなものが幾つも浮かび上がり、提灯のやうにぼんやり赤く光つて見えるといふ。 「淺草のいほ」に「草庵」を、隅田川の「すみだ」に「(影も)澄み」を掛けてゐる。 |
| [牡丹灯籠]は、三遊亭圓朝の人情噺で名高い。お露といふ名の娘の幽靈が、毎夜カランコロンと駒下駄の音をたてながら、牡丹灯籠を提げ、自分を裏切つた昔の恋人新三郎のもとに通つてくる。つひに新三郎は幽靈に取り殺されて仕舞ふ、といふ話。 「しゝあひ」は肉付きのことで、頬などがげつそり削げ落ちて仕舞ふのを「しゝあひが落つ」と言つた。 |
| [川獺](かはうそ)は古來、人を化かして水に引き込むと言はれ、河童の原形とも考へられてゐる。 |
| [札へがし]は札(護符)を剥がす幽靈。札返しともいふ。 「子おろしの女房」は墮胎を業とした女。「この世の札」を剥がす、とは、未生から今生への入場切符を取り上げて仕舞ふ、といつた意味になる。 |
| [木だま]は、文字通り樹木の精靈。平安時代の「和名抄」には、「樹神、古太萬(こたま)」とある。古い木に宿り、人氣のないときに現はれて害をなすと信じられた。やまびこを谺ともいふのは、これを樹神の應答と考へたからである。 |
| [髮切]雪隱の中や井戸端など、狹い場所に突然現はれ、髮を切るといふ道の怪。肩に何か重いものが乘つたと思つた瞬間には、髮がばつさりと前に落ちる。いつの間に切られたのかは決してわからないのだといふ。化け猫のしわざとも狐のしわざとも言はれてゐる。 |